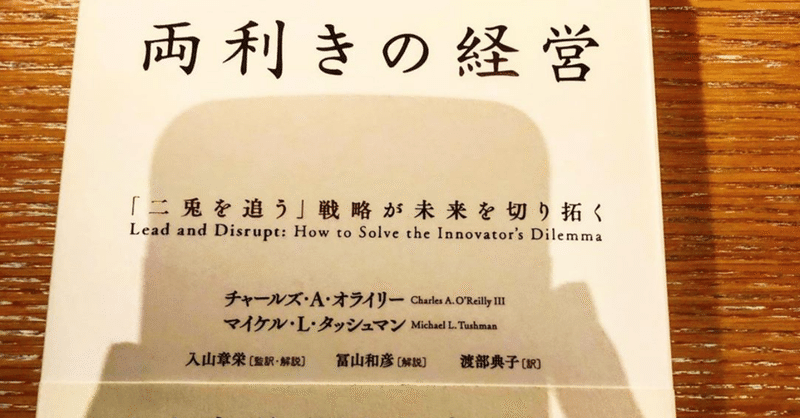
読書まとめ 『両利きの経営』
読書まとめです。
インプット→アウトプットの練習で書いてます。いずれ有料化させます。
と言うのも、本を読むのが面倒、時間がない。とう言う方たちでも内容を要約して伝えられたら良いと感じたからです。
久しぶりの投稿、ふみやです。
最近は経営に関する本を漁っています。
いい本があれば紹介してください。
さて、『両利きの経営』とは。
“深化と探索”
について語られています。
もうこれに尽きます。
深化とは?
一定分野の知識を深めること。
得意分野を伸ばす、というイメージですね。
探索とは?
自身の既存の認知を超えて遠くに認知を広げること。
チャレンジとか新規事業ですね。
なぜ、両利きの経営が必要なのか?
ほとんどの企業が、時代の変化の対応できずに消滅する。
40年続く会社は0.1%ほどだ。
「生き残るのは、最も強い種でも、最も賢い種でもない。最も変化に対応種である」 byダーウィン
ダーウィンの有名な言葉ですね。
「老舗企業は常に深化に専念し、すでに知っていることの活用にかけては腕を磨いていく。
それで短期的には優勢になるが、徐徐に力を失い、潰れる。」 byマーチ
つまり、新時代の変化に対応していくには、既存事業だけではいけない。新規事業が鍵になる。
そけで有名な例
『アマゾン』
・発明と変革をし続け、新しいことを築く。
アマゾンは沢山の挑戦→失敗を繰り返している。
新規事業の撤退リストをみるとすごい。
・アフィリエイト・プログラム
→書籍を宣伝→レビュー
・アマゾンプライム→よそで買い物をしなくなる。
ここでまず成功して、
常に本業以外でリスクを取れるように支援
意図的なダーウィン理論を企業の文化として創出した。
顧客満足度、低価格、長期展望、倹約、
実験への積極性、政治的行動をしない、
などの理念。
→長期志向は顧客利益と株主利益は一致する。
ここまで大きくなった理由について
・企業のミッションと価値観が明確であること。
・共通のアイデンティティー
・分権型アプローチで権限を移譲し、結果について説明責任を持たせる。
「顧客志向を打ち出す会社は多いが、大半はそうなっていない。」 byジェフ・ベゾス
なぜこれをやるべきなのか、自分たちにはその分野のスキルがない
こうなると企業の寿命は有限になる。
アマゾンがこれほど凄い企業に成長したのは、
葛藤を許容する能力と破壊的変化を追求し続けるイノベーションの文化を構築すること。挑戦する勇気が経営者にあるからだ。
『イノベーションのジレンマ』
まず新規事業は、すぐに利益はでない。
というのも
・非常に非効率な経営であること。
・既存事業とはノウハウがあまりにも違うこと。
・新たな市場の開拓
など、時間がかかるものが多い。
そのため、既存事業からしたら疎ましい存在だ。
「既存事業にフォーカスしろ。我々が利益を出している。」
といった具合にね。
有効な手段としては
スピンアウトさせる。
経営陣の支援と監督、
成功の必要な人材、構造、文化の調節。
調節とは
戦略と目標を明確にすること
→目標達成に欠かせないキーが分かる
・達成しようとしていることが明確になっているか
当事者にやる気はあるか
・必要な時に適切な情報が取れるような組織構成をしているか
・適切な項目を評価し報酬を与えているか
・適切なモニタリングとコントロールシステムがあるか
・各自の目標達成に向け取るべき行動が共有されているか
「全ての失敗は経営者の失敗である」
by ピーター・ドラッカー
リーダーは、幹部チームの対立に向き合い、葛藤から学び、事業間のバランスを計る
一貫して矛盾するリーダーシップ行動を実践し、
議論や意思決定の実践に時間をかける。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
