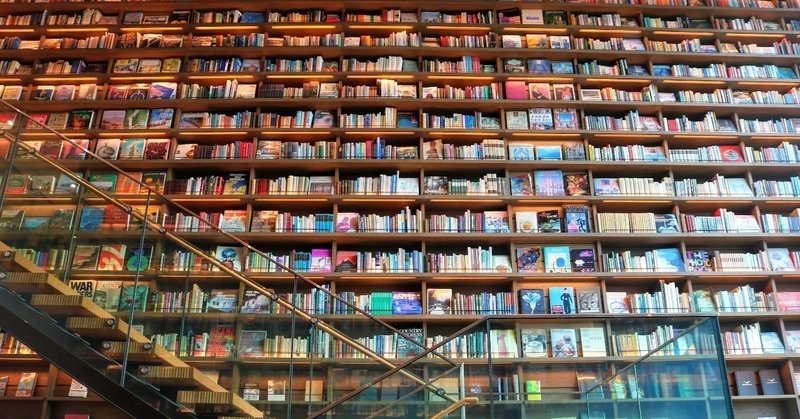
心理士か心理師か、それが問題だ
少し前に書いた,ブラックな元職場に出向いた。
「同じ名前の人が来たら使えるから,返して」と言われたハンコと「クリーニングしますか?」とボスに聞いたら「お願いね」と言われて自腹でクリーニング代を支払った制服を返しに行ったのだ。
最後まで,この職場は人を大事にしないなぁと,笑ってしまった。そんな職場だから,離職率が高く,櫛の歯が欠けるように人が居なくなっていく泥船の職場。
あまりのブラックな労働環境に,月1で通っている治療院の先生に「ここで,辞めますって,電話しなさい」と言われたぐらいだった。
水は低きに流れるというけれど,感覚が麻痺してしまうのだろう。よくぞ1年とちょっとで辞められたと自分を褒めてやりたいくらいだ。なんの恩義もないのに。
そんなブラックな労働条件の職場だったけれど,得られたものは横の繋がりで,スタッフ同士で愚痴り合う連帯感はやけに高かった。
そもそも,心理職は常勤がただでさえ少なく,その常勤でさえ,国家資格ではないから(臨床心理士は公的資格)という理由で,医療や福祉,教育,産業,行政の5分野の中でも特に医療では唯一国家資格のない心理技術職として身分保障もなく,給与も低いことが多い。
臨床心理士になるには,指定大学院という修士課程の2年間に入学し,臨床の現場での研修が必須だっり,必須な単位を取って,やっと臨床心理士の試験を受けられるほど,お金と時間がかかる高学歴な資格だ。
臨床心理士の資格がなくとも,公務員の心理職(行政)の仕事ができるので,難関の公務員試験を受けて,法務省の職員になったり,地方自治体の心理職として入職することもできるが,狭き門である。
また,病院の心理職として常勤で採用される道もあるが,給与は高くても仕事量が半端なく多かったり,給与が逆に低い場合もあって,労働環境はあまりよいとは言えない。
なので,大抵の心理系大学院の修了者は,常勤職を最初から狙わず,非常勤を何か所も掛け持ちしたりして,臨床心理士試験を受け,試験に合格後に転職をしたりする。
こんなふうに高学歴なのに金銭面では報われない仕事であるのが臨床心理士で,臨床心理士が誕生して30年が経つのにその間の労働問題は依然として解消されなかった。
でも,昨年12月に晴れて国家資格として「公認心理師」が誕生した。
国家資格化がされるから,臨床心理士を取っておいて,スライド式に無試験で国家資格に移行するのを待てばいい,という夢物語を院生の頃から聞かされていた。
が,議員立法で国会で審議されたり,一度は法案ができたのにも関わらずとん挫したので,期待はしていなかったけれど,職場の上司のすすめもあって,何が何でも細々と病院臨床は続けて臨床経験を確保していた。
そんな経緯で,ブラック職場であっても,無理くり所属していたのだった。
でも,公認心理師試験に合格したけれど,給与は変わらず,他の職場でも合否をまったく聞かれず,今のところ,公認心理師と臨床心理士のダブルホルダーであっても,まったく関係がない。
この公認心理師の試験だって,臨床心理士の資格がそのままスライドされるわけもなく,それなりに勉強も必要だったので,かなり心身を病んだ。
「ドウシテ,コノ歳デモ,試験ウケルノ」
現任者講習と言って,本来は指定の大学と大学院を卒業していなければ受験できない公認心理師であるが,5年間の移行期間の間は,現時点で何らかの心理職に就いているものが特例で受験できる制度(Gルート)がある。
大学院での指定科目を取っていれば,現任者講習会に出なくても単位の振り替えをしてくれるのでよいのだけど,わたしの場合,指定科目が足りなくて,現任者講習を受けた。
ボーカロイドの電子音で講習テキストが読み上げられ,突貫工事で作ったんだなとおぼしき画像を朝の9時から午後の4時過ぎまで,何科目も見せられる講習会が4日間。
この講習会には,受ける必要がない人でも保険のために受けたり,試験の概要を知りたくて受けている人もいた。
講習会の最終日,大学講師をしているという年配の先生が(心理士は先生と呼ばれるし,呼ぶ)班ごとの発表(一応,班を作りグループ学習をするスタイルもあった)をする時に,「関係ないけれども,この歳になって4日間通うことを強いられるのはきつかった。皆さんもそうだったと思います。お疲れ様でした」と挨拶をされた時,会場で熱い拍手が響いた。
突貫工事の国家試験の準備をされた試験委員の先生方も大変だったと思うし,初回で過去問もなかった中,勉強を強いられた我々受験者もかなり精神を病んだ。
さらに,試験月の数か月前は各地で豪雨があったり,観測史上初の猛暑続きの夏に大阪ではブルーテントが屋根の上を覆うような大きな地震もあって,なんとも落ち着かない勉強の環境でもあった。
試験の数日前には,北海道で地震が起こり,北海道地区の受験は延期され,北海道だけなんと3か月後に追試が行われるという初回から前代未聞の試験だった。
もっと言えば,現任者の定義があいまいで,例え週1回ボランティアで対人援助が指定機関で行って入れば現任者として認められるにも関わらず,臨床心理士としてベテランの先生でも開業届の有無などで受験資格すら与えれられないという事態があったり,どっひゃーだった。
この現任者の定義は非常に幅広く,大抵の国家資格は最終学歴が高等学校あるいは専修学校以上という規定があるにも関わらず,学歴不問。学校歴を記入することもなかった(現任者ルート以外は,大学院修了証や単位表を提出するので,このルートは抜け穴だらけ)。
このような曖昧さは,公認心理師法施行の5年後の改定で,見直されることだと思うが,なんともヒドイ話だと思う。
ということで,心理職という需要はあるだろうけれど,一般の人にとってはどうでもいい内情を書かせていただいた。
果たして5年後,心理職というものが生き残っているのか,さらに心理職を目指す人がいるのかは,この公認心理師の働き方によって命運が決まる。
今のところ,臨床心理士と公認心理師のダブルホルダーが最強だけれども,勢力図はどうなっているのか,心理屋として気になるところである。
論文や所見書き、心理面接にまみれているカシ丸の言葉の力で、読んだ人をほっとエンパワメントできたら嬉しく思います。
