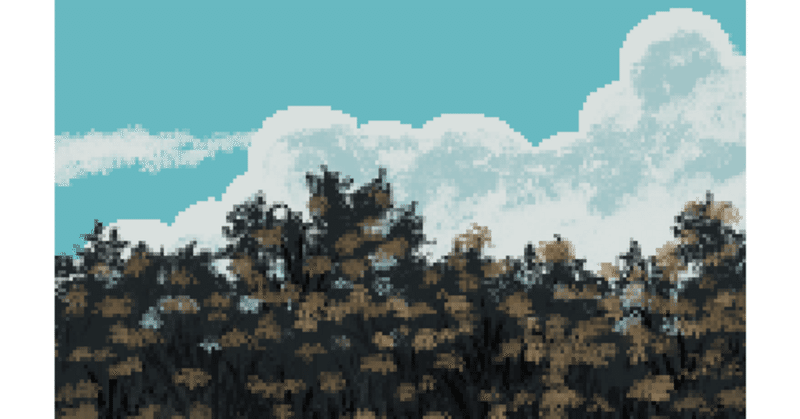
理由がないからこそ貴重で大事、の「からこそ」が分からない
入会していない私でもこれは無料で読めるらしく読んでみた。
最近読んでいる下の本の主題と共通する「死への恐怖」。
私は投稿者の子供の問いには共感するし、なんならいつもそれを考え続けている。それに対する東浩紀氏の娘さんの回答も頷ける。ところで、この高村友也氏『存在消滅』は、微妙な差異だけども、東浩紀氏と東の娘さんが言っているような人生の内部で起こる他人の死や苦しみや孤独などの問題として言われる「死への恐怖」ではなくて、永遠の無、すなわち人生の外部での「永遠性の伴った死への恐怖」について考えているエッセイだ。永遠の無の前では、残念なことに東浩紀氏や娘さんの回答も、何ら慰めにはならない、と高村友也氏なら答えそうな気がする。それはそうと、少しだけ違和感を述べさせてもらえるとするなら、東の最後の言葉にある。
(…)おそらく息子さんは息子さんなりに、安穏と毎日を生きている自分と、戦場で生きなければならない人々のちがいにうっすらと気がついているのではないか。もしそうだとすれば、それはとても大事な気づきなので、決してごまかすことなく、しっかりと受け止めてあげるのがよいように思います。
この世界には、不条理に生を断ち切られるひとが数多くいる。息子さんがなぜそうでないかといえば、それは運としかいいようがなく、理由などない。けれども、理由がないからこそ、息子さんやお母さまがいま生きていることはとても貴重で大事なのです。
前段で、ウクライナ戦争とパレスチナ紛争の報道におそらく感化された投稿者の子供の早熟さを讃えつつ「安穏と毎日を生きている自分と、戦場で生きなければならない人々のちがいにうっすらと気がついているのではないか」と、その子が鋭く察したのかもしれない「ちがい」について東氏は「とても大事な気づき」と言っている。そこに何ら違和感はない。
急に疑問が出てくるというか、端的に分からなかったのは、後段の「この世界には、不条理に生を断ち切られるひとが数多くいる。息子さんがなぜそうでないかといえば、それは運としかいいようがなく、理由などない。けれども、理由がないからこそ、息子さんやお母さまがいま生きていることはとても貴重で大事なのです。」という文の「けれども、理由がないからこそ」の「からこそ」という部分だ。東氏は「(…)けれども、理由がない」と「(…)いま生きていることはとても貴重で大事なのです」を「からこそ」でつなげようとしているのだが、明らかにつながっていない。東氏はただ投稿者とその子供に何とか実のある答えを用意しようと思って上のような定型文を用いたのかもしれない。でも私にはそのつながりが分からなかった。
私に子供がいるとしたらその子の「気づき」を「しっかりと受け止めてあげる」前に、そもそも自分が「決してごまかすことなく」その「気づき」を受け止めていることが本当にできているのだろうか?と思うだろう。
いや、そもそも、つながりのないことを「しっかりと受け止め」ることがどうしてできるのだろうか?とも思う。
