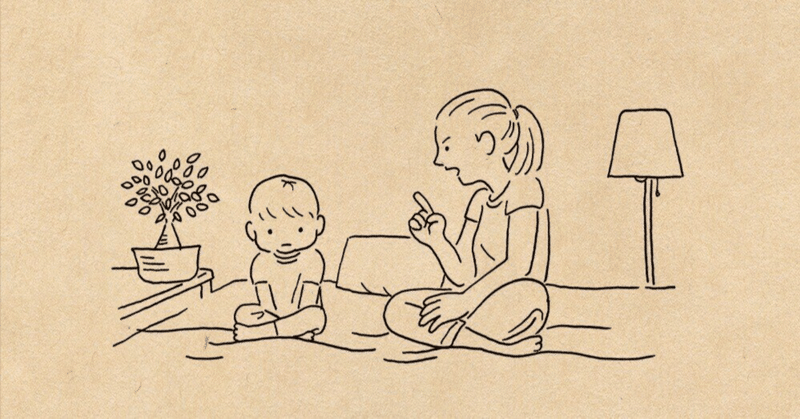
叱るのが苦手、どんなときに「叱る」のか
こんにちは BOKUです。
「子どもが◯◯買ってと駄々をこねる、あばれる」
「すぐにゲーム、家の中でずっとゲームばかりする」
「早く食べ終わってほしいのに、ごはんをのんびり食べる」
「言うことを聞かないわが子にイライラ」
子どもが親や人を困らせる行動をしていても、叱ることが苦手。、うまく叱ることができない。
そして、とっさに感情にまかせて怒ってしまう。どうしたらいいのか。
叱り方について、どういう風に向き合うのが良いのかモヤモヤするところがあるときに「若者に辞められると困るので、強く言えません(横山信弘さん著)」に出会いました。著書の中に「褒める」と「叱る」ことについて大きな気づきがあったので紹介します。
結論から言うと、本当に考えるべきことは、どんなときに褒めて、どんなときに叱るのか。基準とルールをもとに褒めると叱るを決めること。です。
「厳しく叱る」「注意する」「指摘する」
「叱る」と言っても、問題行動を変える「叱る」の働きかけには3種類あります。
1.厳しく叱る
2.注意する
3.指摘する
また補足として「叱る」と「怒る」はまったくの別物です。怒るは、感情的に自分のイライラや怒りをぶつけるもの。叱るは、相手のためを思いアドバイスをしたり注意をしたりするもの。
まず、厳しく叱っていいのは、重大なリスクを相手が軽んじているときだけです。リスクがあるだけなら、言ってきかせればいい。しかし、そのリスクの重大性を理解せず、軽視していると判断したら、厳しく叱ったほうがいい。いったん相手の思考を止めるほどの、何よりもインパクトが重要です。
わかりやすい例でいえば、子どもが急流の川に近づいたときです。
「危ない!近づくな!」と注意を促しても、
「大丈夫、大丈夫!」と言って聞かない。
そういう場合は、「こらァァァァ!」と大声で叱るべきだろう。
子どもがビックリして泣いてしまうかもしれない。そのせいで嫌われるかもしれない。だが、子どもの命には代えられません。
・取り返しのつかないことが起こるリスクを軽視しているとき
・「当たり前の基準」が下がるリスクを軽視しているとき
叱ることの目的は、相手の行動を即刻変えることです。
厳しく叱らないと相手がすぐに行動を変えないから、その手段をとるだけ。叱ることが目的ではありません。「なじる」「罵る」になってしまうような感情に振り回されているときは叱るのをやめたほうがいいです。それは「怒る」になってしまいます。
「注意する」ために必要なルール
何度も言い聞かせて、行動や意識を変えようとするときは、叱ってはいけない。何度も繰り返す必要があるなら注意する。
「注意する」ためには前提条件があります。それが「ルール」。
あらかじめ、決めごと、約束、基準を明文化しておくことが必要です。
何をもとに、注意するのかしないのか判断するためには、基準が必要です。そしてお互いにその基準を共有することが、まず最初に必要です。
「叱る」ときと「注意する」ときの共通点は、相手がわかっているのにもかかわらず軽んじているときにとるべき行動だというところです。著しく気が抜けていたり、意識が低くなっているときに使う手段です。しかし、もし、相手が意識するのを忘れているだろうな、もしくはちゃんと伝わっていないだろうと思ったときは「指摘」してみましょう。
そのときに大切になることは、まず相手の状況を理解すること。コミュニケーションを通じて相手がどんな認識でいるのかを正しく聴くことが大切です。話を聞いて、うまく伝わっていないこと、認識のズレがあると分かれば、そこをお互いにすり合わせしていくことが次のステップです。
分かっていないことだったのに、突然注意されたのはなぜ?と思われないように、認識にズレがないかどうか見極める必要があります。
当たり前の基準
叱るを中心に話を進めてきましたが、「褒める」にも当てはまることが、基準やルールを決めることです。
まずは「当たり前の基準」となるルールを考えて決めます。
つぎに、期待することに注目して、期待以上の場合の「褒める基準」を、
期待を下回った場合の「叱る基準」を自分の中で決めます。
著書の中では「期待」と「感謝」と「褒める」と「叱る」の関係で説明されていました。
「当たり前の基準」「褒める基準」「叱る基準」を決めることができたら、あとはその基準にしたがって褒めるもしくは叱る判断基準とする。
たとえば、勉強する時間を一日1時間すると決めたとしたら、
当たり前の基準:1時間
褒める基準:2時間以上
叱る基準:0分
たとえば、一日1回お手伝いすると決めたとしたら、
当たり前の基準:1回
褒める基準:3回以上
叱る基準:0回
まずは当たり前の基準を家族で決めて、あとはその基準に対して期待以上なら褒める。期待を下回るなら叱る。
「褒めて伸ばす」よりも「期待して伸ばす」のほうがわかりやすいので褒めるコツとしても応用できそうです。
そして、最後に当たり前の基準の達成について、「日々の感謝を習慣化することは褒めることよりも100倍大切なこと」だと述べられていました。
まとめ
良好な関係には「日々の感謝」が大切
「ありがとう。すごく助かっているよ」の一言
最後まで読んでくれてありがとうございます!
面白い!と思われた方は「いいね!」「フォロー」お願いします。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
