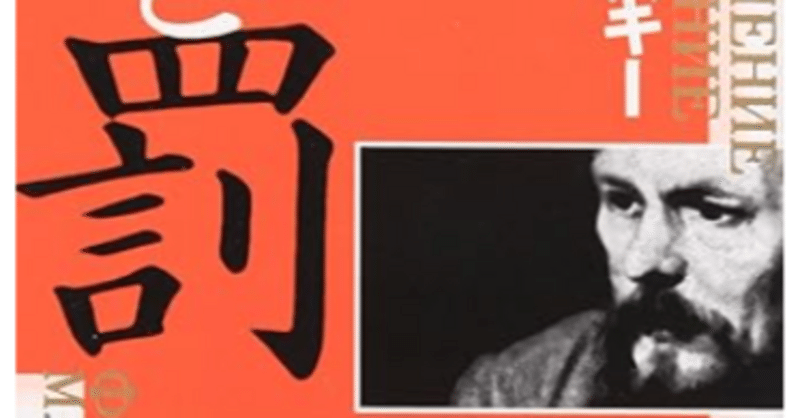
【上智大学の対策】小論文の書き方・考え方⑧
(1)上智小論文に対策あり
私の受け持った生徒には上智大学文学部と法学部の合格実績がある。
小論文の出題形式や参考文を見ると文学部と法学部では異なっている。
しかし、上智大学特有の傾向と対策がにあるように思う。
今回はそれを書いてみたい。
(2)社会は厳罰化に傾いている
法学部を例にとる。
たとえば、「侮辱罪に懲役刑を科せるようにすることを盛りこんだ政府提出の刑法改正案の是非」(獨協大学法学部子女弟妹入試2023年)や「駅構内のエスカレーターでの歩行を禁止し、違反者に科料を課すように法律で定めることの是非」(新潟大学法学部2020年後期)など、法学部では厳罰化の問題を問うことが少なからずある。
現に、新型コロナウイルス感染拡大期に「新型インフルエンザ等対策措置法」でも緊急事態宣言や蔓延防止特別措置の発出時、知事の命令に従わないときには過料を科すように法制化されていて、物議をかもした。
ほかにも、道路交通法で「あおり運転」に対する罰則強化や少年法を改正して、逆送年齢を引き下げるなど、時代の流れは厳罰化に向かっている。
このような、なんでも罰で解決しようという発想には、正直疑問を抱いてきた。
しかし、官僚、政治家や法律家の考え方はこのような「わかりやすく」「国民受けする」方向に傾く。
背景には、安全・安心に神経質になり、一部の逸脱した者の特異な事件に対して過剰に反応する国民意識がある。
ぶたれたら、もっと強くぶち返す。1度ぶたれたら、2度ぶつ。
これは子どもの発想だが、このような罰則強化の流れはこうした態度に通じている。
罰をエスカレートさせるばかりでは、根本的な原因を立たなければ問題は解決しない。
法曹家は抑止効果という言葉を簡単に使いたがるが、死刑制度の存置論(賛成論)にも使われている便利な言葉である。
恐怖や脅しで人々を支配するのは、独裁国家が使う常套手段でもある。
事実、死刑制度が残っている国の顔ぶれ(イラン、イラク、リビア、朝鮮民主主義人民共和国、パキスタン等)を見ると、日本もこれに列していることを恥ずかしく思う。
ここまでエッセイ調に書いたが、ここから小論文的思考に改めて、こうした罰則化や死刑制度について、次章では上智大学小論文ならどう考えるかについて書いていこう。
(3)二項対立を疑え
前章の問題群の要諦は、「犯罪」に対する「処罰」の問題に還元できる。
一見すると、こうした発想は刑法の基本であり、何ら疑いをはさむ要素はないように思われる。
「罪」と「罰」に見られる二項対立でものごとを考える構造は私たちの日常になじんでいる。
入試小論文でも「人工」と「自然」、「自由」と「平等」といった対比関係で考える発想をとることが多い。
普通の大学ではこれで十分に合格答案が書ける。
しかし、早慶上智クラスともなると、ある程度書きなれた受験生はみなこのような二項の対比関係で論じてくるので、採点者としてもやや食傷気味となる。
対比で書く方式はパターン化されて汎用性がある反面、新鮮味が失われて「うまい」けれど「おもしろくない」答案になるケースが多い。
そこで、この二項をずらしたり、こわしたりするというのが、早慶上智の小論文の考え方になる。

(4)ドストエフスキーに倣え
前章で「二項対立をすらせ」と書いたが、これはテクニックで言っているだけはない。
おそらく物事の本質を突き詰めて考えると、どうしても二法対立では収まりきれない何かが見えてくる。
これが「罪」と「罰」の問題にも当てはまる。
どういうことか。
犯罪が起こって、刑事罰を与えて終了、というのが世の習い、刑事訴訟の流れである。
たとえば殺人事件が起こって、被告人に死刑判決が出されて執行される。
遺族にとっては、応報感情が少し晴れるだろうが、亡くなった大切な人は帰ってこない。
たとえ被告人が死刑になっても犯人に対する恨みや憎しみの感情はなかなか消えることはないだろう。
これで事件は本当に解決した、と言えるだろうか。
殺人事件に限らず、何かの犯罪が起こったあと、本当の解決にいたる道筋は二項対立で語られるほど単純ではない。
「罪」のあと、「罰」ではなく、「償い」を必要とする。
刑法からすると、「罰」がこの「償い」にあたるだろうが、いったん法律を離れて考えると、この「償い」は相手に対する「謝罪」であり、社会に対しては「奉仕」という形をとる。
よくタレントが何かをやらかした後、仏門に入ったり、ボランティア活動に従事したりするというのが、この「償い」にあたる。
これだけでは事は終わらない。
最終的には、相手や社会の「許し」があって、ようやく問題は解決する。つまり、罪が晴れて、「贖罪」が完成するのだ。
以上をまとめると、「罪」の問題は二項ではなく、「罪」⇒「償い」⇒「許し」という三項からなる流れのなかで考えるべき問題であることが判明する。
なぜ、「償い」が「罰」になり、「罪」と「罰」というように二項に単純化されてしまったのか。
それは「社会の世俗化」に答えを求めることができる。
「償い」や「許し」というのは、本来宗教が担う領域であった。
「償い」はイエスの「贖罪」に通じるものでもあり、「許し」は「神の許し」でもある。
このようなキリスト教道徳が退潮したのが近代の特徴である。
そもそも日本人に宗教を信じる人が少ないのはかねてから言われるところであった。
とのあれ、「償い」や「許し」が人々の意識から後退したいま、「罪」と「罰」の応酬が繰り返され、これが無限のループとなって、ますます人々を不安のただ中に陥れている。
これが現代社会に閉塞感をもたらしている大きな要因である。
いま、ここでキリスト教の説く「許し」が人々に求められているのではないだろうか。
だからと言って、いますぐ洗礼を受けてクリスチャンになれ、というのも拙速である。
大切なことは、「人を許す心」を持つことだ。
「寛容になれ」ともいえる。
そうなると、もっと社会にゆとりが生まれ、少なくともいまよりも生きやすい世の中になるのではないかと思う。
ドストエフスキーの代表作『罪と罰』を読まれたかたはおわれるだろうか。
不思議なことにこの小説には、殺人の「罪」のことは延々と描かれているにもかかわらず、肝心の「罰」についてはあまり紙幅を費やしていない。
殺人を犯したラスコーリニコフはシベリアに流刑となるが、後半の主題はラスコーリニコフに付き添うソーニャの献身と愛にある。
その献身と愛はもっぱら罪の「償い」と「許し」に向けられたものだ。
ドストエフスキーのなかにも「罪」は「償い」を経て「許し」へと至る魂の軌跡を描こうとする意識が見て取れる。
この問題を法学的に捉え返すと、厳罰の代表である「死刑制度の廃止」という結輪がまずひとつ。
それから、刑務所改革になる。
受刑者の償いはいまの形で本当によいのか。
懲役刑の場合には、刑務所内の労働を通して罪を償う形となるが、その労働の種類と内容について深く考察するという展開が次にくる。
さらに刑務所内での受刑者に対する教育が重要となる。
そうするとキリスト教や仏教などの宗教の意義をやはり考えないと「許し」へ至るパースペクティブは開かれない。
このような趣旨で上智大学小論文を私なら考える。
ここまで補助線を引いたので、受験生は以下の上智大学法学部の問題を考えてみてください。
解答例はOK小論文の以下の講座を受講された希望者に配布しています。
受講を希望される方は、以下のワードで検索してください。
OK小論文 朝田隆 ココナラ 上智大学小論文のオンライン個別指導をします
(5)問題
「不寛容に寛容たるべきか」上智大学法学部国際関係法学科2021年カトリック高等学校対象特別入学試験
次の課題文を読んだのち、下記の問いに答えてください。
① 2015年1月7日、フランスの週刊新聞シャルリー・エブドに暴漢が乱入して12人を射殺してからおよそ2週間、その余波がやまない。そこには2つの流れをみることができるだろう。
② 第一の流れは、言論の自由を守れという国際的連帯である。暴徒の襲撃直後から欧米諸国では「私はシャルリー」という言葉がインターネットで拡散し、プラカードとなって数多くの集会で掲げられた。事件後週末の集会ではフランスのオランド大統領はもちろん、ドイツのメルケル首相など各国首脳が集まり、無法な暴力を前にして言論の自由を守る必要を訴えた。
③ 第二の流れはイスラム圏を中心とした反発である。シャルリー・エブドの最新号がムハンマドの風刺画を表紙にしたことを直接の引き金として、抗議行動がパキスタンやアルジェリアに広がり、ニジェールでは教会が焼き討ちにされた。その抗議の主体は特定のイスラム過激派というよりスラム諸国の一般民衆であり、イスラム教を誹謗する表現に対する激しい反発を認めることができる。
④ このような2つの流れの背後には、今回の事件よりも前から広がっていたさらに2つの流れがある。その第一は、イスラム過激派によるテロの拡大である。イラクからシリアにかけて勢力を広げたISIS(いわゆる「イスラム国」)はイスラム圏ばかりでなく欧米諸国からも参加者を集め、ナイジェリア北部を中心とした地域ではボコ・ハラムによる殺戮(さつりく)も繰り返し伝えられている。シャルリー・エブドの襲撃は、いま世界各地で再燃しているイスラム過激派の数多くの活動の1つとしてみるべきものだろう。
⑤ もう1つの流れは、欧米社会における移民排斥、特にイスラム教徒の移民への制限を求める動きである。既にフランスでは右派政党国民戦線がフランスヘの移民、ことに北アフリカからのイスラム系移民の制限を主張してきたが、二代目党首マリーヌ・ルペンを迎えて勢力を拡大し、2014年の欧州議会選挙ではフランスの得票の25%近くを獲得した。移民制限はオランダやデンマークにも及び,移民制限の声が弱かったドイツでさえ、西洋のイスラム化に反対する愛国的ヨーロッパ人(PEGIDA)と称する団体がドレスデンなどで大規模な政治集会を繰り返している。アメリカでは、テレビ局フォックス・ニュースのコメンテーターが、イギリスのバーミンガムはもはや丸ごとイスラムの町になった、イスラム教徒でなければ入ることができないところだなどという発言を行うに至っている。
⑥ イスラム地域ではイスラムを掲げる急進武装勢力が勢力を伸ばし、ヨーロッパではこれ
までの多文化主義を排して移民を制限する運動が高揚する。荒れた状況というほかはないが、①これをどう考えればよいだろうか。
(中略)
⑦ ここでは2つの恐怖が向かい合っている。ヨーロッパではイスラム過激派ばかりでなくイスラム教徒一般によってヨーロッパ社会の安全が脅かされているという恐怖が生まれた。イスラム諸国では欧州諸国がイスラム教徒から尊厳を奪い、排除を進めているという恐怖が広がっている。恐怖が昂進すれば、それぞれの社会で相手に対する不寛容と排除が広がり、政治的急進派が台頭する。イスラム教に反する行いに対して大量殺戮(さつりく)で応じ、あるいは数の限られた過激派とイスラム教徒一般を区別せずまるごと排斥する行動が、そこから生まれる。
⑧ かつて、ラブレーの翻訳で知られるフランス丈学者の渡辺一夫は、寛容は自らを守るために②不寛容に対して不寛容になるべきかと問いかけた。幾重にも層の重なる渡辺の論考を単純化することは適切ではない。いま世界に広がるのは他者に対する不寛容が他者の存在そのものの排除を招くこと、いわば他者の排除と政治の暴力化の危険である。
⑨ 不寛容を前にしても可能な限り寛容を保たなければ他者との共存を実現することはできない。テロは排除しなければならないからこそ、排除する側は文化と価値の多元性を受け入れ、維持する必要があると私は考える。
(2015年1月20日)(出題にあたり、一部省略。)
出典=藤原帰―「不寛容に寛容たるべきか」『不安定化する世界――何が終わり、何が変わったのか』朝日新聞出版(2020年、122~125頁)
問1 課題文中の(中略)として隠された箇所には、下線部①「これをどう考えればよいだろうか」という問いに対する筆者自身の考えが示されている。下線部①の問いについて、あなた自身の考えを400宇以内でまとめて解答してください。
問2 下線部②「不寛容に対して不寛容になるべきか」とぃう問いに対する筆者の考えと対比しながら、考えを400字以内でまとめて解答してください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
