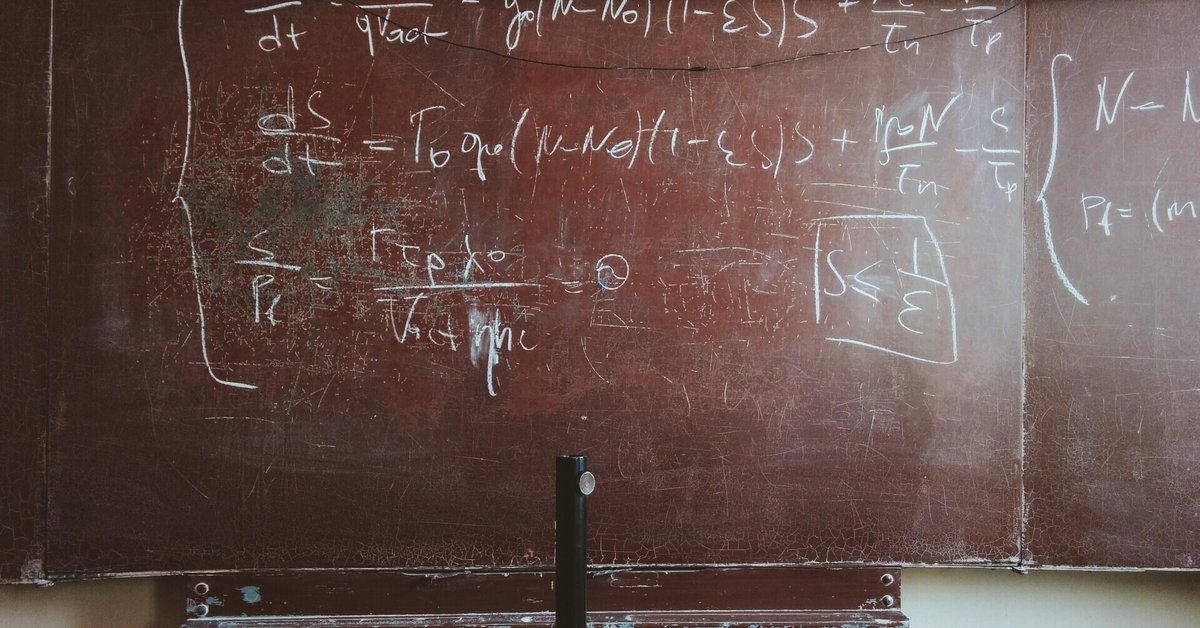
【本】エイドリアン・ベジャン「流れといのち 万物の進化を支配するコンストラクタル法則」感想・レビュー・解説
いやー、難しかった!
本書の中で僕がちゃんと理解できたのは、「解説」と「訳者あとがき」ぐらいだろう。
本文は、ほぼほぼ理解できなかった。
難しいなぁ。
でも、「解説」を読んでとても良かったことがある。それは、前著「流れとかたち」を読んだ時に抱いていた疑問が解消したからだ。その辺りの話から始めよう。
本書は、前著「流れとかたち」を受けて、さらに発展させたバージョンだと思えばいい。イメージとしては、「流れとかたち」で理論について、本書「流れといのち」ではその理論を実践的にどう使うかについて描かれる。前著「流れとかたち」でも、理論だけでなく実例も多数出てくるのだけど、本書ではとにかく、理論をどう応用・適応するか、という話がメインになる。
というわけで、個人的にはとにかく、前著「流れとかたち」を読むことをオススメする。まあ、「流れとかたち」も相当難しかったけど、本書よりはまだついていけると思う。
で、両本が扱っているのが「コンストラクタル法則」というものだ。「コンストラクタル(constructal)」というのは確か、著者の造語のはずで、要するに、それまでの科学界には存在しなかったまったく新しいものだ。
さてこれが、なかなかぶっ飛んだ主張をするのだ。
この「コンストラクタル法則」というのは、大雑把に言うと、「万物はより良く流れるかたちに進化する」というものだ。これだけじゃなんのこっちゃ分からんだろうけど、僕もちゃんと理解しているわけではないのでこれ以上詳しく説明できない。
で、この「コンストラクタル法則」の凄いのは、それこそ副題にあるように「万物」に当てはまる、ということだ。本書のタイトルにある「いのち(生命)」というのは、一般的な「生物」のことを指しているのではない。解説の木村繁雄氏の文章を引用しよう。
【生物、無生物に関わらず、流動するものという概念でとらえることが出来るすべての系(システム)を指す。それは生物内の流体循環であり、河川の流れであり、情報の流れであり、富の流れである。これらの流れを維持している体系がすなわち「生命」なのである】
一般的に、物理学の理論というのは「物質的な現象」に対して当てはまる。原子からなるなんらかの物質(生物なども含む)の動きや反応などについて、物理学の理論というのは当てはまるものだ。もちろん、「コンストラクタル法則」は、そういうものにも当てはまる。しかしこの法則は、「情報や知識がどのように伝播していくか」や「富はどのように流通するのか」など、一般的には物理の法則では説明不能なものにまで当てはまる、と主張するのだ。
それだけでも、なかなかぶっ飛んでいると言っていい。
さらにこの「コンストラクタル法則」は、「存在理由」も指摘する。例えば前著「流れとかたち」では、樹木が例に上げられていた。これまでの植物学では、「樹木がどのように地球上に存在しているのか」という問いに対して様々な答えを見出してきた。しかし「コンストラクタル法則」は、「何故地球上に樹木が存在しているのか」という、これまでの物理理論ではまず導き出せなかった問いにも答えられるというのだ。先ほど「コンストラクタル法則」を、「万物はより良く流れるかたちに進化する」と書いたが、これを樹木に当てはめると、「樹木は、大地から大気へ水を迅速に流す形に進化した」と言えるのだ。
他にもこの「コンストラクタル法則」は、陸上選手はアフリカ出身の選手が、水泳選手はヨーロッパの選手が強い理由も明らかにする。データとしては、明らかにそういう傾向があるのだが、これまでこの点に誰も説明をつけることが出来なかったのだ。
このように「コンストラクタル法則」というのは、樹木・スポーツ・言語・生物・航空機・都市・アイデア…などなど、ありとあらゆる生物・無生物に対して当てはまると主張するのだ。
前著「流れとかたち」を読んで僕は、「メチャクチャ面白い理論だけど、この「コンストラクタル法則」が科学界でどのような扱いを受けているか分からない」というようなことを書いた。この著者は、前著出版時点で「マックス・ヤコブ賞」と「ルイコフメダル」を受賞しており、この2つを共に受賞している研究者は少ないらしい。熱工学の世界で歴史に名を残す人物であり、「世界の最も論文が引用されている工学系の学者100名(個人を含む)」にも入っているという。
そんな著名な人物なのだが、どうもこの「コンストラクタル法則」は眉唾ものと受け取られていたようだ。また解説から引用しよう。
【今から20年ほど前に、ケンブリッジ大学出版局から刊行されたベジャンの『かたちと構造―工学から自然まで(※洋書タイトル省略)』を初めて目にしたときの印象を私は良く覚えている。「何て奇妙なことを始めたものだ」というのが正直なところであった。ごく一部の人を除いて大方の専門家が同じ印象を持ったことは想像に難くない。実際、当時は、国内外の熱工学関係者のあいだでコンストラクタル法則に支持を表明する声をほとんど聞かなかった。ベジャン教授はまた何か奇妙なことを始めたらしいというのが大方の見方であり、この状況は、日本では今でもあまり大きく変化していないように思う】
さらに、解説氏自身も、
【私も彼の「コンストラクタル法則」を抵抗なく受け入れるまでに、実に20年近く掛かったことを告白しなければならない】
と書いている。
いや、そうだろうなぁ、と思ったのだ。科学系の本を結構読んでいる僕の感触としては、「面白そうだけど、地雷感満載だな」という感じだった。そりゃあ、世の中のあまねくすべてのものを説明する法則というのは魅力的だ。訳者もあとがきでこんな風に書いている。
【人間の登場以前から生物はいたのだし、生物の誕生以前から地球や宇宙はあったわけだし、他のいっさいのものと同じで、人間を含めて生物も物質から成り立っており、すべては同じ世界に存在しているのだから、万物が同じ普遍的な物理法則に従っていることに何の不思議があるだろう】
確かにそういう感覚は分かるし、そうであってほしいなぁ、という希望も分かる。
とはいえ、情報も富もスポーツも何もかもぜーんぶ同じ法則で説明できまっせ、というのは、やっぱり無茶があるような気がした。とはいえ、僕は別に研究者でもなく、ただ科学が好きな一般人だ。「コンストラクタル法則」が科学の世界でどんな受け取られ方をしているのかは分からないままだった。
しかし本書を読んで、状況が大きく変わったことを知った。また解説からの引用だ。
【ベジャン教授が「コンストラクタル法則」を含む機械工学に対する貢献によりベンジャミン・フランクリンメダルの受賞が決まり、】(この「ベンジャミン・フランクリンメダル」は、米国版ノーベル賞と言われるくらい特別な賞であるらしい。受賞は2018年4月。)
【受賞理由は「熱力学と伝熱工学を融合させた熱設計の最適化、およびコンストラクタル法則による自然、工学、社会において出現する形態とその進化の予測に貢献した」と簡潔に記されており、「コンストラクタル法則」の提唱も重要な受賞理由となっている】
【これまで「コンストラクタル法則」に関する論文は、過去20年間の累計が5000を超えたと報告されている。5年前には200か300と聞いていたから大変な増えようである。イギリス政府が、政府と国民のあいだの情報伝達問題についてベジャン教授に意見を求めたことも知られている】
著者は「コンストラクタル法則」を1996年に発表したから、20年かけてようやく支持されるようになった、ということだろう。
今ではこの「コンストラクタル法則」は、生物学、政治学、経済学、都市計画、地球科学などの諸分野で、多くの賛同者を獲得しているという。本当に、これほど広範囲で適応可能な法則があって、しかもそれが今更提唱される(もっと以前に誰かが発見していたわけではなく、ということ)というのも驚きだ。
正直、著者自身の説明は難しすぎてなかなか手に負えないが、いつか「コンストラクタル法則」についてさらに噛み砕いて説明してくれる一般向けの本が出たらちゃんと読んで理解したいと思う。
サポートいただけると励みになります!
