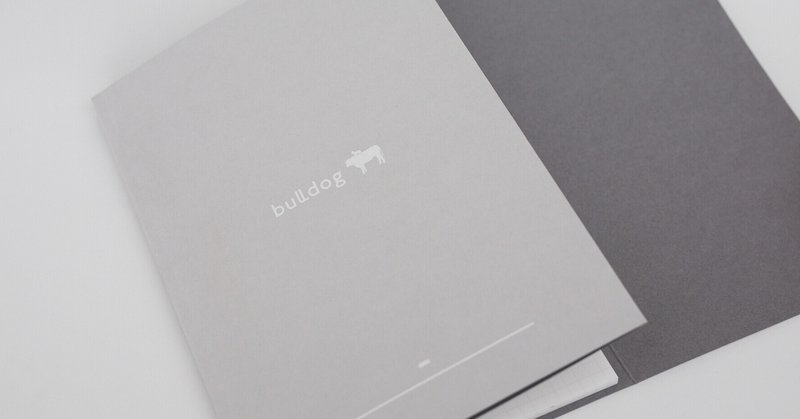
オリジナルノートの仕様について
オリジナルノートを作りました。
制作のきっかけや経緯は以前の記事で書かせていただきました。
今回は、ノート自体の仕様の詳細の紹介させていただきます。
ポイントは以下の4点です。
糸かがり
次に、製本についてですが、開きがとてもよく、強度にもすぐれた「糸かがり」という製本方法で作られています。開いたときに、平たく開くことを優先して糸かがりを選びました。

また、この製本は中国から平安時代に伝わってきたとされ、江戸時代から特に発展したと言われています。日本の古い書物などに使用されている和綴じと呼ばれるものです。
商品としては多少手間やコストのかかるものづくりかもしれませんが、機能としては優れていて、昔からの伝統的な技法を絶やさない意味でもプロダクトにこの手法を取り入れたかった。
ガンダレ製本
表紙はガンダレ製本になっています。

ガンダレにすることで、打ち合わせ中に書いたメモを隠したり、しおり代わりとしても使えます。
また、表紙が本紙より少し大きいサイズになっており(チリ付き)、本体を保護してくれます。持ち歩いても傷みにくい作りになっています。
ガンダレ製本の仕様を生かしてノート片側の記述内容が第3者に見られないようにしました。クライアントとの打ち合わせで、別のクライアントとの打ち合わせのメモが見えてしまうことが気になる方も多いと思います。
リングノートでも解消できますが、リングに手にあたることでストレスになる方もいると思い、この方法を採用しました。

ガンダレの製法メリットを生かして、内側には定規のプリント、もらったショップカードや名刺を挟むことができるスリットを入れた遊びを入れています。
長く快適に使ってもらうために、長く保存してもらうためにガンダレの耐久性の強さを生かし、本紙を痛めないチリの仕様の新しいミックスによって実現しました。
方眼
方眼は、5㎜方眼と10mm方眼にし、色もグレーの濃度を変えています。
方眼紙については書く文字や図形と方眼紙の印字が重なって見えないように出来るだけ薄く印刷しています。

そして、5mm方眼ピッチなんですが、10mm方眼のピッチと印刷濃度を変えることで使用用途によって使い勝手がよくなるように考えました。5mmが同じ濃度だと10mmの感覚が見えずらくなるためです。10mmピッチでも文章を記述できたり、図形を描くときにもメモリが追いやすくなっています。
そして、色の当たる印象や雰囲気にもこだわって色選びをしています。何度も様々なパターンで試し刷りをし、日にちや天気を変えてどの方眼紙が良いかチェックしています。
これはあくまで自社のメンバーがいかに使いやすいかにこだわって使っています。きっと同じ境遇や気持ちの方もいらっしゃると思っています。
書いたものが探しやすくなるために、タイトルと日付の入力欄も入れています。こちらも意外に備わっていないものです。
紙
本文用紙は、npi上質90㎏(菊/T 62.5㎏)を使っています。
ペンの引っかかりが少なく書きやすい紙です。筆記具を選ばないので、ボールペンやサインペン、鉛筆でも書きやすいです。
1枚あたりの厚さも、使いやすさを考えて作られています。
様々な紙に書き込んで鉛筆、ペンの滑り、消しゴムで消した時の後など検証しました。

お店から聞いた話ですと、紙の色は黄色身のホワイトが市場では多いようですが、このノートは白で綺麗で優しい清涼感のあるものにしています。使っていくと黄変の恐れがあるので、他は最初から黄色っぽい白を選んでいるのかなと思いましたが、もしそうだとしても弊社はあまり気にしません。白い紙が黄色くなっていくことも楽しんでもらいたいと思っています。
表紙の紙は、トーンF CG2(オモテ)、CG5(ウラ) 46/Y、160㎏ を2枚合紙です。紙が薄いと傷みやすくなることを考慮して、敢えて2枚の紙を合紙しています。
色は、グレーに特化した紙「トーンF」を使用しています。他ではなかなかない色味になっていると思います。さらに、表裏で違う色を採用しています。紙の色にこだわったので、表紙はどうしてもこのテクスチャーと色でやりたかった。
ただし、厚みが薄いものしかなく貼り合わせの合紙にすることにしましたが、試作してみると非常に丈夫で1枚仕立てとはまた違う仕上がりと製品の品質安心感が出ました。
しかし、どうしても違和感があったので、貼り合わせている楽しさを伝える方が意味はあると思い、色をコンビネーションにしてみました。そうすることで、ノートのグレードは上がりました。非常に興味深く、面白い体験でした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
