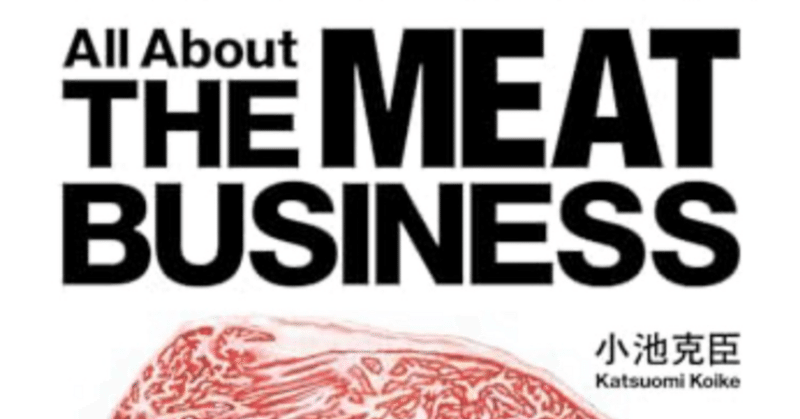
肉ビジネス 小池克臣
年間300日和牛を食べる「肉バカ」が教える、
ビジネスパーソンが知っておきたい「肉の教養」
▼日本の和牛はグッチやルイ・ヴィトンのように、世界が誇る「ブランド品」になる
焼肉やステーキをこよなく愛し、その魅力をInstagramやYouTubeで発信し続け、海外セレブにも肉を振る舞った経験のある著者による、世界に誇るべき日本の牛肉文化について紹介します。
本書は、肉にまつわるビジネスの話から、肉産業の歴史、肉の美味しさを決める要素の解明、焼肉の味わい方、海外で評価される和牛の魅力など、明日からすぐに使える豆知識を紹介する「和牛の入門書」です。
・国産牛と和牛の違い
・和牛における但馬牛の存在
・性別による味わいの違い
・肉の美味しさを決める要素
・牛肉のセリで行われていること
・肉の冷凍技術の進化
・焼肉における本当の希少部位
・美味しい焼肉の食べ方
・海外で和牛が好まれる理由
・ハラル認証への取り組み
など、ビジネスとしてだけでなく、肉を食べる、楽しむためのコンテンツが詰まった1冊です。
【読者特典】肉バカが教える、一生に一度は行ってみたい焼肉・ステーキ店リスト15選
▼本書の構成
第1章:和牛から学ぶ肉ビジネスの世界「国産牛」と「和牛」は何が違うのか
肉産業の歴史
肉産業で行われる検査 ほか
第2章:キーワードに学ぶ美味しさの世界
肉の格付けは味に関係があるのか
性別による味の違いはあるのか
経済効率と美味しさのバランス ほか
第3章:東京食肉市場に学ぶ枝肉流通の世界
国内最大の肉の取引所「芝浦市場」
枝肉のセリでは何が起こっているのか
和牛が高くなる理由 ほか
第4章:美味しさの観点から学ぶ鮮度の世界
「冷凍肉は美味しくない」は本当なのか
冷凍技術の進化
熟成の世界 ほか
第5章:カルビとロースに学ぶ焼肉の世界
カルビとロースはどこの部位か
焼肉ブームの流れ化学調味料の存在 ほか
第6章:焼肉に学ぶ内臓流通の世界
本当の希少部位はタンとハラミ
黒タンは黒毛和牛のタンだけではない
内臓処理による品質の違い ほか
第7章:生肉と火入れから学ぶ温度の世界
生食の歴史とリスク
温度が肉の美味しさを決める
薄切りの難しさ ほか
第8章:海外から学ぶWagyuの世界
世界に広がるWagyu
海外で食べられる和牛の種類
和牛とWagyuは何が違うのか ほか
第9章:これからの肉ビジネスの世界
肉産業の環境と倫理問題
減少し続ける生産農家
仲卸業者・精肉店の未来 ほか
終章:外国人に日本の肉を振る舞う
Amazonより
面白かった。
和牛をメインにその定義、生産の工程、販売などについて詳らかに説明されており、畜産の知識がない人にも勉強になる牛さんについてのボリューム本。
和牛と国産牛の違いって?
国産牛は品種、生まれた地域に関係なく、生まれてから屠畜されるまでの期間の半分以上を日本国内で育てられた牛。
海外からアンガス種を日本に連れてきて、日本での飼育期間が長ければ国産牛と表記される。
和牛は黒毛和種、褐毛和種、日本短角種、無角和種の4品種、及び4品種間の交雑種で構成されている。
又、これらの品種を国内で飼育した牛でないと和牛になれない。和牛は古来から日本に生息してたのでなく、品種改良して外国種との交雑を行い、品種として固定されてるのが大半だそうです。
さて日本人が広く牛肉を食べるようになったのは、一般的には明治時代からだそうで、明治5年1月24日、明治天皇が1200年間禁止されていた牛肉を召し上がり、その美味しさと文明開化の言葉と共に世の中に広がっていったとされていると述べられてます。
生産農家は2種類で繁殖農家と飼育農家とあり専門性も違う。
牛は生後26か月~30か月飼育されると体重は700キロ以上となり、牧場から出荷され生体検査が行われる。
国内最大の取引所、芝浦市場では月曜~金曜まで毎日約300頭の牛が屠畜されている。
屠畜後は枝肉(内臓を取り除く)を冷蔵庫で冷やし込む。
この時早いものではサシが浮かび上がるそうです。
次の工程で不可欠なのが真空パック、流通において大きな役割を果たすツールであり、鮮度、品質、販売効果の向上に大きく貢献。
真空パックは肉の鮮度を保ちながら長期保存する為の方法の1つで空気から隔離することで酸化や腐敗を防ぐ。
肉は酸素に反応し易いため、鮮度を保つために酸素を除去する必要がある。
たまに目にする光景ですがそんな役割と目的があったのですね。
たまに松坂牛を食べに行くのですが定義は雌牛が条件というのには驚きました。
雌牛が好まれる最大の特徴として、脂の融点の低さや風味などが挙げられるそうで、雌牛の脂肪には人間の体内では作ることのできない必須脂肪酸である不飽和脂肪酸の含有量が多く含まれていると。
ここが美味しさの秘訣。
ただ雌牛は雄牛と比べて霜降りが入りにくく、性格的にもデリケートで体も雄ほどは大きくはならない。
ここからも分かるように牛の飼育という観点では雌牛は繊細で難しく、必然的に飼育する生産者さんは高い技術が要求されると述べられてます。
今度食べに行った時には思いを馳せながら、感謝しながら頂きたいです。
本書ではハラルへの配慮も書かれてます。
人も国家も何かを拠り所とするならば、違いも出来てきて当然であり、この手の本を書くのに割と敬遠しがちな事に向き合っておられることは素晴らしいと感じた。
己の立ち位置をしっかり持っておられ、牛さんや肉の勉強だけでなく清々しい読後となりました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
