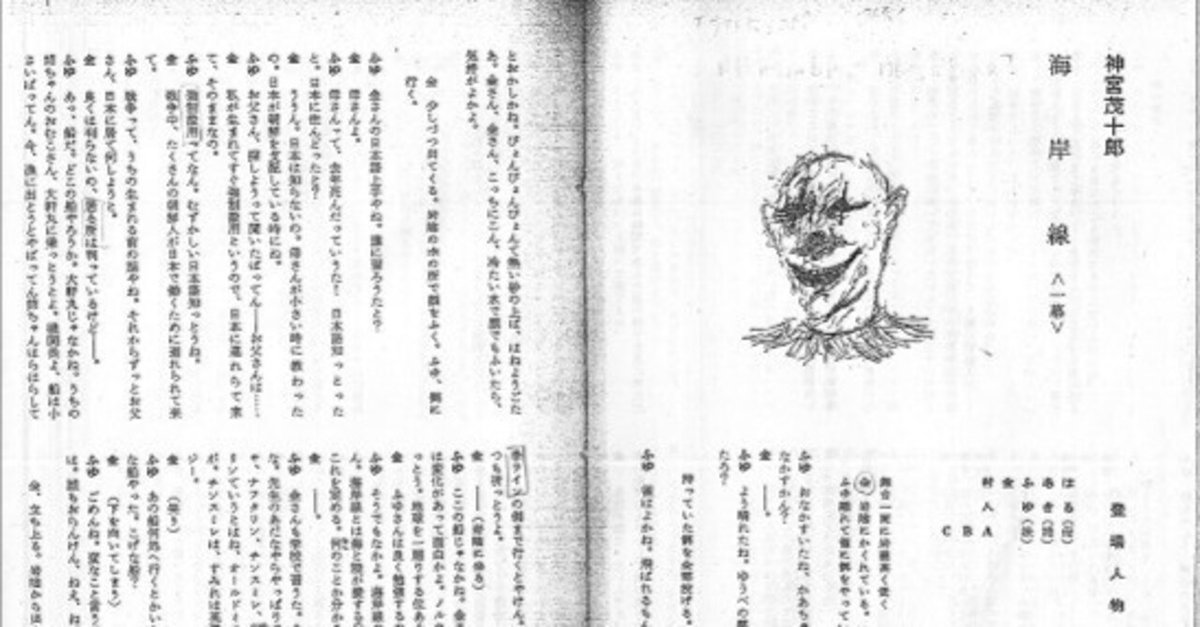
「対立者としての朝鮮人」(1965~1989)
このリストは戦後日本演劇作品のなかから筆者がサンプリングした「日本人作家が執筆した戯曲で、朝鮮人あるいは韓国人の登場する作品」を舞台公演の順序で紹介するものである。第2期は日韓基本条約を締結した1965年から、世界では冷戦が終結し日本では昭和が終わった1989年までの約25年間のことである。第2期を「対立者としての朝鮮人」とした理由は、この時期の作品では朝鮮人を「対立者」として描く傾向が見られたからである。もちろん第2期の作品すべてが朝鮮人を「対立者」として描いたわけではない。しかし第1期にみられたような積極的に日本人に協力する朝鮮人は、第2期ではひとつふたつの作品にしか見られなくなった。
サンプリング作品の朝鮮人表象における3つの変化
1945年の敗戦から2005年に至る約60年間に「日本人劇作家の執筆した朝鮮人・韓国人の登場する作品」に描かれた朝鮮人・韓国人のイメージは、「協力者としての朝鮮人」(1945~1964)と「対立者としての朝鮮人」(1965~1989)、そして「犠牲者としての朝鮮人」(1990~2005)の大きく3つにわけることができる。
サンプリング作品の朝鮮人表象におけるこのような変化は、戦後日本社会の戦争観が変化する時期と一致する。戦後日本社会の戦争観の変化に関する成田龍一(2010)や吉田裕(2005)、道場親信(2005)、吉澤文寿(2009)そして石田雄(2004)などの論考は、各研究者の関心領域によって戦争観の変化する時期設定と概念化に少しずつ違いがある。しかし1965年と1990年に戦争観が大きく変化したことでは、これらの研究者間で見解がほぼ一致する。このことから筆者はサンプリング作品の多くは戦争批判や歴史批判の強度を高める目的で朝鮮人・韓国人を登場させたのではないかと考えている。
第2期サンプリング作品の特徴
第2期サンプリング作品における特徴は第1期に主流を占めた「反戦平和」作品と「社会変革」作品に加え、日本社会における朝鮮人差別を問題視する「差別言及」作品と、日本と朝鮮・韓国との関係に対する言及を試みる「関係言及」作品が上演されたことである。
●まだ分析を終えていない作品もあることから、このリストはサンプリング作品の簡略な紹介にとどめた。
●リストは『作品名』公演主体/作者の順で表記した。上演記録のない作品は(上演記録なし)とし、雑誌などに発表された日時を基準にリストに加えた。
●金達寿(1919~97)や立原正秋(金殷奎:1927~80)など在日作家の執筆した作品も参考資料としてサンプリングしたが、これらの戯曲は「日本人劇作家が執筆した作品」を紹介するという本稿の主題からはずれるのでリストには掲載しない。
●戯曲を入手できなかった作品は「戯曲未入手」と表記した。もし当該の戯曲の存在をご存じであればぜひご連絡いただきたい。
第2期作品リスト(1965年~1989年末)
*リストは『作品名』公演主体/作者/演出者の順で表記
『海岸線』学生演劇作品/協同執筆/伊藤茂雄
雑誌『テアトロ』1965年5月号に神宮茂十郎(本名は伊藤茂雄、1928~)の名義で掲載された『海岸線(1幕)』は、日本と韓国との歴史的関係に対する言及を試みた作品である。都留達児(不詳)の書いた「海岸線上演のための手引き」(『テアトロ』1965/5、p70)によれば、この作品は前年の1964年11月に東京都立白鴎高校定時制の演劇部が演劇コンクールで上演した作品であり、演劇部に所属する女子学生たちが当時の社会的イシューだった「李ライン問題」や「日韓会談」に取材して台本にしたものを、顧問の教諭(伊藤茂雄)が戯曲としてまとめたものである。主人公の韓国人少女〈金〉は戦時中に「強制徴用というので、日本に連れてこられ」(戯曲p73)た父親に会うために日本に密航してきた。密航少女〈金〉を匿った日本婦人〈はる〉の二人の娘〈あき〉と〈ふゆ〉が〈金〉と交わす会話を通じて日本と朝鮮・韓国との歴史的関係が語られる。このように日本と朝鮮あるいは韓国との歴史的関係に対する言及を目的にした作品は第1期にはみられなかったもので、おそらく日韓会談の進展に影響されたものだえろう。なお、密航少女〈金〉は韓国から密入国したので「韓国人」だが、『海岸線』では「朝鮮人」を自称している。
『清正の婿』堂本正樹(上演記録なし)
雑誌「新文明」1966年6月号に掲載された堂本正樹(1933~)の『清正の婿』(上演記録なし)は「朝鮮征伐」に積極荷担した戦国武将の加藤清正に材をとって、日本と朝鮮・韓国の関係に言及した作品である。この〈五郎〉と〈清正〉の確執を軸にした物語に二人の朝鮮人が加わる。ひとりは朝鮮人漢方医の〈王鷺海〉であり、今一人は朝鮮人若武者〈金官〉である。漢方医の〈王〉は清正が朝鮮で矢に当たり重傷を負った際に治療して命を救った医者で、清正の立場からは大恩ある朝鮮人である。一方の〈金官〉は清正が戦闘で孤児となった朝鮮人の幼子を連れ帰って育てた若武者だ。
『清正の婿』の主人公〈横手五郎〉は清正の命を狙って失敗し死んだ木山弾正の遺児である。〈五郎〉にとって〈清正〉は親の敵だが、いまの〈五郎〉は〈清正〉の忠実な家臣である。しかし猜疑心の強い〈清正〉は〈五郎〉を信じることができない。〈清正〉は〈五郎〉に城の地下に抜け道を造る工事を命じたが、工事の完成も間近になって落盤事故が起こり〈五郎〉は命を失う。〈五郎〉の死は事故なのか、あるいは〈清正〉の策略なのか…身の危険を感じた〈王〉は〈金官〉に〈清正〉から得ていた「お墨付き」を示す。この「お墨付き」は〈清正〉が朝鮮で負傷した時に治療してくれた〈王〉に、「どんな願いでも聞き入れる」と一筆書いて渡したものだった。〈王〉は〈金官〉にお墨付きを見せて、〈五郎〉の嫁である姫と〈王〉の妻とともに朝鮮に送り返してほしいと申し出る。ところが〈金官〉は「こんなものがあっては殿のためにならぬ」と言ってお墨付きを破り捨て、〈王〉も彼の妻も姫も殺してしまう…(『新文明』1966年6月号)。
この作品の朝鮮人漢方医〈王鷺海〉は日本にとって古くから交流があり文化的にも縁の深い「朝鮮」を暗示しており、〈清正〉に育てられた朝鮮人武官の〈金官〉とは、かつて日本帝国軍人だった朴正煕を暗示している。つまり『清正の婿』は日・韓が新しい関係を結びつつある時にあって、日本が対話するべき相手は韓国ではなく朝鮮であると主張しているわけである。この当時の日本の進歩的知識人のあいだでは朝鮮民主主義人民共和国に対する評価は高い一方で、大韓民国に対する不信感はきわめて強かった。韓国に対するこのような否定的態度は1980年代の半ばまで続いた。
『まぐだらの女』演劇座/定村忠士/高山図南雄
1966年6月、劇団「演劇座」は高山図南雄(たかやまとなお、1927~2003)の演出で定村忠士(さだむらただし、1932~2001)の執筆した『まぐだらの女(3幕9場)』を上演した。九州の炭鉱町に生まれた主人公〈はな〉の戦争末期から1960年当時までの流転する人生を、5人の男たちとの関係で描写した作品である。この5人の男のうちの二人めと四人めは朝鮮人である。一人は主人公〈はな〉が敗戦直前の「京城」で出会った青年〈李〉であり、もう一人は最初の原水禁世界大会が開催された1955年の広島で出会った中年の〈李〉である。〈李〉青年は総督府の下級官吏である〈はな〉の夫の下で働く若者で、〈はな〉に植民地統治下に生きる朝鮮人の悲惨な状況を語る。いっぽう広島で出会った中年の〈李〉は戦時徴用で日本に連れてこられて広島で被爆した朝鮮人被爆者である。中年の〈李〉は朝鮮人が労働徴用されて日本に来たが、核兵器の被害者となったことの不条理を語る。しかし〈はな〉は彼らの言うことが理解できない。中年の〈李〉と出会ったことで、かつて「京城」に暮らしたことを懐かしがるだけである。『まぐだらの女』の作品意図は戦争批判にあるが、〈はな〉と二人の朝鮮人との対話は敗戦を経てもなお歴史を顧みることのない戦後日本の姿を浮き彫りにする。作品が執筆された当時の日本社会では「戦争体験の風化」(吉田、2005)が問題になっていたが、おそらくこのような社会的雰囲気に対する批判が根底にあったと考えられる。
『地の群れ』青俳/木村光一 脚色・演出
1966年11月、劇団「青俳」は木村光一(1931~)の演出で『地の群れ』を上演した。この作品は井上光春(1926~92)が部落差別と朝鮮人差別に加えて原爆被災者に対する差別をも描いた『地の群れ』を木村光一が脚色した演劇作品である。主人公の日本人青年〈宇南親雄〉が炭鉱で働く朝鮮女性〈宝子〉を妊娠させ、〈宝子〉の姉の〈宰子〉からそのことを詰問される。しかし〈親雄〉は身に覚えがないと言い張り、これが原因となって〈宝子〉は自殺する…という、小説にあるとおりのシーケンスが戯曲でも再現されている。しかし早稲田大学演劇博物館に所蔵されている青俳上演台本では、この〈宰子〉と〈親雄〉の場面が「手書き」で台本の余白に書き加えられている。ことによると、当初は朝鮮人に関する場面は劇化するつもりはなかったのかもしれない。なお、早稲田演劇博物館所蔵の台本は複写不可となっていた。
『白い夜の宴』民藝/木下順二/宇野重吉
1967年5月、劇団民藝は木下順二(1914~2006)の『白い夜の宴』を宇野重吉(1914~88)の演出で上演した。戦時中は左翼青年だったが獄につながれ「転向」した〈父〉を中心にして、戦時中は内務官僚を勤めた〈祖父〉と安保闘争に加わって友人を失い傷ついた長男〈一郎〉がそれぞれの「昭和」を語る…という内容である。この作品は「日本人の全体にかかわっている戦争責任の問題と、わが国における転向がヨーロッパ市民の転向と相違する特殊性を追及」(「民藝の仲間97号」p6)した作品であり、「多くの劇作家が触れなかった朝鮮人問題を書き、それを、現在ブルジョア生活を送っている人物に投影させた。これは意識のドラマだった」(『演劇年鑑』1967、p42)と評価された。この作品には〈父〉が戦時中に監獄で出会った〈小指の無い朝鮮人〉が登場したが、この〈小指の無い朝鮮人〉は現在(物語では1960年代中期)の〈父〉に過去を想起させる記号として機能する。この作品も前述した『まぐだらの女』と同様に日本社会の「戦争体験の風化」を問題視した作品で、「全国戦没者慰霊祭」の催行や「建国記念日」の祝日制定などにみられる日本社会の戦前回帰に対する批判を目的にしたと考えられる。
『あたしのビートルズ』自由劇場/佐藤信 作・演出
1967年8月に劇団「自由劇場」が上演した佐藤信(1943~)作・演出による『あたしのビートルズ』は、1958年8月に起きた「小松川事件」を素材にした作品である。この作品には朝鮮人の若い男性〈鄭〉と母親が日本人で父親が朝鮮人の若い女性〈桂(ケイ)〉、そして〈日本人の男〉が登場して小松川事件を再現する劇中劇が行われる。その劇中劇の場に男女4人で構成された「にせビートルズ」が加わって舞台は進行する…。じつは主人公の〈鄭〉は日本人が扮した「にせ朝鮮人」である。つまり『あたしのビートルズ』は日本人が仮装した朝鮮人を日本人が殺すというストーリー展開で、「小松川事件」の犯人に対する日本人による助命嘆願運動が帯びる欺瞞性を批判しようとする。この作品は自由劇場での上演に先立って同年4月、「早稲田小劇場」が鈴木忠士(1939~)の演出で『あたしのビートルズ・或いは葬式』という題名で上演した。早稲田小劇場が上演した戯曲は未入手。
『オモニの銃』(戯曲未入手)
1967年9月に大阪で開催された「日鮮文化交流の夕」で、ブレヒトの『カルラールのおかみさんの銃(Die Gewehre der Frau Carrar.)』を改作した『オモニの銃』が上演された。『テアトロ』(1967/11、p64)によると、演出家で演劇史家でもある大岡欽治(おおおかきんじ、1906~1992)が原作の背景を「1950年の朝鮮戦線に移しかえ、仁川付近の人民たちの蹶起の姿」として描いた作品であり、「夫と長男を抗戦で失ったオモニが夫の残した銃をとって起つ、いわば祖国の母のものがたり」である。舞台ではアジ・プロのもつ形式主義が目立ったと評された。
『地の群れ』演劇座/脚色・竹内敏晴/程嶋武夫
1967年5月、劇団「演劇座」は竹内敏晴(1925~2009)の脚色した『地の群れ』を程嶋武夫(ほどしまたけお、不詳)の演出で上演した。この作品も井上光春の小説原作に描かれたとおりに朝鮮人の登場する場面を台本に記載した。原作小説は朝鮮人差別に対する言及を目的にした作品ではないことから、この戯曲もとくに朝鮮人差別を問題して脚色したものではないと考えられる。
『ヒロシマについての涙について』劇団三十人会/ふじたあさや/秋浜悟史
1968年5月、劇団「三十人会」(1960~72)は秋浜悟史(あきはまさとし、1934~2005)の演出でふじたあさや(1934~)の執筆した『ヒロシマについての涙について』を上演した。この作品は1960年代中期に高まりつつあった「原爆」に対する批判を背景にして、原爆に関するさまざまな言説をさながらコラージュのように散りばめた作品である。この作品には「外国人」だという理由から原爆被害や生活に対する補償を拒否される〈朝鮮人被爆者〉が登場し、日本社会の朝鮮人被爆者に対する差別を批判した。この当時、NHKでは『原爆と私』シリーズ(1967)を放送し、TBSは『原爆スラム』(1968/8)で朝鮮人被爆者をテレビ画面に広島市基町の原爆スラムの朝鮮人被爆者を登場させた。
*朝鮮人被爆者に対する日本社会の対応は、原爆の投下されたその瞬間から一貫して冷たかった。当時、広島と長崎には多数の朝鮮人が居住しており、彼らは直接被爆したり、あるいは救援活動のために市内に入って間接的に被爆するケースもあった。しかし日本人被爆者とは異なり、朝鮮人被爆者は医療や福祉の面で差別されたままにされたのである。
『私は海峡を越えてしまった』劇団東演/八田元夫 作・演出
1968年5月、劇団「東演」は八田元夫(はったもとお、1903~76)の作・演出で『私は海峡を越えてしまった』を上演した。この作品は関東大震災の時に執拗に行われた「不逞鮮人」探しで幕を開ける。読売新聞(1968/5/16)「東演が大正期の民族差別描いた作品上演/私は海峡を越えてしまった」によると「大震災直後の混乱した時代背景の中で起きた民族差別の実態を描き、今日なお日本人の内部に潜むこの問題を追及」した作品である。主人公の〈南二郎(南二植)〉は日本軍人と朝鮮女性のあいだに生まれた「半日本人」である。自警団に追われた〈南〉をかくまったのは大陸商人の〈川並久蔵〉だが、じつは〈川並久蔵〉の長女(養女)〈川並京子〉も朝鮮女性と日本軍人のあいだに生まれた「半日本人」だった。『八田元夫戯曲集』(1977)によると、作者は〈南〉と〈京子〉の二人を物語の軸にして「日本の帝国主義的朝鮮侵略が産み落とした半日本人の主人公二人の苦悩と、それを乗り越える闘い」を描き、「欧米文化に対する劣等感の裏返しが、東洋諸民族に対する優越感となって、父祖の代の征服意識を無意識に受け継ぐことで加害者になっている。これをはっきり抉りだしたかった」(前掲書pp196~197)という意図で書いた作品である。
『日本への白い道』演劇集団華/堂本正樹/演出者不詳
1968年5月、劇団「演劇集団華」が上演した堂本正樹(1933~)の『日本への白い道』は、1931年に植民地期の朝鮮で起きた「朝鮮排華騒動」を背景にした作品である。「朝鮮排華騒動」とは満州の万宝山で起きた中国人と朝鮮人が衝突した「万宝山事件」(1931)の報道に起因して、朝鮮各地で中国系住民に対する暴力行為が起きた事件である。主人公は〈金利三〉という日本で教育を受けた朝鮮人新聞記者で、排華騒動の背景となった報道を行った記者という設定である。作者が自ら「昭和史の曲がり角に人間の異様な情念を置き、歴史を自分の手で縫い上げようとする女の、敗北を描いている。政治をエロスの世界から見た点に、筆者の視点がある」(『菊と刀―堂本正樹戯曲集』思潮社、1970)と説明した。初演から10年後の1977年10月に作者の堂本自身の演出によって再演された。
『おんなごろしあぶらの地獄』自由劇場/佐藤信 作・演出
1969年5月、劇団「自由劇場」は佐藤信の執筆した『おんなごろしあぶらの地獄』を上演した。佐藤信の作品解説『富士山見えた―佐藤信における革命の演劇』(白水社、1983)を書いたデイヴィッド・グッドマン(1946~2011)によれば、『おんなごろしあぶらの地獄』は佐藤の前作『あたしのビートルズ』(1967)と同様に、日本人と在日朝鮮人の関係に対する言及を試みた作品である。主人公の〈カネコ・ヨシコ〉は「ガソリンスタンドを経営する日本生まれの朝鮮人」であり、同時に10人の仲間たちとともに街の中を疾走するオートバイグループのリーダー〈聖・お吉〉でもある。〈聖・お吉〉と10人の仲間たちは、それぞれ船の底のいけすに身体を隠して海を渡ってきた。このために体には魚の匂いが染みついている(戯曲p147)。〈与兵衛〉も〈聖・お吉〉の仲間の一人だが、彼は魚のにおいがしないので他のメンバーから信用されていない。しかも〈与兵衛〉は「女狩り」という「過去の業病」(戯曲p146)を患っている。
〈聖・お吉〉たちは自分たちをこの街から救い出してくれる「エンジェル」を待っている。しかし「エンジェル」が街にやってくるという話を持ち出したのは外ならぬ〈与兵衛〉だ。登場人物の一人である〈耳彦〉によって、海の向こうのオートバイ集団「ヘルスエンジェルス」の消息が伝えられる。もとは単なる反社会的集団に過ぎなかった米国の「ヘルスエンジェルス」は、しかし米国社会が右傾化することによって徐々に社会的地位が与えられていく。作品の冒頭からラストシーンまで断続的に語られるこのエピソードは、おそらく日本社会の右傾化も暗示しているのであろう。作者は1960年代の右傾化する日本社会にあって、再び「過去の業病」が日本社会で再発することを危惧したのではないだろうか。
『神通川-痛き歴史のなかより』青俳/本田英郎/今井正
1969年5月、劇団「青俳」が映画監督である今井正(1912~91)の演出で上演した本田英郎執筆の『神通川-痛き歴史のなかより』は、富山県下で起きた環境汚染を問題にした作品である。毎日新聞(1969/6/2)「奇病への重々しい告発/劇団青俳公演」では「富山県下で起こった公害イタイイタイ病の実態を追及し、責任者を告発しようとした劇」であると紹介された。この作品では戦時中を回想する場面で、鉱山から逃亡してきた朝鮮人〈趙竜生〉が登場する。村の復員兵〈庄作〉は〈趙竜生〉を捕まえて駐在に引き渡そうとするが、母親の〈そよ〉は止やめさせようとする。〈そよ〉は村を流れる川が白く濁っていることや村人の健康不良などが鉱山に原因があるとうすうす感じている。したがってそのような鉱山に朝鮮人労働者を送り返すことに反対する。しかし〈庄作〉は復員兵の面子を保とうと〈趙竜生〉を駐在に引き渡す。鉱山に連れ戻されることを恐れた〈趙竜生〉は、駐在が目を離したすきに川に身を投げる…という場面が挿入された。作者の本田英郎はシナリオライターとして既に名のある人物で、殺人未遂を犯した在日女性の弁護を通じて朝鮮人差別を告発する『半日本人(ぱんちょっぱり)』(NET『判決』シリーズ、1964/7)や教科書問題を扱った『佐紀子の庭』(同上)、あるい「在日朝鮮人がなぜ祖国へ帰れないかをテーマにした」『北からの人』(同上)など社会性の強い作品を書いた。
『ただ海燕だけが』京浜協同劇団/黒沢参吉/細田寿郎
1969年11月、川崎に本拠地を置く京浜協同劇団は劇団代表であり劇作家の黒沢参吉の執筆した『ただ海燕だけが』を上演した。この作品は1938年から1941年にいたる戦時期の川崎を舞台に、劇団「海燕」の劇団員が戦争を批判しつつも戦争による社会の変化に翻弄される姿を描いた。この作品には朝鮮人〈金山忠幸〉が登場し、「海燕」の劇団員たちと心を交わす姿が描かれた。劇中で劇団を辞して民族独立運動にかかわる〈金山〉の台詞を通じて、朝鮮人としての来歴や日本社会の朝鮮人差別などが語られる。
『もう一人のヒト』民藝/飯沢匡 作・演出
1970年4月、劇団民藝は飯沢匡の作・演出で『もう一人のヒト』を上演した。この作品は現在の天皇は偽物であるという「北朝偽天皇説」を素材にした喜劇作品である。東京の下町に住む皮革職人の〈杉本〉には先祖代々伝わる家宝があった。それは自分が天皇であることを証明する神璽だが、〈杉本〉は生活のためにこの家宝を〈金田〉という朝鮮人の屑屋に売り払った。このことを知った〈香椎宮為久〉は「北朝偽天皇説」を主張する〈小沢中将〉を利用して、皮革職人の〈杉本〉を天皇に祭り上げようとする。その理由は連合軍によって廃嫡されるかもしれない皇統を守ろうとする意図からだった。天皇制を信奉する日本人には神璽は重要な意味を持つが、朝鮮人〈金田〉にとっては単に金銭取り引きの対象にすぎないことが描かれた。飯沢匡は『ヤシと女』(1956)で民主社会として出発した戦後日本社会で徐々に復活する天皇制を批判的に描いたことがあるが、この『もう一人のヒト』も万世一系の天皇制というものに疑問を投げかけたものではないだろうか。
『黒と白と赤と青の遊戯』劇団同人会/高堂要 作・演出
1970年11月、劇団「同人会」は高堂要(高田要、1932~2001)の『黒と白と赤と青の遊戯』を上演した。主人公は「被告」あるいは「彼」と呼ばれる若い男の〈死体〉であり、舞台はこの〈死体〉の生き方を裁くための法廷である。そして「被告」を知る4人の証言者によって生前の人物像を語る裁判として展開する。しかし証言者らによると〈死体〉はかつて「暴力革命家」であったり「社会変革を志したクリスチャン」であったり、あるいは「刹那主義的に現在を生きている行動主義者で愛の革命家」であったり「冷血な殺人者」であったりする。このように証言者ごとにまったく異なる人物像が語られるが、しかし〈死体〉はそれらを否定せずにすべてを受け入れる。
高堂の戯曲集『酔っ払いマルメラードフ』(花神社、2000)に収められた解説「高堂要の劇世界」(三枝禮三牧師)によると、この『黒と白と赤と青の遊戯』は「死者の国」を舞台にして「遊びをテーマに飽くまで遊んで見せる芝居」である。解説者はこの作品をドストエフスキーの『悪霊』になぞらえて、主人公の〈死体〉を『悪霊』の主人公スタヴローギンに見立てる。そして〈死体〉は「革命家」だったと語る証言者〈C〉はスタヴローギンに「暴力革命家」を期待した『悪霊』の登場人物ピュートルであり、「社会変革を志したクリスチャン」だと証言した〈D〉はキリスト教的精神革命を説くスチェパンである。〈死体〉の恋人であり「愛の革命家」だと証言した証言者〈E〉は汪溢する情欲に心酔したシャートフであり、「冷血な殺人者」だと証言したヤクザの〈F〉は無神論的超人論に心酔したキリーロフである。そして解説者は芝居の最後に死刑に処せられた〈死体〉が「まっすぐ、舞台上方に、上がっていって、消える」(戯曲p184)場面から、これは「現代世界におけるほんとうの生き方を問い直している」作品であるとする。
しかし証言者〈C〉によると〈死体〉の父親は朝鮮半島から強制連行されて来た朝鮮人であり、母親は半聾唖者であった。そして〈死体〉は「父親が外国人であり、母親が不具者だということで、いいところには就職できず」、働きながら夜間高校に通ったという(戯曲p149)。つまり〈死体〉の人物形象化のモデルとなったのは1958年8月に起きた「小松川事件」の李珍宇(1940~1962)である。このことから〈死体〉を語るさまざまな「証言」は、在日朝鮮人に対して恣意的にレッテルを貼る日本社会を批判しているのかもしれない。
『ひろしまの冬』上田修(戯曲未入手)
1970年12月に広島公会堂で上演された上田修の『ひろしまの冬』(演出者など詳細は不詳)は朝鮮人被爆者に対する差別問題を主題にした演劇作品である。「韓国にいる朝鮮人被爆者の実態を取材した広島のあるカメラマン(彼も被爆者であるが)が、その氷つくような現状を知ることによって、これまで自分の意識の中にのぼってきようのなかった<日本人>という存在、侵略の歴史を背負い再び加害の刃をふりかざそうとしかねない<日本>の中の自分という存在をはじめて問われる。そしてそこから逃げようとして逃げ切れず、さりとて立ち向かう方法も見出せぬままに激しく苦悩する…(「演劇会議」17号p35)」というストーリーである。この作品は広島の地域劇団が中心になって上演したもので、1980年代に東京で再演された記録がある。戯曲を入手できなかったので朝鮮人登場人物がどのように描写されたのかわからない。
『ココアのひと匙』霜川遠志(上演記録なし)
「新劇」1971年1月号に掲載された霜川遠志(1916~91)の『ココアのひと匙』は、日本社会の変化にともなって九州の小さな炭田が凋落していく姿を描いた作品である。日本人炭鉱夫の〈灰野庄作〉を主人公にして、庄作の妻〈はぎ〉が世間から忘れられていく炭鉱を回想して語るという展開になっている。この作品のなかで1930年代の炭鉱労働者の生活を語る二幕第一場と第二場に、朝鮮人炭鉱夫の〈金〉とその妻の〈玉〉が登場した。〈金〉の生まれ育った朝鮮の田舎には兄弟が多く、自分の耕せる畑がない。そこで日本の炭鉱へ出稼ぎにきて〈玉〉と出会って所帯をかまえ、炭鉱夫仲間と貧しいながらも楽しく暮らしている。朝鮮人〈金〉は人の良い炭鉱夫であり、妻の〈玉(たま)ちゃん〉の尻に敷かれる頼りない男として描かれている。しかし彼らは主人公の〈庄作〉を巻き込んだ悲惨な炭鉱事故を経験したことから、夫婦で朝鮮へ戻ることにする…。作家の関心はかつて近代化の原動力となった石炭産業が日本の産業構造の中核からはずれて寂れ行くプロセスの描写にあり、この作品の日本人登場人物と朝鮮人登場人物はともに貧しいながらも助け合って暮らす労働者として描写された。
『予告の日』民藝/小林勝/宇野重吉
1971年10月、劇団民藝は宇野重吉(1914~88)の演出で小林勝(1927:晋州~71)の『予告の日』を上演した。この作品は「わたしたち日本人の意識の底にどす黒くよどんでいる朝鮮人や『部落』に対する差別観をするどくえぐり出した」(公演プログラム、p6)作品で、「非政治的な日常生活の中にさえつらぬいている〈差別〉が問題」(前掲、p8)とした作品である。主人公の平凡で内気な女子大学生〈假屋園圭子〉は大学の「抵抗権研究会」から兵役を拒否して日本へ密航してきた韓国人青年をかくまってほしいという依頼を受けた。ただしその依頼を承諾して韓国青年をかくまうには家族全員の同意が必要だ。そこで〈圭子〉はこの依頼を一緒に暮らす〈祖父〉と〈叔父〉に相談するが、このことがきっかけとなってそれまで平穏だった假屋園家の日常生活の裏面に隠蔽されていた日本人と朝鮮人の関係が徐々にあばかれていく。つまり〈非在の韓国人青年〉を狂言回しにして、日本社会に遍在する朝鮮人に対する差別を描き出そうとした作品である。小林勝の『午後8時』(「新日本文学」1970/10、pp6~38)という短編小説を劇化した作品であり、こちらの小説の方がより主題が鮮明である。
『二都物語』状況劇場/唐十郎 作・演出
1972年春、劇団「状況劇場」は唐十郎(1940~)の作・演出で『二都物語』をソウル(3月)と東京(4月)で上演した。『唐十郎全作品集』2巻に寄せられた扇田昭彦の「解題」では、この作品は「戦争によってさすらうことを強制された韓国と日本の民衆の物語」と紹介された。「朝鮮海峡を渡ってきた」〈リーラン/ジャスミン〉が、「内地の人らしい名の」〈内田一徹〉を〈李容九〉として召喚しようとする物語である。李容九(1868~1912)は国家主義者の内田良平(1874~1937)に口説かれて日韓併合に協力した朝鮮側人物とされているが、この作品は〈リーラン〉が〈一徹〉を〈李容九〉として覚醒させることで、あたかも日韓併合の歴史を逆転させようとするかのようである。しかし〈リーラン〉に憲兵の父親を殺された、戸籍を求めてさまよう日本人たちが〈一徹〉をつかまえて離さない…。
『身世打鈴』新屋英子 作・演出
1973年4月、劇団「関西芸術座」に所属する演技者の新屋英子(1927~2016)が自作の一人劇『身世打鈴』を初演した。この作品は戦時中に夫の後を追って日本へ渡ってきて主人公〈申英淑〉が、日本で生きていくなかで経験したさまざまな苦労を語るという趣向の作品である。在日女性たちのオーラルヒストリーを集めた『身世打令』(東都書房、1972)を土台にして構成した作品で、新屋が「朝鮮人と間違えられた」と自慢するこの舞台は好評を得て上演回数は2000回を数えたという。
『修羅と死刑台』民藝/大橋喜一/若杉光夫
1973年8月、劇団民藝は若杉光夫(1922~2008)の演出で大橋喜一の『修羅と死刑台』を上演した。この作品は「小松川事件」の犯人と思わせる〈呂珍〉と「連続射殺魔事件」(1968)の犯人に範をとった〈富雄〉、そして『罪と罰』の主人公〈ラスコーリニコフ〉の3人が登場する。彼ら3人がそれぞれの犯罪に対する考えを語り合う非写実的な舞台形式を通じて、〈呂珍〉の犯した犯罪の背景にひそむ日本社会の朝鮮人差別を探っていくという手法をとった。
『海の牙』状況劇場/唐十郎 作・演出
1973年9月、劇団「状況劇場」は唐十郎の作・演出で『海の牙』を上演した。舞台は当代(上演は1973年)の日本でありながら、しかし時間は過去と現在が入り乱れて展開する。『唐十郎前作品集』第3巻に掲載された扇田昭彦の「解題/海の牙」によれば、この作品は前作の「『二都物語』や『ベンガルの虎』の延長線上につらなる二幕劇で、文明批評的な色彩がよくあらわれ」ており、「朝鮮、日本本土、沖縄の三角地帯を、民衆レベルにおいてひとつながりの地域として考察する」作品であるという。主人公「大和パンマ(パンパンで按摩、戯曲p262)」の〈瀬良皿子〉は「チェジュドのカツラ」とチョゴリを身につけて「朝鮮パンマ」になる。ウェノム(日本人)とチェジュド(朝鮮人)の混血とされる〈名和四朗〉は朝鮮人の母を慕う心優しい少年だが、日本語を使うときは詰め襟学生服を着た国士館の学生となって朝鮮人を迫害する。扇田が指摘した「朝鮮と日本の本質的な類縁性に寄せる唐十郎の意思」(前掲書)は、カツラの有無や衣服で朝鮮人と日本人を瞬時に入れ替えることで提示される。あるいは〈名和四朗〉の朝鮮人と日本人に対する相反した態度もまた類縁性に起因する近親憎悪を描いたものなのだろうか。
『蛇姫様』状況劇場/唐十郎 作・演出
1977年4月、劇団「状況劇場」は唐十郎の作・演出で『蛇姫様』を上演した。『唐十郎全作品集』第6巻に寄せられた扇田昭彦の「解題/蛇姫様」によると、この作品は「〈奈蛇(ナジャ)〉と言う実に多義的なことばのイメージに人間の帰属のありかを問う〈帰化〉のテーマがからみあい、ダイナミックな劇構造をつくり出した三幕劇」である。主人公〈あけび〉の母〈シノ〉は朝鮮戦争のさなか、戦死した米兵を日本へ運ぶ死体運搬船に乗って日本へ密航してきた。しかしその船で〈李東順〉を名乗る日本人〈権八〉に犯されてできた子供が〈あけび〉だ。この秘密を知るのは死体運搬船に同乗する教戒師の〈バテレン〉と、小倉に上陸した〈シノ〉を助けた〈伝次〉だった。やがて〈シノ〉が死んで一人残された〈あけび〉は日本に帰化するために、身元保証人をさがして東京へ出る…というストーリーである。
*この作品が筆者の関心を引くのは、前作の『二都物語』と『海の牙』では朝鮮語や朝鮮という表現が頻繁に使用されたが、この作品では朝鮮語が「ハングー語」というあいまいな表現になっていることである。作家にとって朝鮮あるいは韓国はいまや後景に退いたのだろうか。
『燕よ、おまえはなぜ来ないのだ』民藝/大橋喜一/米倉斉加年
1977年6月、劇団民藝は米倉斉加年の演出で大橋喜一の『燕よ、おまえはなぜ来ないのだ』を上演した。この作品は岩波書店の月刊雑誌「世界」に連載された『韓国からの通信』(1973~1988)を土台にして書かれた作品である。雑誌に連載された記事の内容を取り出して台詞にしたが、もとのテキストの持つ意味をそのまま伝達したいという意図から、いわゆる戯曲としてではなく資料をもとにした「報告劇」あるいは「記録劇」として企画された(「演劇会議」(1997年8月号、p43)。
『幻のトラック』民藝/矢田喜美雄/若杉光夫
1977年7月、劇団民藝は新聞記者出身の作家である矢田喜美雄(やだきみお、1913~90)の執筆した『幻のトラック』を民藝の若杉光夫の演出で上演した。この作品は1955年に静岡県三島市で起きた殺人事件である「丸正事件」を素材にした作品で、殺人犯とされた在日朝鮮人の李得賢と日本人の鈴木一男は冤罪だったことを〈八田聞助〉という登場人物が解きほぐしていくという趣向で描かれている。この作品の主題は「丸正事件」を冤罪だとして闘った正木ひろし弁護士(1896~1975)にスポットを当てたもので、殺人犯とされた在日朝鮮人の李得賢は、獄中で正木弁護士に感謝の意を込めて手紙を書く場面のみが描かれた。
『アレン中佐のサイン』民藝/庄野英二/高橋清祐
1977年8月、劇団民藝は高橋清祐(1932~2016)の演出で庄野英二(1915~93)の『アレン中佐のサイン(2幕)』を上演した。朝日新聞(1977/8/19)「庄野英二氏の戯曲、民藝が連続上演へ」によれば、この作品はインドネシアとニューギニアのあいだに広がるバンダ海「オモコロ島」の「イギリス人、オランダ人を収容する日本軍の捕虜収容所を舞台に、戦火をこえたさわやかな人間愛」を描いた作品である。日本が降伏して日本兵と連合軍捕虜の立場が入れ替わる。しかも捕虜監視員をつとめた日本兵は捕虜虐待の罪で戦犯になるかもしれない。「アレン中佐のサイン」とは連合軍捕虜先任官のアレン中佐が、日本軍の〈椎崎大尉〉らは捕虜の扱いに最善を尽くしたという証明書に残したサインのことである。作品では描かれなかったが、このサインのおかげで〈椎崎大尉〉らは戦犯として裁かれることは無かったのであろう。
『アレン中佐のサイン』では捕虜を過酷に扱う日本軍の高級将官と、彼らに対して反感をつのらせる〈椎崎大尉〉らとの間に対立軸が設定されている。そして〈アレン中佐〉と連合軍捕虜および島民は「良心的」日本兵の「善行」を説明する側に配置される。この作品に登場する朝鮮人日本兵〈金石一等兵〉もまた、「良心的」日本兵を戦争犯罪から免責する側にある。〈金石〉は村一番の才児だったことから村の金で中学校を卒業し、その後は日本の金で東京留学を行い大学を出た。そしてその代償として日本軍にむりやり志願させられた(戯曲p2-26)。しかし日本軍が敗戦した時に〈金石〉は日本軍隊には怨みはあるが、ともに苦労した日本兵らには恨みはないと語る(戯曲p2-27)。
作者の庄野は実際に軍人としてジャワの捕虜収容所に勤務しており、敗戦後の一時期に戦犯として捕虜生活を送った。この体験をもとに「捕虜収容所に勤めさせられていたというだけで、戦後、戦犯として処刑された下級兵士のための証言」としてこの作品を執筆したという(読売新聞、1977/8/15)。庄野には「確かに捕虜を虐待した悪い日本兵も、いるにはいました」(前掲の記事)という視点はあったが、しかし作品では日本がアジア諸国を侵略したという事実は捨象されている。『アレン中佐のサイン』は第1期の軍部批判作品と同様に、被害者意識による戦争批判作品と言えよう。なお、この戯曲の底本は庄野が執筆した児童向けの小説『アレン中佐のサイン』(岩波書店、1972)だが、この小説には「金石一等兵」は登場しない。
『ソウル1978・韓国労働者の母』関西芸術座(戯曲未入手)
関西芸術座が1978年に上演した岩田直二の作・演出による『ソウル1978・韓国労働者の母』は、韓国の労働運動家の全泰壹(チョン・テイル、1948~70)とその母親の李小仙(イ・ソソン、1930~2011)に材をとった作品である。作・演出の岩田直二は1962年に帰国朝鮮人を主人公にした『湿地帯』を演出して以来、朝鮮との関係や在日の問題にこだわってきた演劇人だが、韓国の政治状況に対しては70年代に入るまであまり関心が無かったという。岩田は「そのころの韓国の状況に自分も含めて如何に無知であるかという思いが、もっと韓国のことを知らなければという強い願いとなってわたしを戯曲執筆、演出・上演に追い立てた」(岩田直二「新しい出発点に」『同時代戯曲集 光よ!蘇れ』ブレーンセンター、1987、p140)とし、このような「私自身の反省を含めて、韓国にあって民主化を願い、北の朝鮮民主主義人民共和国との統一のために闘っている韓国の人たちへの連帯の気持が、創作の動機となって」(岩田直二『岩田直二の演劇通信』松本工房、1994、p64)執筆された。『ソウル1978・韓国労働者の母』は大阪で1回だけ上演された作品で戯曲は入手できなかった。
『鳳仙花の咲く丘』劇団フジ/直居欽哉/田村丸
1979年3月末、劇団「フジ」は田村丸の演出で直居欽哉(なおいきんや、1922~?)の『鳳仙花の咲く丘』(東京:砂防会館)を上演した。この作品は韓国の木浦市に所在する孤児院「木浦共生園」 に関する実話をもとにして直居が書き下ろした戯曲である。作者の直居欽哉は韓国の劇作家・車凡錫を通じて木浦で孤児院を運営し韓国政府から表彰された尹鶴子(田内千鶴子)のことを知り、「軍人でもない一般日本人の中でもアジアの国々のためにその生涯を捧げた者がいたことを知って感動し、このような人物を紹介することが戦争で生き残った自分の使命だ」(韓国演劇、1979/5)という考えからこの作品を書いたという。『鳳仙花の咲く丘』は「作家が日本人であるにも拘らず内容が日本批判的で、在日僑胞および日本人の若者に深い感動を与えた」(「韓国演劇」1979年4月号)と韓国側から評価された。この作品には白星姫(ペク・ソンヒ、1924~2015)と鄭旭(チョン・ウク)の2人の韓国人演技者が出演して話題になった。
『京浜・1979』京浜協同劇団
1979年12月に京浜共同劇団が上演した『京浜・1979』は現代の労働者の団結の難しさを描いた作品である。もともとは1970年にソウルで起きた「全泰壹事件」を素材にする予定だったが、制作過程で日本の現在状況に置き換えた作品として仕上げることになったという(公演プログラムから引用)。劇中の要所要所に挿入されるテレビの場面を通じて韓国の労働運動の様子が紹介され、〈韓国の母〉が日本の労働者にテレビ画面を通じて語りかける場面が挿入された。
『釈迦内柩唄』前進座/水上勉
1980年10月、劇団「前進座」は水上勉(1919~2004)の作・演出で『釈迦内柩唄』を上演した。「悲劇喜劇」(1980/11、p94)によると、この作品は戦争中の雪深い東北地方の炭鉱町の近くにある火葬場を舞台にした作品で、「穏亡(おんぼう)」と呼ばれる火葬場の職業に対する日本社会の職業差別と朝鮮人に対する差別を重ねた作品である。物語は「火葬場を管理していた当主の〈弥太郎〉が亡くなり、その死体を焼くために、薮内藤子という末娘がカマの掃除をしながらひとりでこれまでの家族の思い出を語る、いわゆる「一人語り」の形式で進行する。過去を回想する場面の中に、近くの炭鉱から逃亡してきた朝鮮人〈崔東伯〉が登場する。〈崔東伯〉は炭鉱から逃亡してきて雪の中を迷っているうちに〈弥太郎〉の家にたどりついた。〈藤子〉の家族は憲兵に追われて逃げ込んできた〈崔東伯〉を温かく迎え、〈崔東伯〉の歌う朝鮮のうたを聞いて楽しく過ごす。しかし〈東伯〉は彼を追ってきた憲兵によって再び鉱山に連行されていくが、その際に逃亡を試みて射殺される。後日、〈東伯〉は棺に入れられて憲兵の引率で火葬場に運ばれて来る。憲兵は〈東伯〉の火葬を要求するが、〈弥太郎〉は正式の手続きを踏んでいないからと頑固に火葬を断る。そこで〈弥太郎〉に代わって娘の〈藤子〉が〈東伯〉を火葬にする。『釈迦内柩唄』は日本社会の身分差別を批判するという観点から書かれた作品であるためか、〈崔東伯〉が日本の炭鉱で強制労働させられることになった経緯は描かれなかった。この作品は1989年に韓国で上演され、朝鮮日報(1989/12/20)「熱い人間愛に好感」というように好評を得た。
『朝まで…』関西芸術座/岩田直二
1981年11月、関西芸術座は岩田直二の作・演出で『朝まで…』を上演した。この作品は1971年の「学園浸透スパイ事件」で拘束された徐勝・徐俊植兄弟の母親である呉己順(オ・ギスン)を主人公に、「徐兄弟の釈放を願って十年間に六十回以上も韓国と日本の間を行き来したオモニ」(『岩田直二の演劇通信』松本工房、1994、p65)を描いた作品である。呉己順を追悼した『朝を見ることなく―徐兄弟の母 呉己順さんの生涯』(社会思想社、1981)を底本に劇化した作品で、上演の動機は「日本の観客に少しでも深く広く韓国の状況を知ってほしいと念願するから」(前掲の岩田書p65)というものであった。舞台は好評を得て同年12月に追加公演を行ない、また1982年から83年にかけて神戸や京都などでも上演されたという。関西芸術座はこれまでにも『キューポラのある街』(1962)や『湿地帯』(1962/1963)など、在日朝鮮人に関連する作品を上演してきた劇団である。このことから『朝まで…』は韓国政府の在日僑胞に対する態度を批判するとともに、在日朝鮮人を生み出した歴史的背景にも目配りをした作品となっている。
『朝を見ることなく』民藝/大橋喜一&李恢成脚色/米倉斉加年演出
1982年5月、劇団民藝は米倉斉加年の演出で大橋喜一と李恢成の共同脚色による『朝を見ることなく』を上演した。この作品もまた前述した呉己順追悼集を土台にして劇化された作品であり、舞台成果が評価されて民藝は「紀伊国屋演劇賞団体賞」と呉己順を演じた北林谷栄が「紀伊国屋演劇賞個人賞」を受賞した。この作品は李恢成が脚色に加わっていることから、本稿の主旨とそぐわないので作品の紹介だけとする。
『鳥は飛んでいるか』劇団ピープルシアター/森井睦作・演出
1982年5月、劇団「ピープルシアター」は森井睦(1938~)の作・演出で『鳥は飛んでいるか』を上演した。この作品もまた前述の呉己順追悼集を底本にした戯曲であり、韓国をさまよう〈母〉が主人公である。森井睦の戯曲集『鳥は飛んでいるか』(テアトロ社、1994、p228)によると作品の力点は「政治劇ではなく家族の愛の劇」を描くことにあり、韓国政府にとらえられた二人の息子(注:徐勝・徐京植兄弟)に会うために、10年のあいだに60回韓国を訪問したという呉己順の母性が強調された。この作品ではコロスの役割を担う〈日本人記者〉が「在日韓国人は日本の植民地時代に、植民地統治下の本国において辛酸をなめ、強制的半強制的に日本に連行され、ありとあらゆる苦労の末に解放を迎え」たと在日の来歴を語る。しかし「韓国全体を覆うファシズム」(戯曲p22)が在日韓国人の家族を引き裂き、呉己順と徐兄弟は軍事政権による反共体制強化の犠牲にされたという面が強調され、在日を生み出した日本の植民地統治に対する批判は行われない。
『ギンネム屋敷』(戯曲未入手)
1982年5月、沖縄ジアンジアンで『ギンネム屋敷』が上演された。これは又吉栄喜(またよしえいき、1947~)の「第4回すばる文学賞」(1980)当選作『ギンネム屋敷』を吉永淳一が脚色した演劇作品である。この小説には「米軍基地のエンジニア」として働く朝鮮人が登場する。この朝鮮人は物語りのなかで極めて重要なポジションにあるが、残念ながら戯曲を入手できなかったのでどのように形象化されたのか不明である。
『翔びたてばトゥイグワー』劇団えるむ/ふじたあさや作・演出
1982年10月、劇団「えるむ」はふじたあさや(1934~)の執筆した『翔びたてばトゥイグワー』を上演した。この作品は戦争批判を目的にしたものであるが、炭鉱事故で生き埋めにされた朝鮮人炭鉱夫らの話や、過去の戦場を回想する場面では日本兵に撃ち殺される〈花子〉と〈英子〉という名の二人の「朝鮮人軍慰安婦」が描かれた。作品の時代背景は沖縄返還が決定した1972年で、雑誌「悲劇喜劇」(84/1)「対談・演劇時評/翔びたてば鳥(トゥイグワー)/宮岸泰治&あずさ欣平」(p71~86)によれば、復員したにもかかわらず戦後30年ちかく家族のもとに現れない復員兵を探してほしいという話を新聞社に持ち込むところから始まる。「皇軍兵士」だった〈伊波良一〉は復員しているはずなのに家族の前に姿をあらわさない。そこで実弟の〈健二〉と母の〈あさ〉が記事にしてもらおうと新聞社に話を持ち込む。〈伊波良一〉が家族に会わない理由は、〈良一〉は「本土」によって差別される「沖縄」出身の人間でありながら、そのことからいっそう「皇軍兵士」であろうとしたことに対する葛藤があった。しかも妹と許嫁は「皇軍兵士」の誤射で殺され、戦場では「皇軍兵士」として朝鮮人軍慰安婦に銃を向けることを命令される…このような過去を忘れたいために、家族にも会わずひっそりと戦後を生きてきたのだった。
『翔びたてばトゥイガー』の作品主題は戦争批判であるが、日本軍兵士によって殺害される「朝鮮人軍慰安婦」を描いたり、あるいは事故の起きた「朝鮮人鉱夫だけの坑道はな、そのまま埋めてしまった」という場面が描かれた(戯曲p160)。このような台詞はこれまでのサンプリング作品には見られなかったものである。
『玄界灘に架ける橋は』劇団未来/和田澄子/森本景文
1982年11月、大阪に本拠を置く劇団「未来」は和田澄子(1932~)の執筆した『玄界灘に架ける橋は』を森本景文(?~2018)の演出で上演した。劇団の梗概によると「戦中を辛くも生き抜き、今まで“生”を得てきた一人のもと日本兵日本人男性が、自分自身の身体の異常に気づく事に端を発し、在日70万という朝鮮人の一人である婦人と向き合います。この2人を取りまく、どこにでも居そうな諸人物達との織りなすドラマの中で…日本人にとって朝鮮人とは、朝鮮人にとって日本人とは…被爆体験とは…今、果さねばならないことは…を問いかける」作品である。被爆したもと日本兵が被爆朝鮮婦人の生活を助けようとするが、その家族から断られる。
『チョゴリを着た被爆者』新屋英子(戯曲未入手)
1983年8月、新屋英子は一人劇『チョゴリを着た被爆者』を上演した。安土政夫(テアトロ1991/10)によれば、この作品は「日本統治下、韓国・慶尚南道で、7人姉妹の末っ子に生まれた女性」の話で、「日本へ強制連行された夫を追って、山口県宇部へ。そこでの炭坑での強制労働。広島への脱走。被爆。目前で長男を、数年後に夫を失う。戦後も続く差別と差別の日々ー」を描く一人芝居である。
『グレイクリスマスー五条家の人びとー』本多劇場プロデュース/斎藤憐/栗山民也
1983年12月、東京・下北沢に位置する本多劇場は斎藤憐(さいとうれん、1940:平壌~2011)の執筆した『グレイクリスマスー五条家の人びとー』を栗山民也(1953~)の演出で上演した。この作品は日本が敗戦した1945年の冬から、韓国戦争(戯曲では朝鮮戦争)の勃発した1950年の12月までを背景にした作品である。敗戦後の日本は米国主導で民主化が進められたが、米国の反共政策が強まるとともに民主化は後方に押しやられる。そして米国と歩調を合わせた日本の旧勢力の台頭で、徐々に日本は戦前の姿を取り戻していく…。この敗戦直後から戦後初期の日本の変化を、旧華族である「五条伯爵家」の没落と復興という形で描きだす。この作品には詐欺師の〈権藤〉とその手下〈藤島〉の二人の朝鮮人が描かれた。彼らは没落して呻吟している五条家の当主〈五条紀明〉にうまく取り入って、世相に疎い〈紀明〉から財産を奪い取っていく。二人の朝鮮人は五条家(日本)と進駐軍(米国)の間でうまく立ち回っていたが、しかし日本の戦前回帰によってまた追われる身となる。このように日本人を騙したり手玉に取る朝鮮人が登場する作品は、サンプリング作品のなかではこの作品が初めてである。
『お茶と刀-利休狂想曲』青年劇場/飯沢匡 作・演出
1986年5月、東京に本拠を置く劇団「青年劇場」は飯沢匡の作・演出で『お茶と刀-利休狂想曲』を上演した。この作品は「豊臣秀吉の朝鮮侵略と現実政権の鋭い風刺」(劇団の作品案内)を目的にした喜劇作品である。作家によると、利休(=芸術)と秀吉(=軍部の非文化性)の対立は戦争中から描きたかった主題であり、戦時中に軍部を止めることのできなかった恨みをこの作品ではらしたかったという(『飯沢匡喜劇全集6巻』)。このために日本社会で喧伝されている英雄としての「太閤秀吉」とは異なり、「むしろ秀吉の狂気のために生命を失った日本人と朝鮮の民衆が沢山いたことを強調したい」(戯曲p355)ことから秀吉の暴力性が語られる。この作品には〈利休〉と交流のあった陶芸家〈長次郎〉の父親として、〈やさしい瓦作りの朴〉という「高麗人」が登場した。高麗人〈朴〉は、自分自身の美意識にあまりに忠実であろうとしてむしろ傲慢になった〈利休〉をいさめるという役を与えられた。しかしけっきょく〈朴〉は秀吉の「朝鮮征伐」の犠牲となり、「鼻」となって〈長次郎〉と再会する。
『もうひとつの教室』関西芸術座/廣澤榮
1987年11月、大阪に本拠を置く新劇団「関西芸術座」はシナリオライターの廣澤榮(1924~96)が執筆した『もうひとつの教室』を上演した。この作品は定時制中学(夜間中学)で学ぶ人々のさまざまな人生模様を描くことで、夜間中学に対する理解促進を目的にしたものである。この作品には〈在日朝鮮人の金正花〉という、42歳で夜間中学に通う勤労学生が登場した。〈金正花〉は済州島から日本へ連れてこられた両親のもとで、1945年に川崎で生まれた。家が貧しかったことから学齢になっても学校へ行けず、中年になって夜間中学へ通っている。また、中国人の〈黄玉珠〉という女子学生も登場する。この〈黄玉珠〉は満州移民の遺児であり、日本へ帰国したけれど日本語がしゃべれず、夜間中学でに勉強しているという設定である。このように〈金正花〉や〈黄玉珠〉の二人の来歴には日本のアジアに対する侵略と支配の歴史が刻印されている。しかし作品では歴史に対する言及はとくに行われない。作品では1945年3月の「東京大空襲」で両親を失った日本人で58歳の戦災孤児〈桜井〉と同様に戦争の犠牲者として言及される。この作品は1987年度の「大阪文化祭賞(現代演劇)」を受賞した。
『光の都』ケンチャナ青年団/平田オリザ 作・演出
1988年に入って平田オリザとケンチャナ青年団は平田オリザの作・演出で「韓国三部作」を上演した。その最初の作品が3月にこまばアゴラ劇場で上演された『光の都』である。ソウルの街の中心を東西に流れる漢江(ハンガン)の川辺をを舞台にしたこの作品に登場するのはすべて韓国人だが、戯曲を読む限りではこれまでのサンプリング作品にみられたような「韓国人あるいは朝鮮人を思わせる形象化」はいっさい行われていない。青年団の「小さい声でしゃべる」「後ろを向いてしゃべる」というスタイルで韓国人を演じたこの作品で語られるのは、オリンピックを目前にした韓国社会が抱えている悩みや問題などである。この作品は翌90年5月に「大幅に改定」して再演された(産経新聞、90/4/24)。「改訂版」は戯曲を入手していない。
『イルボンサラムへー心の叫び』学生演劇作品(戯曲未入手)
朝日新聞(1988/8/2)「時々刻々:ヒロシマ受け止める高校生ら/足元の戦争、見えてきた/調べて知る、差別との二重苦」によれば1988年7月23日、大阪府立松原高校は『イルボンサラムへー心の叫び』を広島中央公民館で上演した。記事によるとこの作品は「被爆と民族差別の両方を体験し、現在、学校近くの病院で来日治療中の在韓被爆者、玄さんの半生に取り組んだ」作品で、「玄さんを演じた2年生の田中富美代(16)はこの劇で日本人には見えにくいもうひとつの原爆の顔がわかった」と語った。
『朗読詩劇/心の中のヒロシマ』学生演劇作品(戯曲未入手)
また、前掲の記事によれば1988年7月25日、大阪府立柴島高校は『朗読詩劇/心の中のヒロシマ』を平和記念館講堂で上演した。この作品には「朝鮮から日本に強制連行されてやってきた。自由を、言葉を、名前を奪われて…字が読めない。言葉がわからない」(前掲の記事)朝鮮人が描かれた。
*これまでサンプリング作品のなかで学生演劇が朝鮮人・韓国人の登場する作品を執筆・上演したのは『海岸線』(1965)だけであった。しかし1990年代に入って全国各地の中・高校や地域劇団によって「地元の戦争体験」を演劇にする作業がさかんに行われるようになる。この結果、朝鮮人・韓国人の登場する学生演劇作品も数多く上演された。
『漢江の虎』ケンチャナ青年団/平田オリザ 作・演出
1988年8月、劇団ケンチャナ青年団は『漢江の虎』を上演した。主人公は日本の女子高校生〈文子〉だが、彼女はカフカの『変身』の主人公のように眠っている間にオリンピック開催中のソウルの高校と東京の(家業の)焼鳥屋のあいだを彷徨う。舞台は東京の焼き鳥屋から始まる。…父と母がなじみの客の高木さんや大谷さんを相手に商売している店内。彼らのそばで文子はカフカの『変身』を読んでいる。客も帰り店じまいも終え、誰もいない店内で文子は一人本を読んでいたが、やがて眠ってしまう。目が覚めるとそこはソウルの高校で、文子は韓国人の生徒たちに「転校生」として紹介される。とまどう〈文子〉の前に体育の金成基先生に連れられて父が現れる…。この作品ではさまざまな形で日本と韓国が重なり合う。主人公〈文子〉の〈母〉は〈父〉の妻だが、ソウルでは〈父〉の〈現地妻〉である。焼鳥屋の客である〈大谷さん〉は韓国人男子生徒〈金英哲〉でもあり、同時に文子の〈弟〉でもある。またソウルの高校の体育教師である〈金成基〉は焼鳥屋の客〈高木さん〉でもある。このようにして重なり合う日・韓の登場人物に仮託して、重なり合う日本と韓国が描かれる。そしてそれは日本による植民地支配の痕跡となっていく。
『花朗~ファラン~』ケンチャナ青年団/平田オリザ 作・演出
1988年12月、青年団は『花朗~ファラン~』を上演した。この作品で重なるのは日本と韓国の古代史である。オリンピックの終わった年の冬、ソウルのとある工事現場で統一新羅時代の古墳と思われる遺跡から日本の埴輪が発掘される。韓国にはありえないはずの埴輪が見つかったことで、古代社会における日本の影響を危惧する会話が、建築現場の業務的な会話の中に挿入される。しかし日本の影響を危惧する韓国人たちの会話は、一方では「万世一系」の天皇の出自に対する懐疑でもあった。このように韓国人たちの会話で進行する中に、陰画としての「日本」を忍び込ませる手法はこれまでのサンプリング作品には見られなかったものである。
『ソウル市民』青年団/平田オリザ 作・演出
1989年9月、平田オリザの主催するケンチャナ青年団は日韓併合直前の漢城(ソウル)に暮らす篠崎家の一日を描いた『ソウル市民』を上演した。前述した「韓国三部作」と同様に、舞台に登場人物が入れ代わり立ち代わり現れては消える形式で進行する。そして観客は日本人登場人物たちの何気ない日常会話のなかに埋め込まれた差別意識や植民地主義に荷担する態度を見出すことになる。この作品も「韓国三部作」と同様に朝鮮人登場人物を際立たせる形象化は行われない。
*第3期作品リスト「犠牲者としての朝鮮人」へ続く
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
