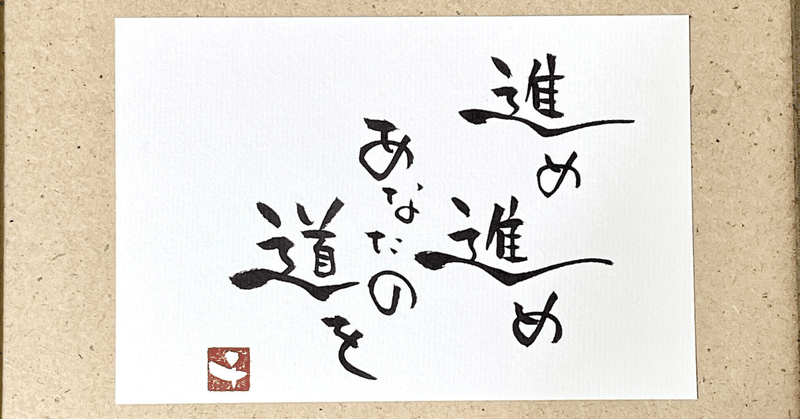
社会科学方法論-高島善哉の学問(9)
「本稿(9)」は,「高島善哉の社会科学の基本的な見地」に関する議論を連続的に考察しているうちの1編である。本日に記述する部分は,初出が2014年11月21日であり,さらに2020年3月1日に更新したものである。
本日の考察は,つぎの要点を置いて論及していくことになる。
要点:1 高島善哉の社会科学論における風土の概念
要点:2 現代の社会科学方法論は,高島善哉を超えられないのか?「社会科学の基礎理論(9)」
この要点2つのなかでは,風土問題に関して「自然主義と人間主義の統一とはなんであったのか,さらにまた「風土の階級への接着」という論点も登場する。
とりわけ,生産力と社会的自然というカテゴリーを使いながら,新しい唯物論の立場から「風土の社会科学理論確立」のための思索を展開する。
※-1「風土に関する八つのノート」1966年〔その7〕-第6のノート:自然主義と人間主義の統一とは何か,再度和辻の風土理論に言及して-
1) 自然主義の肯定から出発する理論
和辻の風土理論の長短が篩い分けらればならない。その長点は,人間の歴史的・社会的な存在共同における〈自然の契機〉を認知する必要を喚起したことであり,その短点はそこで自然の契機を認知する意義を認めながら,そこから足早に遠ざかってしまったことである。
風土理論に対する現代の興味は,その「到達点=全体主義的な国家観」にあるよりは,むしろその「出発点=人間存在の時間的・空間的な構造把握」にある(高島善哉『現代日本の考察-民族・風土・階級-』竹内書店,1966年,271頁)。
風土概念の基本的な性格をいえば,人間と自然が一種独特に結びつき,相互に浸透しあい,人間存在の空間的・時間的な,より正確には人間存在の自然的・社会的な構造連関を作りあげている。
和辻風土論の核心は,人間存在の基本的な存在構造を明確に表現する「空間性の原則」と「時間性の原則」との〈相即的〉〈相互媒介的〉な結びつきという「難解な命題」にみいだせる。
ハイデッガーをはじめ,人間存在の歴史性・時間性について語る哲学者は非常に多いけれども,人間存在の空間性について語る哲学者は皆無であった。和辻はその点で独自の道を切開したと,みずから広言してもいた。
だが,はたしてそうだといえるか。『倫理学』3巻〔上巻 昭和12年,中巻 昭和17年,下巻 昭和24年〕は,実は和辻が問題提起そのものの出発点において誤っていたのではないか(272頁)。
和辻が「人間存在の空間性」というときこれは「人間の『間柄』的性格」を指している。この〈間柄〉という表現は,家や郷土や国土によって「界限」されている〈人間の距離感〉を示すことに終始し,自然と人間との生きた関係を端的に捉えてはいない。
つまり,和辻の「風土」には生きた自然がなく,ただ「人間にとっての自然」であり「人間に対する自然」ではない。結局〈空間的なもの〉が〈自然的なもの〉になっていない。もともと自然の子である人間が,和辻においては自然が人間の子になっていて,人間が生きたままの人間でなくなっている。
これでは人間把握における自然主義の完全な放棄である。高島善哉の求める「風土の理論」は,自然主義の否定ではなく,その肯定から出発する理論なのである(273頁)。
2) 一見明快な和辻理論の誤り
和辻は,自然を人間存在の構造的な一契機に定義した。まず自然があって人間があるのではなく,反対に人間があってしかるのに自然がある。自然は「人間存在から抽象されたひとつの虚構」に過ぎず,ここからして人間の自然離脱への旅が始まる。
「血と土」(Blut und Boden)にまだ結びついている家族共同体や村落共同体から出発し,まだ欲望の体系でしかない経済的組織〔市民社会〕を上向して,民族という文化共同体の高見にまでよじ登ると,この最後に国家がやってくる。
この国家が「すべての血縁-地縁-文化共同体の総合体」「人間の人倫的組織のなかの最高の人倫的組織」となる。だから「人は国家において初めて具体的な人格とその自覚に達することができる」(273-274頁)。
以上,「和辻の理論」は明らかにヘーゲルの再現である。それも近代化され現代的(モダーン)になったヘーゲルである。その難解な「弁証法の命題設定(シェマティズム)」が「明瞭な段階的序列」に組みかえられている。
補注)「シェマティズム」というカタカナ語は,ドイツ語の読みと綴りだとしたら,Schmatismus に相当する単語であり,「シェマティスムス」と表記するのが正しいはずである。シェマティズムということばじたいは,一部で流通しているようであるが,そのように注釈しておく。
要は,私的なものから公共的なものへ,この公共的なものが再び,国家という「公共的であると同時に私的なもの」において自己を限定している。この手順を経て「ナショナルなものの独自性」が打ちだされている。これはヘーゲルに比べると軽快かつ明朗であるけれども,ヘーゲルの枠を越えられているか疑問である(274頁)。
ヘーゲルは市民社会を欲望の体系としながらも,そこに理性の狡智を認め,階級矛盾の必然をはっきりみてとった。ところが,和辻はそこをするりと通りぬけ,文化の王国へと飛躍した。
和辻にとって文化とは第1に言語であり,第2に学問であり,第3に芸術であり,第4に宗教であった。いずれも「人間=文化の主体である人間」が,そこにおいて自己自身を創造し自覚していく人倫的組織,精神的自覚の場において存在する。
こうなると,文化は自然とはまったく別物となった。文化は自然と対立するもの,自然は文化より一段低いものとなった。だが,現実の生きた人間とは自然と文化の統一をその身に実現しえた人間ではないのか? いまさらルソーを俟つまでものく,文化の自然からの背理のうちに近代人の疎外をみなくていいのか(274-275頁)。
3) 自然と人間との相互媒介の結果である風土
高島が自然主義というとき「人間がもともと自然の子である」というふうに,人間存在にとってもっとも基本的な事実の認識から始める。問題は,自然か人間かそのどちらがさきかということである。人間ださきだというのなら,それは人間主義の立場である。
自然を人間存在の一契機として把握しようとする和辻の態度は,まったく妥当である。けれども,それは盾の反面に過ぎない。「人は社会的な動物である」というとき,力点を社会的に置くのが人間主義,動物に置くのが自然主義である。これは実は,私たちの人間観の問題となる(275-256頁)。
「社会的自然の問題」で考えると,人間はまず第1に社会的な動物であるから自己のうちに自然を抱えこんでいる。しかし,人間は本来の自然とは違った〈社会的自然〉を自己のうちにかかえこんでもいる。社会科学とくに経済学の研究対象は,この社会的自然である。
社会関係を「人間の人倫的組織」として掴むヘーゲル的は「発想法に社会的自然の思想がない」と指摘したらいいすぎかもしれないが,和辻『倫理学』にあっては「社会的自然の思想」が皆無である。
和辻の風土論は,せっかく人間と自然の統一の問題に気づきながら,問題提起の出発点において脇道にそれていった。ヘーゲルには色濃くあらわにされていたマテリアリスティックな(materialistic〔英〕,materialistisch〔独〕=唯物論・唯物主義者の,物質主義の)発想は,あとかたもなく消えうせている。和辻は,社会的自然というものの認識に到達できていなかった(276頁)。
補注)本ブログはだいぶ前になるが(「2010. 9. 22」に公表した文章であるが,現在は未公開の状態),主題「和辻倫理学の新解釈」,副題「戦争責任問題を回避した『人倫・間柄』の日本学」「天皇・国体論から逃亡した和辻『風土論的倫理学』の陰影」という記述をおこない,和辻哲郎の哲学・倫理学の本質(本性)を探るための討究をしたことがある。。
その関係でみれば,たとえば,苅部 直『光の領国 和辻哲郎』創文社,1995年(岩波書店,2010年)は,和辻哲郎『倫理学 中巻』昭和17年をこう批判していた。
「民族の主体性に基礎を置く『神聖性』と国家主義の活動との合一が『本来の国家』のありかただとする議論に,当時の読者は現人神たる天皇を想起した」
「官民を含めた幅広い言論が,天皇の名を押し出して国民個々人の中世を徹底的に要求していた戦時下においては,『個人は国家への献身におて己が究極の全体性に還ることできる」と説く和辻哲郎の著書もまた,現実に展開しつつある戦争動員を正統化するものと読まれるのが当然だったのである」
高島は,その発想から風土の社会科学的な理論への道が開拓されねばならない,と主張する。現代の思想状況は,風土というカテゴリーは保守感情に結びつけやすく,〈古いナショナリズムの思い出〉を新たにさせがちでもある。
しかし,この〈罪〉は風土概念そのものにではなく,これを扱う人びとの側にある。「文化の民族的な体質」においては「文化にも血と土の匂いがする」し,「文化の自然を」「感じる」。社会科学者は「自然主義と人間主義の統一の問題」にいかに対決すべきか?(277頁)
※-2「風土に関する八つのノート」1966年〔その8〕-第7のノート:風土の階級への接着はいかに。生産力と社会的自然というカテゴリーを使いながら-
1) 自然と人間を結ぶ「生産力」の意味
高島は,風土を自然と人間の相互規定の場だと規定した。つまり,自然主義と人間主義の統一という思想によって初めて,風土理論の社会科学的な展開が可能となるといった。そして,その「統一の思想」に「限定の場」を設定させるための具体的な媒介項として,「生産力」というカテゴリーが登場する。
この「生産力」は,民族と階級を結びつけるカテゴリーとして認識される。高島の発想によれば,この認識にもとづいて風土の社会科学的理論が展開されるのである(高島『現代日本の考察-民族・風土・階級-』278頁)。
「生産力」が「自然と人間の相互規定の場」であるとは,人間の「自然への適応」=「ネガティヴ:自然による人間の限定」と,この「自然への適応の修得」=「ポジティヴ:人間の自然への働きかけの可能性」とを意味する。ここに「生産力」のもっとも《原初的なかたち》を認めることができる。
この「生産力」は自然の側にではなく人間の側にある。というよりはむしろ,自然を生産力化する働きは人間の側にある。自然は客体であって主体ではない。これが哲学的にいって,自然と人間の相互規定ということの〈正しい意味〉である。社会科学者もまたここから出発しなければならない(278-279頁)。
「『生産力』の把握がいかに重要である」といえば,これにおいてこそ「風土理論への関門が開かれている」からである(280頁)。
2) 「生産力」の構造と自然・人間の関係
「生産力」とは「主体としての人間」が「客体としての自然」に働きかけるところに成立する概念である。ちなみに「生産性」とはその働きを結果を表わす,それも数値として具体的に表現されることの多い概念である。
ここで注意したいのは,生産力を高める役目を果たす労働手段が,一面では「主体の働きの結果」であると同時に,他面では「ひとつの自然物質」であるように,「『生産力』の『主体としての人間』がすでに『ひとつの自然』であると同時に,『生産力』の『客体としての自然』がすでにひとつの人間的所産である」ことである。人間と自然とは「生産力」の構造的な2契機なのである(280頁)。
【参考画像資料】-旧東ドイツ紙幣に印刷されていたマルクス像-

100マルク紙幣「表裏」
高島は「人は自然に働きかけることによって彼自身を変化させる」といったマルクスの命題のなかに,自然主義と人間主義との統一の可能性をみてとる。
したがって,風土理論の展開にための可能性も,そこに含まれていると考える。人間が文化を創りあげるという一面的な理解ではなく,文化が人間の自然本質と内面的に結びついていること,端的にいって文化が人間の体質であることを物語っている,というのである(280-281頁)。
3) 第2の自然である精神的・文化的風土
精神的風土あるいは文化的風土という概念は,本来の風土とは別物であって,いうなれば本来の風土から転用されたカテゴリーではあるけれども,精神や文化の世界に定着して長い歴史的な時間の経過のうちに「第2の自然」となっていったひとつの文化体質を表わしている。
その意味で精神的風土・文化的風土は,本来の自然に対して「第2の自然」「社会のなかで生まれた自然」,つづめて「社会的自然」と名づけられる(高島『現代日本の考察-民族・風土・階級-』282頁)。
風土の理論を展開するためにはまず,風土概念の社会科学的な設定が必要である。そのさい「生産力」の概念によって《風土の機構》を明らかにしようとする。「風土」も「生産力」もともに『自然と人間の結合の場』において成立する。
しかし「生産力」が社会科学的にはより明白な概念であるから,これを手がかりにして,より曖昧なである「風土」の性格と構造を明らかにすることになる。
さらに重要な問題が「社会的自然」である。もし「生産力」の理論を媒介として風土理論を展開したいのであれば,風土と社会的自然との連関が問われねばならない。
要するに,問題は,階級と民族の相克と相互媒介という複雑な現実を目前にして,どうしたら風土の社会科学的理論を打ちだすことができるかである(283頁)。
4) 風土理論を階級理論と結びつける
マルクスの基本的なテーゼを思い出さざるをえない。生産力の概念は当然に生産関係の概念に結びついてくるし,階級の概念にも結びついてくる。それでは「生産力」と「社会的自然」というカテゴリーを使いながら,いかにして風土理論を階級理論と接着させることができるか。和辻風土理論はこの問いに答えられない。
観念論者和辻を去って唯物論者の陣営に赴かねばならない。それも18世紀的な古い唯物論者ではなく,20世紀の唯物論者のことである。その目的のために戸坂 潤の和辻批判がとりあげられる。これまでのところ,唯物論の陣営から発せられた和辻批判としては,戸坂のものがただひとつ存在するだけである。これは現代唯物論者の怠慢の結果ではないか(284頁)。
※-3「風土に関する八つのノート」1966年〔その9〕-第8のノート:新しい唯物論の立場から。風土の社会科学理論確立のために-
1) 戸坂 潤の和辻哲郎「批判より前進」すること
戸坂 潤は,和辻哲郎「風土の概念」について「独創的で奇抜」「解説(リーズニング)ははなはだ細心なもの」である点を認め,和辻の「没することのできない業績」と高く評価した。
けれども,同時に「風土の和辻哲郎的観念とその観念的摘要の心事とが」「この業績を濁ったものにしている」と批判することも忘れなかった。高島善哉は「あたかも自分の言葉がそこに語られている」「とわが耳を疑わざるをえな」かったと言及していた(高島『現代日本の考察-民族・風土・階級-』285頁)。
しかし,戸坂の和辻批判はそこまでで終っていた。思想的に戸坂と「心事」を同じくする人たちもそこに留まっていた。風土のカテゴリーをもち出すことが間違いではなく〔それはひとつの発見である〕,その「風土」の捉えかたとその適用のしかたが問題になっていた。
ところが,こう和辻を批判した戸坂は,そのさきの吟味を戦後の社会科学者の手に委ねたのではないか。戸坂のいうとおり,今日のマルクス主義社会科学は,風土という一種の武器によっていわば〈虚〉を突かれた。だから問題はいかにしてこの〈虚〉を充填するかということになる。

そこで,高島が風土概念の前進のために提案するのは,
第1に「生産力の構造」を明らかにすること,
第2に「社会的自然のカテゴリー」を使用してその接着をより効果的で耐久力のあるものたらしめることである。
(高島『現代日本の考察-民族・風土・階級-』285-286頁)。
2) 生産力の主体たる実践的人間
史的唯物論の立場は,生産力と生産関係の関係をもっとも基本的な問題として措定する。決まり文句でもって公式的に「生産力が内容であり生産関係は形式である」といっただけでは,まだ充分ではない。
ヘーゲル流に「内容は形式であり,形式は内容である」といってみたところで,どこまでこの公式を自己説得的に理解しえたかといえば,他人を説得できる水準まで達しておらず,この点では「戦前戦中を通じてもっとも卓越した唯物論の哲学者であった戸坂」も同じであった(286頁)。
a)「生産力の構造」 生産力の主体は「人間」,その客体は「自然」であり,これらを媒介し結合するものが「技術」である。その「人間」とはなにかといえば「特定の人間関係のなかにおいてのみ生産力の主体であるほかない」。
そして「この人間関係は社会体制の違いによりさまざまでありうるばかりでなく,経済,政治,教育,学問,宗教等々において〔も〕さまざまでありうる」。
それゆえ「生産力の問題はただ単に経済の世界の問題ばかりと考えてはいけない」し,「人間関係の特殊なありかたを離れては理解され」ない。「真の問題は,このような生産諸力を並べたてる」のではなく,「その立体的な構造を把握するところになる」。「史的唯物論の狙いはここにあった」(287頁)。
b)「生産力の主体」 「生産力の構造」問題においては民族が主体でない。民族の代わりに国民ということばを使い,国民生産力という表現があるにしても,これが真の主体にはならない。問題は「生産力の主体である人間は実は単に文化的・自己了解的な人間(和辻哲郎の人間主体はこれであった)ではなくて,みずからがひとつの自然でありながら自然に働きかける実践的な人間だからである」。
c)「生産力の客体」 これは自然を意味するが,自然一般を指していない。狭義の自然=本来の自然」のほかに「社会的自然」という,次元の高い意味での自然を想定する。「人間の経済活動における生産力の発動は以上の意味で2つの自然を媒介する」。
さらに「政治や教育や学問や芸術や宗教などの領域における人間の生産力の発動は,第2の自然である『社会的自然』を踏まえておこなわれる」。だから「経済の領域よりは,第1次的自然との関係がより間接的だとい」える。
この観点から判断すれば「政治が国家において人倫態の最高の存在形態をかたちづくるという和辻哲郎の思想の誤り」は,「生産力としての政治と教育は,一方では経済と,他方では学問,芸術,宗教と結びついて,生産力の三重構造をかたちづく」っている(288頁)ことが認識できていない点にある。
3) 社会的自然のもつ2つの意味
「社会的自然」の客体性をありまのままに認めようとする思想は,唯物論に通ずる。人間は歴史的・社会的な生活において,その「社会的自然」の支配から完全に離脱できない。
戸坂 潤が和辻『倫理学』の批判において,人間の社会生活はひとつの物質的・現実的過程であることを力説したのは,唯物論者として当然過ぎた。しかし,戸坂はそこからさきに1歩も進もうとはしなかった(高島『現代日本の考察-民族・風土・階級-』289頁)。
補注)高島はここで,『戸坂 潤全集 第2巻』(勁草書房,昭和41〔1966〕年)「日本倫理学と人間学-和辻倫理学の社会的意義を分析する-」『日本イデオロギー論』(白掲社,昭和10〔1935〕年,増補版,昭和〔1936〕11年)を行間に註記していた。
戸坂に直接聞いてみると,和辻の論旨をこう分析していた。
「解釈学的倫理学は,歴史的社会の物質的生産関係をけっして無視しないとはいう」ものの,それは「人間存在の表現としてであるに過ぎない」
「人間存在が物質的生産関係を通じて因果し又交叉作用した結果が倫理であるというのではなくて,そうした物的基礎の構造連関の代わりに,観念的な意味の構造連関がとり出され,そういう一種の社会的象徴として,歴史社会の物質的基底がとりあげられるに過ぎない」
さて,高島善哉のいう「社会的自然」は2つの意味をもつものとされていた(以下は本ブログ筆者の補筆部分もくわえた記述となっている)。
☆-1「自然的自然(自然的風土:地理的風土)」 ひとつは社会のなかに引きこまれ,人間の手によって引き上げられた自然である。これは,ひとつの民族を民族たらしめる人種・気候・地味など,その民族の棲んでいる国土の「地理的環境」などである。
☆-2「社会的自然(精神的風土:経済的風土)」 もうひとつは,人間が歴史と社会で自分の手によって創りだしながら,あたかも人為的な自然として,文化的・社会的な体質としてそれをそのままに受けとり,そのなかに入りこみ,それを踏まえて初めて人間としての主体性を実現できるような種類のものである。
こちらが本来の意味における「社会的自然」であるが,社会のなかにもちこまれた自然とも不可分に結びついている関連が重要である(289-290頁)。
4)「風土」の前向きの適用-生産力理論の観点-
「風土」は「自然と社会の結び目」にその座を占めている。生産力理論の立場においては「社会的自然」が生産力の客体であって,主体ではない。このことは単に人間にとっての条件に留まらない。
つまり,「社会的自然」は主体から独立し,主体を規定するひとつの客体でありながら〔和辻がみそこなったもの〕,しかも生産力の構造的な一契機として〔和辻はこの認識へのよき助言者である〕主体化され,この主体に内在もしうるものなのである(290頁)。
「風土」の社会科学理論が確立されねばならない。「魔術からの解放」(die Entzauberung der Welt:現世の呪術からの解放)のためには「人間と社会」「自然と社会」についての哲学的な観方が打ちだされていなければならない。「風土」の問題は「思想と科学の統一」を考える人たちのためにとって,もっとも興味ある問題のひとつである(291頁)。
※-4 高島善哉「社会科学としての風土論」-まとめ-
1) 風土理論の社会科学的な展開
高島善哉による「風土問題の社会科学的討究」のあとに,この風土論的な研究視座を本格的に継承した日本の学究がいたかと問われば,そうとは思われないのである。
オギュスタン・ベルクの一連の著作,篠田勝英訳『風土の日本-自然と文化の通態-』(筑摩書房,2002年),宮原 信訳『空間の日本文化』(筑摩書房,1985年),宮原 信訳『都市の日本』(筑摩書房,1996年)などを介在させるかたちで,「風土の問題」は,社会科学の見地に限定されない方途に向かって発展したという意味あいでは,その検討の課題や対象となる論点が拡散してもきた。
そのせいなのか,高島が意図した「風土概念」の「社会科学な研究の場」における理論的前進が〈批判的に〉発展させられてきた様子は,みられない。高島自身ももとより,こう予想していたのである。
「階級と民族のあいだに」「風土」というカテゴリーを「挿入して」「現代社会科学の基礎理論を」「深め」る作業,いいかえれば「基本的な大問題が1人の学究者の手によって解決されうるはずはない」ゆえ,「学界の共同の作業として推進されなければならない性質の問題なのである」(高島『現代日本の考察-民族・風土・階級-』303-304頁参照)。
「本稿」はこの「(9)」まで,高島の見解をくわしくとりあげ議論するなかで「社会科学としての風土概念」の重要性,いいかえれば,社会科学としての基礎理論」に位置する「風土問題の学問的な価値」に論及してきた。
2) 唯物史観という基本的な立場-その思想と科学の制約-
渡辺雅男編『シンポジウム 高島善哉 その学問的世界』(こぶし書房,2000年)には,参考になる意見が示されていた。
a)「高島が民族や風土の問題,日本の近代化の問題に積極的にかかわらざるをえなかったひとつの理由」は,「高島が日本の社会科学がほかならぬ日本の社会科学となりうるための条件を真剣に模索した研究の1人であった」からで,「生産力の論理を歴史的行為の論理として主体的に把握する」という構想を,実際に理論として展開した(渡辺,前掲書,152頁)。
b) 高島善哉『経済社会学の根本問題-経済社会学者としてのスミスとリスト-』 (日本評論社,昭和16年3月)のうちに構想されていた「大胆不敵な課題」は「かつてマルクスがそうであったように,みずからの理論の完成に努めつつ,それが永遠に果たされぬことの苦々しさを生涯味わいつづけ高島善哉画像る」だけでなく,
「彼〔高島〕の学問的仕事は彼がかかわった無数の課題のうちせいぜいひとつかふたつの分野にしか従事しない研究者によって継承され,論評されるばあいには,当事者の意図に反してより一面化され通俗化されたかたちで受容されたり,拒絶されたするほかな」かった(148頁)。
c) 本ブログの筆者は「本稿(1)」以降,その全体の記述をしていくなかで示唆してきたつもりであるが,つぎのような所感を抱いている。
それは,高島が助手論文「静観的経済学止揚の方法」(初稿:1928〔昭和3〕年11月18日,定稿:1929〔昭和4〕年2月)で明示していたこと,つまり「高島は『マルクス主義の思想と科学』へと『思想的な転換』を遂げてい」き,「それ以後,この道から離れようと思ったことは一度もなかったし,ひそかに(あの戦争の最中でも)動揺を感じたことも一度もなかった」と「述懐し」た(上岡 修『高島善哉 研究者への軌跡-孤独ではあるが孤立ではない-』新評論,2010年,92頁),と説明された事項についての感想である。
高島善哉がその「マルクス主義の思想と科学」の立場に則って確信していた学問的理念は,1904年に誕生し,1990年1月に没した彼のことであったから,はたして20世紀末葉から21世紀の今日までの段階においては,必要かつ十分に再検討されることにはならなかった。
いまとなっては,周囲の学問が発展していく状況のなかで,よりあらわになってきた高島善哉「社会科学論」の基本的な問題性を「孤独ではあるが孤立ではない」といって済ませている解釈もあった(上岡 前掲書,234頁)。
しかしながら,今日的な課題にまでかかわる「高島」的論点を,そのように残置させておいていいという事由は,なんらみいだしえない。
d) 高島は自身の若き日をこう回想していた。
「学説に対する戦い,社会に対する戦い,階級に対する戦いから,まったく自分自身に対する戦いに転向」のすえ,「社会科学の道を歩む以外に生きかたはないと考えた」
「私は社会科学者として唯物論の問題を考えつづけてきたが,いまあらためてそれをみなお」し,「唯物論は主体的なものでなければならない」と「いう感じを深くした」(上岡,前掲書,221頁)
高島の学問論=社会科学論が唯物史観から出立した前提が,いまでは彼の理論発展にとっての制約,いいかえれば決定的な重荷となって,21世紀に向ける進展を阻んでいる。
しかも,この高島の試図を今日的な段階において打開し,さらに発展させようとする気概をもち,社会科学論の研究に挑戦しようとする《社会科学者》が育っていない。
ここに,日本の「社会科学」界的な状況に伏在する難題が潜んでいる。
筆者の専攻する分野・領域においてもしかりであって,社会科学の理論的な展開をめざしつつこれに裏づけられた「基礎論:本質・方法論」を背景にする経営理論は,21世紀に入るころまでにはほとんど期待できなくなった。それは理論的混迷と形容するよりは,研究基盤の破綻ないしは崩壊だと受けとるべきであった。。
この※-4における議論については,一歩踏みこんで検討したい論点が残されているが,これは次回に譲りたい。
「本稿(9)」の最後にとくに指摘しておきたいのは,唯物史観:史的唯物論を根柢に踏まえた高島善哉「社会科学論」とその「風土論」に関する抜きがたい制約が,あらためて鮮明にされつつ吟味されるべき学的作業として残されていたことである。
※-5【補 説】「社会科学者・高島善哉に今学ぶこと-激動の「昭和」を生き抜いた生涯-」という文章
この文章は現在(2023年7月3日時点)において削除されており,参照できない。その出所は引用の末尾に註記してある。
この文章からは,以下の3点を拾って紹介してみたい。
イ)「戦時体制期の〈異常日本〉」に生きた高島善哉
敗戦後の日本国憲法(1947〔昭和22〕年5月3日施行)は,学問・思想の自由を建前としては保障している。だが,敗戦までの明治憲法下ではその自由はなく,抑圧されていた。
真実をそのまま語ることは許されなかった。当時は警察権力(思想犯は警視庁特別高等課が担当)によって多くの教授たちが治安維持法違反として検挙,起訴された。
高島善哉(当時は講師)も例外ではなかった。1933〔昭和8〕年12月自宅を杉並署特高係に襲われ,検挙された。共産党中央機関紙の購読者であるなどが,その理由として挙げられた。
数時間留置場に拘束されたのち釈放されたが,当時の新聞は「高島講師召喚」,「赤化教授の温床 商大を清掃-高島講師を最後に」などと,国家権力に抵抗する学者たちの拘束を肯定する立場から派手に書き立てた。
ロ)「戦時中,出陣学徒に『生きて帰ってこい』と激励」した高島善哉
太平洋戦争(=大東亜戦争)が始まった1941〔昭和16〕年12月8日,高島はつぎのような「学生補導課長としての訓辞」をおこなっていた。
「諸君は,今日から始まった大東亜戦争の最後の戦士である。遠くない日に諸君は戦場に征くであろう。戦地において卑怯未練といわれてはならぬ。青白いインテリと笑われてはなりません。しかし,その時まで諸君は,この大学でいままで同様にしっかりと勉強してほしい。諸君の任務は戦後の経営にある」,といったのである。
高島が一番いいたかったことは,末尾の「諸君の任務は戦後の経営にある」であった。ここでの「戦後の経営」とは,単に企業経営を指しているのではなく,「戦後日本再建の経営」を意味していたはずである。
これを聴いた当時の学生の1人,平田清明は「忘れがたい言葉」であったという回顧談を遺している。それ以降高島は,繰り返し学生たちに向かって「生きて帰ってこい」といいつづけた。
ハ)「『生きて帰ってこい』は当時の『常識』に反していた」というのは,戦争中は禁句であり,反国体・非国民の立場・思想であった
「先生は『生きて帰ってくれ』といったので驚いた。出陣学徒の壮行会(1943年10月)でも出陣学徒代表が『生等もとより生還を期さず』と答辞で述べたように,兵隊にいくからには生きて帰らない覚悟というのが当時の常識になっていた。その常識と正反対の,『生きて帰ってくれ』という高島先生の言葉は奇異に聞こえたからである」と。
たしかに当時の常識とは180度異なっていた。ただし常識といっても,それは奇怪な常識であった。当時の多くの日本人を「常識」の虚名で精神的な金縛り状態にしていた具体例として『戦陣訓』(せんじんくん)を挙げることができる。
この『戦陣訓』は1941年1月当時の陸軍大臣・東條英機が出した訓令で,軍人としての行動規範を示した文書としてしられ,そのなかに「生きて虜囚の辱を受けず」などと命じた文言があった。
そこで考えてみたいことがある。高島善哉があの戦争中に,「生きて帰ってこい」と世の大勢に抵抗した姿勢は,この21世紀のいまなら「どういう生き方」につながるのか,についてである。
端的にいえば,反「日米安保」ではないか。日米安保体制は「アメリカの戦争」(テロへの戦争行為も含めた)のための暴力装置であって,しかも日本がアメリカに軍事面から下属する同盟関係を意味していた。
しかし,現在においては,反「安保」を堅持したからといって,あるいはこの安保の大枠のなかで護られてきた日本国天皇・天皇制に反対したからといつて,治安維持法における死刑が待っているわけでもない。なかでも反「安保」の世論は増えつつある。
だが,官僚統治の国家体制,米国追従(服従)外交しかできない外務省の存在は,アメリカ幕府〔あるいはその日本総督府〕の統治下に置かれているこの日本国の真相を正直に反映している。すでに集団的自衛権行使容認は閣議決定されており,特定秘密保護法の施行を目前に控えているこの日本国であるゆえ,いよいよ対米追従路線は深まるしかない。
にもかかわらず大手メディアは事実上,安保批判の精神を失っている。これはなにを意味するのか。あえていえば,権力批判を忘れて,目を曇らせ,状況追随型の単純思考に囚われているのではないか。これでは軍国少年だった者たちの小学生時代の思考と大差ない。
註記)以上,http://chikyuza.net/archives/1668,『ちきゅう座-メディアネット 地球の目 見る・聞く・話す-』2010年6月25日を参照。
補注)なお前述してもあったが,この註記を付けた引用は,2014年11月に書いた段落であったが,論旨・文意の方向性に問題はない。安倍晋三の第2次政権を経て,以上のごとき日本国の軍事路線,対米服属国家体制の枠組のなかでの方途は,すでに防衛省自衛隊3軍を完全にアメリカの傭兵である位置づけを済ましている。
ニ) 「若干の考察」 販売部数では日本一を誇る読売新聞は,かつて原発を導入する社主をいただき,最近では憲法改正案まで提案していた。ときの政府を応援する論調に慣れきった大手新聞社は,早くから「社会の木鐸」たる基本の資格をみずから放擲していた。
読売新聞に比べると多少はましであった朝日新聞のような新聞社が,従軍慰安婦問題に関するひとつの誤報記事のために,保守・右翼・国粋である反動的な言論界勢力から集中砲火を浴びせられるご時世である。
まるで,かつての戦争の時代におけるごとき〈ファッショの雰囲気〉が,一気に舞いもどってきたかのようなこの社会の空気である。
日本の産業経済・日常生活は「失われた10年」を,2014年の段階で観たときは3回目の段階にまで突入していたし,2023年の7月になった現在は,すでにその4回目にまでのめりこんでいる始末。
アベノミクス(これがミクスと称するに値するのか?)の空騒ぎは,いままでなにを残してきたか。それは,日本社会のいっそうの沈滞化であり,経済格差のさらなる拡大であり,政治行政方面での硬直化である。
このところ一番肝心である人口減少の対策問題ひとつにしても,これに対応すべきまともな国家政策的な展望や施策を描けず,実質的に拱手傍観の体であった。
フランスといえば,大昔から人口停滞・減少を来した先進国として有名であったが,いまでは,出生率を 2.01 まで回復させえた(その後は少し低下し,2020年は1.83まで下がっている)。
こ れに対して日本では,有効性のみこめる具体的な対策をいまだに立案できないでいる。すでにその模範となる実例が,フランス〔など〕に先行事例として明示されているのに,である。
さて,2014年12月14日には,高慢と稚拙と独善と奇矯などをないまぜにした自民党安倍晋三政権が決めた衆議院解散総選挙が実施されていた。その結果は自民党が291議席,連立を組む公明党が35議席を獲得,自公両党で計326議席となり,事後,安倍政権の悪政がさらにのさばる国会になっていた。
なにせ,自民党は単独ですべての常任委員会で過半数を占めることのできる絶対安定多数(266)を占め,自公両党では衆院で法案の再可決が可能となる3分の2の議席(317)を大きく上回ってもいたゆえ,安倍政権の傲岸不遜を最高潮にさせる原因を提供していた。
もっとも,有権者の半数近くが投票にいかず,棄権するような国政選挙が民意を反映しているとはいえず,別の表現をすると,4分の1しかいない自民党の支持者だけで,この独裁的な為政を許す「日本の選挙」の実情は,民主主義本来の機能を発動させえていない。
それでいて,「大東亜」戦争と呼んではいたものの,緒戦の優勢は半年しかもたず,その後は,「太平洋」戦争として大敗北を喫した旧大日本帝国を郷愁する「愚昧な宰相」が,2010年から7年と8カ月もの長期間,最高指導者の地位に居座りつづけてきた結果,この国の国家体制は実質,溶融・崩落したも同然となった。彼はそれなりに,この国を3流国に転落させるために「大きな負の貢献」をなしとげたわけである。
いま,この国は瀬戸際に立たされている。前世紀においてドイツが体験した2度の敗戦後における過酷な体験,つまり,その失敗過程(第1次大戦後;ヒトラーの台頭)とその克服過程(第2次大戦後;西ドイツだけによる奇跡の経済回復)などとは,政治的意味において無縁に戦後の復興過程をたどってきた日本のほうは,
21世紀の現段階になっても「過去の問題」に対する態度としてはなお,あたかも「戦争に負けたことなどなかった国家」であるかのような姿勢で,近隣諸国に対峙しつづけてきた。
日本という国が「歴史に対する現実的な姿勢」において持続してきた不徹底な国家精神が,近隣諸国との外交関係の良好な構築を妨げつづけてきた。靖国神社が「勝利神社(←幻想!)であった国家神道的な基本性格」をいまだに誇ってやまない実情(逆立ちしている狂気?)は,敗戦したこの国のその後にもつづく不徹底を,端的かつ正直に物語っている。
大東亜戦争のさなか高島善哉が一橋の学徒に向かい「諸君の任務は戦後の経営にある」といった〈歴史の含意〉は,いったいなんであったのか。この種の問いに関する歴史の記憶がいまさらにように再起されねばならない。この問いを裏返していえば,現在は「対米(戦勝国)従属の国家(戦敗国)である日本」に対する詰問になるはずである。
安倍晋三のように「戦後レジーム」を懐旧趣味にこだわって叫んできただけでは,敗戦国日本の対米「関係」を,なにひとつ改変できるわけがなかった。「密約が豊富に隠されている」日米安保条約の撤廃ができるというならば,安倍晋三流の「戦時レジーム」になんらかの意味が生まれうるかもしれない。しかし,この発想ははかない白日夢である。いまのところは……,永遠に……。
※-6 2020年3月1日「補遺」
安倍晋三が第2次政権を発足させてからというもの,いままでに「日本を改造してきた」実績があったと問えば,それは,例の「戦後レジームからの脱却」として成功してきた面があったといえなくもない。
だが,その成功は「失敗の成功」であった。本ブログ筆者もほかの記述中で,おおよそつぎのように表現したことがある。
安倍晋三は「自国を先進国集団の一群から後進国(発展途上国)の1国」に転落させてきたが,それもみずからが自国をそこへ蹴りこむ愚挙を犯した。
しかも,当人にはその自覚症状が全然ななかった。この国日本の「明治維新から以降に関した歴史の記録に対する総合評価」はさておいても,ただ1人,安倍晋三という人物にかぎっては,21世紀になってからこの日本を本格的にぶち壊す役目を,文字どおり果たしてきた。
その結末がどうなっていたかは,いうまでもなく,目前に展開されている現実が指示しているとおりであった。今後さらに時計の針が進むにつれ,彼がたくさん記録してきたその愚行さのかげんが,正確に棚卸しされれば,この国の脊柱が完全に破砕されていた事実は,嫌というほど,思いしらされるはずである。
--------------------
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
