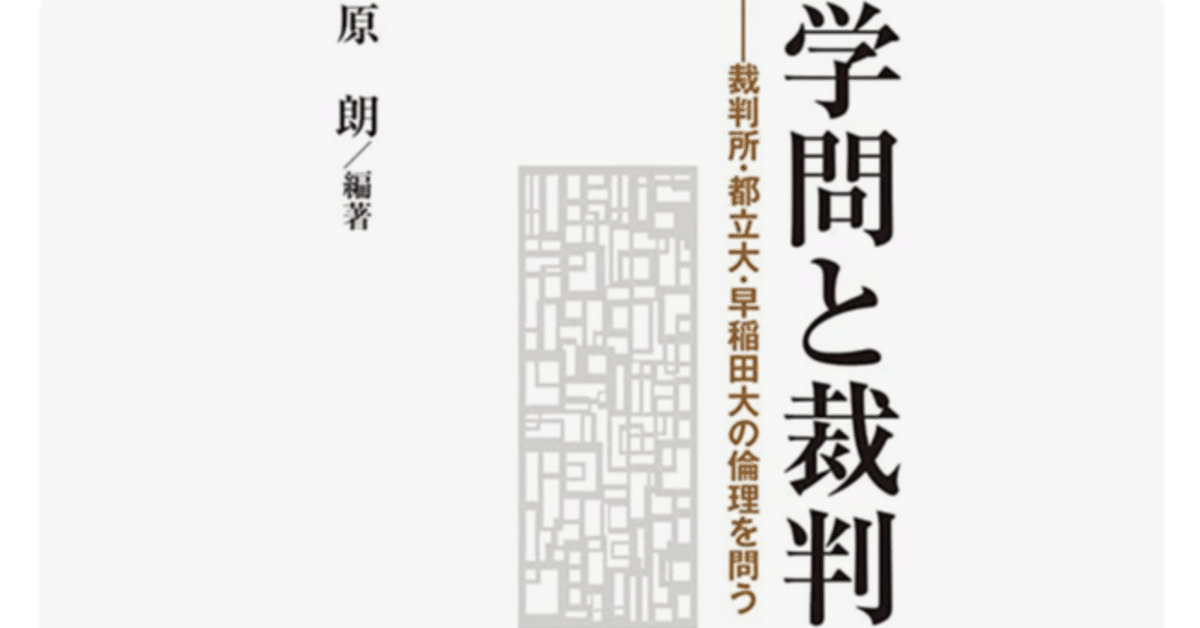
原 朗『創作か 盗作か 「大東亜共栄圏」論をめぐって』同時代社,2020年2月の公刊が意味する学問のあり方,小林英夫における学術作法「逸脱の問題」,そして「日本的に絶望の裁判所」(2)
※-1「本稿(2)」は,学問も問題領域」との交差において不可避に発生していた「絶望の最高裁判所」の姿を論じる「続編」である
この「本稿(2)」の記述は,原 朗『学問と裁判 裁判所-都立大・早稲田大の倫理を問う -』同時代社,2022年8月と題名の著作を話題の中心に置き,以下の議論をしていくことになる。
経済学研究における剽窃事件-半世紀以上も前に「原 朗の学問構想」を盗んだ小林英夫-をまともに裁けなかった日本の裁判所は,「専門知に対する基本的な知的限界」を,みずからはしなくも暴露した。法哲学とも無縁の司法機関であった。
#原朗 #小林英夫 #剽窃 #盗作 #絶望の裁判所 また,法律問題に真正面からとりくみ,裁判という国家にとって大事な仕事を担当する官庁である裁判所が,その知的水準においてひどく劣化・荒廃した本体を隠していた事実を露呈させた1件は,「小林英夫による原 朗の知的詐取」の問題をまともに裁くこと(審理さえ)できなかった「裁判所の姿」を,真正直に発現させたことになる。

いうなれば,裁判所なりの立場から有しているはずの「法哲学」はもちろんのこと,法律に関する一定の思想や特定の精神など,まるで存在しないかのような実体になりはてていた日本の裁判所は,瀬木比呂志『絶望の裁判所』(講談社,2014年)が批判した基本体質を,変革などできる態勢などまったく備えていない。そこまで極論されてもなんらおかしくはない。
この瀬木比呂志の『絶望の裁判所』に対する「Amazon 内の書評」には,冒頭の「それ」からして,こう書かれていた。なお〔 〕内の補正は引用者である。
裁判官はとくに司法試験という国家試験で最難関をクリアーしたエリートである。こういうエリートは,頭はいいが,凄まじいエリート意識と順位付け(上下関係)にすごく敏感で,プライドが高く,その言動はすさまじく,人をけちょんけちょんにすることに喜びと優越感を感じるタイプが多い。
それが,組織として行われている実態を暴いてくれている。本来,裁判官は憲法で「法と自分の両親〔良心〕にだけ基づいて判決する独立した任務者」として保障されているが,実際はかなり違うようだ。
最高裁長官及び司法行政を担う事務総局(裁判官資格を持つ司法官僚)以下,中央集権的なピラミッド型のヒエラルキーでがっちりと固められている。それは,人事任用,昇給昇格,異動などの手を使って,決まった枠をはみ出して,新しい解釈や社会の変化を取り入れて新機軸を出したり,藩論〔反論〕をするように人財は,露骨に,または隠微に冷遇され,冷や飯を食うことになる。
「本稿(2)」は,経済学における大東亜経済史研究にかかわって発生した剽窃事件(原 朗の学問構想を盗んだ当人であった小林英夫が,なんと原を提訴して勝訴した裁判)を,民事事件としてまともに裁けなかった絶望の裁判所(最高裁まで)の,その「専門知に対する裁判所の基本的な知的狭量あるいは理性の閉塞」を探る試みとなる。
【参考資料】-加藤陽子による関連の意見表明,上下に長い赤線の楕円は引用者-

※-2「まえがき」-裁判官という人たちの基本的な能力の限界-
2020年2月に,原 朗が『創作か 盗作か 「大東亜共栄圏」論をめぐって』という著書を同時代社から公刊していた。
この著作は,原が自分の若い時期から温めてきた東アジア経済史に関する「学問の構想」そのものが,研究仲間となっていた小林英夫によって全面的に盗用された(パクられた)と受けとめた事実を,しかも,それこそ生涯にわたって自分が受けてきたその悪影響を基軸に据え,記録として著わしたものである。
「本稿(2)」でもあらためて触れる点となるが,早稲田大学当局は自学とのかかわりにおいて,つまり早稲田大学の教員であった経歴も有する小林英夫の「論文」1966年の剽窃行為を認定する判断を下していた。
学問における剽窃の問題は,各学界において絶えず頻繁に問題になっており,それぞれなりに深刻な関連事情を意味する。今回における「原 朗の学問構想が小林英夫によってみごとなまで統合的・一体的に切り取られていた」という剽窃の一件は,
ウィキペディアの記述をのぞいてみると,しかしながら小林英夫側に偏した関連事情の記述しかなされておらず,裁判所の「不全に終わった判断」については記述していない。そういった,きわめて一方的で異様な解説になっていた。むしろ,裁判所の「完全に錯誤していた審理の結果」を踏まえたウィキペディアの記述になっていた,とも判断できる。
要は,日本の裁判所じたいにおける固有の問題もともなっていたわけだが,学問剽窃の問題に対する最高裁までの判断が,完全に「よりまともではなかった」という基本的な疑念だけが残された。
また,早稲田大学が独自に学内で判断して下した結論は,「小林英夫は原 朗の学問構想を盗んだ」という特定の評価になっていた。しかし,早稲田大学側のその後における原 朗側への対応も「逃げの姿勢」に変質していた。これにも司法の誤判断が大きく影響したものと解釈して,間違いはない。
裁判所の判決を重くみるのか,それとも大学側,そして当該学会(学界)側の専門的な判断を尊重すべきなのかといったごとき,まったく別次元での検討を切実に要求する顛末が,「原 朗の学問構想が小林英夫によってみごとなまで全体的・有機的に切り取られていた出来事」と受けとめて当然だった事件を介してであったが,いまさらのように,われわれの面前に登場していた。
今回の剽窃事件は,裁判所が最高裁まで示してきた「学問の問題,理論の解釈」に関する判決が,法律学を学び法曹界:裁判所の人間になった「裁判官」たちの,ねじれて不全になりはてた立場の制約を如実に表現していた。
いいかえれば彼らの立場は,経済学の研究領域で生じていた「学問構想全体の剽窃事件」が,必要かつ十分に裁かれるようにするための努力を,あからさまに回避していた。この事件を担当した裁判官たちが記録した,「彼らの側の〈実行力〉」に関した「かなりヒドイやる気のなさ」,すなわち「知性・理性の脱力ぶり」だけが,きわめて異様なかたちになって,それもみごとなまで鮮明に露呈されていた。
要は,国家試験である司法試験に合格し,しかも上位の合格者であったからこそ裁判官になれていたはずの「彼らの手に」,学界次元における剽窃・盗作問題が争点がもちこまれたところ,「学問・研究の領域」にかかわる提訴であったためか,裁判官たちはなぜか,好んで思考停止を選択したかのように反応した。彼らが残したその行状には,驚愕するほかない。
以下につづく記述で論及するのは「学術作法としての『逸脱の問題』」であり,その逸脱の程度が極端であった事例となっていた,小林英夫が原 朗を提訴した1件を,まったくまともに審理できなかった「裁判所におけるもろもろの限界:力不足あるいは関心の欠如」は,このさいあらためて,着目されるべき「司法の問題」となって浮上した。
いずれにせよ小林英夫は,早稲田大学当局が独自に調査した結果,処女論文の「元山ゼネスト-1929年朝鮮人民のたたかい」が,北朝鮮の学術雑誌『歴史科学』1964年第2号に掲載されていた,尹 亨彬「1929年元山労働者の総罷業とその教訓」1966年からの剽窃であった事実を認定された。
その小林英夫の剽窃は,尹 亨彬の「1929年元山労働者の総罷業とその教訓」1966年から,自分の論考のなかにその48%もの原文(朝鮮語)を日本語に翻訳したかたちで,それでいてその事実(朝鮮語・韓国語⇒日本語)を隠蔽するかたちで剽窃をおこなっていた。それでいて,そのすべてが自分の創作:独自の執筆だとして公表していた。
つぎの画像資料は,堀 和生が解明した事実を当該論文をもちだして説明している。文章の48%が,北朝鮮の研究者の2年前(1966年)の論文を,そのまま(もちろん翻訳して)引用注をつけずに,また資料的根拠も示さずに使ったものゆえ,典型的な剽窃・盗作をした論文として,むしろ,断罪されることになった。

むろん,原 朗からも,1970年代前半に小林英夫が「原の学問構想を盗作をした」と疑ってよい当然の経緯が相当詳細に説明されており,これを読んだ人は,原の訴えを否定できない。しかもこの場合,社会科学における「剽窃の発生」が,同一人において半世紀以上にもわたり,大々的かつ堂々と持続してきた事実が注目される。
原 朗が自分の人生行路を大きく狂わされた小林英夫の「剽窃問題」については,昨日:2023年3月22日に公開した「本稿(1)」が主にとりあげ議論した『創作か盗作か-「大東亜共栄圏」論をめぐって-』同時代社,2020年につづけて,
本日,3月23日に公開しているこの「本稿(2)」では,『学問と裁判-都立大・早稲田大の倫理を問う-』同時代社,2022年をもって検討されていた関連の諸問題をとりあげ議論している。
以下の記述は「本稿(1)」と重なる部分も出てくるので,事前にことわっておきたい。
ここまでの記述に関係しては,つぎの関連する文章がある。本日のこの話題に関して,ひとつの詳細な説明がなされている。ウェブ上でつぎに出所を明示しておくが,この紙面だと「タイトル未設定」の反応となってしまい,なんの表記もなされないので,住所(アドレス)のみを以下にかかげておく。もちろん,リンク先にはつながる。
⇒ http://eba-www.yokohama-cu.ac.jp/~kogiseminagamine/2019-06-30Horironbun-kakkisei.html
上記住所をクリックして開けると,冒頭に「堀和生論文『小林英夫氏盗作行為の起源』(詳細はこちら)の画期性」2019年6月30日記(後,適宜,添削,2020年7月15日現在)という,題名に相当する文句が書かれている。
前掲の「Amazon 広告」で挙げてみた原 朗の2著を買って読まないまでも,上記のごときウェブ上で参照できる記述を読んで済ませてもかまわない。もっとも,原 朗の『学問と裁判』2022年は,関連する文献や資料を相当数収録している。本書を取り寄せ,腰を据えて本格的に読んだほうが,断片的に拾って読むよりも体系的な理解がえられることは,いうまでもない。
※-3 本記述のごとき話題となれば,本来注目すべきことがらは,研究者自身の「研究力の不足」の問題だったのか,それとも,研究者自身の人間性にまつわる「倫理的な問題」だったのかなどに注目が集まる
a) 学術研究の専門的な展開にかかわる理論の問題であるだけに,この種の剽窃問題をめぐる「事実の把握および理論的な認識」については「根気のいる努力」と「持続した苦労」が必要となっていた。
b) ところが,この剽窃事件を裁いた裁判所は「この事件を裁く能力に不足ないしは欠損があり過ぎて」いて,提訴された事実をまっとうに審理できていなかった。というか,高裁以上の段階になると思考停止状態を,さらに連続させて発症していた。
裁判官になる人物は司法試験に合格した人材のなかでも,その成績が優秀な人物が選ばれている。けれども,今回における学問構想の剽窃事件を裁く能力も資格もない点をみずから露呈させた事実は,なんとも名状しがたい印象を抱かされた。
c) もっとも,学問の世界におけるこの種の特定の理論問題が,裁判所によって適切に吟味・検討(審理)しうるかというべき,関連させていえばもっとも基本的な疑念も同時に浮上していた。
さて,原 朗『創作か 盗作か 「大東亜共栄圏」論をめぐって』同時代社,2020年2月が公刊され,当時,この本の広告が出ていたのをしった本ブログ筆者が注文したのは,この本が自宅に投函されて届いたのは2020年3月2日であったから,前日の午前中には注文していたことになる。
ともかく,この本を読みはじめたが,事前にそれも予断的に感知していたつもりであった点は,多分,「裁判官が専門的な知識で追いつけず」に,トンデモない判断(裁判の審理)をしていたのではないか,という「予想」であった。
実際に,この本を読んでみたところ,まったくそのとおりにドンピシャリの中身であった点が確認できた。
簡単にいってしまえば,法理をあつかう専門家である裁判官には荷の重すぎた,それも社会科学領域において発生していた「剽窃問題」の検討・吟味が迫られていて,結局,やる気のなかった裁判官たちであっただけに,「彼らには荷が重すぎた」案件であったことになる。
しかし,裁判官は世の中のあらゆる出来事・事件をあつかわねばならない立場に置かれているゆえ,この提訴(民事の場合)の審理はよくできるが,ほかの提訴はそうではないなどと,事前に仕分けなどすることは許されない。彼らは,法律の次元から裁判所にもちこまれる「世間のあらゆる問題」を引きうけ,それこそまっこうからとりくみ,裁かねばならない。
ところが,学問や理論,ここでは経済学の経済史,それも戦時体制期における東アジア圏域の国際政治・経済史にかかわる専門的な学識を前提とした裁判における審理が,東京地裁および東京高裁の判決がともに,経済学の研究分野において詮議をする実力・能力(学識や情報)を,もとより完全といっていくらいもちあわせていなかった点が実証(暴露?)される結果になっていた。
補注)なお,当該の裁判は,最高裁判所までもちこまれたが,2020年6月に上告棄却の決定が出ていた。
原 朗のこの本『創作か 盗作か 「大東亜共栄圏」論をめぐって』2020年2月のなかでも触れられているように,裁判(官)が学問の内容について,その研究領域の業績・成果に関した現状把握をよく理解できないまま詮議した結果,しかも今回の場合,「盗作」された原が「盗作した小林英夫」に提訴されて,一審・二審ともに被告の原が敗訴までするという,学問の世界における視座からみれば “驚天動地の顛末” が現象させられていた。
補注)原 朗(1939年生まれ)の主な履歴は元東京大学経済学部教授。くわしくはつぎの資料を参照されたい。
⇒ https://www.keisen.ac.jp/campuslife/pdf/keisen_2.pdf
d) 以上の概略に関して “そもそもの話” をする。関連する画像資料は前段にかかげてあったので,念のため断わっておきたい。
小林英夫が学究として初めて公表した学術論文「元山ゼネスト-1929年朝鮮人民のたたかい」『労働運動史研究』第44号,1966年6月の内容が,なんと48%もの割合で,原資料(朝鮮語:韓国語を翻訳した)の文献資料からの盗作⇔利用であった事実が指摘されていた。
さらに,この小林「論稿」1966年の延長線上に,小林英夫『「大東亜共栄圏」の形成と崩壊』御茶の水書房,1975年が位置していた。この「前後の関係性」の理解をしたところで,大筋の点でも枝葉の面でもけっして間違いにならない。
補注)なおここでは,「サイト紹介,、「原朗氏を支援する会」ウェブサイト 小林英夫氏盗作行為の起源(全国国公私立大学の事件情報)」( ↓ )の参照を勧めておきたい。
繰りかえしになるが,堀 和生によって,小林英夫の処女論文の「元山ゼネスト-1929年朝鮮人民のたたかい」が,北朝鮮の学術雑誌に発表された論文,尹 亨彬「1929年元山労働者の総罷業とその教訓」『歴史科学』1964年第2号の剽窃であったことが指摘されていたが,この事実は小林英夫のその後における学者人生の起点を意味することになった。
小林英夫は,尹 亨彬論文の結論部分を,出所を明示することなくほとんどそのまま引用しており,小林論文のなかで尹 亨彬論文と重複する比率は,文字換算すると48%に達していることが,堀 和生によって解明されるまでは,学問の世界で「発覚する」ことになっていなかった。
しかし事後,その事実は小林英夫自身の学究としての存在価値を計る試金石になっていた。
「小林英夫原告 ✕ 原 朗被告」という裁判の構図のなかでは,いったいなにが肝心な問題として争点になっていたのか。裁判所側の自堕落な審理の方途を,まえもって確実に理解しておき,吟味する必要があった。
e) ここで「人物紹介」をしておく。
小林 英夫(こばやし・ひでお)は1943年8月24日)東京生まれ,1966年東京都立大学経済学部卒業,1971年東京都立大学大学院社会科学研究科博士課程修了後,同経済学部助手。その後,1973年駒澤大学経済学部教授(~1997年),1978年文学博士(東京都立大学)。
研究者としての小林英夫は歴史学者・経済学者で,専門は東アジア経済論および植民地経済史である。とくに,第2次世界大戦以前における帝国日本の東アジア支配の研究や,近現代日本の社会経済史で戦後の日本の経済発展の研究をしてきた。近年は満州国・満鉄・満鉄調査部に関する著作を多く公刊した。
※-4「原朗氏を支援する会」ウェブサイト
なお,このウェブサイト https://sites.google.com/view/aharashien/堀和生小林英夫氏盗作行為の起源 は(少し前段に既出であった),2020年3月3日の記述をもって,つぎのように報告していた。冒頭の段落付近からしばらく引用する。
なお,以下の記述は「本稿(1)」の反復となるが,重要な論点ゆえ,再度とりあげておくことにした。そちらですでに読了していた人は,結論部までは飛ばしてもらって,けっこうである。
◆ お知らせ ◆
【早稲田大学が小林英夫氏の過去の論文を「盗作」と断定しました】(2020年3月3日更新)
a) 原 朗氏を名誉毀損で訴えている小林英夫氏は,ほかにも盗作事例が多い人物であるといわれており,原氏が刊行を予定していた著作物の内容・構想を小林氏が無断で先に出版してしまった今回の事案も,その一つであったと私たちは考えております。
補注)ここで「小林英夫」「は,ほかにも盗作事例が多い人物……」と説明されている点は,今回におけるこの問題を決定的に印象づける表現である。
「三つ子の魂百まで」とよくいわれるが,前出の「元山ゼネスト-1929年朝鮮人民のたたかい」は,実は小林英夫『「大東亜共栄圏」の形成と崩壊』1975年にとってみれば,その「嚆矢:とっかかり」を意味していたと解釈できる。
〔引用の記述に戻る→〕 この件に関連して私たち,原 朗氏を支援する会では,小林氏が早稲田大学に所属しておられた時点で,自著『論戦「満州国」・満鉄調査部事件ー学問的論争の深まりを期して』(彩流社,2011年)に収録した自身の過去の論文が,
尹 亨彬著「1929年元山労働者の総罷業とその教訓」(『歴史科学』1964年第2号,1964年3月刊,朝鮮語)の盗作であることを発見し,早稲田大学に対して本会の会員個人(以下,「通報者」という)の名によって,その点の確認を求めておりました(2019年7月2日)。
補注)1966年の盗作論文を半世紀近くも時間が経過して,新著のなかに収録するという勇気(蛮勇?)には関心するが,小林英夫は「元山ゼネスト-1929年朝鮮人民のたたかい」と題した論稿が,いつか必らず誰かの手によって「その秘密が暴露される」かもしれない危険性を,前もって感じてはいなかったのか?
その間において,日本人研究者で韓国語を駆使して研究する学究の数が大幅に増えた状況をしっていれば,そうした「危険性」(自分の盗作がバレてしまう可能性)が徐々に高まっていく時代の流れを感知(不安視)できていなかったのか,ということになる。
学問の世界では正式に公表された文献・資料は,ほぼ永久的にといってくらい,図書館という容れ物(資料館)のなかにその現物を保存されている。いいかえれば,学問の発展に生かすための踏み台とされ,利用される場面を期待している。
文献・資料は,図書館に保存されつづけるのは,そうした場面が来ることに備えているからである。図書館という容れ物(資料館)は,そのためにこそ存在するのであった。文献・資料が電子化のかたちで保存されていっても,基本的になんら事情に変りはない。
小林英夫がその原資料(『東亜日報』1929年当時など原資料)を利用した『元の朝鮮語文献』を,日本語に翻訳するといった浄化の方法を使い,大々的に剽窃していた事実が,21世紀のいまごろにもなってから「白日のもとに晒されていた」。
相当に時間はかかったが,まさに「天網恢々疎にして漏らさず」ではないか。それでも,小林英夫はこんどは,早大当局を相手に自分は盗作はしていないと,裁判に訴えることにでもなるのか?
〔引用の記述に戻る→〕 この間の経緯はすでに本ホームページの「おしらせ(2019年8月31日更新)」に掲載してあるとおりです。また,その関連文献は本ホームページの「おしらせ(2019年6月28日更新) 小林英夫氏の剽窃疑惑に関する新たな指摘について」にも,原 朗著『創作か盗作かー「大東亜共栄圏」論をめぐって』(同時代社,2020年2月)の471~488頁にも収録されております。
b) 私たちの照会を受けて早稲田大学では,学術研究倫理委員会が学内規則にしたがって調査委員会(学外者,朝鮮史研究者を含む)を設置して審理をおこない,本〔2020年〕2月25日付けで「アジア太平洋研究科における研究不正事案(盗用)に関する調査報告書」(以下,「報告書」という)を採択し,通報者にその旨,連絡がありました。
補注)なお,小林英夫の「当該論文」,「元山ゼネスト-1929年朝鮮人民のたたかい」『労働運動史研究』第44号,1966年6月については,つぎ(以下の画像資料)のように「その現物」が紹介されていた。
これをのぞいてみればすぐにみてとれるように,「小林論文のなかで尹 亨彬論文と重複する比率は,文字換算すると48%に達している」事実が,視覚的にも分かる。盗作している個所にはすべて赤線〔で傍線〕が引かれている。
その画像資料は前掲されていたが,だいぶ段落が進んできており,あいだが開いてきたるの,ここでも再度挙げておいた。

〔引用の記述に戻る→〕 〔その早大の〕「報告書」は小林氏からの聞き取りを含む調査をおこなったうえで,「小林氏が盗作をおこなった」事実を明確に認定しております。公開されている同大学の学内規則によれば,この事案は今後,アジア太平洋研究科での審議を経て,理事会による処分の決定に移ることになったと理解されます。
c) 小林氏の盗作方法〔ここでは『「大東亜共栄圏」の形成と崩壊』御茶の水書房,1975年に関する話題に移動している〕は,文章そのままをまねるという方式ではなかったため,これまで名指しの批判はなされてきませんでしたが,論文の冒頭で何人もの先行研究者の名前を列挙し,本論に入ると個々の実証,評価ともに,内容的には特定の研究者の成果をそのまま利用しているにもかかわらず,読者にはすべて小林氏の研究成果とみえるようになっている点で共通しています。
d) 今回の事案についても,調査委員会の調査に対して小林氏は,引用した研究者名を先行研究者として最初に断わっているのだから盗用には当たらないと主張していますが,調査委員会と学術研究倫理委員会は学術的にみてそれは認められないと判断して,明確に「盗用」と認定しています。
裁判官は「盗作とまではいえない」と判断停止状態であった小林氏の手法が,学術界の当然の基準によって明快に断罪されたことの意義は大きいと評価できます。
e) 原 朗氏の裁判においても小林氏がとっている手法はこの事案と同じなのですから,小林氏の行為は盗作に当たるはずであり,したがってその事実を指摘した原 朗氏の行為が重い責を負わされる理由はなく,最高裁が一審,二審の判決を追認することは許されるはずはありません。
この案件の経緯を最高裁に伝えることによって,最高裁が素直に事実に向かいあい,地裁,高裁の誤った判断を正すことを切に望みます。それが実現すれば,司法の判断によってではなく,学術界の判断が主導して,他人の業績を盗用した不祥事が正当に指弾されたという望ましい結果を,私たちは手にすることができます。
その可能性に期待して,私たちもいっそう努力したいと決意を新たにしております。そのために必要であれば,今回の事態の詳しい経過や小林氏の他の類似案件等についても,このホームページで事実関係を明らかにしていきます。(中略)
f) 〔原 朗『創作か 盗作か 「大東亜共栄圏」論をめぐって』同時代社,2020年は〕6年半を経過してなお決着がつかない長期裁判のなかで,原氏側から提出した主張類と,一審・二審の判決,原氏の主張を支える堀和生氏・松村高夫氏の「意見書」,小林英夫氏による他の剽窃行為の新証拠などを収録し,それらのおのおのに原朗氏本人がそれぞれ短い解説をつけて読者の便に供しています。
この裁判は,盗作された側が訴えられ,盗作した側は「盗作とまではいえない」として推定無罪とされ,他方,原氏は無罪の者を「盗作」と口外したとして名誉毀損で有罪とされ,多額の賠償金を課せられています。
万一この判決が最高裁でも維持されると,学会・大学等で盗作と判断した事案が,裁判に訴えられれば,事案を提起・審議・処分決定した人たちが名誉毀損に問われることになりかねません。
最高裁判決に向けて,ぜひ本書をお読みになり,ご支援くださいますようお願いいたします。
g) 「石井寛治氏の推薦文」から
本来, 剽窃の認定は,アカデミズムの内部で自治的・自律的に判断が下されるべきものです。にもかかわらず,小林氏は,突如として司法の場に自己の正当性を訴え出たのでした。そして,2019年1月に下された第一審判決では,原告である小林氏の主張を大幅に認め,被告である原氏に対して賠償金220万円及び遅延損害金の支払いを命じるという不当な判断が下されました。
そこでは,分析視角の設定や歴史的事実の確定は「誰にでも行い得るもの」として独創性を否定され,表現の類似や重複も免罪する,現在のアカデミズムにおける厳しい基準からすれば極めて杜撰といわざるをえない認識が示されていました。(中略)
h) 原 朗氏を支援する会(以下,本会とする)を構成する私たちは,この裁判が小林氏と原氏との個人的な関係に留まらず,社会と学界にとってきわめて深刻な意義を有するものと捉え,裁判資料を公開することによって広く問題を提起したいと考えています。
i) 【新年のご挨拶】(2020年1月1日更新)
原 朗氏より皆様へのお礼を兼ねた年頭のご挨拶が送られてきましたので,掲載いたします。
「支援する会」のみなさまへ -2020年を迎えて- 原 朗
昨年中は貴重なお時間を割いて,たびたび小生の裁判の傍聴や集会などにお集まり下さり,さまざまな形で大きな力強いご支援を賜りまして,まことに有難うございました。年の初めにあたり,みなさまの本年のご健勝とご研鑽を心からお祈り申し上げます。
ご承知の通り,私の裁判では地裁・高裁とも,学問的にはほとんど理解不可能な,誤まった不当な判決に終わりましたが,昨〔2019〕年11月下旬に無事「上告理由書」と「上告受理申立理由書」を裁判所に提出することができました。
最高裁判所の判決までには若干の時間がかかるようですので,現在私は裁判の記録のとりまとめの作業を進めております。地裁や高裁の際のような司法による非論理的かつ非合理的な判決がそのまま学術の世界に持ち込まれることは絶対に防がなければならないと考えるからです。
まず地裁の判決があった時点で,私はこの裁判が,被告である私と原告である小林英夫氏との個人的な争い,すなわち盗作(盗用・剽窃)行為の有無・名誉毀損行為の有無のみにはとどまらず,裁判所と学界,すなわち司法的判断と学術的判断との深刻な対立を含むものに局面が急変した,そう判断いたしました。
学界において長い年月をかけて作りあげられてきた研究倫理に関する慣行と議論を無視した根拠のない判定がなされたのです。地裁の裁判官たちは,この学界の盗作を厳禁する慣行を無視し,それと全く異なる非学術的・恣意的な基準を用いて,被告の主張をほとんど全面的に退け,学術的・学問的にみて本質的・内容的な論点は全て回避し,表面的・形式的論理のみによって判決を言渡しました。
研究不正を行ったものを,学界が自律的に処分した場合に,被処分者が裁判所に訴え出れば,形式的・非学問的基準によって逆に「名誉」が回復されるばかりか,数百万円の慰謝料すら得ることになり,学界に大混乱をもたらすことになりましょう。
裁判に要する長期の時間と巨額の費用を考えて,研究不正の摘発は極めて抑制されることになるのは必至です。地裁では審理に6年近い時間を費やし,何回も判決期日を延期しながら,最終的には没論理的にただただ原告側を勝訴させるためにひたすら原告側の誤った論法に辻褄を合わせ,上記のような学術と司法の深刻な対立の問題を孕む判決文を急遽とりまとめざるを得なかったのだ,という印象を禁じ得ませんでした。
高裁での審議と判決にも驚くことがいくつかありました。まず5分もかからぬ初回のみの結審で,最後の事実審としての役割は全く果されなかったこと,判決期日は1回延長されただけでしたが,他の案件と十把一絡げに判決がなされたこと,判決の内容が地裁判決の不備を弥縫するのに懸命で,当方がすでに地裁段階から詳細に示しておいた「剽窃の定義」も全く無視してわざわざ『広辞苑』などの簡単な語釈などに依拠したことについては,驚倒するほかありませんでした。
また当方への立証責任のハードルを極端に高めたこと,「(剽窃)とまではいえない」というレトリックを何回も多用して,なぜ「とまではいえない」かの論証は全くなされていないこと,学術と司法との関係にも全く無意識であること,地裁判決を維持することに汲々として,本質的論点については地裁判決と同様に全く触れず,要するに高裁判決と地裁判決とはお互いに庇い合おうとしていることが明白に読み取れてしまうこと,等々枚挙にいとまがありません。
地裁・高裁の審理が上記のようなものでしたから,その実態を明らかにするためには,原告の訴状提出から,地裁・高裁を経て,今回の上告に至るまでの経過を私なりに整理し,要約して,「司法」的判断がこれほどにも非論理的であることを,学問の世界で日夜研究教育に励んでおられる方々や,一般社会の市民の人々に,具体的にこのような裁判が進行中であり,かつ最高裁の判断を求めていることを,裁判関係の当事者のみではなく,他の分野の研究者や一般読者にもわかりやすくまとめておくことが必要だろうと考えました。
やはりこの裁判も歴史の中の一つの事件として,時の流れに沿って書き綴っておきたいと思うわけです。まだ少々時間がかかるかと思いますが,しばらくお待ち下さいますよう。そして今後ともこの事件と裁判につきよろしくご支援のほどお願い申し上げます。
以上をもちましてみなさまへの年初のご挨拶かたがた現状のご報告とさせて頂きます。
2020年1月1日
※-4 本ブログ筆者の関連するかのような思い出
いまからだとだいぶ昔になる。大学の教員になりたてのころであった。同僚の,それも本ブログ筆者と年齢の近い(若干年上だった)教員が,他大学のある教員が書いた論文1編を,まるごと剽窃というか,完全にドロボウして自分の論文として,自学の研究紀要に投稿し,公表した。
付記)この※-4以下の記述は「本稿(1)」と同一であるが,この「本稿(2)」に入って読んでくれた人を配慮し,そのまま再掲している。
ところが,この事実はたちまち盗作された当人(たまたま近くの大学の先生であった)にバレてしまい,当方の大学幹部にその旨の抗議がなされた。その後のくわしい経緯はさておき,論文の盗みをしたその教員はただちに大学を辞めた。
ただし,その処理(処分)の方法は,彼の同僚たちに対しては,その論文剽窃の事実を教えていなかった。だが,その事実はその後,たちまちに同僚たちがしることになった。
この事件を起こすとき,その剽窃行為をおこなった教員は,実はほかの件でも “同僚との関係” のなかである特定の “出し抜く行為” をしていた。
どういうことかというと,本ブログ筆者が当時所属していた当該の大学が新学部を作った初年度だったので,これを記念して特集・記念号を組むことを企画したのだが,それ(学部の特色)に適した論文を,既存学部に所属するわれわれ(本ブログ筆者を含む数名)に対して,そのうちの誰かが寄稿してほしいという依頼があった。
その数名のなかに前段の彼(教員)も含まれていた。ところがその後,なんの相談も協議もないまま,彼が勝手に投稿した論文がいきなりその特集・記念号に掲載されていた。
当初は,本ブログ筆者やそのときいっしょにその寄稿の依頼を受けていて数人の同僚が,それでは,あとであらためて皆で相談のうえ,誰が請け負って書くか決めることにしようということになっていた。にもかかわらず,彼が独断の抜け駆けで内緒・勝手に寄稿していた。
ところがである,この彼が書いた論文が前段に触れたように,完全にといっていいくらい百%剽窃したものであった。結局,彼は2つの過ちを犯していた。ひとつは同僚を無視して自分で書いた(はず?)の論文を提出していたことである。もうひとつは,この論文が剽窃したといっても,他者の論文をまるごとそっくりそのままパクった中身であった。
だから,即座といっていいくらいに原著者に発見されてしまい,「盗作」したと告発されてしまった。最後に付けくわえておくと,その彼は経営学者であり,所属する大学の商学部で労務管理論を担当する教員であった。
補注)大学間においては通常,研究紀要はおたがいに寄贈しあっているし,とくに同じような学部がある大学のあいだでは,そうした寄贈の相互関係はかなり密である。以上に説明してきた盗作の場合は,それこそ一発で,原執筆者に看破されていた。
というのも,地方の都市圏において,双方の(剽窃をされた・した)教員がそれぞれ所属する大学2校は,かなり近い位置関係で立地してもいた。
おそらく,盗作の被害を受けた教員のほうは,その現物の研究紀要を初めて開いてみたとき,おそらく腰が抜けるほどびっくりしたと想像する。なにせ,自分の論文と瓜二つ(?)のそれが,他大学の研究紀要のなかで,他者の氏名で掲載されていたのだから……。
以上に説明した『問題の教員』がその後,どのような人生を送っていったかしらないけれども,ずいぶん間の抜けた愚かな行為をしたものである。
前述に触れた関連の事情に戻っていえば,同僚には書かせたくなくて,自分がどうしてもなにかを書きたかったのか? それにしても他者の論文をそっくりそのまま盗んで自学の研究紀要に投稿したのであるから,厳密には盗用とはいえない。
なんといったらいいのか,完全に密輸入をした現物を自分の論文として自学の研究紀要に投稿していた。空いた口が塞がらなかいというべき,実にお粗末な出来事であった。
だが,小林英夫『「大東亜共栄圏」の形成と崩壊』御茶の水書房,1975年の場合は,そもそも「著作の構想」全体が剽窃的な著作だったとしても,たいそうな大作であった。ともかくも,本格的に相当に手のこんだ盗作行為が,堂々と披露されていた。
それが可能であった理由・事情は,原 朗『創作か 盗作か-「大東亜共栄圏」をめぐって』2020年を読めば理解できる。分かりやするために,あえてたとえていうとしたら,原は「飼い犬に手を噛まれた」どころか,命こそ落とさなかったが,喉元の急所すれすれに牙を食らった。
原はそのせいで,自分の学究生活の全過程にわたる「大損害」を受けたことになる。
本ブログ筆者が小林英夫の研究業績に関しては,いままでとくに感じていた点があった。それは,小林英夫が32歳の時に公刊した『「大東亜共栄圏」の形成と崩壊』御茶の水書房,1975年以降においては,これに匹敵するか,あるいはそれ以上だと評価されていい業績が産出されていない点であった。
小林英夫は本書をもって「天才だ」とまで讃美を受けていたそうである。だが,年齢的に判断すると,小林が同書を上梓できる本当の学究力であったならば,一般的には40歳台・50歳台になっても,もっとさらに充実した浩瀚な業績を,それぞれ最低1冊や2冊は上梓できうる「潜在的な研究力・学識の実力」を,もともと十二分に有していたと推察されてよい。
ところが,小林英夫が事後に公表していく著作は,この『「大東亜共栄圏」の形成と崩壊』1975年(A5版で本文 545頁)に比較すると,いずれも質的には比肩する中身をもつものがなかった。多作・多産であったが,内容面ではそのように評価されてよい。
その事実について本ブログ筆者は,いままでは具象的には表現できなかったけれども,どうしてもすっきりしない印象を抱きつづけてきた。しかしながら,今回の原 朗『創作か 盗作か-大東亜共栄圏」論をめぐって』2020年の公刊は,そうした本ブログ筆者の “薄淡くて不確かな疑念” に照明を当ててくれるものになった。
また,原 朗は2010年代になってからようやく,小林英夫に剽窃されたと判断されてよい「自身の学問な創案」(理論枠組や研究課題のこと)を,論文のかたちではなく単著のかたちにして,あらためて公刊した。
※-1 『日本戦時経済研究』東京大学出版会,2013年3月,本文A5版,491頁。英文書名,The Japanese war economy, 1937 - 1945.
※-2 『満洲経済統制研究』東京大学出版会,2013年3月,本文A5版,213頁。英文書名,Japanese control of the Manchurian economy, 1931 - 1941.
本ブログ筆者や経済学者ではなく経営学者として教員の人生を過ごしてきたので,原 朗の研究業績を十分にかつ細密に講釈・解説しきれる立場にはない。けれども,日本と満洲の戦時体制期における企業経営史には関心をもって研究をおこなってきた関係で,それなりに関心をもって原の業績には接してきた。
ところが,そのなかで継続して不思議に感じていた点があった。それは,原 朗(1939年生まれ)はなぜ,前段のごときの自著:単行本を,比較的若い時期に出版・公表していなかったのかという疑問であった。編著中心となっている彼の刊行物が多く,単著は放送大学用の教科書1冊をのぞけば,研究書の公刊は2010年を過ぎてからであった。年齢的には70歳台での公刊になっていた。
後づけ的な都合のよい解釈となるほかないが,そこにはなにか,意味深長な背景・事情があったわけである。もちろん,そのあたりに関する経緯・物語については,原 朗『創作か 盗作か-「大東亜共栄圏」をめぐって』2020年を一読すれば氷解することがたくさんある。
以上に述べたごとき,これまでは,なにかあいまいであった「小林英夫と原 朗」の関連をめぐる一定の疑念が,ようやく具体的な構図となって,歴史的の流れに即して可視化しえたしだいである。
仮に,最高裁で小林英夫が三度目に勝訴しえた(上告棄却であった)としても,原 朗に対しては “実質的に完全に敗訴” であった。その点は,学問の立場を尊重する者たちが判定を下すとしたら,誰もが確信をもって必らずいいきれる1点である。
仮に,原 朗が三度目に小林英夫に敗訴したとしても(前段での指摘どおり,そうなっていた),学究の立場ではいっさいなにも負けてはいない。裁判所の判断と社会科学的研究の立場が出せる評価とが同一であらねばならない絶対的な事由は,なんら特別にもありえない。
原 朗が自分の創説した「学問の構想と課題」を,小林英夫にごっそりと盗まれた時点においてすでに,小林のほうが「学術研究」に従事する1人の人間としては,みずから「敗北宣言」を放っていたに等しい。
およそ半世紀近くもの期間(正確には半世紀ほど経っている)を,小林英夫から受けた仕打ちに耐えてきた原 朗に対しては同情してもしきれない。それほど気の毒な目に遭わされてきた。
はたして,最高裁までいったから三度にもわたって,「小林英夫は『勝負〔裁判〕に勝ったけれども,真の試合〔学問〕に負ける』」ことになっていた。
日本の裁判所は最近,その体たらくぶりがめだってはげしいが--原発裁判ではまだその特性がめだち,自民党政権の腐敗・堕落をまともにとりあげて裁こうとすらしない--,このような問題の領域(学問の領域)にあってまで,そのダメぶりを発揮していたのか?
安倍晋三への忖度は不要の領域に思えるのは当然に過ぎるが,学問の世界にまで裁判所のだらけた審理をもちこむようでは,世も末である。ガリレオガリレイの時代でもあるまいに……。
ともかく,早稲田大学側は一時期,自学の教員であった小林英夫「論文」1966年の剽窃行為を認定する判断を下した。
裁判所が最終的に三度も,小林英夫が『著書』1975年において剽窃していた原 朗「学問の理論枠組・研究課題」の存在を認定しなかったとしても,社会科学である経済学の経済史研究という学域で発生した剽窃事件に対して,裁判所側がそれに応じられるだけの「法廷の指揮力」や「法曹:司法として枠組を形成しえなかった点」だけが,いたずらにきわだつ歴史を記録したことになる。
※-5 補 記
a) 松村高夫・江田憲治・柳沢 遊編『満鉄の調査と研究-その「神話」と実像』青木書店,2008年をなにげなしに,今回のこの記述に関連する文献の1冊として書棚から採りだして観たところ,ある事実に気づいた。
それは小林英夫を,巻末の人名索引に挙げていない点である。本文や註記中において,小林英夫の姓名がまったく登場しないのではなく,かなりの回数出ている。なんらかの含みを感じざるをえなかった。
本記述がとりあげている問題が「問題になる」以前に公刊されたこの著作が,そのような小林英夫のあつかいをしていた事実は,やや不自然に感じられた。
b) すでになんどか触れたが,『「原朗氏を支援する会」ウェブサイト』 https://sites.google.com/view/aharashien/堀和生小林英夫氏盗作行為の起源 があった。
以上の「本論」の記述では追加できなかった「その後の出来事」については,そのサイト内を参照されたい。その間における関連の活動報告が詳細に記載されている。
c) 原 朗編著『学問と裁判-裁判所・都立大・早稲田大の倫理を問う』同時代社,2022年8月が公刊された。本記述で論じたさらに以降の時期に関して,当該の問題をめぐり制作された本である。
日本の『絶望の裁判所』(瀬木比呂志著,講談社,2014年〔の書名〕)は,ほかの誤審裁判を挙げるまでもないが,学問の世界における剽窃・盗作問題になると,まるで・あたかも無力・無策(無気力・無責任)であるかのような基本姿勢を一貫させてきた裁判所の立場を,その当事者の立場に居た人間の側から説明している。
------------------------------
【参考資料】-「本稿(1)」でも参考用に挙げてあった関連の資料-

------------------------------
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
