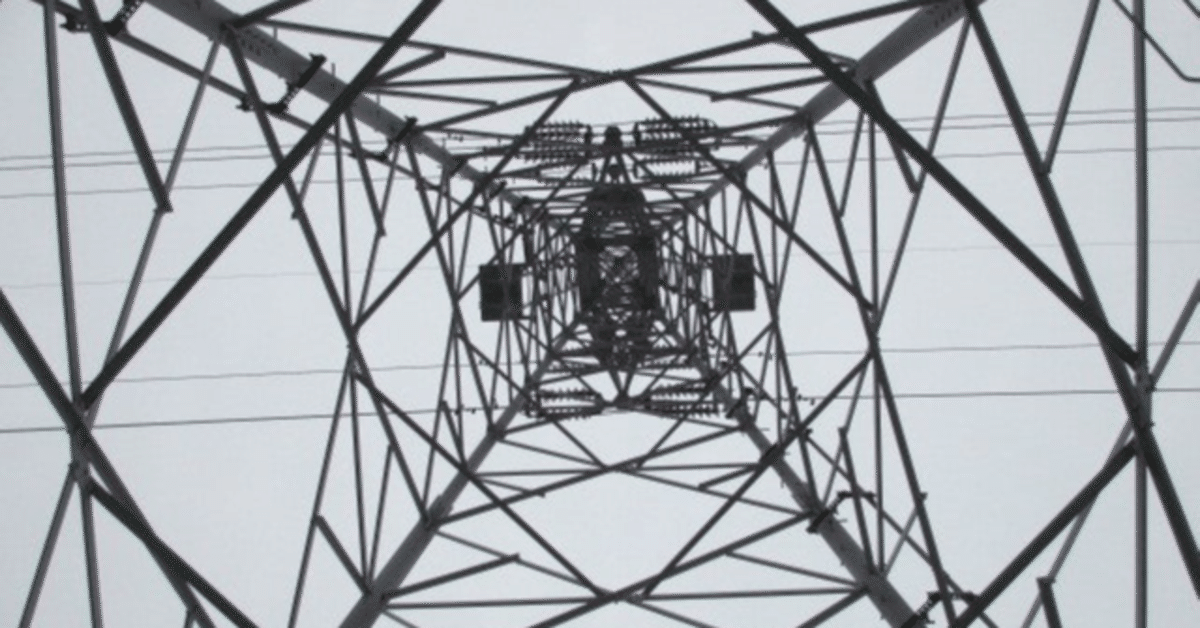
考え事#19 主観的な学びと客観的な学び
こんにちは。以前、深い学びについて記事を書きました。
今回は、タイトルの通りなのですが、数日前に思ったことを書いてみようかと。
主体的・対話的という言葉の個別性
主体的・対話的で深い学び。
この言葉が改めて、しっくりこないような感覚が最近どうも自分の中に出てきている。言いたいことはわかるし、言っていることに対しても基本的に賛同の立場なのだが、僕の記事でも何度も触れている通り、主体的・対話的というのがあまりにも人それぞれ感覚が異なる事が原因だと思う。
主体的だなぁとか対話的だなぁ、というのは、誰もが過去の自分と照らし合わせて、自分にとっての主体的、対話的をもとに考えるしかない。そもそも”僕の主体的のイメージ”と全く同じ主体的のイメージを持っている人はいるのでしょうか?という問いにいつもぶつかる。
人それぞれ、主体的というもののイメージが個々に異なるだろうという事なのだが、そうなると議論する際にはまず、そこに差があるよね?という合意形成に始まり、ではあなたの主体的のイメージは何ですか?と、すり合わせをした上で本論に入らなければならない。そんな議論をここ数年何度も、色んな人と繰り返してきたのだが、はっきり言って毎回、回りくどくて面倒くさいと感じる。
そもそも、主体的・対話的な学びというのは、あくまで手段なのではないか?
大切なのは、主体的・対話的な学びを繰り返すなかで、「深い学び」を達成することだ。深い学びに突入する過程に「主体的・対話的な学び」を認識する人が多いはずだ、という仮定に基づいてこの言葉は形成されていると認識している。
であるならば、手段としての「主体的・対話的」は代替可能というか、再定義可能なのではないかと思う。もう少し客観的に把握しやすい言葉があるのではないかというのが主に言いたい事だ。
深い学びを客観的に表してみる
これも冒頭に挙げた記事に書いていることなのだが、再掲する。
話を深い学びに戻す。
とにかく深い学びっていうのは、その形は多種多様で、誰にもコントロールできない類のものだ。深く学んでいる本人でさえ、自分の知的好奇心をコントロールできないからこそ深い学びに潜っていくわけだし、コントロールしたら多分浅いところで終わる。
https://note.com/brain_of_phys/n/n391ee4c8dea2
深い学びの尺度に「深さ」というものがあるとすれば、それはつまり「知識の構造化」という認識で良いのではないかと考える。これは、学んだ内容、1つ1つの知識やコンテンツに付随する情報(Ideas)や、それら同士のつながり(Connections)を拡げていくコンセプトマップのようなイメージで良いのだと思う。深さというのはこの繋がりの量によって恐らく定義可能だ。Aという知識がBと繋がっており、BはCと繋がっている。Cからは分岐して、DとEの知識に繋がっている、などの状況が完成しているのであれば、A-Bのつながりしかない状況よりは深い(構造化された)学びであると捉えてよさそうだ。
従って、深い学びというのは「構造的な知識体系を形成する学び」またはもっと単純に「構造化された学び」と認識してもよさそうだ。「構造化された」という表現は、「深い」という言葉よりも客観的に他者と共有できる表現なのではないだろうか。
構造化した時に大事になることは、完成した構造が実際の知識体系と比較して正しいものになっていることだ。
学校などのペーパーテストではいわゆるこの構造化された知識を基にアウトプットを行う能力を計測していることになるのだが、一夜漬けなどでただ膨大に短期記憶で覚えこんだ内容をアウトプットしているのと区別することが難しい訳で、その辺が近年の入試改革のきっかけとなったわけだ。
構造化された学びに向かうプロセス
では、「正しく構造化」するために必要なプロセスは一体何なのか。
そこには2つの段階があると考えられる。
1.主観的な学びによる構造化
これは本当に単純に、自分で学んでみたことを構造的に自分でアウトプットしてみることで可視化できる。学んだ内容を自分でアウトプットして貰えば、評価も可能だ。実際に、コンセプトマップを作成する課題やテストを課してみたことがあるが、理解度が高いと感じる生徒ほど、何も見ない状態でも細かく構造を書くことができる。
主体的な学びというのは、まさにこの構造化を主体的に実施する、ということだと僕は感じる(僕の主体的な学びのイメージは、知識の構造を自分で構築することといえる)。
2.客観的な学びによる構造化
これも、かなり単純に実施可能である。
1.で述べた、学習者各々の主観的な学びの成果としての構造を持ち寄り、同一の部分と異なる部分について議論をすれば良い。他の学習者と同じ繋がりが見いだせているところは多くの場合正しい構造(または非常に正解に近い構造)となっているだろう。更に、自分にはつながりが見いだせていないけれど、他者にはつながりが見いだせている構造や、その逆を見つけることによって、自然に学び合いが発生し、対話が生じる。
対話的な学びというのは、このように自分の認知の歪みを修正するような学びだと僕は感じる。認知の歪みは自分一人ではそもそも認識ができない。他者の認識と自分の認識を客観的に比較してみたときに、初めて自分の認知の歪みを認め、修正することができる。
主観的・客観的な学びを往復することで起こる、構造的な学び
まとめると、このように表現できると思う。
主体的・対話的で深い学び
≒主観的・客観的な学びを往復することで起こる、構造的な学び
元の表現はそれこそ主観的な表現であり、抽象度が高すぎて議論が収束しにくかった(きっと、あえてそうしたのだと思われる)。
でも、ある程度自分の言葉でこうして表現しておくことには一定の意味があるだろう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
