
100年前、宮古諸島の綾なる歌に魅せられたロシア人研究者ネフスキーの軌跡を追う。
100年前、ロシアからひとりの民族・言語学者が宮古諸島を3度訪れた。
彼の名前はニコライ・ネフスキー。自在に宮古の言葉を操り、島民たちから古来より伝わる言葉、歌、風習を聞き集めた。
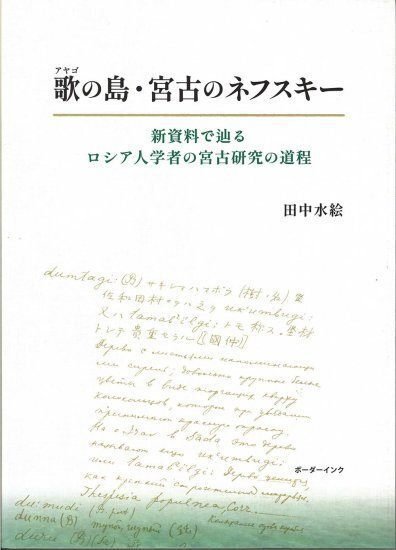
新資料で辿るロシア人学者の宮古研究の道程』
田中水絵 著
綾なる古語で紡がれたアヤゴ(歌)に魅了されたネフスキーだが、大粛清の時代のソ連で悲劇的な死をとげた。しかし彼が残した資料は宮古研究の光源として、いまも宮古の島々を照らし出している。
日露の新資料が明かす「何故、宮古なのか?」
宮古来島100年を記念して、いま蘇るネフスキーの旅。
序章 ネフスキーとの出会い―何故、宮古なのか
第1章 1892(明治25)年~1919(大正8)年・夏
1.ペテルブルグ大学入学まで―ロシア艦隊―日本語教育
2.L.シュテルンベルグ教授―「民族・言語学的方法」
3.日本留学―民俗学者たちとの出会い
4.「大学への報告書」―『風俗画報』
5.帰国延期―『万葉集』
6.東恩納寛惇―先島地誌4種―『混効験集』
第2章 ネフスキーと黎明期の琉球・宮古研究
1.田島利三郎―『おもろさうし』『混効験集』「先島の歌」
2.『沖縄風俗図絵』―謎多き「宮古島言語」
3.伊波普猷―『古琉球』
4.知られざるドイツ人A.ウィルト―「新琉球諸方言」
5.先輩E.D.ポリワーノフ―「日琉語比較音韻論」
第3章 1919(大正8)年・夏~1922(大正11)年・春
1.小樽赴任前夜―上運天賢敷―宮古方言
2.小樽―『混効験集』『おもろさうし』の学習―オシラ神研究
3.柳田国男の沖縄旅行―折口信夫の沖縄旅行
4.八重山の宮良當壮―日記
5.小樽高商のノート―宮古方言学習再開
6.冬の日記1―アイヌ語―宮古方言
7.冬の日記2―萬谷イソ―大阪へ
第4章 1922(大正11)年・夏
1.1回目の宮古調査旅行―折口信夫宛の絵葉書
2.富盛寛卓―採録の方法
3.ムナイ―サバニ
4.伊良部島―国仲寛徒村長
5.村長夫人の歌―小学校のベッド
6.佐良浜―会えない神カカリャ
7.佐良浜の結婚—佐喜眞興英—シマ
8.不明な足取り—下地島
9.狩俣―《根間の主》のアヤゴ
10.池間島―四シマ
11.多良間島―エーグ―《正月の歌》
12. 多良間の八月踊―組踊
13.水納島―百合若大臣
第5章 1922(大正11)年・秋~1926(昭和元)年
1.沖縄図書館―伊波普猷―田島利三郎「宮古島の歌」
2.吹き続けたムナイ風―同志・宮良當壮
3.ティムバヴ―口頭発表「天の蛇としての虹の観念」
4.虹―ライバル・宮良當壮
5.親友・前泊克子―佐良浜の巴御前
6.「アヤゴの研究」―田島利三郎の研究の伝道者
第6章 1926(昭和元)年・夏~1928(昭和3)年・春
1.2回目の宮古調査旅行―慶世村恒任
2.「宮古島子供遊戯資料」―島民の協力
3.『音声の研究』―台湾調査旅行
4.恩師シュテルンベルグとの約束―鷲信仰―《正月の歌》
5.「月と不死」―若水―折口信夫
第7章 1928(昭和3)年・夏~1929(昭和4)年・秋
1.3回目の宮古旅行―平良の知識人―「白い鳥についての歌」
2.国仲寛徒―神祈りの文句
3.伊波普猷からの絵葉書―ポリヷーノフ先生のアドレス
第8章 1929(昭和4)年・秋~2012(平成24)年
1.帰国―活動―日本旅行の申請
2. 二つ目の「天の蛇としての虹の観念」―消えた「ムナイ」
3.ネフスキーの死―死の真相―蘇った研究
4.宮古に帰ったネフスキー
―『宮古のフォークロア』『方言ノート』
5.生誕120周年サンクトペテルブルグ国際シンポジウム
―蘇るネフスキー
終章 何故、宮古なのか
