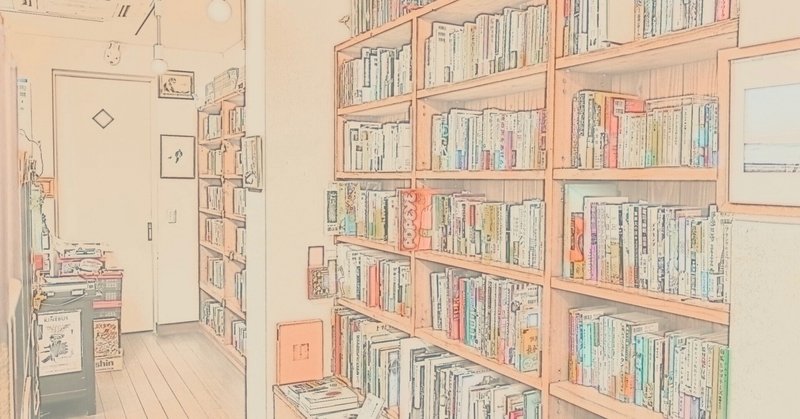
レティシア書房店長日誌
関口竜平「ユートピアとしての本屋」
大型新刊書店の店長をしていた頃のことですから、もう十数年前になりますが、反韓国・反中国を主張するいわゆるヘイト本が、毎日大量に配本されてきたことがありました。最初は、まぁそれも考え方の一つかと思って店頭に出しましたが、あまりにも稚拙な内容とヘイト感情を助長するような中身に唖然としてしまい、自分の判断で入荷即返本を繰り返しました。
ところがある日、上司にバレてしまい、本屋が読む人の自由を奪っていいのかと問われました。確かに、その言い分も一理あるかなぁ〜とは思いつつ、いや、やはりこれは置くべきではないと思ったまま年数が経ってしまいました。今もその時のわだかまりは残っていました。

しかし、関口竜平「ユートピアとしての本屋」(新刊/大月書店1870円)を読んで、解消しました。あの判断は正しかったのだと。
本のカバーに「反差別・反搾取の意思表示で注目される『本屋lighthouse』をたったひとりで立ち上げた新世代の書店員による”みんなのための”本屋論」と書かれています。そして、「本屋にとっての反ヘイト・反差別とは」「差別は道徳では解決しない」「出版業界もまた差別/支配構造の中にある」等の見出し。従来の本屋が書いた本屋論とは、ちょっと違うぞと感じて読み始めました。
「『読者が読みたいと思う本がある本屋がいい本屋だ。』『表現の自由は本屋が率先して守るべきものだ』といった、一見するといいことを言っているような言説によって、本屋が無色透明であること=意思や意図を持たないことが、本屋の責任/義務/高評価の理由になってしまう。しかし、そこで傷を負うことになる存在を、私たちはケアしなくてもいいのでしょうか。あるいは『いないこと』にしてしまっていいのでしょうか。」と著者は問いかけます。そうなんです。ヘイト本を偶然目にした当事者の気分の悪さを誰がケアすべきなのか、ということなのです。置くべきでないと思いながらも、小心者のサラリーマンとしては、上司に逆らっていいのかと悩んでしまっていたのです。
「あらためて確認しておきたいのは、本屋は本屋である前にひとりの人間であるということです。つまり本屋ひとりひとりに人権があり、生存権があるということ。そして表現の自由もまた同様に、当然の権利として持っているということです。となると本屋が『置きたくない本は置かない』という権利を行使することは、なんら批判されるべきことではないのです。あるいは『こういう社会になってほしい』という思いを込めた選書をして、そのフィルターを通して選ばれた本を置くということもまた、保証されている権利です。」
そして、こんなことも書かれています。「本屋の本質は置いていない本にあらわれる、というのは『誰を守りたいのか、どんな人を大切にしたいのか』と言い換えることもできるかもしれません。そしてその『誰/どんな人』は本屋各々が決めていいのです。」
差別感情を助長するような本、例えば LGBTQの人たちを差別するような本を置かない=当事者と共に生きてゆくことを主体的に選ぶことを日々の仕事の中で実践するということになります。当店も最後までそうでありたいと思っています。
●レティシア書房のお知らせ
8月21日〜29日の間休業いたします。よろしくお願いいたします。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
