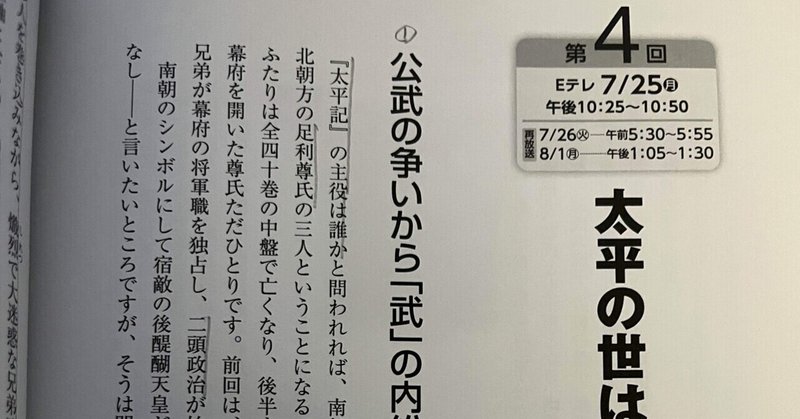
【100分de名著を語ろう】『太平記』~④太平の世は訪れるのか
こんにちは。
4回の放送の最終回を迎えた100分de名著『太平記』。明日7月28日(木)には、定例の「100分de名著を語ろう」ルームをclubhouse内にて開きます(21時から)。このテキストについては、第1回と2回、第3回と4回の放送を、それぞれまとめて扱わざるを得ませんでした。改めてお詫び申し上げます。では、以下に「小見出し」単位での引用やまとめを記載してまいります。
①公武の争いから「武」の内紛へ
・前回まで→後醍醐天皇死去、尊氏と直義とが将軍職を専有する「二頭体制」が確立。
・観応の擾乱→足利氏の兄弟・親子間と、代理戦争が加わった内紛。
・後醍醐天皇という共通の敵がなくなったことで、身内に対立軸が。
・尊氏=武を象徴、直義=武の内における「公」的存在(文)。武と公(文)との間のバランスの変化。
②足利直義と驕れる高兄弟の軋轢
・兄弟の対立を深刻にした高師直・師泰兄弟。朝廷などの権威を軽んじていた「婆娑羅大名」。
・直義が尊氏に追われて出家。
・尊氏と直冬の親子間の対立。
③尊氏と直義の直接対決へ
・「禅」を重用した直義に不満を抱く高兄弟。
・高家、滅ぼされる→尊氏と直義に「直接対決」の時が迫る。
④国中を巻き込んだ兄弟喧嘩の決着
・尊氏が完勝し、和睦が成った2か月後に直義が急死。
⑤キャスティングボードを握った南朝
・「『太平記』後半の中心となる観応の擾乱は、天下国家を考えての争いではなく、身内による勢力争いの繰り返しでした」(107)。
・「興味深いのは、そんな無意味な争いが幕府内で続いたことで、ほとんど無力だった南朝がにわかに存在感を増してきたことでしょう」(108)。
⑥最後の主人公、尊氏の死
・尊氏、54歳で死去。
⑦夜叉となった後醍醐天皇
・義詮、第二代将軍に。
⑧南北朝の統一に向けて
⑨二頭政治の終焉は突然に
・「鎌倉時代と室町時代の「あわい」で対立の軸となっていたのは、「武」の北朝と「公」の南朝でした。しかし、北朝の法皇が、文字どおり歩み寄ったことで朝廷同士の融和が図られ、ようやく太平の世へ向かう道筋が見えてきました」(114)。
・義詮、没。息子の義満が第三代将軍に。守護大名・細川頼之が補佐。
・「内徳の忠賢の臣である細川頼之によって、幼い義満が聖明の君となることを暗示して、『太平記』は終わるのです」(116)。
⑩「文」の力で太平の世を築いた義満
・南北朝の統一、成る。
・「文化」による統治で南北朝の分断を解消。
・「「文」によって、「公」と「武」を化合させてまったく新しい世を完成させようとした、それが北山文化だったのではないでしょうか」(118)。
⑪現代に『太平記』を読む意味
・「(略)揺れ動く「あわいの時代」に翻弄される人々の姿、強かに生き抜いた人々の姿を、『太平記』に見いだすことが意味をもってくると思います」(121)。
* * *
今回は以上といたします。最後までお読みくださいまして、ありがとうございました。それではまた!
最後までお読みくださいまして、ありがとうございました。ときどき課金設定をしていることがあります。ご検討ください。もし気に入っていただけたら、コメントやサポートをしていただけると喜びます。今後ともよろしくお願い申し上げます。
