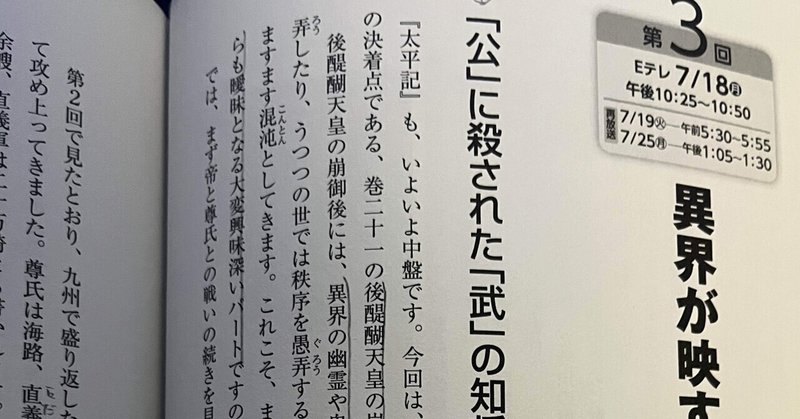
【100分de名著を語ろう】#68~『太平記』③異界が映す時代のエネルギー
こんにちは。
今回のnoteでは、7月18日(木)21時から予定しているclubhouse「100分de名著を語ろう」ルームで用いるためのレジュメをお届けします。今回取り扱うのは、第3週の放送内容です。◯で囲っている数字は、放送テキストにある小見出しに便宜的に割り振った連番、太文字としている部分は、テキストからの「引用」です。
①「公」に殺された「武」の知将
・後醍醐天皇と足利尊氏の対立が、天皇の崩御で決着を見る(~巻21)。
・尊氏が九州から攻め上ってくるが、新田義貞軍は兵庫まで退いてしまう。後醍醐天皇は、楠木正成の派兵を命ずるがそれが危険であることを奏上される。しかし、天皇の側近の公家からの口出しで正成は出兵を決める。
②死して時代を変える捨て石に
・もしかすると帝を勝たせること自体をやめたのではないか(略)この乱世を終わらせるには、天皇一統の政治にこだわる後醍醐天皇を助けるのではなく、南北朝の統一――つまり「武」の傀儡である北朝と、「公」の南朝を一つにまとめる必要がある(72)。
③追い詰められた南朝軍の悲惨
・このとき正成の念頭にある朝敵は、すでに尊氏その人ではなく、この乱世を引き起こしている人の欲だったのではないでしょうか。もはや尊氏を討つことへの執着は薄れていたのかもしれません(73)。
・彼(正行。引用者注)もまた、父・正成の言外の遺志を継ぎ、もっと大きな流れのために自らの命を投げ出したのでしょう。公武合体の枷となっていた南朝の勢力を弱めることこそが、平和な世の実現に至る道だと思ったのかもしれません(75)。
④『太平記』に描かれる人肉食
・これほど悲惨な戦は、『太平記』以前の戦記にはありません(76)。
⑤後醍醐天皇、無念の崩御
・時代は公武の「あわい」にあったのに、後醍醐天皇はかつての天皇一統の時代すなわち過去に目が向いていたのです(79)。
⑥常識を超えたバサラ大名
・尊氏が征夷大将軍、弟・直義が副将軍に任ぜられる。
・乱暴狼藉のやりたい放題の「バサラ(婆娑羅)」大名の出現。
・朝廷や比叡山といった既存勢力の権威が失墜していたこと。
⑦異界から舞い戻る主人公たち
・死者たちが実体化して登場してくる。
⑧「死ぬ」と「死する」の違い
・日本語の「死ぬ」と、漢語の「死」とは、系統が違った言葉。「死す」(漢語)は、永続的な死を意味するが、日本語の「死ぬ」は、「しなしなになる」の意。しなびただけの「一時的な死」を表す語。
⑨亡霊サミット、転生して現世を動かす
・当時の人々にとって、亡霊はインタンジブルな(触れることのできない)現実でした。実体はなくとも、極めてリアルな存在だったのだと思います(87)。
⑩能と『太平記』の深い関係
・『太平記』と、世阿弥が大成した「夢幻能」は構造が似通っている。また、『平家物語』のスタンダードの成立の3つは、ほぼ同時期に成立。
⑪念仏という発見
・「他力」本願の思想によって、死ぬことが怖くなくなったのが『平家物語』の時代。
⑫『太平記』の死生観
・「他力」による救い+禅宗の「自力」本願へと移っていく。
・自害する人が多いのは、自力本願の思想の影響か。
・死生観の「あわい」。
⑬共通の敵を失った足利兄弟の内紛
* * *
今回は以上といたします。最後までお読みくださり、ありがとうございました。それではまた!
22/07/27 追記
22/07/28 実施の「100分de名著を語ろう」は、③④を一括して取り上げます。④のレジュメは以下のリンクをご利用ください。
最後までお読みくださいまして、ありがとうございました。ときどき課金設定をしていることがあります。ご検討ください。もし気に入っていただけたら、コメントやサポートをしていただけると喜びます。今後ともよろしくお願い申し上げます。
