オススメする高校数学の教材
カテゴリーの順番通りにやれば基礎から標準、応用とステップアップできるようにしています。
追記:この記事は前に自分が執筆した4本の記事の内容をまとめ、適宜修正を施したものになります。オススメのものとその代わりとなるものを途中途中で紹介しているので、かなり長い記事になっていますがご容赦ください。
1.インプット用
入門問題精講
分野それぞれに丁寧な説明がついています。そのあとに基礎的な問題演習もすることができるので初学で使う本に最適です。
特徴として、公式が応用されている具体例を基に証明が書かれているので(イメージは共通テストに近い)、学習のモチベが維持しやすいです。
''特性方程式'' による解法についての解説が「不思議と上手くいけました」みたいなノリで書かれているという欠点はありますが、それ以外の分野はは教科書と合わせて使えば理解できるようになっています。特に数IIIの完成度が高いです。そのため、新高3や既卒生で「IAIIBは共通テスト対策で割とやったけど、数IIIは出来ない」という人には「IIIだけ」入門問題精講という使い方がオススメです。
入試数学の基礎徹底/数学ⅢCの入試基礎
大学への数学で有名な東京出版が作っている最も易しい問題集。ただし、ホントの初学ではなく既に全範囲を習っている人が復習用として使うのが本来の使用目的であるという点に注意。
文理共通範囲とⅢCの2冊に分かれていて、それぞれ、分野別で章を構成しています。各章のはじめには、公式の証明とそれに関連する例題・解説が書かれており、演習問題も別で用意されています。教科書よりもレベルの高い証明の仕方がされていて、基礎問題が多く載っているのが特徴です。
時間のある高1・高2生は先程の入門と合わせて取り組むことで基礎固めの段階で大きな差をつけることができます。
白チャート
ポテンシャルがかなり高い教材の代表格。可能性の獣ですね。
そもそも論、チャートは例題だけを比較すると、青/黄色/白でそこまで大きな差はありません。演習や章末問題、巻末問題のレベルが離れているので、レベルに差が出ているのです。ですが、チャートのエクササイズや総合問題に取り組んでいる人を見たことがありますか?私は高校時代、1人しか見たことがありませんでした。 ほとんどの人は例題を学習するのに手一杯なのです。
だったら、一番”問題数の少ない”白をやるべきだというのが個人の意見です。
解説がほかの色と比べて解り易いので1人で学習するのに向いています。漸化式が解ける仕組みや内積の意味など、初学では理解しづらい内容に関する説明が充実しています。受験勉強を学校の定期対策の勉強の延長線上でやりたい人にはかなりオススメです(指定校推薦とか取りたい人は特に)。
ただ、問題量は理系範囲まで合わせると600問以上あるので、時間に余裕がない人は代替案を教えるのでそれに取り組んでください。
文系の数学/数学Ⅲ 重要事項完全習得編
チャートとかの代替案です。昔は基礎問題精講が代わりの代表でしたが、問題数が少なく、解説でキレイに問題の要点をまとめてくれているこちらを最近はオススメしています。
この教材のコンセプトは模試や入試本番で自分が解いた経験のある問題(類題)をしっかりと完答できるようにする。というものなので、演習問題も1人で取り組みやすくなっています。
※ここからは問題数が極端に多い教材です。
NEW ACTION LEGEND
概念の説明や定理の証明が良くまとまっていて、完成度が高い教材です。コラムとして逆像法や外積・正射影ベクトル、帰納法に関する知識などについまとめてくれています。
例題のレベルはチャート式やフォーカスゴールドに比べて基礎寄りになっていて、解答の部分に別解が多く書かれています(イメージは大学への数学に近い)。
「定義に戻る」みたいな、本当に大切なこともしっかりと書かれているので、自習がしやすくなっています。
先ほど、例題が簡単である。ということを特徴として挙げましたが、この本は例題だけでは基礎の習得ができないので、LET'S TRY(チャートのエクササイズみたいなもの)までやる必要があります。
追記:既に学校でチャート式やフォーカスゴールドが配られている人は買い替える必要はありません。時間の無駄です。
ニューグローバル×LEGEND プレミアム版
1対1対応の演習
かなり有名な教材ですが、長所と短所がかなり明確です。
長所としては、
・数学的な思考に基づいた問題の解き方を学べる
・複数分野の知識が必要な問題を解く経験をすることができる
短所としては、
・例題と演習題のレベルの差が大きすぎる
・レイアウトに癖があるので、勉強しづらいと感じる人が一定数いる
という点が挙げられます。
意外と人を選ぶ教材なので、有名だからと安易に手を出してしまうと良くないです。
一対一をどうしてもやりたいという人は、分野を選んで学習するのが効率的で学習の定着率も上がります。
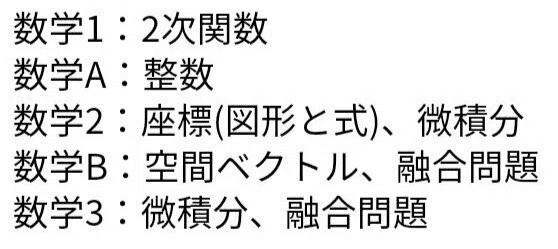
それか、"部分点を狙え"という教材を代わりに使うのもおすすめです。こちらは、解説が詳しく、記述対策が手厚くできるので数学に自信がない人でも使いこなすことができます。
標準問題精講
一対一と比べられることが多い教材です。こちらのほうがレイアウトが優れていて、解説も多くの人にとってわかりやすいものになっています。
欠点としては、問題のレベル感がIA・IIB・IIICでそれぞれ違うため、独学しづらい点があります。一対一と比べてみると、IA・IIBはほぼ同じ、IIIは標問のほうが問題も解説も難しいといった感じです(個人の感想)。
余談:標問Ⅲを気に入った受験生は、同じ著者が書かれた’’探求と演習’’というのも見てみることをお勧めします。
2.アウトプットに使える教材
新数学/数学IIIスタンダード演習
一対一対応以上の問題で構成されていて、インプット用の教材よりも標準問題が多く載っているのが特徴。
実際に入試で出題された出題頻度は低いがパターン問題のため、解いた経験があれば完答が比較的簡単な問題が多く載っており、電農名繊や5Sといった難しめの国立大志望でも使用することをおすすめする(特に数学を安定して稼ぎたい層)。
理系数学の良問プラチカ IAIIBC
こちらもパターン問題が多く、インプット用教材の章末問題の代わりとして使用することができます。
スタンダード演習と比べて、解答が平凡で解説も特段詳しいわけではありません(河合塾の教材全体に言える特徴です)。 なので、自力で抽象度の高い理解をすることができる頭の良い人向け、あるいは定期的にサポートしてくれる人がいる環境を作れる人向けの教材になっています。
理系ⅢCについては、典型問題がほぼなく、背景に大学数学が絡んでいる問題が多く載っているという特徴があるので、微積分の難問が頻出の大学(東工大など)を志望している人にはオススメですが、ほとんどの人にとっては、優先順位の高い教材ではありません。
ⅢCも理系プラチカと同じレベル帯で演習したい場合は、同じく河合出版の"
"理系272"か駿台の"CanPassⅢC"と組み合わせて使うのがオススメです。
272は1冊で全範囲カバーできるので非常にコスパがいいです。Canpassのほうは記述式が課せられる理系学科を志望している人にオススメできます。
※CanpassⅠAⅡBのほうは整数のセレクトが悪いのでオススメしていません。
文系に関しては、癖が強い問題が数多くあるものの、解説はかなり面白いものになっているので、東大・京大・一橋の文系学部志望者で数学で点を稼ぎたいと思っている受験生は取り組むことをお勧めします。
理系数学マスト160
理系プラチカや272と比べて、問題数もレベルも抑え気味になっています。載っている問題の質、解答の詳しさ、知識の整理を含んでいる解説など、とにかく使いやすいのが特徴。
キンドルアンリミテッドにも対応しているので、入っている人は無料で試すことができるのもいい点です。
重要問題集
数研の問題集。学校で青チャートを配られた人には特におすすめする。理由としては、青チャートの例題が重要問題集のどの問題と対応しているのかを公式が発表しているからだ。これにより、青チャートの例題+重要問題集→過去問というルートが確立された。
また、問題がA・B・Cの3段階に明確に分かれているので、基礎が不安だからAだけやるとか、Bだけ集めて模試みたいに解けるようにするとか、色々使えます。
現状、分野を分けずに難易度で問題を選び、志望校と同じ形式で実践演習する”テスト演習”みたいな使い方をするのに一番向いている問題集です。
3.自力で解く力を付ける為に使う教材
高度な問題を解くときに詰まった場合は
基礎知識を実戦で使える様に整理する、
何をすべきかを把握し、整理する、
の2つのアプローチがあります。
ここからは、これらを”知識”、”突破”として、教材を紹介していきます。
入試数学の掌握
知識も突破も必要十分です。
※問題ごとに記述が分かれているので、どれがどの問題に対して有用なのかは自分で整理しないといけない点に注意。
また、旧課程の行列の問題が載っているので、大学に入ってからもある程度は使えます。余談ですが、私は旧課程の新スタを使って、線形代数の演習をしていました。
以下、参考になる記事のリンクです。
世界一わかりやすい京大/阪大の理系数学
京都大学と大阪大学の理系学部で実際に入試問題として出題された問題をテーマごとに分類して、例題と演習問題のセットで知識定着を図る参考書になっています(性質としては、問題集よりも参考書に近い)。
特徴としては、各例題に対して、必要な知識を列挙した後に、記述の書き方を説明して、最後に模範解答が付けられているので、問題ごとに知識と突破の両方を理解することができます。
そのため、京大・阪大以外を志望する受験生も使うことができます。
ただ、同じ問題を反復する。要は、復習が主な使用用途と考えられているようなので、ここに載っている問題を利用して、6題150分の実戦形式を作るのは時間的に余裕がある人以外にはお勧めしません。
ハイレベル数学の完全攻略 ⅢC
数Ⅲ(特に積分)は知識重視の問題が非常に多いので、基本公式のような概念の理解が甘いと大量失点につながるという性質があります。
この本は、知識に関する記述が詳しいので、基本問題がなぜとけるのかを理解するときに助けになります。
ただ、載っている問題がリアル入試数学などと比べて、かなり難しいので、志望校とのレベル差がかなりあると感じた場合は一回、過去問演習を挟んだほうが時間効率を考えるとよいと思います。
注意:ここから紹介する本はIAIIBの内容だけを取り扱っています。
リアル入試数学
この本は、知識に関する解説がかなり良いです(特に整数と図形)。章立ても分野別ではないので、良い感じです。レベルも「掌握」よりずっと抑えられていて、地方旧帝大やそれに近いレベルの国立大、早慶理工にも使えます。
途中の対話形式は、好みが分かれるかもしれませんが、私は嫌いではありません。
真・解法への道
この本は、「初心者向け掌握(または対話形式を省いたリアル入試数学)+実践演習」という内容になっています。
問題の前に講義調の記述があり、知識の整理に関する説明や、教科書よりも詳しい解説が載っています(もちろん、基礎が固まっている受験生向けの記述です)。
章立ては教科書の分野割りに近いものになっています。
まず、知識に関する記述が、基本的なものを中心にかなり丁寧に扱われています(特に不等式と図形が良いです)。ただ、章立てが教科書の分野割りに近いので、掌握のような俯瞰的な知識の整理には至っていない気がします。また、突破(「解法の突破口」的なもの)に関しては、問題個々の解答の中に記述がバラバラに書かれているので整理が必要です(これは掌握も同様です)。
一方、教科書的な配置だからこそ、「等面四面体」「完全順列」などの高度な知識問題が取り入れられており、下記の内容も同時に勉強できる本になっています(網羅性についてはあまり確認していません)。完全順列に関しては共通テストで出題されたこともあります。
掌握よりはかなり敷居が低く、より多くの受験生が取り組める本だと思います(掌握は知識の要求がやや厳しいと感じます)。
また、論理を最初に扱っている点がとても良いです。この単元で数学的な考え方を身に着けることができると、かなり数学に対する見方が整理されると思います。
4.高度な問題集
受験生は1.2.3の教材を5冊は使って数学の勉強をすることになりますが、これだけこなすのには2年くらいかかるのでそこを踏まえたうえでこれからの教材には取り組んでください
文系の数学 実戦力向上編
文系プラチカと同じくらいのレベルの問題で、解説がやや詳しくなっている。例題に比べて演習問題が少し難しすぎるので、どの例題と対応しているのかをしっかりと把握して学習するのが良い。
なお、ⅢCの内容がない点には注意してください。
上級問題精講
選ばれている問題もその解答・解説も文句無しの出来です。入試特有のテクニックも数学的な記述もかなりのクオリティです。
計算力に自信のない人は、新数学演習のほうが処理の多い問題に触れることができるのでお勧めです。
Mathematics monster
問題集じゃなくてすいません。YouTube上で数学の入試問題の解説動画を定期的に挙げていらっしゃるチャンネルです。
選ばれている問題の意図を明確に伝えてくれるので、自習が非常にしやすいです。問題を解く中でどうしても必要になる途中の処理に関する解説もあるので、分かりやすいです。
筆者がⅢの微分積分でお世話になったので、紹介させていただきました。
終わりに
最近、高校数学に関連している参考書の数はかなりの数になっています。
そのため、いろいろな問題集に目移りしてしまう人も少なくないでしょう(自分もそうでした)。
個人的な意見ですが、網羅系が学校で配られた人は配られた教材と過去問は必ずやってほしいですが、他の教材に関しては自分にとって一番いいものに出会うまで乗り換えてもいいと思います。
最後に、大学への数学で有名な安田亨氏が尊敬しているる一松
信京大名誉教授のお言葉を引用させて頂きます。
「書籍は三割も読めば読破したことになる」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
