
【SS】グレンデルに関する前哨的課題
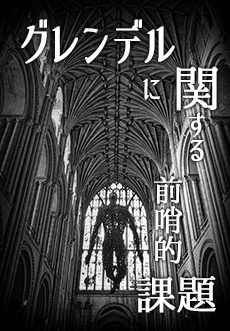

【問題】
以下の文章を読んで違和感を形にせよ。
陰鬱な自然に挑むように、その城はあった。
ヘオロット城は、前線である。
王とその麾下の兵士たちは、異形たちが荒れ地を越えて人の世界に流入しないように、ここで睨みをきかせる。
これまでも、これからも。
しかし緊張の糸は張り詰めれば細く、長引けば切れ易くなるものだ。
それは稀な休息の日。遠くコルキスから訪れた賓客をもてなすために、城に暮らす約三百名は料理係と僅かな衛兵を除いて、宴の真っ直中にあった。
葡萄酒が荒くれ者の体内で代謝されて、賑やかな笑い声に混じってアルデヒドが振りまかれていく。
肉とチーズとパンは尽きることがなく、腹を満たす意味以上にそれは権力の象徴であり、辺境に覇を唱える王の恵みそのものだ。
フロースガール王は始終上機嫌で、しきりに隣席の客人に話しかけていた。人間の限界地では、世界の情勢を知る機会に乏しい。
何よりコルキスの賓客の語る夢幻のような挿話が、寒々しい石壁に煌めくベールをかけるのだった。
その裏側で、彼等が備え続けてきた脅威が、姿を表しつつあった。脅威は衛兵の喉を容易く握りつぶし、最後の息を叫びには変えさせない。
間もなく宴席に、毒々しい沼の濃緑の気配が先触れした。
最初に濃緑に喰われた広場の獲物は、食い意地の張った百人長だった。王と賓客の前に据えられた干し果物は下賜されるまで手を出すことは許されていない。
宴もそろそろお開きになるにも関わらず、賓客との話に夢中の王は部下への施しを忘れているようだった。
塩漬け肉とチーズで塩辛くなった舌に我慢ができなくなった彼は部下の新兵に干し果物をとってくるよう命じた。
だがその新兵がいっこうに戻ってこない。
いらだった百人長はチーズの転がったテーブルにナイフを突き立て食糧庫へ向かった。広間をでた瞬間、彼の鋭敏な嗅覚がぬるんだ苔むす水の臭い、沼の巨人グレンデルの臭いを捉えた。
仇敵の名を告げる百人長の末期の悲鳴、彼の首、濃緑の獣が一斉に広間に飛び込むのを正面の王は驚愕を、賓客は咀嚼をもって迎えた。
遅れて来た沼の客人は主の断りもなく、彼にとっての料理の一番大事な所を一口ずつかじっていき、勝手に逃げていかないようにしていく。
千切り、食べ、啜り、また次へ。
圧倒的な暴威を前に、二人の百人長も声をあげられない。広間の奥には序列も隊列もない、混沌とした人間の塊が波打っていた。
動かなくなった食いさしの料理が百皿になる頃、残りの内勇敢な五十皿がナイフを持参で向かってきてくれたがグレンデルはその厚意を無下にし、やはり素手での食事を続けた。縄張りの内側で宴を開かれたのだから自分も喰ってなにがわるいとばかりに食人鬼は食い散らかすのをやめなかった。
窮状を聞いてベオウルフが駆け付けた時、被食者は四千五百人に届かんとしていた。
その時グレンデルは上席でくつろいでおり、自分に徒手で歩いてくる獲物に何の気なしに食指を伸ばしたがベオウルフの剛力により弾かれた。
それが数合続き、彼はようやくここが招かれた宴ではなく、目の前の人間が脅威であることを思い出していた。
だが結局、夢から覚めるのが遅すぎた巨人は剣無き英雄の素手により左腕をねじ切られ逃げ出す羽目になる。
巨人との宴は終わり、兵士達と共に王はベオウルフに深く感謝した。
――問題は以上。
‡ ‡
「さて」
サイファーは、胸の前で指を組み合わせた。
「本来なら他文献をあたって違和感の正体を探す。けれど今回は僕がそれを代行しよう」
「あなたが膨大な古書群に混じって、地道であてどない作業をやるというの?
あなたが?」
「二度言われたのが気になるけれど、少し違う。君が質問してくれれば僕が事実を答える。僕自身が本の代わりをして、君の手間を省くというわけだ。
さあ始めたまえ。早く魔述師として熟達したいのだろう」
サイファーは僅かに目を伏せた。
「質問は十……いや、五つまでにしよう。そしてイエスかノーかで答えられるものに限る」
違和感。それが何かだけは僕には解る。
グレンデルの殺害数だ。
三百人が詰める城で、四千五百人を殺す。
沼地の怪物がどれだけ強くても、数字の概念を超えることはできない……はずだ。
僕は非常識の首魁たる至高のイデアの横顔を見遣る。
「魔述だのファンタジーだので解決するつもりじゃないか」
「正宗くんのも質問回数に含んでいいかな」
「かまわないわ。私の質問は一つ。それで違和感を形に、真相を露わにできる」
感情の起伏に乏しく、ともすれば冷たく映る礼貌は、信じられない宣言をした。
「君はもう、真相に気づいている?」
「そうね。コモンセンス」
瞑目する姿に気負いはない。
「では、一応正宗くんに答えておこう。魔述の介入なしにこの問題は解決できる。巴くん、君の質問は?」
全てを解明できるたったひとつの問いかけ。そんなものがあるのだろうか。
「コルキスの賓客……これは、あなたでしょう。サイファー」
「イエス。だが、ああ、なるほど。これは問題外だ」
人外は眩い白金髪の頭を振った。
「君は問題の内部ではなく問題の外、出題者の意図を読むことで正解にたどり着いたのか」
「たしかに私は幣魔述師として未熟ね。けれど、あなた自身の研究において人後に落ちない自負があるわ」
「研究者の研究? 無為で退屈な行為をよくぞ続けたものだ」
想定外の解法を使われたためか、満足とも落胆ともつかない表情で出題者は皮肉を述べる。
「けれどそれが今、生きるでしょう。
あなたにとって問題にする程度に興味深い話の現場にあなたが登場している。これで暗躍していないほうがおかしいわ」
「つまり僕が違和感の原因? 僕が動いたから不自然に早くベオウルフが駆け付けたということか」
そうではないことを承知の上でサイファーが続きを促す。
「まさか。単なるグレンデルの殺戮やベオウルフの討伐を目的にあなたが指一つ動かすはずないでしょう。
けれど一方的な展開を何より嫌うあなたは、ルールを整備した。双方に利益のある取引」
「人間側においての利益とはなんだろう、正宗くん」
急に話を振られて、僕は慌てて考えを巡らせる。
「これ以上犠牲が増えないこと――」
言いながら、これは間違いだと気づいた。コルキスの賓客=サイファーが行動したなら、強者の五十人が屠られた後だろう。けれど結局四千五百人まで死者は増えたのだ。
「同意見だわ」
面食らう僕に向けて【御前】が頷く。形の良い指先が、自らの黒髪の一房を梳いた。
「でも、誰にとってかしら。被害の大きさは、人数だけで測るとは限らない。自分か他人か。王かただの兵士か。残念ながらそれで評価は変わってしまうのよ」
何かが引っかかった。
パニック下の、生存本能という名の保身。
それを必要以上に鮮明に浮かび上がらせたのは、人間を実験動物程度にしか見做していない存在だ。僕の隣において美しい人の形で本性を欺く、この……。
僕の視線に気づいて、古書の行間に注意深い者だけが見い出す登場人物が、顔を上げた。
花のような香のような、サイファーの瞑想を誘う肌の香りが鼻をくすぐる。
「ねえ、自分のせいで四千五百人が死んだ事故を見るのと、自分が死ぬの、君はどっちが好き?」
サイファーが口の端を釣り上げながらこちらに一瞥をくれる。すでに真相にたどり着いた【御前】のかわりに僕を俎上に載せるつもりのようだ。
二択は嫌いだ。どちらかを選ばなければいけないと、無意識に強制されるから。
それを口に出したなら、選べるだけマシだとこの人外は微笑むだろう。ヘオロット城が迫られたのは恐らく、破滅を逃れ、細い希望につながる一択だった。
その選択肢をぶらさげた張本人もまたこの人外なのだ。
各々の破滅とは? その宴で食われること? あたりまえだ。じゃあベオウルフが窮状を聞いて駆けつけるまでなぜ彼らは逃亡しなかった?
逃亡が破滅につながるからだ。フロースガール王が城を捨てたとあれば王としての身の破滅。兵卒も逃亡の行き着く先は野盗の類、破滅まで少し猶予があるだけだ。
いや、そこじゃない。破滅を逃れたその裏側だ。保身のために王は何を犠牲にした? 兵は何を犠牲にした?
「王に代わりはいない、だから犠牲になるのは兵士だけど、王も兵士もそれぞれ保身に走るはず……」
「グレンデル側の利益を考えれば、もっと構造は簡略化されるわ」
【御前】の助言が最後のひと押しだ。
「グレンデル側の利益は食人……そうか。一致するんだ。双方に利益のある取引がある。それをサイファーは提案した」
論法の階段は消え、真相だけが眼前に啓かれた。
――蜜月の共犯者。
城の人間は抵抗すれば自分達が全滅するのは理解していた。そしてグレンデルも王の殺害でさらに強い人間を呼び込むことになる事がわかる程度には人間社会に明るかったのだろう。
その場にいない人間を巻き込む提案に同意した。
死体は腐る。食人鬼と食屍鬼は似て非なるものだ。腐肉は食べられない。いくら巨人だってうわばみじゃない。一度に食べられる量も、蓄えられる脂肪にも限界がある。
ジガバチ等の狩りバチは子供の食料としてマヒさせた多量の青虫を泥部屋に閉じ込める。その習性を思い出して気持ちが悪くなった。
「さあ、いよいよ本丸だ。四千五百人はどこから湧いて出てきたのかな?」
この話がジガバチと違うのは青虫の集団が喰われた分を自らずっと補充し続けた点だ。
「この話に漂う違和感は時間にまつわるもの。賓客の提案した余興によって宴の夜は明けることがなくなった。ベオウルフがグレンデルを討伐するまで」
「正解。グレンデルの宴はベオウルフが来るまで十二年間続いていたんだよ」
人の形をした純粋理論が前のめりに、金無垢の瞳を一層輝かせる。
「サイファー、あなたはこう提案した。”王を当ててごらん。そうすれば人間たちは君の縄張りから去る。新しい王も軍勢も来ない”」
対する【御前】の淡々とした応答に心の中で安堵する。魔述師としての熟達が人外思考への共感ではあってはならない。
「”ただし、一日に一人だ。君は指名し、それを殺す。正解するまでずっと”」
【御前】の推察にサイファーは満足そうにうなずいている。
十二年間、四千五百人、計算上それでほぼ辻褄があう。
「フロースガール王たちは十二年間も対抗策を練らず、毎日諾々と生贄を差し出し続けたってことか」
十二年という長さにまだ十代の僕の頭は想像が追い付かない。
「指摘されても彼らは決して認めなかったでしょう。これが、この物語の一番恐ろしい部分かもしれないわ」
グレンデルは四千五百人を差し出せとは言わなかった、王も承諾していなかった。四千五百人という数字は王が、百人長が、古参兵が、締め切りのない募集に知らず応じてしまった新兵が、それぞれヘオロット城という泥部屋の中で我が身の破滅を回避する選択をし続けた結果だった。
実験狂いをネゴシエーターにしてしまった彼らには同情を禁じ得ない。
「窮状を聞いて駆けつけたベオウルフが、剣を持っていない――これも不自然。でも怯懦なヘオロット城側の作為だったら説明がつく」
「ベオウルフの登場は歓迎されなかった。もしも彼が善戦の上討伐に失敗すれば」
「より強い人間を差し向けてきた外部の人間を恐れ、グレンデルは逃亡を準備。全員を殺し、食えるだけ食いだめをする……かもな」
これは0.3%と、100%の死を天秤にかける話にシフトしていたのだ。
無抵抗であれば、城に詰める三百人から選ばれるたった一人にならなければいい。99.7%生き残れる。次の日も補充された一人が加算され、やはり99.7%が生き残れる。
この考えに反対する者は、積極的に0.3%が的中したことだろう。
敵でありかつ共犯者のグレンデルは、真面目に王を推理することはない。用意されたその日の食事を、永劫支給されるはずのそれが終わらないように、正解を外し続けるのだ。
こうして醸成されたムードは、救助者をも排除しようとした。
「彼等は信じきれなかった。ベオウルフの強さがグレンデルにまさると」
ベオウルフが、グレンデルを傷つけた挙句に敗北したら大問題だ。100%の死に追い立てられるように、英雄の剣は隠された。
これが、ベオウルフが徒手で的に挑んだ真相だ。
「それでも勝つのが、ベオウルフの凄さなのだけどね」
講義は終了とばかりにサイファーはその身をクッションに投げ出す。
結局英雄は知ったのだろうか。助けようとした相手が、彼を窮地へと追いやっていたことを。
そして僕は思い至る。
「未遂者一名。これ、サイファーなんだろう」
「ああ、よくわかったね。フロースガール王 にとって、グレンデルと結んだ契約は、人目に触れさせたくない醜聞だったのだろう。ベオウルフが入城してから静かに発狂していった彼に
強制的に食卓に運ばれてしまったよ。余所者で提案者である僕も、0.3%に選ばれかけたわけだね」
自称最強のイデアがこともなげにすくめる首はやはり細い。自業自得と、この時ばかりは僕も言い切れなかった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
