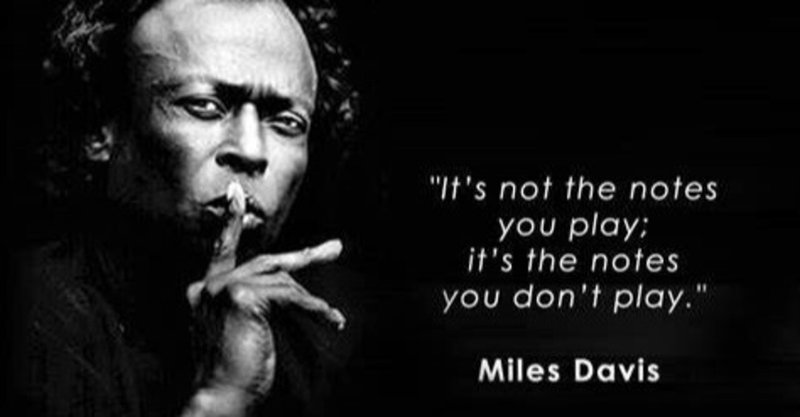
マイルス、マッコイ、ガレスピー、ジョーヘン・・・往年のジャズジャイアントがビッグバンドで輝きを放つ!!グラミー賞受賞ビッグバンドを年代別にみていく【90年代編】
はい、ビッグバンドファンです。今日はグラミー賞の「最優秀ジャズ大規模アンサンブル・アルバム賞」の歴代の受賞作について1990年代の受賞作について見ていきたいと思います。
早速ですが1990年代の「Big Band」部門、1991年からは「Large Jazz Ensemble」となりますが、受賞者を見て行きたいと思います。受賞者一覧は以下の通りです。
第32回(1990年) Aura | Miles Davis
第33回(1991年) Basie's Bag | Frank Foster
第34回(1992年) Live at the Royal Festival Hall | Dizzy Gillespie
第35回(1993年) The Turning Point | McCoy Tyner
第36回(1994年) Miles & Quincy Live at Montreux | Miles Davis & Quincy Jones
第37回(1995年) Journey | McCoy Tyner
第38回(1996年) All Blues | Tom Scott, GRP All-Star Big Band
第39回(1997年) Live at Manchester Craftsmen's Guild | Grover Mitchell
第40回(1998年) Big Band | Joe Henderson
第41回(1999年) Count Plays Duke | Grover Mitchell, Count Basie Orchestra
さぁ、80年代においてかつてのビッグバンドスターが相次いでこの世を去った中、グラミー賞の受賞者自体はどちらかというと80年代は「保守」側が多かった。しかし89年に「保守」とは対極の「革新」側の鬼才ギルエヴァンスがグラミー賞を取ったことでグラミー賞受賞アルバムの傾向はどうなっていくか、というところから90年代は始まります。
帝王マイルス・デイビス
90年、まず受賞しているのがマイルス・デイビスの「Aura」です。この年のグラミー賞ではこのビッグバンド部門だけでなく、ジャズソリスト部門でも同アルバムが受賞している他、長年の音楽業界への貢献を称えた功労賞的なものも受賞しており、少なくともジャズ系部門におけるマイルスのグラミーにおける存在感はとても強かった年です。サウンド的には聞いて頂くのが早いと思いますが、89年のギル・エヴァンスの流れそのまま、ビッグバンド的には「革新」ど真ん中をついたものになります。そもそもアルバム自体、デンマークの作曲家兼トランペット奏者であるパレミッケルボルグがプロデュースしたもので、マイルス・デイビスがビッグバンドを率いたのではなく、ビッグバンドの部分もデンマークのDanish Radio BigBandが務めています。
https://www.youtube.com/watch?v=i8Q72UUMHoM&list=PLDedzOsxJWdHdNiCXyz8Vl9RHZ-gwIMW6
ちなみにデンマークのビッグバンドと聞いてピンとくる方、なかなかのビッグバンド通です。そう、サド・ジョーンズがデンマークに引っ越したのち、このDanish Radio BigBandの首席指揮者を1年という短い期間ではありますがつとめており、その後もジム・マクニーリーやボブ・ブルックマイヤーといったメル・ルイス・ジャズオーケストラで起用が増えた気鋭の作編曲家が首席指揮者を務めるなどサドメルバンドのカラーが色濃く残っているビッグバンドです。ただ、ジム・マクニーリーが2002年まで首席指揮者をつとめたのち、長らく首席指揮者不在の状態でしたが、2019年に狭間美帆氏が就任しています。彼女はジム・マクニーリー氏にも師事しており、そうした流れも含めて非常に今後の活動も楽しみとなっています。
というわけで、話をマイルスに戻しますが、そんな帝王も1991年9月に他界します。94年にグラミー賞受賞しているアルバム「Miles & Quincy Live at Montreux」は、ヨーロッパの名門ジャズ祭であるモントルージャズフェスティバル25周年を記念して実現した帝王、最後の勇姿が聞けるアルバムで、亡くなる3ヶ月前の演奏です。既にこの時マイルス・デイビスは重病であったということです。そして、なんと、なんとぉ!!これがYouTubeにあがっているというね。これはね、もう絶対に見た方がいいです。クインシージョーンズがギル・エヴァンスオーケストラとジョージ・グルンツ・コンサート・ジャズバンドという2つのスペシャルなビッグバンドを指揮、トランペットにベニー・ベイリーやウォレス・ルーニー、ドラムにグレイディ・テイト、ベースにカルレス・ベナベント、アルトサックスにケニー・ギャレットといったマイルスと共演したゲストも出演、そこに現れる帝王。映像で見ると、帝王が現れただけでもう鳥肌立ってきます。大舞台ならではの圧倒的なスケール感、しかも映像で見ると観客が近いのに驚きます!!こんな間近でこんなとんでもないライブを聞けたなんて、羨ましすぎるぞ!!!そして何といっても演奏がクーーーーーーーーーール!!マイルスの音楽人生を振り返るような、まさに集大成の記念碑的名盤と呼んでいいかと思います。そしてそして、何よりサウンドがビッグバンドです!!ビッグバンドファン的にこれはとても大切。これは本当にビッグバンドのアルバムと言っていい、保守と革新の二極化が進むビッグバンド、その先の未来を切り開いたといっても良い、そういう意味では革新の側のアルバムなのでしょうけど、まぁあとは聞けば分かります。また、帝王の最後の演奏がビッグバンドと共にあった、これも何か嬉しいですよね。そしてこんな映像をインターネットで世界中の誰もが楽しむことが出来る時代になったという、帝王もこれはさすがに予想してなかったでしょう。凄い時代になったとつくづく思います。
ディジー・ガレスピー
というわけで、グラミー賞受賞となった帝王マイルスのアルバム2枚の紹介に続いて、今度はディジー・ガレスピー、マッコイ・タイナー、ジョー・ヘンダーソンといった往年のジャズの名プレイヤー達のビッグバンドに注目したいと思います。3人とも説明は不要と思われるぐらいの偉大なジャズミュージシャンでありますが、ディジー・ガレスピーに関しては意外なことにビッグバンドでグラミーを受賞しているのはこの1回だけです。自身のビッグバンド活動歴も長く、「チュニジアの夜」や「マンテカ」といった名曲においても、早い時期からラテンを中心とした独特のリズムパターンを楽曲に取り入れる等革新性のあるビッグバンドサウンドを世に送り出し、今でも多くの人に愛されているプレイヤーではありますが、1976年にジャズ・ソリスト賞という形でオスカー・ピーターソンと共に受賞しているものの、あとは1989年にマイルスも受賞しました功労賞、95年これは死後になりますが殿堂賞を受賞という、グラミーの舞台にあがってくるのはこれだけです。意外ですよね。そんなガレスピーも93年にこの世を去ります。なので、グラミー賞受賞の「Live at the Royal Festival Hall」はそんなガレスピーの最晩年を飾ったアルバムとなります。Claudio Roditi、Arturo Sandoval、Paquito D'Rivera、Slide Hamptonなどお馴染みのスーパープレイヤーが勢揃いしてのビッグバンドサウンドはまさに圧巻、グルーヴの嵐が渦巻くスーパーライブです。これもテイストは全く違いますが、帝王のラストライブに匹敵する迫力、ビッグバンドが持つ音楽的パワーというものをまざまざと見せつけてくれる、そんな内容になりますので是非聞いて頂きたいです。
マッコイ・タイナー
そしてマッコイ・タイナー。かつてコルトレーンバンドのピアニストとして60年代を走り抜け、脱退後の70年代には自身のグループで『エンライトメント』『アトランティス』『ザ・グリーティングス』『パッション・ダンス』といった傑作をリリース、モードスタイルの楽曲で力感あふれるアドリブを展開するピアノ、ちょっと聴いただけでガシッと心をわしづかみにしてくる力強さはビッグバンドでこそ活きてくると考えたのでしょうかね、後年はビッグバンドのアルバムを立て続けに発表、「The Turning Point」「Journey」の2作でそれぞれグラミー賞受賞となります。
今申し上げた通り、ビッグバンドという形ではあるもののサウンド的にはマッコイ・タイナーのピアノを前面に押し出したものになります。ただ、とにかくマッコイのピアノが力強いので、ビッグバンドに負けない。トランペットにメル・ルイス楽団のリードトランペットでも有名なEarl Gardnerが入って凄まじい轟音とハイノートをぶちかまそうとも、Dennis Mackrel,やSlide Hamptonのエグエグアレンジを管楽器隊が襲い掛かるような勢いで吹ききっても、全く負けない。ビッグバンドを活かすというか使い倒すというか、なるほどこういう使い方もあるんだな、と。
音楽的には全く違いますが、MISIAさんがSOUL JAZZシリーズでビッグバンドとコラボしたアルバムを発表、ライブも行いましたが、これに近いものを感じます。EverythingにおけるMISIAの圧倒的存在感、それを引き立たせる為のビッグバンドという。フロントの圧倒的な存在感無しには成立しない形ですが、逆に言うとそれだけのプレイヤーであればビッグバンドこそが引き立て役にふさわしい、そんなことを思わせます。
ちなみに私、以前自分のビッグバンドでこのThe Turning Pointの一曲目「Passion Dance」やったんですが、その時にピアノを担当していたメンバーから未だに「あれだけはもうやりたくない」と言われていまして、困ってます。またやりたいんだけどなぁ。。。というわけで、個人的にこのマッコイ・タイナーのビッグバンドは好きです。ただ、この方も昨年3月にお亡くなりになりました。ご冥福をお祈りいたします。
ジョー・ヘンダーソン
そして、ジョー・ヘンダーソンさんです。この方も1960年代70年代、ブルーノートやマイルストーンといった名レーベルより数々の名演を発表してきたジャズ巨人の一人ですが、そんな彼もかつて71年に「Blood Sweat & Tears」に参加するなど、音楽的に色々模索をしてきた方です。グラミーの舞台には90年代になるまでは縁がなかったのですが、93年にレーベルをヴァーヴに移したところ、ヴァーヴが大々的に広告キャンペーンを打ち、彼をコンテンポラリー・ジャズ・シーンの第一人者に据えることに成功したそうです。1992年にリリースした『ラッシュ・ライフ』が商業的に大きく成功し、グラミー賞のジャズ・ソリスト部門を受賞すると、その翌年も「Miles Ahead」で受賞、そこからこのタイトルそのままの「BigBand」というアルバムでビッグバンド部門でも受賞という流れになります。このアルバムも先程のマッコイ・タイナーのアルバムと同様、基本はジョー・ヘンダーソンの往年のナンバーをジョー・ヘンダーソンをフィーチャリングする形で聞かせるというものですが、それにしてもビッグバンドの演奏が力強い!!
https://www.youtube.com/watch?v=lE2dymqd3ro&list=PLBJix3e33cOLTvMJmz7v6xZJQ79LpU28t
GRP All-Star Big Band
そして、もう1つ出てくるのがGRP All-Star Big Bandです。GRPはレーベルです。レーベルはジャズやビッグバンドにおいてもいわゆる名門と言われるものがあり、一番有名なのはブルーノートとかですね。そのレーベルからアルバムを出す、それ自体が一つのステータスともなっていたわけですが、時代とともに求められる音楽性が変わり、アーティストの音楽性も変化する、ビッグバンドにおいてもそうです、ミュージシャンが変化するということはレーベルにもまた変化が求められるわけです。GRPはそうした変化を求める潮流と歩を合わせる形で出てきた新興レーベルです。1970年に発足したデイブ・グルーシンとラリー・ローゼンのプロダクション、GはGrusin、RはRosen、PはProductionということで設立されたGRP、これのレーベルとして1976年に発足したのがGRPレコードです。レーベルはそのレーベルがリリースするアルバム、このアルバムの音楽性とともにブランディングされていきますが、GRPはフュージョンやAOR/アダルト・コンテンポラリー、スムーズ・ジャズと呼ばれるようなジャンルを手掛けるレーベルとして急成長していきます。GRP All-Star Big Bandはそんな急成長中のレーベルがレーベル初のビッグバンドということでレーベルに所属する売れっ子ミュージシャンを集めて結成したビッグバンドです。従ってメンバーもバンド名通りオールスター、腕利き、実力者、人気者が揃ったビッグバンドです。当然GRPである以上、ビッグバンドにおいてもサウンドの方向性はフュージョン等新しいサウンドを指向しているものの、取り上げている曲は例えばタイトル曲である「All Blues」は1959年にマイルス・デイビスがリリースした代表作「Kind of Blue」に収められたものであり、その他の楽曲にしてもホレス・シルバーやチャールズ・ミンガス、セロニアス・モンクやジョン・コルトレーンといった往年のジャズ巨人の名曲となります。
共通する点
ここまで見てきたディジー・ガレスピー、マッコイ・タイナー、ジョー・ヘンダーソン、そしてGRP。いずれのアルバムも「サウンドは革新、選曲はジャズ巨人の伝統を踏まえたもの」という構造をもっている。マイルスにしても「Aura」は別にすれば、「Miles & Quincy Live at Montreux」はまさにマイルスの総決算的な内容になっており、マイルス自身の伝統を踏まえた選曲と考えれば同じ構造を持っている。これは90年代グラミー賞受賞の一つの特徴と考えても良いと思う。
カウント・ベイシー亡き後のカウント・ベイシー楽団
一方、33回(1991年)のFrank Foster「Basie’s Bag」、第39回(1997年)のGrover Mitchel「Live at Manchester Craftsmen's Guild」、41回(1999年)のGrover Mitchell「Count Plays Duke」、この3つは全てCount Basie BigBandのものになります。
■Live at Manchester Craftsmen's Guild
https://www.youtube.com/watch?v=ZlPKrWdifzY&list=OLAK5uy_miSaCet0l1Kly5IfOXHMlquy7V-KrssvY
■Count Plays Duke
https://www.youtube.com/watch?v=VcDnzSwWNF4&list=OLAK5uy_nqqDwKMNQArHb465GuKbvWchsCYGcO6fY
エリントン楽団は74年にデューク・エリントンが他界した後は息子のマーサー・エリントンが率いて、80年代にはDigital Dukeでグラミー賞を取るなどしていましたが、一方のベイシー楽団は世襲ではなく有志がリーダーを引き継ぐという形になりました。まず最初にベイシー楽団を率いたのは78年にデンマークに引っ越していた且つてはベイシー楽団の花形トランペッターでもありその後66年からはサドメルとしてビッグバンド史に数々の名曲を残したサド・ジョーンズ、彼がベイシー亡きあとのベイシー楽団を率います。このサド・ジョーンズ率いるベイシー楽団は日本にも来日しており、日本のビッグバンド愛好家の中には生で演奏聞いたよという方も結構多くいます。しかしそんなサド・ジョーンズも86年にベイシーの後を追うように63歳でこの世を去ってしまいます。サド・ジョーンズの後を継いでリーダーになったのは、こちらもベイシーバンドの名物テナーサックスプレイヤーとして数々の名演を繰り広げてきたフランク・フォスターです。このフランク・フォスターがリーダーとなったカウント・ベイシー楽団がリリースしたのが、91年にグラミー賞を受賞している「Basie’s Bag」です。サウンド的にはベイシー楽団ならではのスウィンギーでビッグバンドらしいグルーヴを軸にしたものですが、1曲目にCeder WaltonのFirm Roots、2曲目にはアルバムタイトル曲であるBasie’s Bag、この曲はジョージ・ベンソンの作曲になります。
ここで聞かせるサウンドは80年代のグラミー賞受賞バンドが見せたような、伝統的なビッグバンドサウンドを軸としつつ、モダンな響きを取り入れることで古臭さを無くし、それでいながら実験的ではなくむしろキャッチーさを包含した、そんなサウンドです。これもまたビッグバンドの正統進化の一つと言えると思います。
閑話休題(オールド・ベイシー、ニュー・ベイシー)
さて、ここまで60年代から順に話を進めてきて90年代に入ったところで、ちょっと横道にそれるのですが、エリントンのところでも少し触れましたが、ベイシーにも大きく分けて1936年から一旦解散となる1945年までを「オールド・ベイシー」、1951年の再結成後を「ニュー・ベイシー」とする2つの時期があると言われてます。
またニュー・ベイシーにおいても68年にサミー・ネスティコ氏がアレンジャーとして加わることでこの前後でサウンドが変わったという方もいて、特に日本においてはこのネスティコ氏が加わって以降のものがビッグバンド愛好家の間でも多く親しまれています。
ここでどうしても出てくるのが「オールド・ベイシーこそベイシーサウンドだ!!」「ネスティコが加わってからのベイシーサウンドは下品だ」「ベイシーが亡くなってからのベイシー楽団は聞くに堪えない」といった話。これね、話としては分かるんです。単に回顧主義とはちょっと違う面があると思うんですよ。これは完全に私なりの解釈ですが、特にニュー・ベイシーにおける50年代以降のビッグバンドの潮流として、ここでも60年代以降グラミー賞の受賞を通じて少し見ていきましたが、エリントンやハーマンといったビッグバンドリーダーが様々な音楽の要素をビッグバンドに取り入れつつ時に実験的に時に先鋭的に時に発展的にサウンドを変化させていったのに対し、ベイシーはスウィングを基軸とした往年のビッグバンドサウンドを大切にしていた。それが時代を超えて評価されている部分でもあるのですが、それ故にベイシーサウンドを深く理解し愛し共感すればするほど、より古い時代のサウンドに本物が見えてしまう、そのように感じると思うんです。これはつまり構造的なものなのであり、リスナー側に何か問題があるというのではなく、なので誰かが誰かを批判・批評するような類の話ではないのかなと。
結果的にビッグバンドが背負うこととなった【伝統】という看板
そもそも「ビッグバンドが【伝統】を背負う」ことになったのは80年代に相次ぐビッグバンドスターが逝去したことで決定的になったものであり、象徴的な話が1988年のLincoln Center Jazz Orchestraの登場と1991年のウィントン・マルサリスの同楽団の芸術監督就任と考えています。
ただ、これはあくまで私の見方ですが、いわゆる「【伝統的】ビッグバンド」というそのイメージこそが構造的に作られたものなのではないか?様々な流れ、社会背景、音楽市場の変化、人々の生活スタイルの変化など様々な要因があるものの、とにかく結果として構造的に作られたこの「【伝統的】ビッグバンド」というイメージ、しかしそこに囚われて音楽をやっても意味がない、そのようにミュージシャンも考えた。
そのような仮説を置いてもう一度90年代のグラミー賞の流れを整理すると、ベイシー亡きあとのベイシー楽団による3度の受賞は「往年のビッグバンドスターのビッグバンドサウンドの継承」という話になりますが、しかしその中にもジョージ・ベンソンとのカップリングナンバー「Basie’s Bag」を取り入れるなどの変化が見られます。またマイルスやマッコイ、ジョーヘンといったジャズの巨人をフィーチャリングしたビッグバンドや、50年代60年代のジャズの名曲を現代的にアレンジして演奏したGRP含め共通しているのは「サウンドは革新、選曲はジャズ巨人の伝統を踏まえたもの」。これが先程仮説とした「ビッグバンドが背負うことになった【伝統】という看板を消化しながらも、そこに囚われずに前に進もう」とした結果であったとするなら、それがグラミー賞という形で評価されたことは一つの成果であったとも考えられるわけです。
しかもこの流れが今度は、1994年にデビューアルバムを発表、2000年代のグラミーにその名を示すこととなるマリア・シュナイダーの登場にもつながってきます。彼女のバンドが示したものは、サウンドの系譜としてはギル・エヴァンスやメル・ルイスといった【革新】に連なるものでありながら、彼女自身の履歴にはマイルスやマッコイ、ジョーヘン、あるいはマーサー・エリントンやフランク・フォスターのような【保守】としての伝統が記されていない、つまり【革新】そのものというビッグバンドの方向性(とはいえこれもギル・エヴァンスやメル・ルイスももはや【保守】とみることが出来る、そういう考え方も出来るのですがその辺は一旦脇に置いておきます)を示したわけです。
と、ここは次の2000年代のところで熱く語るとして、90年代のグラミーの流れをまとめると「80年代にビッグバンドが背負うことになった【伝統】という看板をどのように消化しつつ、どのように前に進んでいくことが出来るか」これがテーマであり、このテーマに対する答えが作品として示された、そのようにまとめられるのではないかと考えます。
というわけで、90年代グラミー賞受賞ビッグバンドをみていきましたが、いかがでしたでしょうか?何だか時代が進むにつれてドンドン話す内容が膨れてきてしまって、このまま2000年代に突入したら一体どうなってしまうのか、不安で仕方ありませんが、まぁとりあえずこのまま頑張ってやっていきたいと思います。ここまでお読み頂きありがとうございます。よろしければフォローよろしくお願いします。以上、ビッグバンドファンでした。ばいばい~~~
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
