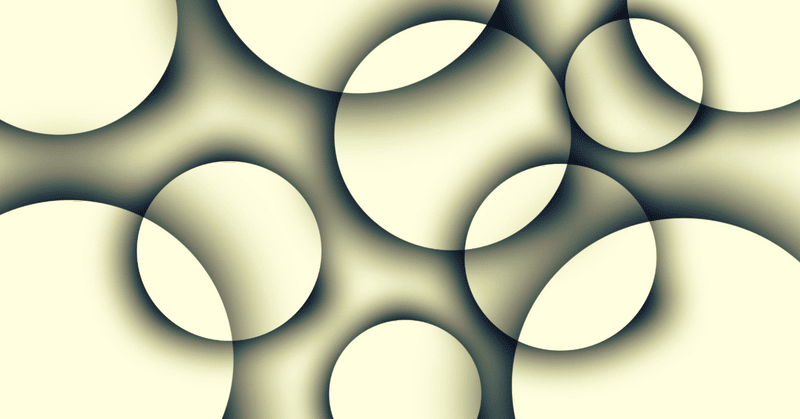
”境界線”と”居場所”と”間”と”所属”の話
タイトルがごたついているけれど、わざとだ。
わたしは専門家ではない。
おそらくこのことについて体系的に書くことはできないので、すごくわかりづらい文章になってしまう。
読んで欲しいとは言いづらい。
けれど、わたしはこれを知ったことですごく楽になったので、必要なひとに届くように、と願っている。
おそらくHSPとか愛着障害に関わる話だ。
18ヶ月までの赤ちゃんの脳に与える影響がとてつもなく大きい、というのはよく聞く話で、それについての具体的な話だ。
そのひとは、「死のおっぱい」という表現をしていた。
お母さんがくれるおっぱいが嫌いで、おばあちゃんが哺乳瓶で飲ませてくれるミルクの方が好きだったそうだ。
その理由は、その時期のお母さんが精神的に不安定で死の恐怖に取り憑かれていたことだったとそのひとは語った。
わたしも、長女を育てているとき、怖くて怖くて仕方なかった。
もうひとつ、印象に残るエピソードがある。
ある母親がこどもを連れてきた。
話を聞いても、まったく問題が見当たらないので、母親がこどもと接する動画を撮った。
それを見たひとは、「息苦しい」と言ったそうだ。
母親は、ずっとこどもに何かをし続けていて、「間」がない。
あやし、こどもがふいと別のところを向けば、追いかけていってあやす。さらに泣けば抱っこしてあやし、ミルクをあげる。
正しいコミュニケーションというのは、こどもが目をそらしたら放っておく≒「間」を作ることなのだそうだ。
2つの話の共通点は、母親の持つ「恐れ」だ。
「恐れ」は「間」をなくす。
18ヶ月までの体験がなぜ重要なのか。
それは、表層に出る感情の大元となるシステムが作られる時期だからだ。
そこでシステムが作られ、反応の癖が決まってしまう。
母親の「恐れ」はこのシステムの形を歪める。
まともに育てられたひとが持つはずの感情が生じない場合がでてくる。
あるいは、ひとつの感情ばかりが反応してしまう。
安心には境界線が必要だ。
境界線は自分を守ってくれる。
境界線の内側が、自分の居場所になる。
境界線の内側にいることは、所属意識につながる。
親は、言葉ではなく体験でもって、こどもにこの境界線の基礎を教える必要があるけれど、「恐れ」に満たされた母親は、こどもに境界線をプレゼントできない。
境界線を持つこどもは、その境界線をもって外の世界に出ていくことができる。
危険で不安定な外の世界でも、境界線の内側には安心がある。
だから、チャレンジができるのだ。
そして起きたことに対して、正しく反応し対応することができる。
この18ヶ月までに作られたシステムは、何かが起きたとき、感情よりも早く作動し、体に影響を及ぼす。
そして、そのシステムは、後から作り変えることができる部分とできない部分がある。
わたしは、ずっと自分の文章に息苦しさを感じていた。
「間」がなかったのだと今は思う。
日常でも、zoomでの会議中の「間」の難しさを思い知っていた。
この話を聞いて、いくつかワークをしたのだけれど、わたしのシステムは変化し、日常の息苦しさが半減した。
一番変わったのは、「今」にいられるようになったことだ。
境界線が不安定だということは、いつもそこが居場所だと感じられなくて、生きたマグロのようにずっと動いていたくなってしまうということなのかもしれない。
かといって、冷凍マグロになりたいわけではないけれど。
▼続き。
サポート嬉しいです!新しい記事執筆のためシュタイナーの本購入に使わせていただきます。
