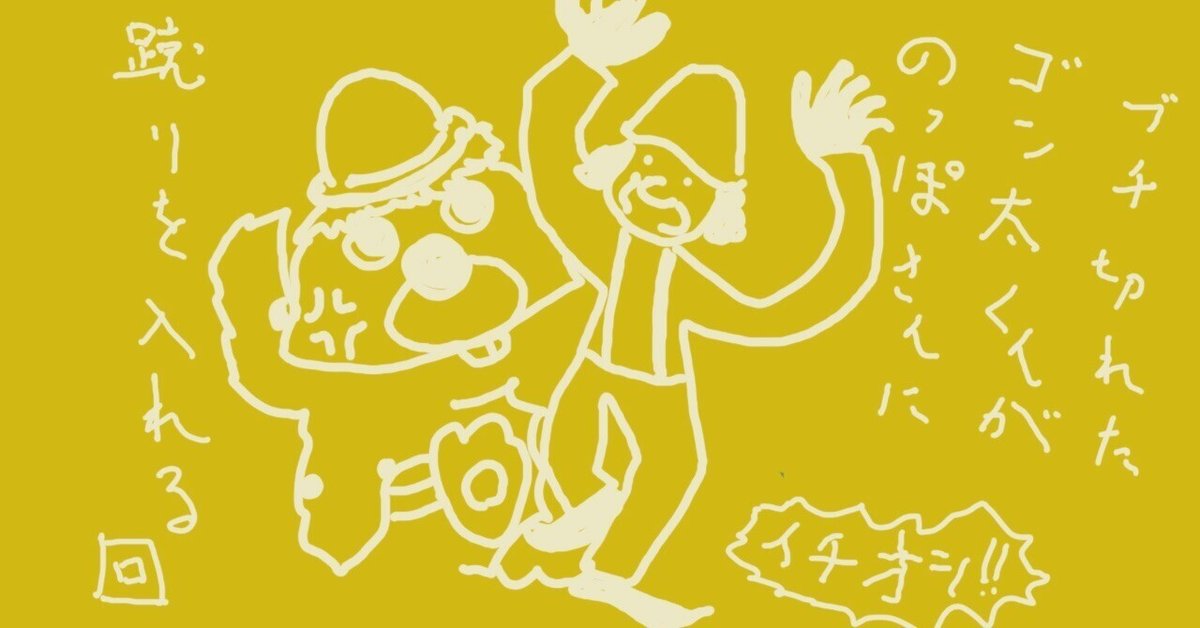
#104 あこがれ
高見映さんが……ぢゃないんだってね、最近はずっと高見のっぽさんだったラスイ――が、亡くなったということで深夜に「できるかな」たっぷり4回分一時間やってるのを録って観た。うちのヤングらにも見せたら大変好評でヘビーローテーションしている。これも珍しいことである。
で、観ていて思い出した。この後継作の「つくってあそぼ」はダメだったのだ。個人的にハマらなかったことを「駄目」と云っていいのかと云えば、いいのである。その一方で誰かは「おれはわくわくさんとゴロリが好きで好きでしかたねえ!」と強く云えばいいだけの話なのである。好きという気持ちで負けてはならぬ。
畢竟、のっぽさんはどこまでも「おとな」だったんだな。今回の内、ロボットレストラン回なんかはとりわけ顕著で、出だしから颯爽としている。タップダンスでもひと踊りして、さあ今日は何をやらかそうかい、みたいな。自分の芸で視聴者であるこどもにちゃんと対峙しようとしているのが、すごく憧れる。これはスタッフワークもそうで、「ロボットレストラン」、いろいなロボットを紙の工作で作ってはいるが、実際にそのロボットたちは中に沢山のスタッフが入って動かしている、これがすごい。家庭では出来ないけど、テレビでしか出来ないことをやっているから「あこがれ」となる――その後NHK教育の回顧リクエスト番組みたいなので「つくってあそぼ」も観たけれど、画面の中で出来ていることが全て家庭で再現できちゃああこがれにならないんだよなぁ、という点でやはり劣る。いわんやノイジーをや……である。クラフトさんは「こどもを不安にさせない程度の大人フレーバー」でしかないのだ……。
この辺の気持ちにはもっと古いあこがれがある。ディズニー「メリー・ポピンズ」の「バート」ディック・ヴァン・ダイクだ。全身に楽器を点けてひと踊り、おひねりの一つももらえず別の日は路上絵描き、煙突掃除……子どもから見ると「何をやっているひとなんだろう」なんだが、それでも、周りの大人達の間では一目置かれている気配だけはわかる。ついには厳格な銀行員であるジェーンとマイケルの父親も冷静に諭すことができる。
眼の前で楽しいことはしてるが、決して馴れ合うことはない。本体は、自分の届かない遠くにある――これを「あこがれ」と呼ばずして何をあこがれとするのか。
往時はとてもいい時代だったと思うのだが、「できるかな」が終わったあたりで決定的に美意識に対する転換点があったのかもしれず、ノスタルジー込みでそこを掘り下げると、また楽しいのかもしれない。なにもないのかもしれない。
みなさんのおかげでまいばすのちくわや食パンに30%OFFのシールが付いているかいないかを気にせずに生きていくことができるかもしれません。よろしくお願いいたします。
