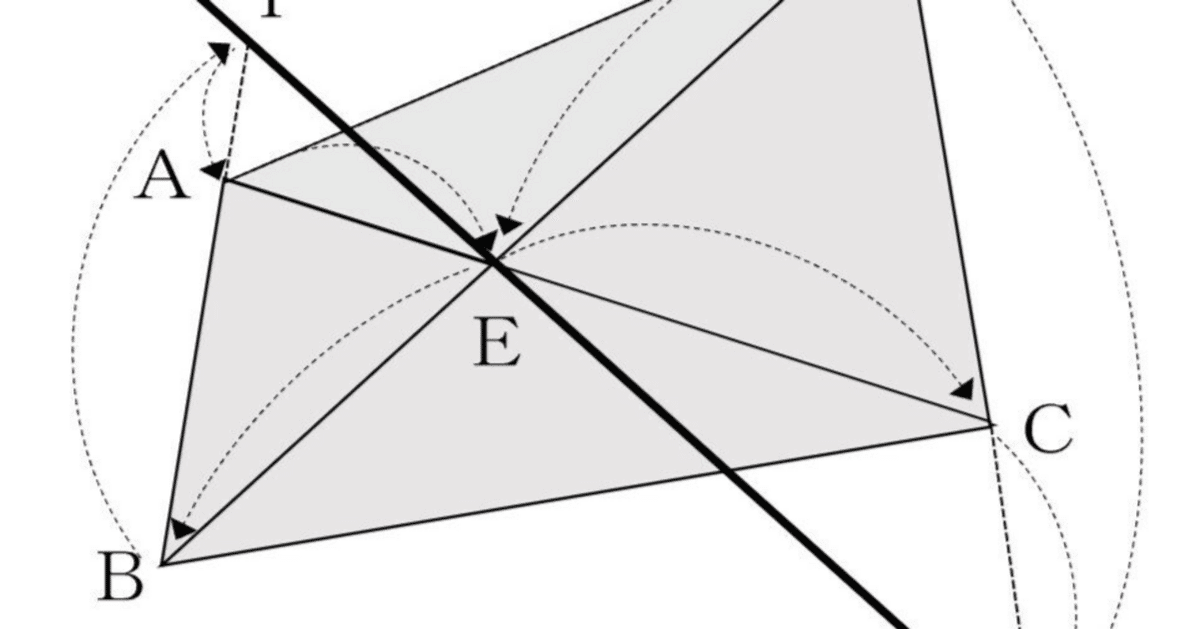
トラぺジウム
見た。以下の文章はネタバレに塗れています。言ったからね。
随分と地味な映画だったなぁと思う。
見ごたえのあるアクションシーンがあるわけでもなし、壮大な伏線回収があるわけでもなし、複雑な人間模様が描かれているわけでもなし。小説の映画化とは本来こういうものなのかもしれない。それくらい地味な映画だった。
それでも確かに面白かったので、きっと原作小説も優れた作品なのだろう。
この派手さのない面白さの大部分を担っていたのはやはりこの作品の主人公だった。東ゆうさん。凄い人だった。凄く悪い人だった。
アイドルになる。ただそれだけの単純過ぎる目標のために、ここまで人生を捧げられる人間というのはそう多くないはずだ。
だからこそ彼女は最終的にアイドルとして活躍できていたのだろうが、彼女くらいアイドルに一直線でないとアイドルとしてはやっていけないよというメッセージを強く感じた。
東西南北からかわいい子を集めてグループを作る、というのも彼女にとってはあくまでアイドルになるための道の一つだったのではと思う。実際彼女は数えきれないくらいのオーディションを受けた上で一度も手が届いたことは無いそうで、オーディションではない道を考えた時に浮かんだ手法が映画の序盤で描かれているあの仲間集めだったのだろう。
目的の女の子とお近づきになれた証として主人公が指を折り曲げカウントを重ねていく様がまあ怖かった。
この子には目の前の女の子が数字か方角くらいにしか見えていないのではないかと思ってしまったが、恐らくそれはあながち間違った見方でもないのかもしれない。それを隠そうともせず方角で名前を呼んでしまうあたりにも主人公の異常性は良く表れていた。
北の子との距離を縮めるために下心満載でボランティアへの参加を決めたシーンの恐怖感といったらもうたまらない。
その後に移される車椅子利用者の姿には思わず鳥肌が立ってしまった。オイオイそこは結構センシティブじゃないか、この主人公とそこを掛け合わせてしまって大丈夫なのか、と心配が止まらない。
その心配は全く杞憂に終わらず、車椅子利用者でさえ主人公の目線を通せば等しくアイドルになるために活用できる手段の内の一つでしかなく、その意味で彼女ほど平等を体現した人間というのも貴重なのかもしれない。平等性というアイドルに非常に求められがちなスキルをこの時から持ち合わせていたのもまた、彼女が最終的にアイドルとして大成した要因の一つなのだろう。
城でのボランティアを通じてメディアに取り上げられ、夢見たアイドルへの道を順風満帆に進んで行く主人公の姿には、ああ一体いつこの幸せいっぱいドリームロードが音を立てて崩れてくれるんだと、中盤はそんな期待で胸がいっぱいだった。
喫茶店であのカメラ眼鏡くんと一緒にいるところを撮られるのか、大人の事情に巻き込まれて止む無くアイドルの道を断たれるのか。考えられる崩れ方はいくつもあって、しかしそのすべてに共通していたのは、主人公の及ばない範囲で起きたトラブルに寄って、彼女の道は断たれるんだろうなということだった。
順調にアイドルとしての歩みを進めていく主人公が、その順調さの一因でもあった大人の事情が形を変えて困難として襲い来るのに巻き込まれ、アイドルとして生きていくことの難しさを思い知らされるのだろう。この作品の原作小説は元アイドルの人が書かれているらしいし、そんな芸能の世界の厳しさが描かれるのだろうと思っていたのだが。
崩壊は、彼女自身に寄ってもたらされた。
彼女のアイドルとして成功することしか見えていない視野の狭さがしっかりと因果応報という形で彼女の身に降りかかっていた。
この圧倒的正しさには感服せざるを得ない。ここまでやけにリアリティに乏しかった作品に唐突にもたらされた強すぎるリアリティ。強すぎる。
この作品はやはり、最終的に主人公がアイドルとしての輝かしい道を歩み始める様を描きたかったのではないかと思った。
そのための理由付けが、説得力の向上が、あの映画の尺の9割をかけて描かれていたのではないかと、そう思うのだ。
アイドルになることしか考えていなくて、すべての人間や事象を自分がアイドルになるただそのためだけに利用する逞しさ。
仮にも共に苦楽を共にしてきたであろう仲間たちに諭され、そんな仲間の厳しい姿を目にしてもなお、アイドルという職業への憧れを捨てることのない盲目さ。
それだけ自分本位であるにも関わらず不思議と周りに人を集めてしまうカリスマ性。
一度の大失敗にもめげずアイドルへの道を諦めないしぶとさ。
終盤に至るまでに繰り返し描かれていた主人公のそんな姿は、すべて彼女がアイドルとして成功することの理由付けに思えてならない。
最後に4人であの公園で、あの時は叶わなかった自分たちで作詞した曲を歌い合うパート。ここで主人公は自身の行いを悔いて心を改めたような気がしてしまうが、しかし安心して欲しい。
あんなことがあっても4人の仲は元通りになって良かったねと言わんばかりになんてことのない砕けた会話が交わされるシーンで、主人公は「じゃあもう一度アイドルやってみる?」的なことを冗談めかして呟いていた。それも、一番にアイドル活動に心と体を壊された女の子相手に、だ。いやぁひどい。惚れ惚れしてしまうほどに、仲間集めのシーンで指折り数えていたあの時から主人公の根っこの部分は何も変わっていなかった。そしてそれはきっと、数年後のアイドルとして活躍している主人公もまた、根っこの部分は一切変化していなかったのだろう。
映画だからと言って、一つの作品だからと言って、キャラクターが成長しなければいけないとか、考えを改めなければいけない、なんてのは、自分は詭弁だと思っている。面白ければ主人公がずっと最悪なままでも何も問題はないからだ。
それを地で言っていたのがこの作品だった。主人公は結局最後の最後まで最悪で、その最悪さが一度の大失敗と二度の大成功に繋がっていた。そんな徹頭徹尾変わらず我々の目線を引き付ける主人公が大活躍するこの映画は本当に面白かった。
彼氏がいるなら友達にならなきゃよかった、のたった一言に彼女の最悪さがすべて詰まっていたように思う。
その前のシーンで、私を友達とは言ってくれないんだねと不満を噴出させたキャラへの当て擦りも込めた、あの最高にして最低の捨て台詞は忘れられない。あの言葉を真正面から吐いて吐かれて、最終的に彼女らが一生涯の友人として大人になっても付き合いを続けているのは本当に凄いことだ。
どれだけ最悪でも、その最悪さがまた一助となって、彼女は結局アイドルとして大成功を収めてしまうのだ。
正直主人公以外の登場人物に関する印象が薄いのは、この作品がとにかく主人公一人で完結しすぎていたからだと思う。主人公が他の人間をアイドルになるための手段にしか捉えていなかったのと同じように、自分にはこの作品が、主人公が自分の持ち合わせたものだけでアイドルとして大成する物語にしか見えなかった。
それは登場人物にも言えることなのではないか、ということもまた思った。これだけ最悪で自分本位な主人公でも西南北の3人は最終的に彼女を許している。それはきっと彼女たち3人にとって、それぞれ主人公がアイドルであったからだと思う。
魅力がないと思っていた自分と初めて友達になってくれて、自分の魅力を教えてくれたアイドルとして。
初めての女友達として自分の世界に興味を持ってくれて、その上自分の世界を広げてくれたアイドルとして。
幼いころから変わらない芯の強さを持って、あの頃の弱かった自分を救ってくれたヒーローのようなアイドルとして。
三者三様、彼女たちの目に主人公がアイドルとして映っていたからこそ最後の公園でのあのみんなで自分たちの言葉を乗せた歌を歌う描写があったのだと思う。それはきっとお城のボランティアのおじいさんズもそうだし、カメラ眼鏡くんも、喫茶店のマスターも、古賀ちゃんも、お母さんもそうなのだろう。主人公のアイドル性の前では彼女のお母さんすら彼女を応援するファンの一人に思えてしまうほど、彼女のアイドルとしての姿は眩しかった。
彼女は東西南北の中でもぶっちぎって化粧映えがする子だったと思う。アイドルになる以前から例の3人は見た目に言及されるシーンがあったものの、主人公だけはその限りではなかった。
ジャージばかり着ていた彼女が、しかしアイドルとして髪を巻いてメイクを施して華やかな衣装を着ている姿はとてもかわいかった。ここのギャップが一番激しかったのは間違いなく主人公だ。
そんな姿からも、とことん彼女はアイドルとして成功するべくして成功したのだということがよくわかる。
この映画の地味さはやはり、登場人物として印象に残るのが主人公たった一人だけであることも理由の一つなのかもしれない。
そのたった一人がここまで強烈であるからこそ、ここまで面白い作品になっているのだが。
引っかかったのはそれだけアイドルに入れ込んでいる主人公を描いている割に、主人公がアイドルに惹かれるきっかけというかアイドルへの憧れを語るシーンが妙にふわふわしていたことだ。
あれだけアイドルを目指して止まない、アイドルまっしぐらな主人公を描いている割には、そのきっかけを語るシーンの手ごたえのなさは見ていて違和感がすごかった。主人公が普段からアイドルの曲を聴いている様子もささやかにしか描かれていなかったし、主人公の好きにあまり中身が見えなかったのが、この作品で描こうとしていたものを思うと大分辛い。
あと会話が妙に噛み合っていないように感じた。
喫茶店でカメラ眼鏡くんと自分の野望を語るシーンも会話が噛み合っているようで噛み合っていなかったし、北ちゃんが突然、私たちのことをを友達だと言ってくれないんだ、と不満を噴出させたシーンもあまりに唐突過ぎやしなかったか。
終始主人公の姿しか見えていなかった自分でも気になってしまうほどコミュニケーションが取れていなかっなたと感じたのは、もしかして周囲の人間に人間としての興味を示さない主人公の目線を演出する意図が込められていたのだろうか。
映画の尺にあの物語を収めるための取捨選択があまりうまくいかなかったのかな、とは思ってしまった。
あと北ちゃんがかなりフランクに整形したんだ、的なことを言っていてビビってしまった。
彼女はまだ高校生で、彼女がトラブルに合って決意を新たにした頃はまだアイドルを目指していたわけでもないだろうに、整形ってのはそんなにカジュアルに行われるものなんだろうか。
自分の想像が一切及ばない世界の話なので、この描写はリアリティに欠ける!と言ってしまいたくなるが、この作品の原作の作者がアイドルの人である事実が強すぎて、自分がグチグチ口を出せる話ではないんだろうなと諦念に似た感情を覚える。
そりゃあ中盤の主人公たちの成り上がり方には多少のご都合主義は感じてしまうが、しかしこれを書いたのがその厳しい世界を生き抜いているであろうアイドルの人だからなぁと思うと、どうしたって口をつぐんでしまう。
気になったのはそれくらいか。
書きそびれたが、序盤は自室でアイドルの曲を聴いていた主人公が、自分がアイドルとしての道を歩み始めた頃にはラジオを流していたのが印象的だった。アイドルに近づいているはずなのにアイドルから距離が遠ざかってしまっている難しさ、みたいなものがあそこの描写には詰まっていたと思う。
徹頭徹尾、良くも悪くも、主人公の印象が強すぎた作品だったと思う。
これほど手放しに称賛しづらい方向に芯の通ったキャラクターというのはかなり自分好みで、個人的にはとても楽しんで見られた作品だったのだが、人を選ぶ作品だよなぁともまた思う。
でも面白かったな。
ただ、おじいさんズの内の二人の声が明らかに若い女性のものだったことだけはまだ納得がいっていない。
後から見たら原作の人とその人と同じ乃木坂の人だったのか!
内村さんが良かっただけにあの二人だけかなり浮いていたなぁ。
この主人公も将来アニメ映画の声優に挑戦したりするんだろうか。それはものすごく見てみたいな。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
