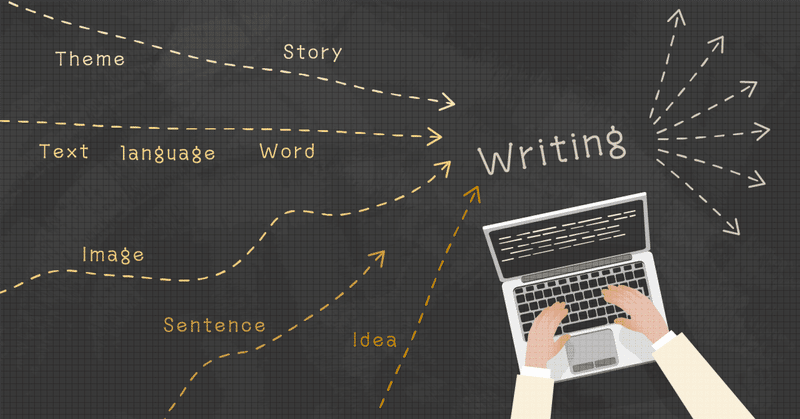
Latexを使うわけ/使わないわけ
今時、パソコンなりで文書を作成するといえば、Microsoft Officeなりを使うのが一般的と思う。出版関係だと、Adobe InDesignとか使うのだろうか。筆者は仕事の関係でMacintoshとQuakXPressという環境をしばらく使っていた(じじぃである)。イラストや画像の作成は長くなるので、ここでは触れない。
筆者だって、普段はWordとExcelを使っている。普通に仕事でパソコンを使っていれば、外部から受け取る文書ファイルはMicrosoft OfficeかPDFが殆どなので、選択の余地はない。
しかし、長らくTex系のシステム(LaTex含む)には憧れというか、使いたい欲求があった。それは、テクニカルな論文や文書を作成する場合に顕著である。
LaTexを使う利点
①数式の作成が楽。
最近のワープロは数式エディタがかなり良くなったが、昔はそれほどでもなかった。色々やって、駄目なので、結局ドローイングソフトで作成して貼り付けるとか、結構やった。何度Tex使えないかなと思ったか分からん。
②外部のテキスト処理システムと連携できる
例えば、図表や数式を入れると、通し番号を振っておく必要がでることが多い(普通にそうだと思う)。それで、通し番号を振った図表や数式は、勿論、本文中で参照するのだが、これが、面倒を呼ぶ。
図の1から10までを作成し、本文に挿入した後、図1の後ろに別の図表を図2として挿入したくなったりすると、泣きたくなるのである。それは、図2から10までを新しく、図3から11までにリナンバリングしなければならないというだけでなく、それらを参照している本文中のナンバーも書き換える必要があるからだ。
こういう作業は、実は、Wordなんかでもできるのだが、実際に、こんな芸当ができる人は少ないだろう。できるのとやれるのは違う。
それで、院生時代に修士論文をWordで書いて送ったら(教官はLaTexとか無理なので)、この手の自動相互参照部分を全部潰された改訂版を送り返されて絶句したこともある。相互にやり取りできるとか、共有できるということは、そのシステムの理解が一番低いメンバーに機能が限定されてしまうということでもある。こういうのが苦痛なのである。
それで、LaTexだとどうなるかというと、実は、LaTexには、こんな機能はないらしい(あったらスマン)。しかし、無くてもそんなに困らない。外部のテキスト処理システムとか使えば解決するのである。
例えば、図表のタイトルには@@Figure_00とか、本文中の図表参照部分には@@@Figure_00とか入れておいて、@@Figure_00と@@Figure_01の間に新しい図表を入れたくなったら@@Figure_005とか、適当なタグを付ければ良く、最終的にLaTexにかける前に、外部のテキスト処理プログラム(筆者の若いころはPerlが多かった)にかけて@@Figure_00などを出現順に図1などに変換してからLaTexにかければ、綺麗にできあがる。
ちなみ、元の原稿ファイルをテキスト処理プログラムにかけてからLaTexに送るなどの処理はmakeというコマンドを使えばかなり自動化できるので、Unix系のコマンドプロンプト環境は工夫が効く。
図表のナンバリング以外にも、工夫次第で色々どうにかできてしまうところがあるのだ。
この辺りは、プレーンなテキストファイルを入力にとる、LaTexのようなテキスト処理システムの強みではある。
LaTexが普及しない理由
LaTexなりが出現してから、かなり時間が経った。なんなら、日本語が使えるLaTex系のシステムが出現してからでも、結構時間が経過していると思う。
それでも、LaTexは現在でもあまりメジャーな文書作成システムにはなっていないと思う。
色々理由はあるだろうが、まず、普通の人にはタグをコーディングして文書を作成していくスタイルが理解できないのだと思う。Webサイトを作るときに、HTMLを手打ちで作る人はいないのと同じといえば、判るだろうか。
また、商業印刷の分野でもあまり普及しなかった気がするが、これは、(商業印刷で利用可能な)日本語のフォントが極めて高価であり、また、LaTexのようなフリーのシステムでは利用しにくかったことなどが主な原因ではないかと思う。また、日本の商業印刷で要求される組版の仕様が欧米のそれとはかなり違っており、そのギャップを埋めようと悪戦苦闘したLaTexエンジニアの苦労話をその昔に読んだ記憶もある。
外部のテキスト処理システムとの連携が強みであると、上述した手前、申し訳ないが、肝心のテキスト処理システム(昔はPerl、今だとPythonか?)というのを使える(あるいはプログラミングできる)人は極めて少ない。これも広く普及するには足枷であろう。
結局、今でも理系の論文を作成する人たちの中の(そのまた)一握りの人たちが中心に細々と使われているシステムなのかなと思ったりもする。
それでも
それでも、LaTexは今でも使われ続けており、何だか、開発も続けられている現役のシステムである。最近、LaTexに挑戦し始めた筆者のような者もいる。世界の片隅にいる、少数のコンピュータ巧者たちだけが使うシステムで終わって欲しくないなと、時々思うのである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
