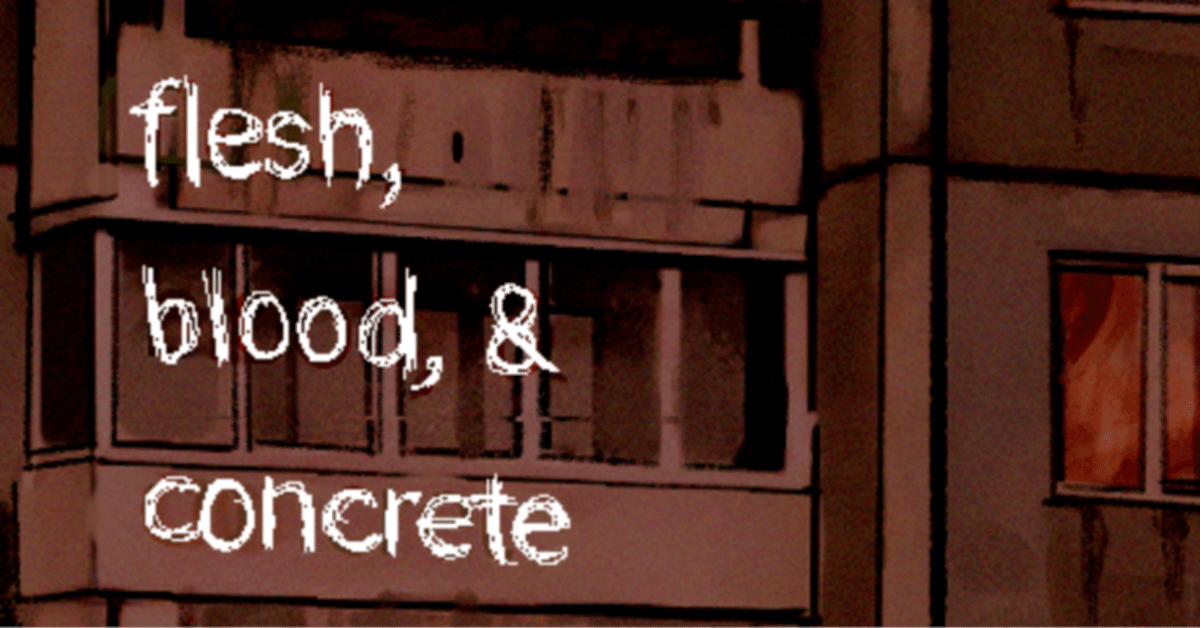
「Flesh,Blood,& Concrete」、あるいは選択のエチカ
辺り一面激しい雪に覆われたシベリア。ソ連時代に作られた無愛想なコンクリート建築群に迷い込むのは主人公レラ。生きにくい現実から車に乗って逃避する最中だった。車が故障したために、その修理や、物資を得るために不気味なコンクリートの中に入っていく。そこで出会うのは少女ニカである。どうやら少女は、この不気味な建築に一人で暮らしているらしい。
本作「Flesh,Blood,& Concrete」は2021年にリリースされたRPG Maker製ホラー・アドヴェンチャーゲームであり、itch.ioにてフリーダウンロードが可能である。日本語版は2023年の4月にローカライズされ、一ヶ月弱たった現在において徐々に話題になりつつある。作者IO氏はそのホームページ(https://denpa.neocities.org)で確認できるように、キャラへの愛着(キャラの倫理)とこの世ならざる世界観とを同時に表現できるアーティストであり、そうした雰囲気に影響を受けたfanartも海外の掲示板等で知ることができる。IO氏のこうした世界観は日本のゲーム『ゆめにっき』やイラストレーション作品から少なからず影響を受けていて(HP内の、「game log」あるいは「art book shelf」を参照)、複数の文化の結節点として作品が成立していることを知ることができる。
ゲームシステムは至ってシンプルだ。プレイヤーは主人公のレラと一体になり、廃墟と化した建築を探索する。そこここに転がるアイテムを収集しつつ、レラの車を動かすためのガソリンを探して歩き回る。歩き回りながらニカとの会話を進めて行き、時折現れる選択肢に、レラになりきったり、あるいは「プレイヤー自身」として答えていく。他のゲームもそうであるように、このような「選択」が物語を進め、分岐点を生む。それは複数のエンディング、すなわち終局を用意し、それぞれの違いがプレイヤーのモチベーションとなる。

ところで本作において、「選択」はゲーム・システムであると同時に、主人公であるレラというキャラの人生に(=人格に)生じた様々な困難を連想させる重要な概念となる。プレイヤーはレラと一体になり、それを追体験する。すなわち、「選択」によって繋がったゲームシステムとレラの人生=人格、この混じり合った全体がプレイヤーに働きかけ、一つの不思議なゲーム体験をつくりあげる。
レラの人生に、あるいは人格に生じた「選択」とはなんだったのか。ニカとのやりとりから想像してみよう。様々な規範から成り立つ現実の社会で、それらを正しく選択すること(普通の大人らしく、正しく、常識的に、あるいは、愛着や愛情をまっとうに誰かに注ぐこと、普通の女性らしく生きること、など)と言えるだろうか。それら全てから逃れること、「選択をやめること」を選んだからこそ、この不気味な場所にたどり着いたのである。

あるいは、であればこそこのゲームの悲しさは、まさにゲームであることによって「選択」をしなくてはならない、という点にあるかもしれない。選択をしなければ、永遠に止まった時間の中にレラを閉じ込めることになる。もっとも、ニカの望みはこれかもしれないが。
このゲームを理解するための一つの鍵は、コンクリートの深層でレラが体験する彼女の幻想の中にある。壁に描かれた建築デッサン。ロシア革命期において重要な構成主義建築家、ウラジミル・タトリンの「第三インターナショナルへのモニュメント」である。ガラスと金属とからなり、エッフェル塔よりも高く作られることが予定され、1920年以降の世界を象徴するはずだった。しかし計画は未完成でおわってしまう。夢破れたユートピアに対してレラは、愛憎入り混じった表現でこのように言う。「私はタトリンのようになりたかった」と。「新時代をきりひらく」と彼女が表現するもの。そうした理想的な世界と、現在の「(正しい)選択」にまみれたレラの世界との乖離が、この部屋から痛いほど伝わる。


この点に関して、作者IO氏の考えを直接知りたければ、丁寧に準備されたホームページを覗くと良いだろう。「Machine dreams」という項目へ。「窓の外には果てしない白しかない。夜が来ることはない。スモッグが濃すぎてどうせ気づかないだろう。この街は存在しない」という書き出しとともに、ruDALL-E(テキストからイメージを生み出すAI)によって生成された架空の建築群が並んでいる。レラが逃げ込んだのはこの中の一棟であることは間違いない。しかしなぜ、このような、ソ連風の無愛想な建築群に夢を託すのだろうか。(これは、ニカというもう一人のキャラと、「ホラーアドヴェンチャー」というゲーム形式それ自体に直接関係すると思う。長くなるので割愛)


「市場原理が人間の魂にまで侵食した現代、私たちの価値(個性)はどこまで行ってもいくつかの支配的なアルゴリズムに規定されている。この世界のオルタナティブを求めるために、1917年=分岐点にまで遡り、別の選択を想像しようではないか!」。IO氏にここまでの主張があるかはわからない。あくまで私の考えであることを強調したい。ちなみに、タトリンが引用されている点はやはりかなり重要である。芸術と革命の相性の良さと悪さを同時に体現した人だと思うので。
さて、ゲームは選択の末、少なくとも2種類の結末を見せてくれるだろう(他の結末があるかはまだ調べられていない)。そのどちらもが、レラにとって、あるいはニカにとって意味を持った結末だったと思う。なにより重要なのは結末よりも(Happy Endか、True Endか、よりも)、そこに至る過程の、すなわち「選択」自体が、より厚みのある体験として、レラとニカとプレイヤーに対して影響する過程をじっくり考えることだ。またこの体験は、他のADVゲームのプレイ体験へ、大きな影響を持つだろう、少なくとも、私にとっては。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
