
鳴潮(wuthering waves)クローズドβテスト オープンワールドについての考察
0.今回の目的
Twitterのやり取りで、とある話題が。
「鳴潮って、オープンワールドを活かしきれていないのでは」
クローズドβテストではあるため、運営さんが検討・模索している部分だと思いますが、
確かに活かしきれていないと共感できる部分があり、自分なりの答えを出してみたいと思いました。
※今回は意見まとめ・メモに近いです。ご了承ください。
1.今回の鳴潮におけるオープンワールドはどうだったか
どんな遊びがあったか
7種の遊びを感じました。
「①道中」
スタミナ考慮して、崖や穴をジャンプ・落下傘(※カービィのパラソル)・鉤縄(※モンハンRiseの翔蟲)を駆使して、うまく進む。
「②謎解きギミック」
※マップアイコンとSEを頼りに箱アイテム探し/3つの鍵アイテムを見つけて障害物解放/障害物を壁にぶつけてルート開拓/素早く移動する小動物を攻撃/射的/複数のサンドバックを時間内に攻撃し終える/音骸に変身して輪っかくぐり/時間内にすべての輪っかくぐり/光る蝶を追いかける
所々に宝箱を空けるためのギミックがあり、謎を解く。
「③塔の解放」
ファストトラベルとして飛べるようになる塔を解放していく。
→④敵討伐・⑤素材収集・⑥クエストの集めやすさに直結する。
「④敵討伐」
音骸集め・素材収集・宝箱を空ける目的で、敵を倒す。
「⑤素材収集」
料理と成長要素に繋がるアイテムを集める。
「⑥クエスト(任務)」
主に共感レベル(プレイヤーレベル)を上げる。
「⑦ビューポイント(フィールド説明)」
おまけ要素。世界観的な説明が入る。
面白かったか
バトルに紐づく「④敵討伐」、バトルのアクションを扱って進む「①道中」、そしてそれを円滑させる「③拠点の解放」は良かった印象です。
ただ、バトルとは異なる遊びである、
「②謎解きギミック」「⑤素材収集」「⑥クエスト」は、要改良と感じました。下記が理由です。
謎解きがスムーズにいかないものが目立ち、すこしテンポを悪くする(次のバトルを楽しむ機会・時間を奪ってしまう)。
素材収集で集まるアイテムが、どういう強化要素に繋がるか分かりづらい。
クエストは、ローカライズ問題が大きいからですが、世界観・ストーリーの把握が難しく楽しみづらい。
なにが懸念なのか
「①道中」・「④敵討伐」・「③拠点の解放」が楽しかったということは、
「別にオープンワールドでなくても良かったのではないか」
という印象が強くなります。
パニグレのように、バトルに集中できる設計の方が楽しみやすいのでは(ただ広いオープンワールドではなく、適切な"狭さ"に収めておくべきではないか)
アクション重視のゲーム性で、オープンワールドを採用した理由はなにか
プレイヤーに寄り道で、どう"夢中"にさせたかったか
確かに、
利便性の高いアクションで、広いフィールドを駆け巡る…だけでも、悪くはないのですが、
原神
幻塔
モンスターハンターWORLD(※少しオープンワールドとは違うかも)
エルデンリング
Marvel's Spider-Man
ソニックフロンティア
ゼルダの伝説ブレスオブザワイルド・ティアーズ オブ ザ キングダム
などの、すでにアクション×オープンワールドを採用したゲームは多くあります。
「オープンワールドで、あらゆる場所・地形で謎解きしつつ世界を救ったら楽しいのでは」

「オープンワールドに配置されたアイテムやギミックを利用して、うまく大型モンスターの特性を把握して狩りできたら楽しいのでは」

「オープンワールドを、自由に駆け巡れるアクションでヒーロー活動できたら楽しいのでは」

「オープンワールドで、誰もが困難を極めるフィールドで、開拓しつつ制覇したら楽しいのでは」

CoreでStylishなアクションバトルが楽しめる鳴潮で、オープンワールドがどうあるべきか。
とても興味深いことだと思います。

海面の上には、もう1つの世界がある…?
オープンワールド(Open world)とは、ゲーム内の仮想世界において、移動的制限の無い、プレイヤーが自由に探索し、目的に到達できるように環境設計されたコンピュータゲームを指す
余談です。
鳴潮で、本当に優れていた点がありました。
それは、道中は本当にストレスなく、気持ち良く移動が楽しめたことです。
ゼルダの伝説ブレスオブザワイルドや原神と比べても、程よい障害となっている地形で、快適なアクションが楽しめるようになっています。
個人的には、乗り物はなくても楽しいと思えるほどでした。
2.オープンワールドの特徴(どうゲームに影響しているか)
オープンワールドは、
一言でいうと「クッソでかい遊び場」であり、
本来は、最短ルートを進む方が、最適解(楽しい・効率が良い・目的達成に適している)なのを、
様々な寄り道のルートを進む方が、最適解…となっていることだと思います。

寄り道(赤矢印)の意味が弱くなる。
変な例ですが、「パワプロのサクセス」が分かりやすい体験だと思います。
本来は、野球ゲームがメインの遊びですが、
サクセスでプレイヤー好みの能力で育成し、選手を作って準備をする。
この準備が、オープンワールドにおける寄り道と同じ部分といえるのではないか、と思います。
いざ野球ゲームで、サクセスで意図して伸ばした長所を活かして、勝ちに繋げることが出来たら、
「自分が準備してきたことは正しかった、意味があった」という、
その成功に至るまでの"過程の重さ"が違います。

鳴潮で例える場合、
"バトル"がメインの遊びです。
そのバトルに勝った際に、準備(寄り道)をした意味があったと感じられたら、オープンワールドを設けた意味があります。
ただ、クローズドβテスト段階だと、
どんな成長要素があるのか、正しく意図通りに成長を選ぶことができたか、謎解きギミックを効率良くクリアできるのか…といった、
少し不足な点が目立ち、"過程の重さ"は感じづらかった印象でした。
また、謎解きギミックに本腰入れると、
本来やりたいバトルがしばらく出来なくなってしまうので、
あまり時間かけないものにするか、バトルに強く関わりある謎解きギミック(バトルに関わるテクニックみたいな)が、欲しいと思いました。
まとめ:オープンワールドとは、メインの遊びの準備のための、寄り道を楽しむこと。
余談です。
真っ先に思ったのは、
「オープンワールドとは、その広いフィールドを活かして〇〇(メインの遊び)をすることではないか」と考えました。
オープンワールドで"謎解き"
オープンワールドで"狩り"
オープンワールドで"スピーディーな移動アクション"
オープンワールドで"サバイバル"
しかし、"バトル"のゲーム性だと、
敵対象と近づきあい、互いに影響を与えあう都合上、
ある程度の広さがあれば充分。広いフィールドは不要になってしまう。
例えば、
プレイヤーキャラが空を飛べる能力を持っていて、
対象ボスも飛んでて、あらゆる場所へと移動して攻撃してくるから、
それを追いかけ、広大なフィールドで地形特性を活かして戦う。
これがオープンワールドのゲームなのかといわれると、すこし違う気がします。
理由は、その遊びにおいて、それだけの広さが必要な遊び場になっているだけであり、適正な広さのバトル場を設けただけであって、
上記の遊びでオープンワールドを取り入れた場合、さらにもっと広いバトル場にして、オープンに感じさせる必要があります。
では、モンスターハンターWORLDはどうなのか。
大型モンスターとは1エリア内で戦うけど、
「一時休戦・下準備戦略が存在する」のが特徴です。
戦って不利になったら、距離をとって逃げる(プレイヤーから逃げることもあるし、大型モンスターもエリア移動として逃げる)。
離れたら、長期的な準備ができる。待ち構えて、先手の仕掛けを模索できる。
※モンスターハンターWORLDでは、エリア移動のロードが無くなったおかげで、これらがとてもスムーズになった。常に大型モンスターのことを考えるようになった。
なのでモンスターハンターWORLDは、オープンワールドでないと言われていますが、
一時的で簡易的な準備があるから、オープンワールド要素が少し含まれていると考えています。
3.自由とは、好みを表現すること
「オープンワールドといえば、自由だー!!」
ですが、"自由"ってなんでしょうか。
ぱっと思いつくのは、どこでもいけること。

・・・
どこにいけばいいんでしょう。
そう、どこにいっても、たとえ移動しなくても、
「変わらない」ので、これでは自由に感じません。

自由とは"好みを表現する"ことだと思います。
人によって、自由に対する答えは違いますが、
人それぞれが思う答えは、各々の好みに基づくはずです。
プレイヤーの好みが、オープンワールドで行動し続けられる原動力です。

連続的で選び、プレイヤーが好みで選び続けている感を目指す。
好みが選べなくなったら、プレイヤーは迷い、ゲームを止めてしまいます。
しかし2択に落とし込めば、心理的には「選びやすく」、「片方が好みで、もう片方は好みでない」という気持ちになります。
筆者が適当に思いついた、好みにおける2択の種類
・メインルートに近いか、遠いか
・複雑で困難な場所か、簡単か
・中央か、端か
・成長Aか、成長Bか
・高い場所か、平地か
・簡単か、難しいか
・複数か、強敵か
・攻めか、逃げか
・見えるか、隠されているか
・バトルか、それ以外か
・選択か、巻き込まれか
ふと上記を見て、なんとなく自分はこっちだな…と、無意識に決められると思います。これが2択の凄さです。
※好みって色々ある。
もちろん、Aの後にBへ行っても良いし、
どちらも選ばずに先へ進んでも良いのが、オープンワールドの特徴ともいえます。自由だー!!
まとめ:オープンワールドを歩む原動力として、"自由(好み)を感じさせ続ける"こと。
4.楽しい寄り道、準備とは何か

ゼルダの伝説ブレスオブザワイルドで、寄り道の内容についてどうだったか、整理してみます。
メインの遊び:
大型ダンジョンへたどり着くまでのイベント進行の謎解き
大型ダンジョン(神獣)のギミックの謎解き
大ボスの攻略(※これもある意味で、倒し方の謎解き)
寄り道の内容:
ザコ敵の拠点の討伐
中ボス討伐
強ボス(※ガーディアン、ライネルなど)からの回避or討伐
希少敵の発見と討伐
フィールドに隠された宝箱
コログの小ミニゲーム
ほこらの謎解き
フィールドギミック(落雷/溶岩/吹雪/風)の対策や利用
NPCや動物
クエスト進行
巻き込まれ系イベント
報酬(※準備内容):
・装備(武器・弓・盾・防具などなど)
・回復/一時強化アイテム
・永続強化アイテム
・フィールド用アイテム
・交換用アイテム
・ポーチ増強
・移動の最適化(馬、スタミナなど)
・地図開放&ファストトラベル
・便利な施設の開拓
・フィールドの開拓(新しい場所へいく)
思ったことは、
寄り道の内容には、様々な「変化」があることです。
1.今までなかった建築物・ルートによる、発見の"驚き(変化)"があり
2.寄り道で見つけた内容の"種類(変化)"があり、
3.進めた内容に応じて、場所や環境の"影響(変化)"が生じる上に、
4.扱った手段・アクションにも"成長(変化)"がある。
寄り道が、ただ準備や好みで選ぶのが楽しいかと言われると、それだけではなく、
寄り道の内容・体験を楽しむ上で、前と異なる変化を求め、変化に対応し続けること。
それをプレイヤーは寄り道として、繰り返しに飽きなく楽しんでいると思います。
この辺りは、パニグレのバトルで例える方が分かりやすいと思います。
1.新敵が登場した場合に警戒して
2.敵の種類・数に応じて
3.地形やギミック、敵の配置位置によって
4.新しいキャラが増えたりアクションが増える・もしくはプレイヤー自身が反省してスキルアップすることで
倒し方は変わります。
「挑戦する度に、倒し方を適切に変えるのが楽しい!」のと同じように、
オープンワールドの寄り道にも、同様なことがいえると思います。
まとめ:寄り道を楽しむには、今までにない"変化"が求められる。
5.納得がある変化は、世界観に紐づく
寄り道の楽しさには、"変化"が要ると考えましたが、
極端に違うものだと、"違和感"が生じます。
例えば、ファンタジーな世界なのに、急に「コンビニのアルバイトをしてくれ」みたいな内容だったら、
ありえない内容なので、『なんでそれを進めなければいけないんだ…』という違和感があり、楽しめないはずです。
もし、武器施設が発達したファンタジーな世界なら、「とある武器屋の店主が腰を悪くした。代わりに経営してくれないか」と言われ、武器屋の経営の体験(素材を集める→鉄を叩く…)ができたら、
確かにその世界ならではのイベントであり、楽しいものになると思います。
またその世界観で最終的に目指すこと(例えば「最強の武器を作る」とか)も推測しやすく、不思議とその理想へと目指したくなります。
"世界観"は、現実で生きているプレイヤーに、そのゲームが現実と比べてどんな違いがあるのかを暗に伝える"ルールブック"です。
世界観に合った遊び、またはその世界観だからこそ生じる遊びを楽しむことで、その世界観の没入でき、変化に納得して楽しむことが出来ます。
例えば、現実とまったく同じ世界観のゲーム性が出た場合、あまり面白くないと思います。
理由は、現実との変化も弱い上に、実際に体験した方が楽しいからです。
※ただ、「現実だけどヤクザ体験」とか、「現実だけど高層ビルで綱渡り」とか、「現実だけど、プロに近い技術体験でスポーツを楽しめる」とか。そういった現実だけど"非現実的"なことは別です。
6.オープンワールド=世界観の表現
オープンワールドを採用したゲームは、
そのフィールドをみたら、象徴的に配置されている物体を見たら、
どういうゲーム・世界観なのか、想像できるようになっています。

鳴潮の世界観は、どうだったか。
筆者は、まだ表現しきれていないように感じています。
ファンタジーな世界…とは思うのですが、
より具体的にどんなファンタジーな世界なのか、表現しきれていない。
また、世界観ならではの"変化"が設けられているかというと、まだ検討段階だったように思います。

違和感の例でいうと、謎解きギミックは「なぜ解くと良いのか(どういう原理で、どんなメリットが生じるか)」が不透明で、世界観に合っていなかった気がします。
7.鳴潮の世界観設定とは
("オープンワールドが合っていない"という思える要因。本件が大きな理由だと思います)
筆者がストーリー等を見て知った、世界観の内容は下記です。
・"鳴調子"というパニシングに似た物質で、ファントム(化物)が活発化し始めている
・過去に"ファントムの大群"が生じて、人類はその戦争に勝利した(その時に、特殊で大型な音骸を使用した?)
・毎日、仲間の戦死が絶えない
・一応、街以外にも拠点がある
・追放者という、社会から追放された存在がいる
・フィールドに不思議と近代兵器が廃棄されている(過去の方が文明が発達していた?)
・鳴調子に適用する者を、共鳴者と呼ぶ(プレイヤーキャラたちのこと)
・共鳴者といえでも、鳴調子の許容量を超えると、危篤状態になる
※ちなみに秧秧は、最初ボスの"無冠者"の攻撃で死にかけたっぽい
・無冠者のような、巨大なファントム系が何体かいる
・キャラは、ボスから手に入る素材で、上限突破を上げている
・"音骸"は、おそらく魂を奪い、主人公たちが操っている?
筆者が上記の内容で思ったことは、
鳴潮の世界は、ヤバそうな世界だと思うんです。
でも、オープンワールドとしてみると…ヤバそうに感じないんです。
パニグレのストーリーのように、リアルタイムでヤバくなっていく様子がないんです。
この世界観では、何のためにメインの遊び"バトル"するのか…それはファントムを排除するためではありますが、
そのバトルのために、どういった準備していくのか。
世界観の関わりに薄そうな謎解きギミックだったり、
攻略を進めても、特にフィールド・環境には影響がなく、
キャラは成長するのですが、特にオープンワールド用のアクション追加・強化はなく、エスカレーションがないため、
鳴潮がオープンワールドを活かしきれていないと感じる最大の要因は、
世界観に合ったオープンワールドを、まだ表現しきれていないから(世界観が定まっていないから)…だと思います。
8.改良案について
ここからは、筆者が思った改良案です。
まず、
世界をヤバそうに見せるために(もう今にも街まで危険が迫っていると分かるように)…
■侵蝕度システム
・各エリアごとに侵蝕度(100~0%)がある。
・ザコ敵の集団を倒す。侵蝕度を軽減させる"ギミック装置"を起動させると、侵蝕度が下がっていく。
※謎解きギミックがこのシステムに大きく関わるようにすれば、バトルが有利になるため、動機付けになると思う。
・侵蝕度が高いと、そのエリアでは下記のデメリットが生じる。
案1.そのエリア内でのマイナス効果が生じる
(パニグレのバベルの塔のギミックのような、落雷が落ちる、ダメージエリアがある、敵がスーパーアーマーになる…等)。
侵蝕度が低いほど、マイナス効果は無くなっていく。
案2.そのエリアのボスやイベントエリアの難易度が上がる。
案3.スタミナ減少量が多くなる or 落下傘使用時の落下速度が速くなる。(侵蝕度が高い時は登れない地形ばかりになるが、侵蝕度が低いと登れる地形が増えて、よりオープンワールドとして攻略する意味が生まれる)。
案4.音骸の入手確率が下がる。
案5.ファストトラベルが利用できない(侵蝕度を下げないと利用できない)
そのため、拠点近くから攻略していく流れになる。=奥地へ行くほど困難な場所となり、少しずつ解放していくことで、世界を良くしている感覚になる。
・侵蝕度が0%にできた時、やりこみ要素として、逆に侵蝕度120%の世界に挑むことが出来る。この時、強敵だが様々なメリットが生じる。
・・・もしくは。
侵蝕度が0%になると、空に海面が出来上がり、フィールドの岩が持ち上がる。その岩を辿ると、"海面上の異世界(高難易度)"を探索できる…とか。

オープンワールドで、侵蝕度システムを採用した、異世界になるゲームはあったか。
これがありました。「デスストランディング」


これ、本当にヤバいです。世界の崩壊を感じさせます。赤ちゃんの泣き声がさらにアカン。
フィールドの探索時間が長くなるように…
■塔(ファストトラベル)の数は、減らす
現状は、一番近い塔にファストトラベルで飛び、すぐに必要な素材を集め終える状態になっており、
塔が多すぎることで、便利なのですが…オープンワールドとしての探索が乏しくなり、寄り道の意味が弱いと思いました
(疑似的に最短な道を歩む状態になっている。もしかしたら探索後はオープンワールドの楽しさでなく、効率的に集められる楽しさを優先している可能性もあるかもですが…)。
街や拠点、ボス・イベントエリアの近くだけにして良いと思いました。
もしくは、ファストトラベル禁止のクエストモードがあると楽しいのかも。街からスタートして、対象となる敵を倒すとか。HP回復するアイテムもあるので、あまりファストトラベルに頼らずに戦うモードがあっても良い、と思いました。

次はTwitterで取り上げられていたアイデアです。素敵案。
■音骸のサポート効果
もし、音骸がポケモンのように、プレイヤーキャラをサポートするような相棒的ポジションなら、
音骸は、本ゲームならではの特徴となるシステムなので、音骸によってフィールド用アクションが設けられたら良さそうに思いました。
※バイクを扱うボス・音骸がいるのですが、筆者もバイクは乗ってみたい…
でももう少し、プレイヤーキャラと共に音骸が居るような…
マスコットとは言わないけど、プレイヤーキャラが使役している協力キャラというイメージがあると良さそうと思いました。
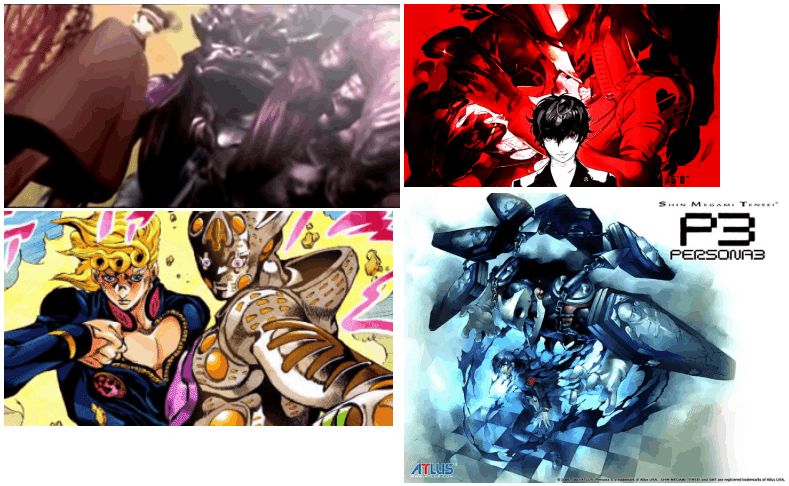
その表現が難しい場合は、
音骸は、プレイヤーキャラに力を与える存在でもあるとして、
そこまで特徴的なアクションは出来ないけど、
音骸を育てることで、プレイヤーキャラの移動速度・ジャンプ力・スタミナ力・鉤縄の距離アップなどに少し上がるとか、
音骸でしか解けない結界が解けるようになるとか。
■ギミックの改良化
いま、少しスムーズにクリアできない状態なので、
分かりやすく、アクション次第で素早く終えられるように改良する必要があると思いました。
マップアイコンとSEを頼りに箱アイテム探し
→これが一番楽しいギミックでした。このままで良いと思います。
3つの鍵アイテムを見つけて障害物解放
→もう少し、配置してある方向が示唆されていると、迷わず時間かからずに攻略できそうです。
障害物を壁にぶつけてルート開拓
→このままで良いと思いますが、音骸を利用した開拓の方が面白いかも…
素早く移動する小動物を攻撃 / 射的
→たまに空中へ飛び出てしまうのが気になりました(銃キャラでないと攻略が難しいものになっている)
複数のサンドバックを時間内に攻撃し終える
→これが惜しい。サンドバックの位置が分かりづらいのが問題なので、光の柱などで全サンドバックの位置が分かるようにすれば楽しそう。
音骸に変身して輪っかくぐり / 時間内にすべての輪っか゚くぐり / 光る蝶をおいかける
→あって良い遊びなのですが、ちょっと時間がかかるのが気になりました(時間かかるならバトルがしたい)。もう少し希少ギミックな扱いで、報酬を少し多くした方が良さそうに思いました。
■オープンワールドで見つかる「呪い(ミッション)」
これは、もう寝て起きて「?!」と思いついた案ですが、
もう思い切って、フィールドはバトルが大半にしてしまって、
フィールドで「呪い(ミッション)」が見つかるようにし、
バトルの中で達成しなければならないアクション回数・何戦かバトル中でデメリットとして働く呪い効果を持って、バトルに勝つ…とかでも、
バトル自体に変化が起きて、楽しいと思うんです。
かつ、「呪い(ミッション)」は重複するようにして、フィールドで探索しつつ、自分の実力に合わせて難しくしながら遊ぶことが出来れば、面白いと思いました、が…うーん。

カオスという、デメリットをしばらく抱えて戦った後、パワーアップ効果が得られるシステム。
9.おわりに
ここまでまとめて、暴露してしまうのですが、
筆者は、オープンワールドが苦手なタイプです。
いえ、楽しくは感じるのですが、
いかんせん、時間かかるものが苦手で…
でも、やるなら全部探索しまくりたいという…
そのため、当初は鳴潮を楽しめるか、不安でした。
実際に序盤は「ぁ、これけっこう色んな場所いけそうだな…(やばいな…大丈夫かな…)」と感じてました。
そんな筆者でも、鳴潮は楽しく遊べました。
理由は、やはり道中にストレスがなく、むしろアクション性を感じて楽しめたのと、
目的地が常に表示されていて、シンプルに迷わず向かえたこと。
寄り道は、あまり気にしなくて済んだので、
(寄り道が重要要素ではあるのですが、他ゲームと比べるとバトルはプレイスキルでなんとか出来ちゃうのが良かったです。また、中盤までどの素材どの成長に繋がるかが分からなかったのが、逆に重要でないように感じて良かった…かもしれない)
軽いオープンワールドという感じが、ちょうど良かったんです。
でも、オープンワールドを扱っている限り、鳴潮らしさのある遊びを構成してもらえれば、もっと楽しめそうだと思います。
皆さんにも、鳴潮のオープンワールドがどうあったら良さそうか、考えるきっかけになれば…と思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
