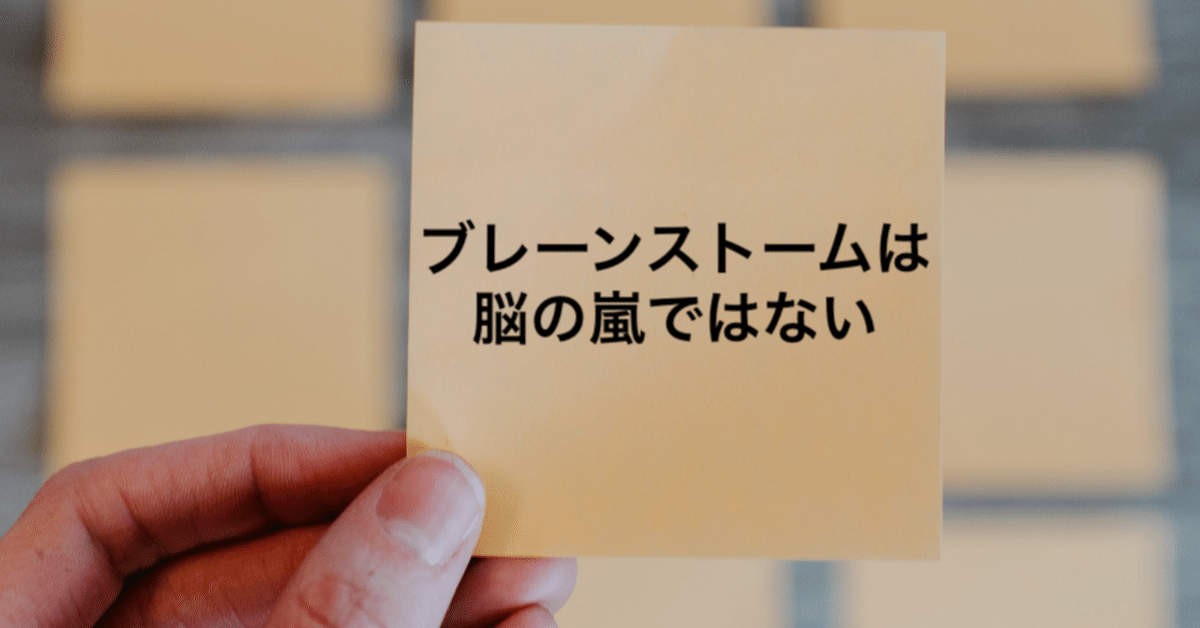
ブレーンストームは「脳の嵐」ではない
今では、ブレーンストーミングといえば、日本では「ブレスト」と4文字に略されるまでに一般的になってきており、先週もNHKで「やわらかアタマが世界を救う」という小峠(ことうげ)がMCを務めるバラエティクイズで、なんと参加者全員がホワイトボードと付箋を使って、ブレストで正解を見つけ出すという番組をやっているのを見て驚いた。
実はこのブレーンストーム、考案されたのは1939年のアメリカ、しかもニューヨークに本社を置く世界的な広告代理店ネットワークであるBBDOの幹部だったアレックス・フェイクニー・オズボーン(1888年生まれ)によってだったのだ。
1929年10月24日の株式市場の暴落(通称ブラックチューズデー)で始まった世界大恐慌を乗り越えたBBDOは、1938年に経営危機に見舞われたときに、オズボーンはニューヨーク支店に勤務しており、その際にグッドリッチ・タイヤを顧客として獲得することで会社を救い、1939年に彼はBBDOの執行副社長になった。
業績は好転したが、顧客への提案は、一部のクリエイティブに依存するばかりで、圧倒的に人手が足りなかったために、「どうすれば、アイデアを量産できるだろうか」という課題を抱えていた。
そこで1939年にオズボーンは、一人の天才的なクリエイティブだけに依存せずに、複数人で構成されるグループで思考する方法を採用し始めたのだ。
そして参加者達がこの方法をブレーンストーム会議と勝手に名付けたのだ。
これをオズボーンが1942年の著書「How To Think Up(絶版で入手不可)」で紹介したところ、あっという間にアメリカで広く知れ渡るようになり、独創的努力をするという意味の動詞ブレーンストーム(brainstorm)がウェプスター辞典に収録され、つぎのように定義されている。
Definition of brainstorm
(MERRIAM-WEBSTER DICTIONARIES)
to try to solve a problem or come up with new ideas by having a discussion that includes all members of a group : to discuss a problem or issue and suggest solutions and ideas
「グループのメンバー全員を含めた議論をして、問題を解決したり、新しいアイデアを出したりすること
問題や課題を議論し、解決策やアイデアを提案すること
しかし、この種の会議がまったく新しい方法だったわけではない、とオズボーンは1953年の著書「Applied Imagination」で回想している(この本は、後に日本語にも訳されて「独創力を伸ばせ!(絶版)」というタイトルで1957年にダイヤモンド社から出版されている)
もう400年以上も前からインドのヒンズー教の指導者たちが使っていたテクニックとして知られているそうで、このやり方をインド語でプレイ・バーシャナ(prai Barshana) と呼ぶらしい。
プレイは「outside yourself あなた以外の」という意味で、
バーシャナは「question 問題・疑問」の意味である。
このプレイ・バーシャナ会議でもブレーンストーム同様に討論や批判は行なわれない。アイデアの評価も、同じグループで会議の後で行なわれる。
オズボーンが紹介して広まったブレーンストーム会議は、いわばアイデアのチェック・リストを作成することを唯一の目的とした独創的な会議形式だった。
「1950年代の初期にブレーンストーミングは急速に普及し、やたらに人気がでたので、まちがった使われ方をしていることが多い」とオズボーンは嘆いている。万能薬のように考えて飛びついたが、奇跡はついに起こらなかったといって離れていった人も多く、同じようにブレインストーミングをグループによる完全な問題解決過程と誤解した向きも多い。
そうなのだ、ブレーンストーミングは、あくまでアイデア発想の段階の―つにすぎず、それが適切に行なわれれば、普通の会議に比べて短時間で、多くの名案を生み出せるという点なのだ。
ブレーンストーミングは「アイデアを量産する」には極めて生産性の高い方法であるが、それだけでは収束が付かなくなる。
オリジナルのブレーンストーミングでは、書き上げたアイデアのすべてをチェックリストにして、それらを「良いアイデアかどうか」をしらみつぶしに試行錯誤していくだけなのだ。
そこに目をつけたのが、日本の地理学者で文化人類学者でもあった川喜多二郎だ。
彼は1967年に出版した「発想法―創造性開発のために(中公新書)」のなかで、複数人で問題を解決する手法の第一段階としてブレーンストーミングを「アイデアを吐き出すところまでは、オズボーン氏の方法は大変良いものを含んでいる。」と高く評価している。
しかしながら、続いて「ところがあとが感心しない。」とブレーンストーミングをアイデアを創り出すためだけに考えられたものであると一刀両断している。
そしてブレーンストーミングで列挙したアイデアを「なんらかの構造のあるものに組み立てなければならない」として、自身が考案したKJ法を問題解決の第2段階として紹介している。
ブレーンストーミングの名前の由来は?
ところで、このブレーンストーミングを、ブレイン(脳)ストーム(嵐)と言う単語を直訳して、昨日のNHKの番組でも、「脳の嵐、すなわち思考の嵐を起こすことでアイデアを出す手法です」と間違って紹介されていたが、オズボーンは、この名前の由来をそうは説明していない。
ウェブスター辞典に掲載されたように、brainstormは動詞なので、「嵐」ではなく、「〔敵陣地に対して〕襲撃する、猛攻撃する、急襲する」と言う意味で使われるようで、湾岸戦争の有名な作戦「OPERATION DESERT STORM」は、砂嵐のSandStormにひっかっけて、砂漠急襲作戦と言う意味で使われているようだ。(日本語で砂漠の嵐作戦と訳されており、軍事作戦でよく使われるSTORMの急襲する、と言う意味にはなっていない)
オズボーンも著書の中で
「brainstormとは脳を使って問題を急襲する と言う意味である」と解説している。
参考文献)Alex F. Osborn著 Applied Imagination, Amazon Kindle Books
そうそう、この投稿で何を言いたかったのか、というと、ブレーンストームと日本語でググると、ほとんどすべての大手コンサルもビジネススクールも、「脳の嵐の」と説明して、それが定説になってしまっているが、せめて考案者に敬意を評して、原典を読んで調べて確認するくらいのことをして欲しい、ということ。
この記事を読んで、支援したいなと思っていただいたみなさま、このブログは自分のヒラメキの備忘録みたいなものですから、金銭的な支援よりは、いいねやスキ♥️ボタンを押したり、SNSでシェアいただいたり、フォローしてもらえた方がはるかに嬉しいのです。 是非リアクションをお願いしますね♪
