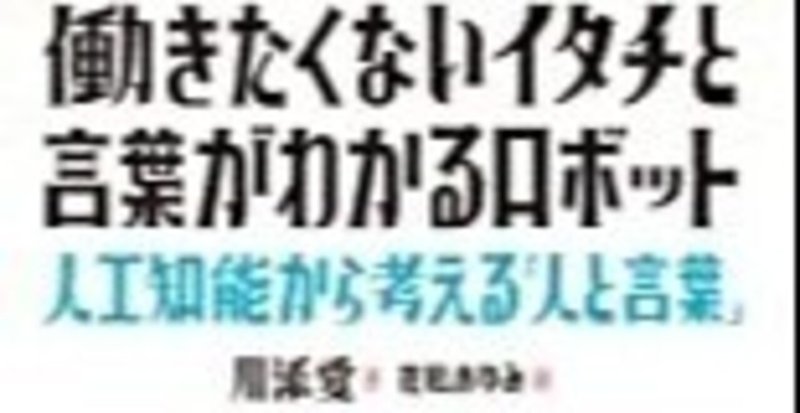
働きたくないイタチと言葉がわかるロボット
岡ノ谷一夫先生お勧めの本90冊の89番目に紹介されている著作、言語学者川添愛先生の「働きたくないイタチと言葉がわかるロボット」です。昨秋、我が家にアレクサが来て、家人とアレクサの頓珍漢なやり取りが日々繰り広げられているので、音声認識の仕組みについて興味があり、表紙のイラストも面白く思わず手に取りました。
この本で扱っている命題は、「言葉がわかる」とは何かということです。言葉がわかるといっても、いろいろな段階があり、その段階に沿って、イタチやフクロウ、カメレオンなどの動物が繰り広げる物語の部分と学術的な解説が並行して展開され、言語学やコンピューターに詳しくない人でも読み進めやすい構成になっています。
最近のスマートホンは、話した言葉を文字に変換する機能がありますが、それを使ってSNSのメッセージを作成できるぐらい実用性がります。これは、話された音を音素という単位で捉え、その音素の組み合わせを単語のデータを照合し、適切な単語を選ぶ作業をコンピューターがしているからできることだそうです。日本語、英語、中国語など各言語によって音素のくくり方が異なる(例えば、英語のLOCKとROCKをカタカナにするとどちらもロックになってしまうようなこと)もあり、これができるだけでもすごいことだと思います。
さらに、コンピューターの記憶力と検索力を生かせば、百科事典に載っているようなことを問うクイズでは、人間を超える能力を発揮します。しかし、リンゴという単語が特定できてリンゴは果物だと説明できたとしても、現実のリンゴを知らなけば、本当に言葉がわかったといえないという指摘がされています。私たちは、リンゴと聞いたら甘酸っぱい味を思い浮かべることができますが、コンピューターはリンゴを食べた体験がないので想像できないのです。
そのほかにも、文と文の論理的な関係を理解すること、話し手の意図を理解することが今のコンピューターにとっての大きな壁として解説されています。
この本を読んで、実際に私たちは人と会話するとき、相手の表情やしぐさ、目の前にあるもの、過去の記憶など、現実にやり取りしている言葉以外のいろいろな情報を参照しながら考え、言葉を選んで話していることに改めて気づかされました。
そんなことから、これからコンピューターの活用がどんどん広がる時代に、人間が人間らしく生きるためには、想像力が鍵になるのではないか。また、人間の成長には、体験(文学作品を通した体験も含む)が重要で、それが想像力の源ではないかと思ったところです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
