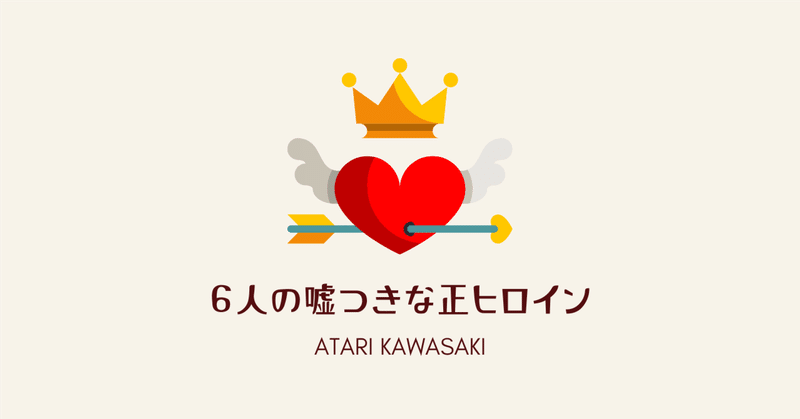
9 さよならのパーティ
御坊ちゃま。
御坊ちゃまはこの数日間お楽しみになられたでしょうか。そのお心の内をいまいま知ることは叶いませんが、しかしそのご決断によって目の当たりにするのでしょう。
さて、シャンデリアが吊るされた過剰なマンションの一室に着飾った子女が整列し、御坊ちゃまはどこか不安げに足元に視線を落としております。
部屋は植物の腐ったような甘い匂いで満たされています。
香りの正体は黄色が鮮やかなキンセンカ。花弁が多く細かい繊細なこの花の花言葉は『変わらぬ愛』。しかしそれは、別れを告げる相手に向ける言葉。別れの花で、五本用意されております。
それはそのまま、お別れをする子女の数でしょう。
緊張感が張り詰め、時はもう満ち満ちていました。
「それでは、フィアンセ候補の中から一人、さよならを告げていただきます。御坊ちゃま、準備はよろしいですか?」
御坊ちゃまは軽く片手をあげ、遮りました。
「ああ、それなんだけど、実は一つお願いがあるんだ」
「何でしょうか?」
「今回実は二人を落とそうと思っているんだけど、構わないかな?」
子女たちに一様の動揺が走ります。もしかしたら自分が落とされるかもしれないという動揺かもしれないし、あるいは御坊ちゃまの素早いご決断に歓喜しているのかもしれません。
「構いません。最終的には一人になるものですからね。それでは御坊ちゃま。早速お別れするお嬢様にキンセンカをお渡しください」
御坊ちゃまは花瓶から、一本のキンセンカを抜き取りました。
きっとそれぞれが十分な時間を過ごせておらず、たくさんの知らない部分を諦めながらご決断なさるのでしょう。
もっと過ごせば、自分のいいところが伝えられるのに。もっと過ごせば、たくさん分かり合えるのに。
でもそんな事情は、このゲームは考慮してくれません。
時間が来たらただ淡々と、御坊ちゃまは結論を下していくしかないのです。
「それでは、御坊ちゃまのフィアンセになり得ないと判断したお嬢様にキンセンカをお渡しください」
御坊ちゃまは手に取った一本のキンセンカを見つめ、ついでお顔をあげました。
子女を一人一人見つめて、それぞれと目が合いました。遊び感覚が抜けない子も、あるいは人生をかけた子もいることでしょう。
御坊ちゃまの決断は狂おしいほど気になります。本当は彼の一挙手一投足に心が破裂しそうになります。
しかし自分はどんなことがあろうとも、あくまで客観的に、その決断を尊重しようと思います。
それが、王沢の付き人なのです。
ふっと、御坊ちゃまの目が鋭くなりました。
ああ、迷いがないんだとわかりました。知っていますよ、御坊ちゃま。古い付き合いなのですから。その御坊ちゃまの目は、きっと絶対の確信があるのでしょう。
御坊ちゃまは、一人の少女の前に立ちました。その少女は、悲しそうに言いました。
「……苺はよっぽど怜君の好みじゃなかったというわけでありますね」
なぜか背筋に悪寒が走りました。
子女たちの間にも動揺が走ります。少なくとも彼女は、客観的には御坊ちゃまと仲良くしていたように見えました。幸運にも御坊ちゃまの隣の席で、一貫して親切に接していて、側から見ていて彼女に失点は見えません。
それでも、さよならをする。それこそが、恋愛というものなのでしょうか。
御坊ちゃまは独田苺様に、さよならには鮮やかすぎるキンセンカを差し出しました。
「受け取って」
「ええ」
意外なほどあっさりと、苺様はそれを受け取りました。
「やっぱり意外じゃなかった?」
「苺はこの間、怜君の心を掴めたとは思っていないのです。苺なんてぜんぜん可愛くないし、それは仕方のないことでありますです」
「一応言うけど、僕は苺は本当に可愛いと思っているよ。僕には勿体無いくらいに」
「ええ、何それサイテー」「未練たらたらじゃん」「これあとからワンチャン狙ってんのんちゃう?」
子女たちがヒソヒソ話を始めます。
御坊ちゃまは、あれ? そんなにおかしなこと言った? という表情を浮かべておりますが、客観的に言ってさよならを告げる相手に気を持たせるセリフを言うのは最低だと思います!
苺様は続けます。
「そもそもですけど、苺が怜君のフィアンセのリストに載るって言うのが場違いだったのであります。他のみんなはこんなに素敵なのに……」
「いや、何度も言うけど、苺が他の子に比べて見劣りするだなんてこれっぽっちも思ってないよ。苺とさよならする理由は明確だ。それは可愛さとか、魅力とか、そういった曖昧な要素とはまったく別次元のことだから」
「もういいのです、そういうの」
苺様は会話をはやくも終わらせようとしておりました。
しかし、御坊ちゃまはそんな彼女を逃しませんでした。よほどまだチャンスを残して、念のため彼女を今後の保険にしておきたい気持ちが強いのでしょうか……。
御坊ちゃま、ひどい男です!
「苺はもう行きますね」
しかし、御坊ちゃまの次のお言葉は、まるで空から降ってきたかのような予想外のものでした。
「独田苺。君は、暗殺者だ」
……――暗殺者?
自分は耳を疑いました。
いったい御坊ちゃまは何を言っているのでしょう。部屋が沈黙で支配されました。
そして、それは並ぶ子女たちも同意見だったご様子。
「ちょっと怜君って頭おかしいの?」「漫画の読みすぎじゃん」「いや、これボケちゃう? ええと……なんでやねん!」
思ったより皆様、御坊ちゃまへのあたりが強いですね。
ひょっとしてあまり人気がないのかな?
御坊ちゃまは子女みんなに語りかけるようにいいました。
「いや、これはおかしな話じゃないんだよ。僕は王沢の息子だから、狙われることがままあるんだ」
御坊ちゃまがそう言うと、一歩前に出たのは一華様です。
「待って! 苺が暗殺者? そんな荒唐無稽なこと、信じろったって無理だよ。そんな冗談、怜だって言って許されることじゃない」
「ふ、ふふふ」
「……何笑ってるの? 怜」
「いや、相変わらず一華は頭が高いなぁと思ってさ」
「はぁ?」
一華様の表情に怒気がこもりました。彼女からすれば、大切な友達を侮辱されたというのもあったかもしれません。自分自身を貶されたというのもあったかもしれません。
怒りは当然です。
しかし、王沢。
御坊ちゃまは、常人とは感覚を逸にしているのです。
「僕は王沢だよ? 何を言ったって最終的に許されるんだ。それから僕は冗談なんて言っていない。僕は実際殺されそうになっている。その話をこれからするんだ。覚悟はできてる? 苺」
帰ろうとしていた苺様は足を止めました。
そしてくるりとおぼっちゃまに向き直り、とても素敵な笑顔で言ってのけたのです。
「ええ、ぜひ聞かせて欲しいと思うのであります」
さぁ、戦いましょう。その言葉は、自分にはそんなふうにさえ聞こえました。
御坊ちゃまは一度咳払いして、続けました。
「じゃあ、僕に何が起こったかの顛末を話させてもらおう。早速なんだけど、苺。とうぜん栞が飼っているラットを知っているよね」
苺様は一瞬ぽかんとした顔をしましたが、少し間を置いて続けました。
「ええ、当然知っているのであります。栞は大学の研究で使うラットを飼育するアルバイトをしているのは公然の事実でありますので」
「話が早くて助かるな。それじゃさ、僕はこの前、栞に『僕に似たラットがいる』って紹介されたんだ。そのラットの名前は何かわかるかな?」
苺様は御坊ちゃまをキッと見つめました。
「それって答える必要あるのでありますか?」
可愛らしいお姿からは想像できない挑発的な態度です。顎をあげて見下すような言い方。彼女は完全に開き直っておりました。
一方、二人以外は自分を含めずっとぽかんとしている状況でありました。
なぜ御坊ちゃまがこんな話をしているのか。皆、いえ、少なくとも自分は、王沢のお心。御坊ちゃまのお心。それを、心の底から知りたかったのです。
「ああ、あるとも。君がこの質問に答えられたら、僕のアイディアは間違っていたかも知れないと思い直すよ。それくらいこれは重要な質問なんだ。どうか教えて欲しいな、苺。栞の飼っているラットのうち、僕に似たラットの名前を教えてよ」
渋々と言った体で、苺はそれに答えた。
「覚えておりますよ。確か『ガリガリさん』だったと思うのであります」
「ダウト!」
御坊ちゃまは指を鳴らして栞様に尋ねました。
「本当の名前は何かな?」
「……『チューペット』です」
「そう。栞が僕に似ているといったラットは『チューペット』だ。そして、栞に『チューペット』が僕に似ていると吹聴したのは君だよね? 苺」
「そうだったでしょうか?」
「ちなみに『ガリガリさん』は僕がその場で適当につけた嘘の名前だよ」
「……それがなんだと言うのでしょう!? 結局怜くんが証明したことは、苺がラットの名前を間違えたと言うことだけですよね? 何が言いたいのかまったく理解できませんが」
「つまり苺は、本当はラットに何も興味がなかったんだ。僕は苺に、そのラットのどこが僕に似ているのかも尋ねたけど、その理由も曖昧なものだった。苺は興味もないし、見分けもつかないようなラットだ。それにも関わらず、苺は栞に『このラットは怜くんに似ている』なんて話をふっかけた。栞。今までの学園生活で、苺がその件以外でラットに興味を持ったことは?」
「……ありません」
御坊ちゃまは、悪魔のように笑い手を広げました。
「不自然なんだ! 今までまったくラットに興味がなかったにも関わらず、僕が転入してきて突然栞にこのラットが僕に似ているだなんて話してみるだなんて!」
捲し立てる御坊ちゃまを、苺様は睨みつけ続けます。
それでも御坊ちゃまの話はとまりません。
「不自然なことには理由がある。なぜそんな不自然なことが起こったのか。僕はこう考えた。苺は僕とあのラットを接触させたかったんだ。それこそが僕を暗殺する肝でもある」
一同が注目する中、御坊ちゃまは言いました。
「あのラットは狂牛病にかかっていたんだからね」
「……狂牛病?」
一華様が首を傾げ尋ねました。
「狂犬病って、犬とかがかかるやつでしょ。ラットだよ?」
「あれは哺乳類に感染する病気なんだ。人間も、ラットもかかる」
それは確かにその通り。
職業柄、毒物や病原菌の勉強もさせていただきましたが、狂牛病は哺乳類全般を死に至らしめる恐ろしい病気です。ライサウイルス科に属するウイルスによって引き起こされる感染症で、この病は犬や猫、そして人間にも感染することは比較的知られていますが、ネズミやリスなどの小動物にも多分に漏れません。病の伝播は、感染した動物の唾液を介して噛みつきによって行われます。一度症状が現れたら、それはほぼ必ず絶命します。
ただ、ラットなどの小動物は通常噛まれた段階で死んでしまうため、その後他の動物に感染させることは稀で騒ぎになることはありません。
「君のお父さんは大学病院の教授なんだろ? ひょっとして大学に病原菌の検体があったとしてもおかしくはない。あるいは、狂犬病は日本では撲滅されているけど、発展途上国では珍しくない病気だ。唾液を介して感染するから、海外に行って狂犬病の犬を見つけて唾液を採取すればいい。あとはそれを日本に持ち帰って、注射器かなんかでラットに感染させれば、狂犬病のラットの完成だ」
それが事実であれば、どれほど恐ろしいのでしょう。
しかし、苺様の余裕は消えませんでした。
「言いたいことはそれだけでありますか。ラットが狂牛病? いくらなんでも話が飛躍しすぎでは? 証拠もないのにそんなこと、苺は困ってしまうのであります」
「後で調べればそれはそれでわかることかもしれないけど、ここで否定するのまぁ、わかるよ。でももし僕の思い込みっていうのであれば、そのラットがここにいてもまったく怖くないよねぇ?
「月夜、そこのカバンにケージが入っている。こっちへ持ってきて」
御坊ちゃまはそれを受け取ると、蓋を開けました。
「さて、苺。これが例のチューペットだけど、どうだい? 僕に似ているかな? もしこの推理が僕の妄想だとするのであれば、ここに手を入れられるはずだ」
御坊ちゃまは苺様にケージを差し出しました。
自分はそれを見守ることしかできません。そして、驚くべきことに苺は手を入れたのです。
「……馬鹿にしないでいただけないでありますか? このラットが狂牛病なわけ、ないであります」
苺様が言い切ります。
まさか、御坊ちゃまの言葉が間違っていた? そんな空気が場を支配しました。
「……はっはっは! まさか手を入れるとはねぇ!」
「な、なんなのです、突然笑い出して」
「だってもし苺がこの件に関わっていないのであれば、怖くて手を入れられないはずさ。1%でも本当かもしれないと頭に過れば、ここに手を入れられないよ! 怖いからね。もっと言えば、馬鹿にして部屋から出ていってもよかった。
「それなのに、君は手を入れたんだ。狂牛病になって死ぬリスクを取って!
「なんでか教えてあげようか?
「弁解するチャンスがきたと思ったからだよ!
「このラットが狂牛病だったとしても、噛まれないことを君は知っていたからさ!」
そのときに初めて、苺様の表情が歪んだのです。
「狂牛病にかかった動物は、恐れが強くなるんだ。だから、自分より大きな生き物の手が入ってきたら逃げるに決まってる! それを知っていたから、君はいま手をいれることができたんだ」
蛇がカエルを追い詰めるように、御坊ちゃまは理路整然と苺様を追い詰めました。
そしてついに、苺様から表情が抜け落ちたのです。
「どうして気がついたのであります?」
「チューペットの様子は明らかにおかしかった。妙に落ち着きがなかったし、よだれもすごい。見た瞬間ピンときたよ。僕は王沢だから、昔から危険な目にあうこともあった。警戒しているんだ。いつも」
「なるほど驚きでありますです」
苺様はぱっと手を合わせて殊勝に感心してみせました。
「すっかり見抜かれてしまったようですね。苺が怜くんを殺そうとした暗殺者だってことに」
あまりにもあっさりと、彼女は認めてしまいました。
その笑顔は無邪気そのもの。
それでも彼女は、自分は暗殺者だと告白したのです。
「そんな」「苺がまさか」「うせやん? ウチは信じられんわ!」
今まで仲良くしていた友達であったとしても、一枚皮をはいだ内側では何を考えているかなど知る由もないのかもしれません。
あくまでも落ち着いた様子で、苺様は悪魔の言葉を続けました。
「もうここまできたら仕方ありません。色々言い訳することもできるかも知れませんが、しかし怜君には通じそうもないであります。
「あーあ、残念でしたねぇ……栞ちゃん」
栞ちゃん。
それは当然、香澄栞様のことでしょう。ラットを飼っていた張本人は、かのお嬢様なのですから。
彼女の方を見ると、栞様はギョッと目を見開いておりました。
その表情は、何を言っているの? と訴えかけるようでした。
「わ、わたくしが……なんでしょう」
そんな栞様に、苺様はため息をついて続けました。
「いやいやいや、もうバレているのですからそんな演技は意味ないでありますよ。もう大人しくお縄につくしかないであります。最初に怜君は言っていたじゃないですか。今回は二人落とそうと思っているって。それって、どう考えても苺と栞ちゃんじゃないですか」
「わ、わたくしですか」
「そりゃそうであります。だって私がきっかけを作って、栞がマウスを使って怜君を病気にする。そういう約束だったのでありますよ。今更なにをしらばってくれているのであります?」
苺様が白状した今、栞様がそうやって逃れる意味はありません。
その悪あがきは、本当に意味のないことのように見えました。
御坊ちゃまは言いました。
「苺は本当に頭が回るな。 そもそも頭が回るからこそ、僕が適当につけたガリガリさんという名前に乗っかったんだ」
「さよならを告げる相手にそんな褒め言葉は酷であります」
まるで長年のライバルのように二人は言葉を交わします。
二人のやりとりに、周りは誰一人ついていけていないご様子でした。そもそもこんな恐ろしいことが計画されただなんて、自分たちは本当の意味で信じることができていなかったのかもしれません。もちろん、栞様も。きっと彼女は、まだ自分が告発されたことをちゃんと理解できていないのです。
だからこそ、御坊ちゃまの次の言葉は苺様以外に通じなかったのです。
「ただ、その誘導には乗れないな」
「……誘導、でありますか」
そして御坊ちゃまの矛先は、別の子女に向いたのです。
「栞はまだリストから外さない。今回さよならをするのは珊瑚だからね」
「……ええ、ウチなん!? 急に!?」
理解すると同時に珊瑚様は驚きの声をあげました。それはそうでしょう。ここまで彼女の名前はまったくと言っていいほどでてきていなかったのです。
もちろん自分も、これがどういう展開かまったく見えません。
「ちょっと待ってください怜くん。苺の共犯者は栞なのでありますが」
「そうなの? 栞」
栞様はブンブン顔を横に振っておられました。
「咄嗟に矛先を栞に向けたのはさすがだけど、それは悪手だよ。もし栞が犯人であれば、僕に似ているラットがいるっていう話を苺が栞に提案する必要がない。わざわざ苺が栞にそんな話をしたこと自体が、彼女がなんの関係もない証拠さ」
苺様の表情に緊張が走りました。ギリ、という音は強く奥歯を噛み締めたそれでしょう。
……なるほど、確かに御坊ちゃまのいう通り。もし栞様と苺様が共犯ならば、事前に二人の繋がりを消しておくのが得策に決まっております。
御坊ちゃまは続けます。
「だから栞は関係ない」
「だからって、なんでウチなん? おかしいやろ!」
「ところで珊瑚。君は、貧乏なの? お金持ちなの? どっちなの?」
「はぁ、貧乏に決まってるやん。それがなんやねん」
「いやー、甘いよ。設定が甘すぎる」
御坊ちゃまは時折、悪魔のような表情を浮かべます。それは王沢が故か、彼自身の特性か自分には判別はつきませんが、それを見ると恐ろしい気持ちになるのでした。
「設定……? なんやねん」
「君は成績が悪いんだろう?」
「はぁ? 喧嘩売っとんの?」
「これは君のくれたイラストだよ」御坊ちゃまは一枚の色紙を取り出しました。それは出会いのときに珊瑚様が渡した、御坊ちゃまと珊瑚様が描かれたイラストです。
「ウチの描いた絵がそんなに気に入らなかったん?」
「……問題は絵じゃない。ここに入ってる文字さ。ア、パーフェクト、マッチ。書かれているスペルは、『A・P・A・R・F・E・C・T・M・U・T・C・H』」
「え、めっちゃバカじゃん。パーフェクトとかマッチとか間違えるって、ある?」
思わず声をあげたのは一華様でした。そして自分も同意見です。大都学園で、小学生レベルの英語ができないだなんて!
珊瑚様は顔を真っ赤にして怒りました!
「スペルミスがなんやいうねんムカつくわ!」
いつも穏やかな珊瑚様とは思えません。彼女の隠れた一面が、いま暴かれたのでした。
「簡単な話さ。こんな英語レベルでは、到底特待生にはなれない。貧乏な君は特に、大都学園の生徒ではありえないんだよ」
珊瑚様は御坊ちゃまを睨んでいます。
しかし、言葉が出てくることはありません。御坊ちゃまが続けます。
「他にも設定ミスはある。調理実習のあと、僕の手に塗ってくれたハンドクリームだよ。あれは高級品だって月夜が教えてくれた。君は貧乏設定なのに、成績が悪くブランド物のハンドクリームを使っている。ああ、あまりにも設定がガタガタだ!」
「待ってよ怜。珊瑚が馬鹿なのはわかったけど、それがなんなのかあたし全然わかんない」
不安そうに一華様が言いました。
そんな彼女に、御坊ちゃまは答えます。
「要するに、設定がおかしいところにはおかしいなりの理由があるはずなんだ。
「例えば珊瑚が貧乏なのに馬鹿だっていうのは、本来彼女がこの学園の生徒じゃないことを意味している。
「貧乏設定なのに彼女は僕の手に高級ハンドクリームを塗ってくれた。それは、そうしなければならなかったからさ!
「月夜、今はめている手袋を借りても?」
「ええ、どうぞ」
御坊ちゃまは手袋を受け取ります。そして、懐から何やらチューブを取り出しました。
「これはおそらく珊瑚が塗ってくれたものと同じ高級ハンドクリームだ。事前に買っておいたんだよ。これをこの手袋に塗り込む。さて、じゃあこの手袋を先ほどのラットのケージに入れてみよう」
御坊ちゃまがつまむように下ろした手袋。中には何かに怯えている病気のラット。
しかし手袋が近づいたそのとき、驚くほどの勢いでラットが齧りついたのでした。
「狂犬病の動物は怯えるようになる。当然手を近づければ逃げていく。だから、例え狂犬病のラットを用意して、それに触れさせようとしても不完全な工作なのさ。
「だからこそ苺は手を入れられた!
「一方でこのハンドクリームの匂いは随分ラットを魅了するみたいだね。そんな都合のいいハンドクリームがたまたま高級品で、それでこの計画に利用せざるをえなかった。
「確かに、ラットを管理していたのは栞だ。しかし、彼女の管理していたラットを狂犬病に感染させ、その上で僕がそこに至る導線を引き、間違いなく噛み付くよう小細工をしたのは苺と珊瑚だろ?」
御坊ちゃまが言い切りました。しかし、珊瑚様は折れませんでした。
「待ってよ。ウチがクリームを塗ったんはちょっと怜ちゃんのおてて触りたかっただけやんけ。高級クリームだっていうのんも貰いもんや」
「誰に貰ったの?」
「覚えとらん!」
「怜くんのために言いますけど、苺が手を組んでたのは栞ちゃんです! 珊瑚は関係ありませんよ?」
「そんな!」
御坊ちゃまの説明を聞けば、確かに苺様と珊瑚様が手を組んで御坊ちゃまを病気に追いやろうとしたように見えます。
しかしそれは、見えるだけの話。
御坊ちゃまは決定的な物証を出せていないことは否定できません。
ただこれは、幸運なことに犯人当てゲームではないのです。たかだか『王沢の伴侶選び』。
御坊ちゃまの印象こそがすべてなのです。
それでも。
御坊ちゃまはそれでよしとしませんでした。
「引かないなら、壊そうか。なぁ苺」
「……え?」
「はっきり聞くよ。君の共犯者は珊瑚だろ?」
「……違いますよ? 怜君は勘違いしているのです。共犯者は――」
「悪いんだけどさ。もう苺のことは理解してるんだ。君は暗殺者だと確信があった。だから、教室での別れのとき、準備しておいたんだ」
自分には分かります。
放課後になった直後、御坊ちゃまは苺様を抱き返しました。その時に、使ったのです。
彼女を理解したのです。
「なぁ苺、頭が高いんだよ」
それ以外は、何も分かりません。それが感じられないことが残念でなりません。
御坊ちゃまに発動せし、王族の特権(インペラトル・ライト)。王沢に授けられしそれが、今まさに苺様を絡めとったのが、その反応から分かります。苺様の表情に急激に怯えが混じりました。
「立場をわきまえよ。平民が。おまえの立場は、どこだっけ?」
「……は、はい。地の底であります」
苺様が何かに怯えるように、キンセンカを強く握りしめました。
「で、共犯者は、誰?」
「珊瑚であります。すべて……王沢様のおっしゃる通りなのです」
子女たちは言葉を発することもできません。
スポットライトが当たったように、御坊ちゃまと苺様、ふたりの世界。
例えば、御坊ちゃまの殺害を依頼されたとして。
ベストは犯行がバレずに御坊ちゃまを殺害すること。
ワーストは犯行がバレた上で御坊ちゃまが生きていること。
そこ間には、たくさんのグラデーションが存在します。しかしその程度の余白は、王沢の付き人であれば簡単に埋められるのです。
からんからんと、地面に落ちたナイフ。
「御坊ちゃま、取り押さえておきました。お嬢様方の正体を暴かれたこと、お見事です」
組み伏せられたのは珊瑚様で、最後の悪あがきをしたかったのでしょう。その程度の腕前では、到底御坊ちゃまをなんとかすることは不可能です。
愛に殉じ、死に殉じ、それでも届かないのです。
御坊ちゃまは、珊瑚様にキンセンカを投げ捨てました。
「よろしいのですね?」
御坊ちゃまは頷きます。
「それではここで二名の脱落者が決定いたしました。これより四人のお嬢様との愛の旅を、再び続けてまいりましょう!」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
