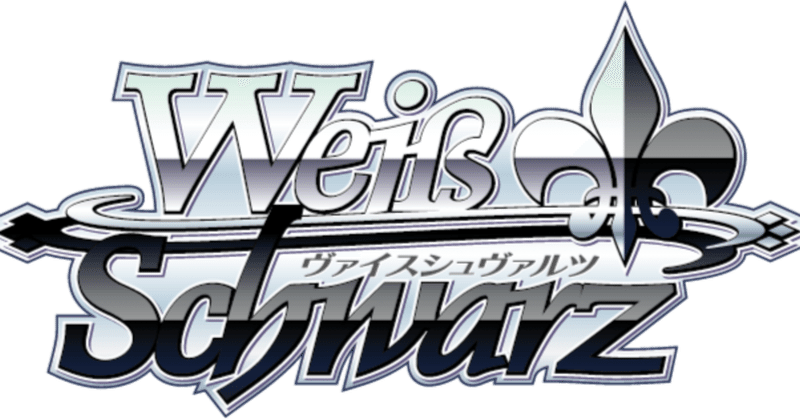
【ヴァイス学校】デッキ構築の基本【初心者向け2限目】
こんにちわ、なっつんです。
今回より新シリーズとして、初心者・中級者向けが上達するためのノウハウを解説していきたいと思います。
今回は初心者向け2限目「デッキ構築の基本」です。
この記事を読むことでデッキ構築の際に必要なカードの判断が早くなり、また大型大会で結果を残したデッキがどういったコンセプトなのかを理解できるようになると思います。
かなり長丁場になると思いますが、見出しをうまく使って最後までお付き合いいただけたら幸いです。
なおこの記事は2022年9月9日(PRD vol.2発売後)時点での情報である事、そしてあくまで僕個人の主観でお話する事をあらかじめご了承ください。
それでは行きましょう。
前提
長文化を避けるため、一部の効果について以下の表記を使います。
CX:クライマックスカード
CIP:手札から舞台に置いた際に発動する効果
PIG:舞台から控え室に置いた際に発動する効果
ルーター:1枚引いて、1枚捨てる効果
Xルック:山札の上からX枚まで見て、任意のカードを手札に加える効果
コンソール:山札の上を公開し、それが指定されたカードなら手札に加えて手札を1枚捨てる効果
トップチェック:山札の上を見て、それを山札の上か指定された場所に置く効果。
(控え)フィレス:ストックと手札1枚を捨てて、山札や控え室から指定されたカードを手札に加える効果
多生:ストックと手札1枚を捨てて、控え室から指定されたカードを手札に加え、他のキャラに+1000する効果
収録中:CXを捨てて、控え室の指定されたカードを手札に加える効果
ツインドライブ:トリガーチェックを2回行う効果
ヒール:クロックのカードを控え室に置く効果
相殺:リバースした際に条件を満たすバトル相手をリバースする効果
特殊相殺:リバースした際に条件を満たすバトル相手を他の領域に移動する効果
ガッツンダー:アタック時にバトル相手のレベルが指定された値だと+6000する効果
また、今回の内容は1限目の記事を読んでいる前提で解説するので、まだの方はそちらを先に読んでいただけるとより深く理解できるようになると思います。
すべてのデッキは3つのタイプに分けられる
まず最初に基本となる3つのデッキタイプについて解説します。
他のTCGでもそうですが、ヴァイスにおいてもデッキそれぞれに得意なゲームスピードが存在します。
アグロ/テンポ
序盤から積極的にアタックを伸ばしたり試行打点を高めることで大量のクロックを積み上げ、そこで得たライフアドバンテージを維持して殴り抜ける戦術を主体としたデッキタイプです。
レベル0CXコンボを採用することでゲーム開始時から手札を減らさず、あるいは増やしながら高い打点を構築することが可能になっており、キャンセル期待値が低い1周目の山札に大量の打点を浴びせていきます。
特に緩やかなゲームメイクをしたいコントロール/コンボに強く出ることができる反面、レベル2以降のカードパワーがあまり高くないため、序盤でしっかりクロックを積み上げられないと理想のゲームプランを通せないという欠点があります。
現環境では+2電源再集結、宝枝プロセカ、炎扉ゾンサガなどが活躍しています。
ミッドレンジ
柔軟な立ち回りを重視したデッキタイプです。
攻撃力と対応力を併せ持っており、メインプランを豊富な選択肢で補強しています。
採用されているカードもバリューが落ちにくいものが多く、終始ドローフェイズの期待値が高く保たれる点もメリット。
一方でアグロ/テンポやコントロール/コンボのような尖った強みを持たせづらく、そういった部分のぶつけ合いの環境になると相対的に活躍しづらくなるという欠点も持ち合わせています。
現環境では8門D_Cide、宝扉冴えカノ、アニバ軸バンドリなど多くのデッキが活躍しています。
コントロール/コンボ
レベル2以降で強固な盤面を構築して逆転することを重視したデッキタイプです。
レベル0~1は受け一辺倒に回ることが多く、相手の理想の動きを許してしまいがちになります。
特に1周目の山札に高い打点を叩き込む手段に乏しく、1-6リフによって2周目の山札を強くさせやすくなっているのがかなり痛いです。
一方で一度盤面を完成させてしまえば相手は対処が困難になりキャンセル頼みのゲームになります。
リソースも潤沢になるため強い圧縮もしやすく、序盤の劣勢を取り返すことは容易です。
現環境ではかなた軸ホロライブ、8電源五等分の花嫁、扉電源かぐや様などが活躍しています。
タイトルごとに強く組めるデッキタイプは限られる
ヴァイスはフィレスや多生といった全タイトルが共通して保有する基本カードと、明確にタイトルの強みとしてデザインされた固有カードを組み合わせてデッキを組む関係上、1タイトルですべてのデッキタイプが組めるとは限りません。
たとえば、ミッドレンジやコントロール/コンボ向けの強い固有カードで構成されているタイトルで強いアグロ/テンポのデッキは組めないことになります。
デッキ構築のセオリー
ではここからデッキ構築のセオリーについて解説していきます。
使いたいフィニッシャーを決める
強いデッキを組むコツとして、フィニッシャーから逆算的に採用カードを決めていくのが最も簡単で上達しやすいです。
例として、僕のお気に入りカードでもあるホロライブの「"穏やかな時間"潤羽るしあ」をフィニッシャーに採用した前提で話していきます。

フィニッシャーができることを理解・把握する
一口にフィニッシャーと言ってもその性能は千差万別です。
そのカードがどれだけのフィニッシュ力を持ち、それ以外の役割を持っていないかなどを理解できないと100%の性能は引き出せません。
では例に挙げた「"穏やかな時間"潤羽るしあ」について見ていきましょう。
るしあはフィニッシャーとしての性能が高くないですが「やさしいエルフ 不知火フレア」の起動能力によって、レベル2からプレイした上で自身のCXコンボの効果で控え室のるしあを舞台に出すことが可能です。
レベル2で盤面制圧を狙えるということは優勢を固定しやすく、劣勢を覆す力に長けているといえます。
そのため、るしあを軸としたデッキを組む場合、
レベル0~1に強いカードを集めることで序盤にアドバンテージを稼ぎ、レベル2で盤面を制圧して相手の逆転を難しくする
といった動きを狙うのが最も強力になります。
では以上を踏まえて、実際に採用するカードを選んでいきましょう。
採用するカードを考える
先ほどの考察で、「レベル0~1に強いカードを集める」という大まかな方向性は決まりました。
では今度は実際に採用するカードを決めていきましょう。
■CXコンボを決め、できることを理解・把握する
まず、動きの中核となりうるCXコンボについて見ていきます。
「"穏やかな時間"潤羽るしあ」を採用する場合、候補として上がるのは主に以下の2枚です。

「呆然 白銀ノエル」はホロライブが苦手とする0/0/4000の対処を可能にしつつ、後列に配置するだけでCXコンボを待機状態にできるため、手札に加えた対応CXを早期からサーチカードとして運用できる点が優れています。
「君と一緒にお花見 不知火フレア」は舞台を埋めるだけで常時6000になる上、確実に配置することになる「修羅場 白銀ノエル」1枚につき追加で+1000されるため、0コストながら最大8000という非常に高い数値を叩き出すことができます。
CXコンボを使用せずともその高い数値で盤面を制圧することも可能なので、対応されるまでこのカードに盤面を任せてしまい、対処された段階でるしあを展開するといったプランを取ることもできるので動きに幅を持たせることができます。
元々るしあを軸としたデッキはあまり選択肢が広くないので、これは非常に大きなアドバンテージになるといえます。
■採用したCXコンボを持つカードと親和性の高いカードを探す
次に採用したCXコンボを持つカードの動きに合致するカードを探し、採用候補に挙げていきます。
「呆然 白銀ノエル」を採用する場合、レベル0からCXを積極的にプレイすることが可能なので始動札を多めに採用していきます。
ノエルをアタッカーとして機能させられる「秋の小路 桐生ココ」や、アドバンテージ源にもなる「山田ハーマイオニー 湊あくあ」「残酷な事実 アキロゼ」「面接中 ときのそら」などから3種12枚採用すればいいでしょう。

「君と一緒にお花見 不知火フレア」のCXコンボを採用する場合は、枝をトリガーすることで「"穏やかな時間"潤羽るしあ」関連のカードを集めたりストックを貯めることができるので、フィレスや多生といったシステムを多めに採用してレベル1でしっかり盤面を構築できるようにします。
枝のトリガー効果やCXコンボで相手に見えたときのプレッシャーが凶悪なので「あの夏で君と 夜空メル」を1枚挿しておくと結構活躍してくれます。

■デッキの方向性に合致するカードを探す
最後にデッキの方向性に合致するカードを採用候補に挙げていきます。
青黄デッキなので経験を満たすと強力なサーチカードになる「#プロテインザスバル 大空スバル」や、早出し可能になる上に相手の盤面に干渉できる「未来へ一緒に 百鬼あやめ」は積極的に採用していいと思います。

るしあのCXコンボを何度も使いたいので、CIP効果で控え室の対応CXを手札に加えられる「吟遊詩人 角巻わため」もデッキの方向性に合致しているといえるでしょう。

■完成
デッキが完成したらとにかく対戦を積み重ねて細部の調整を行っていきます。
環境に応じてデッキに投入しておきたいカードや採用する意味がないカードなどもあるので、採用枚数を調節できる枠を使ってチューニングしていきましょう。
特にミッドレンジは調整できる枚数が他のデッキタイプと比べて多いのが強みになっていますので、それを活かすためにも調整はより綿密に行う必要があります。
さいごに
前回と今回は主にデッキ構築について解説をしてきました。
次回は実際にデッキを回す際、手札を効率よく取り回すためにカードバリューについて解説する予定です。
今回は以上となります。
もしよかったら、他の記事も読んでいただけたら幸いです。
ご覧いただきありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
