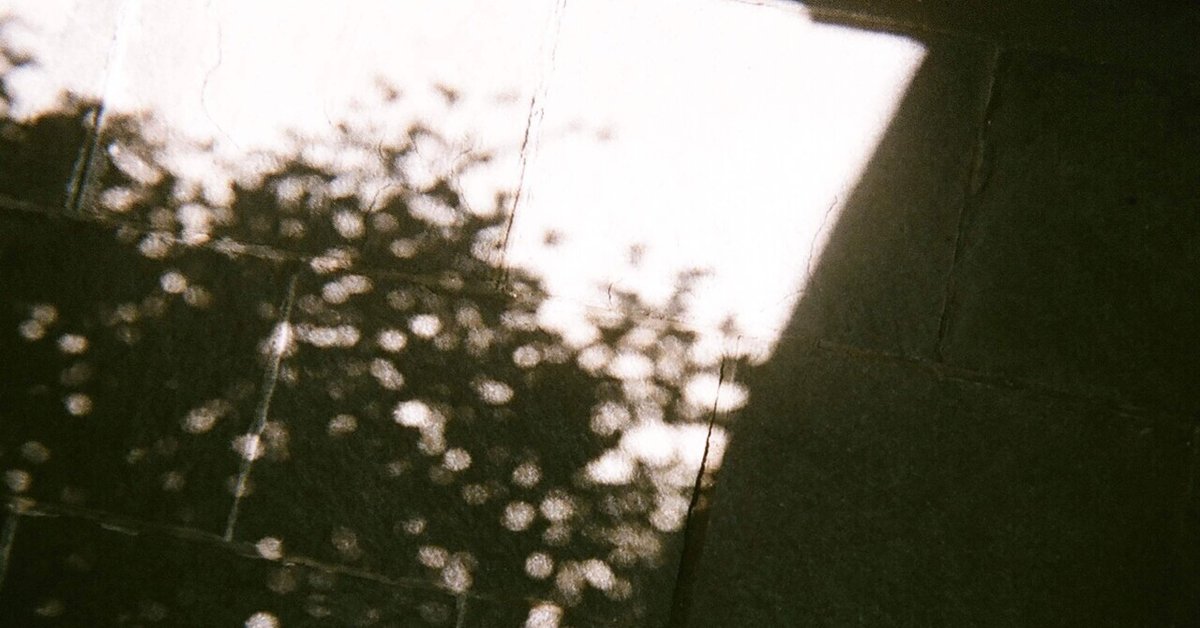
【恋物語】蝉時雨/第三章⑵ 火傷とシーグラス
沈黙の後、今度は小春が話しはじめた。
「入学式のあの日、貴方と目が合って、思い出したの。
ずっと胸の奥の抽斗に了ってあった色が蘇ったように」
「それって、どんな色?」
彼女は左下に目線を落として少し沈黙した。
蝉時雨と雨が容赦なく降る。
「半透明の緑色。質感はシーグラスだった。」
「今はちがうの?」
「あんまり訊かないでよ」
金曜の夕方ということもあってか少々店内が混んできた。
ここはお酒の提供もしている、所謂"カフェバー"という種類の店で、僕の横を通り過ぎた男女からは夜の香りがする。
「出ようか」
僕らはもう一度車に乗り、当てもなく田舎道を走った。
夜に近づいて行くと共に、まるで、木々が半透明かのように不思議に過ぎてゆく。
「思い出したけれど、」
彼女の声で、沈黙が赤く色づいた。
「私、いやなのよ」
弱々しかった。今までに無く、何かを恐れているような。
「キスなんてしたら、みんな、消えてしまうんだもの。」
"みんな"とは、今まで小春と恋愛をしてきた男たちのことだろう。
「男女ってね、なんだかおかしいの。大切だと思えば思うほど触れたくなって、触れるとそれを皮切りに離れていく。大切な人を失うのがキス。」
小春は、初めてちゃんと、彼女自身の恋の話をしてくれた。
中学で付き合った後輩、高校で付き合った同級生。二人とも、キスをすると、それっきり連絡が来なくなったと言う。
その哀しい思い出を話す瞳は、赤く靄がかかっている様に見えた。
「私にとって貴方は、初めての恋で。
ずっと忘れていた事が嘘みたいにいつも鮮やかなの。
シーグラスがずっと、心の瓶の中で、カラカラ、キラキラ、蠢いているの。
あの入学式の時、貴方彼女さんと居たでしょ?
それを見た時、噴水の記憶が蘇るのと同時に、近づいたらいけない人だって思った。
もちろん仲良くしたいけれど、それ以上に近づいてはいけないって。
だから、彼女さんを盾にして自制した。」
「盾に?」
「何度も貴方に言ったわ。
『あの子のこと忘れていないんでしょ』って。
距離を保つ為にそうしてた。
本当に貴方は、ずっと忘れられていなかったみたいだけど。」
僕の家の坂の下にある公園の駐車場に車を停めた。
いつの間にか雨は止んでいったようだ。
湿っぽい夏の空気が漂う。
話そうか、話すまいか、今まで散々迷っていたことばかりを、今日は話している。
ずっとかけていた鍵が開いたというよりも、鍵のかかったままで、隙間から溢れていくような感じだ。
僕はもう一つ、溢れた言葉を掬って小春に差し出した。
「中々忘れられなかったよ。あの子のこと。」
「わかってる」
「入学式の日に君と目が合ったとき、あの子に言われたんだよ。」
ざらざらとしていて取れない記憶。言葉にするのが痛いもの。いつまでも熱を持っている火傷に夏の潮風が延々と吹き続けるような。
「『汚い目だ』って。彼女は僕に言った。
君に見惚れてる僕に。」
小春は手で顔を覆った。
あの悪い夢の時のように。
沈黙の後、僕の目を見て小春は、涙を浮かべていた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
