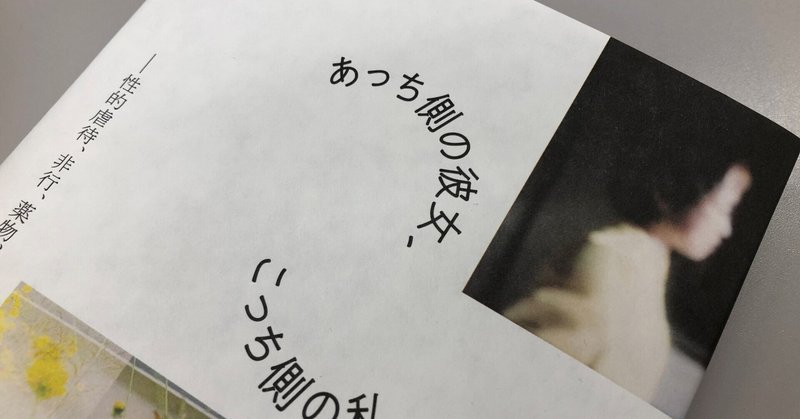
施設で暮らしたり虐待を受けたりしていない人たちは、遠い「あっち側の世界」だった
結生さんは、生まれてまもなく実父のDVで乳児院に預けられ、その後、一時期は実母と義父のもとで暮らしますが、両親から暴力と性暴力を受け、再び児童養護施設に入り、育ちました。思春期には荒れて、援助交際や薬物依存で女子少年院に送られたこともあります。
新聞記者だった小坂綾子さんが「18歳の風景」という連載企画の取材のために、結生さんにインタビューを申し込んだことをきっかけに生まれた、書籍『あっち側の彼女、こっち側の私』。
結生さんと小坂さん、年齢も歩んできた人生もまったく異なる二人でしたが、お互いにお互いを一目で好きなったと言います。もっと話したいという何気ない気持ちが、「本」という形に結実していくまでの交流のさまを、二人に振り返っていただきました。(取材・文=海田文/イラスト=結生)
■一目見て「この人なら大丈夫かな」と思った
小坂:本づくりは、初対面のインタビューで結生さんの口から「あっち側」という言葉が出たところから始まりました。当時、私は京都新聞の記者で、社会の分断についてぼんやり考えていた時だったので、「あっち側」が心に引っかかって、その意味を探りに行くしかなくなった感じだったんですよね。
出会いは、さまざまな背景をもつ18歳から見た社会を描きたくて企画した連載「18歳の風景」の取材でした。少年少女の事件を担当されていた弁護士の安保千秋さんから、困難を抱えつつも前を向いて生きている18歳の女の子がいる、ということで紹介してもらったんですよ。
結生:「あっち側の世界」って、人によって感覚が違うと思うんですが、私にとっての「あっち側」は、施設で暮らしたり虐待を受けたりしていない人たちのこと。あっちとこっちの境界線がある気がしていました。あやちゃんからの取材の話は、当時暮らし始めていた自立支援ホーム「カルーナ」の施設長の山本知恵さんから聞いたんですけど、迷いはあんまりなかったですね。昔から何か発信したいっていう気持ちがあったので、すごくうれしかったし、「受けたい」って思いました。
小坂:結生さんと対面する前は、「どんな人かな」と楽しみな半面、緊張もしていました。「18歳の風景」は、自分の中では初めて問題のジャンルを超えて企画した連載で、思い入れが強かったんです。それまで、働き方の問題やキャリア教育、育児困難、子どもの貧困や引きこもりなど、関心の向くままに取材をしてきましたが、書いても書いても閉塞感を拭いきれず、根っこで繋がっている重要な問題がある気がしていました。
大人と子どもの間にいる「18歳」という年齢で区切ってみたら、何か糸口が見えるかもしれないと思っていました。結生さんが経験した性的虐待も薬物依存も少年院も、当事者にじっくり取材するのは初めてで「ちゃんと聞かなきゃ」と思っていて、いろいろな意味で気負いがあったんですよね。でも、結生さんが現れた瞬間、場の雰囲気が変わって、緊張感が全部吹き飛んでしまいました。
結生:あやちゃんと初めて会った時は、身振り手振りとか表情の変化とか、すごい落ち着きのない人だなと思いました。新聞記者っていうイメージとかけ離れていて、拍子抜けして、生活感が漂ってることに親近感をもちました。勝手なイメージで、メガネかけてジャケット着てみたいな、そういうかしこまった人だったらどうしよう……って思っていたんですけど、あやちゃんを一目見て「この人なら大丈夫かな」と。自分の思い込みだったんですよね。
小坂:私も初対面ですぐに親近感が湧きました。本にも書いたんですけど、まず洋服がかわいかった。リサ・ラーソンのライオン柄の服を着てはったんですけど、私の好きなデザインだったので、「えっ」って釘付けになって、背もちっちゃいし「私とおんなじやん」って。あと、遅れて来た時、普通ならもっと「すいません……」って申し訳ない雰囲気になるところを、「あ、どうも~」みたいな感じだったんで、面白かった。こういう「空気」は好きだな、って思ったんです。
■出会いを機に、自分の生き方を自分で選べるように

結生:取材が終わって新聞に記事が掲載された時、「新聞記者」と「答える側」という関係はいったん終わったのに、まだ「続き」があるような気がしました。あやちゃんとの関係は、これまでになかった初めての関係だったんです。施設の職員さんとも、学校の先生とも違うし、友だちかって言われるとそれも違うし、支援者かって言われるとまた違って……。でも、今までになかったけど、この関係性は自分にとってすごく心地いいので、シンプルに「この人となら一緒に生きやすいかも」って思いました。この関係性に何かヒントがあるんじゃないかと思って、「また話したい」ってメールを送りました。
小坂:メールがきた時は、ちょっとびっくりしましたね。でも、私も「話したい」と思ったので掲載紙を持ってカルーナに会いに行きました。一緒におやつを食べて話したんですけど、いろいろな種類のおやつを盛った大皿の中に北海道銘菓のマルセイバターサンドがあって、「あ、バターサンドや」って手を伸ばしたら、結生さんも同時に掴んでて。「おお、好きなん?」って、心がジワッとなりました。初めて会った時に洋服もそうだったみたいに、「同じものが好き」っていう瞬間に何かを超えていく感じがしたんです。
そのあとすぐ、私は京都から滋賀に異動になったんですけど、忙しい職場で。自分が追ってきたテーマを継続できる環境でもなかった上、娘が小学校に入学したばかりで行き渋りがあって、うまく子育てと記者を両立できなくて、会社を辞めるかどうするか1年ぐらい葛藤しました。時々結生さんのことを思い出して会いたいなと思ったんですけど、忙しくて叶いませんでした。
その後、京都の本社に戻してもらったんですけど、次の異動先は取材には出ない内勤の部署でした。取材して書きたいことがたくさんあるのにそれができない日々で、「自分は一体どう生きたいのか」と真剣に考えました。子どもとの時間を大切にしながら書き手として発信し続ける働き方は不可能なのか、どうすればできるのか、結生さんだったらどうするか意見を聞きたくて、唐突に私が「お茶しよう」っていうメールを送ったんです。「会社辞めようかな」って話をして、結生さんが彼氏のDVで苦しんでいた話を聞いて、お互いの人生について語り合いました。
結生:直接会って話せたのは嬉しかったですね。私も私ですごく変化のある生活で、会わないと伝えきれないような量があって、積もり積もってたっていう感じでしたね。この日をきっかけに、LINEで数日おきくらいの頻度でお互いの気持ちの変化や近況を伝えあって、やり取りをしていました。
小坂:秋に久しぶりに会って、その半年後に私は会社を辞めるんですけど、「本を作ろう」と思ったのは、実はそのあとです。それまでは、結生さんと対話しつつ自分自身の生き方を考えるのに必死でした。結生さんと話すたびに自分の考えが深まって、視野が広がって、これまで取材してきたいろいろな問題の根っこを二人で一緒に探っていくような作業でもあって、ただただ面白かったんですよね。
退職を決断できたことは大きくて、「自分の生き方を自分で選べた」っていう実感を持てたことで突然、結生さんの歩みの軌跡を本にしたいな、って思いつきました。結生さんの人生を追う中で、自分自身の悩みや葛藤も同時に整理されていく感覚があったので、この素晴らしい体験をほかの人たちもできたらいいんじゃないかと思いました。自分のあり方を考えるきっかけにしてもらえる気がして、「一緒に本、作らへん?」と提案して、対話の記録をもとに原稿を書き始めました。
■親を敵視するような構図では描きたくなかった

結生:あやちゃんは、結生と向き合ってるけど、あやちゃん自身と向き合う感じだったって言ってくれるんですよね。でも、私としては、あやちゃんとの会話の時間にはいつも不思議な感覚があって、私のことを、私が思う以上にわかってくれているし、正確に表現してくれる人だっていう信頼感がありました。
それまでは、自分の体験を言葉にする、っていうことをしてこなかったので、言葉を探しきれずにいて。みんなに伝えたいとか発信したい気持ちはあるけど、うまく言葉にできないもどかしさっていうのがずっとありました。あやちゃんと話すと、モヤモヤした感じを言葉に表して繋ぎ合わせてくれたり、引き出してくれたりするのがすごくうれしかった。
新聞の取材でインタビューしてもらった時、こういう方法があるんやなっていう気づきがあって。発信することで、読者の顔は見えへんけど、向こう側の人と繋がっているような感覚になれたし、「あっち側」にいる人の存在を感じられて、それがすごい素敵なことやなって思えました。あやちゃんとは、大事にしたいものが一緒で、目指す方向性が一緒だということもわかってたから、「本にしよう」って話になった時、結生の目線であやちゃんが描いていく、その描き方で任せたいなって思いました。
小坂:結生さんは、多くの困難を抱えながらも真正面から自分と向き合って希望を見出して生きているので、本を作る大前提として、彼女の生きざまを伝えられれば、今しんどい思いをしている人の力になるはずだ、という確信がありました。教育や支援のあり方を問う側面もあります。ただ、「壮絶な人生を歩んできた人の物語」として作りたくはなかった。もっと普遍的な、人間の本質を問う内容にしたかったんですよね。
だって、大きな困難を抱えていなくても、生きるか死ぬかの深刻な状況に置かれていなくても、誰でも何かしら悩んでいるはず。それは結生さんもよく口にしていました。「人は変われる」っていう希望を伝えたいけれど、「こんなにしんどい人が頑張ったんですよ」って言いたいわけじゃない。同じ体験をしていない人でも、「あ、こんなふうに自分と向き合えばいいんだな」っていう小さなヒントがいくつも見つかるような、自己啓発本のようなものになればと思っていました。私自身、彼女と出会って行動を起こしているので、その経験が大きかったですね。
結生さんに対しては、出会った時から「あっち側」っていう言葉にハッとする感覚があったし、生育環境も年齢も違う相手だけど、同じ問題意識をもって同じ方向を目指している人なのかなと、ぼんやり思っていたのかもしれません。出会った当初はお互い「あっち側」だと思っていたけれど、対話するなかでそれがよくわからなくなってきて、「あっち」と「こっち」を隔てる壁の正体を解き明かしていく感じだったから、社会の分断を生む「見えない境界線」は一つの大きなテーマでした。
結生:「本を作ろう」って話になった時に、世の中にどんな本があるか探っていたら、「毒親」っていうキーワードがけっこう目に付いたんです。最初、毒親っていう言葉を知らなかったんですけど、調べていくと、一番に感じたのは負のエネルギーでした。親から虐待を受けた人の中には、そういう捉え方をすることで自分を保っている人はいるんだろうな、っていう気持ちはあるし、それが悪いことではないと思うんですけど、自分としては、そこに重きを置きたくありませんでした。もちろん、自分の中でも親に対する復讐心みたいなものがなかったわけではないし、「許せない」っていう気持ちももちろんありました。でも、「子」対「親」みたいな、親を敵視するような構図では描きたくなかった。
何かを責め立てる気持ちって、仲間を集めやすいって思います。でも、もっと緩やかな流れのほうが大切かなっていうのがあって、責め立てるような仲間ではなくて、自分が大事にしたいって思えるものを共有できる仲間と繋がっていきたいっていう気持ちが大きかったです。あやちゃんとの関係性は、あやちゃんは子育てや働き方の悩みを相談してくれて、私は性との向き合い方を相談していて、「お互い大変やな」「お互いいろいろあるよな」って、自然に考えられるものでした。こういう関係性が社会にもっと増えていったらいいのになと思ってこの本を作ったので、そのメッセージを発信していけたらうれしいです。
■「あたり前」はそれぞれ違っても「変わらないもの」もあるはず

小坂:結生さんは、育った環境の「特異性」と、人の心としての「普遍性」を持ち合わせていて、それを言葉にできる人なんですよね。結生さんの二面性をきちんと描いていくことが重要で、それこそが、異世界のように見える問題について読者が「自分ごと」として考える鍵になるのではないかと思っていました。
結生さんを取材した連載が新聞に載ったあと、いくつかの大学から授業に呼んでもらって話をしたんですけど、記事を読んだ学生たちの感想が印象的だったんですよ。「ドラマみたいだけど本当にあるんだ」とか「私はこういう家庭で育たなくて幸せだ」とか言う学生が少なくなくて。
みんな真剣に私の話に耳を傾けて、問題を考えてくれていたし、不真面目なわけではなくて正直な感想なんだろうなと思ったけれど、壮絶な現実を丁寧に描いて問題提起すればするほど多くの人にとって「遠い」出来事になってしまう現実を突き付けられた気がしました。本当にこれでいいのかな、というモヤモヤがあって、どういう発信をすれば、「ドラマのような壮絶な体験をしている少年少女」と「自分たち」の生きている社会が地続きであることに気づけるのか、ずっと考えていました。その答えが、結生さんの二面性を描くことでした。
結生:施設にいた時から、「社会に何かを発信したい」「社会と繋がりたい」っていう気持ちがあったんですけど、そういうふうに思い始めたのは、学校の友達との会話とかがきっかけなのかなって思います。私が施設にいることはみんな知ってて、興味をもってくれる人もいるし、施設自体知らない人もいる。「施設ってどういうところなの?」って聞かれた時は、素直に「親がいない子とか、そういう環境がない子たちが一緒に暮らしている」って答えていました。
友達には、親と一緒に生活していないというところが羨ましく映ったり、「虐待されている子」っていうのは、「自分とは違う世界に住んでいる人」っていう風に見えたり、そういう感覚をもつ子が多かったんですよね。その感覚をもつのは普通なのかなって思っていたけど、でも自分が施設で生活しているのは、自分の中では当たり前のこと。虐待されて生活してきたというのも、社会から見たら普通ではないかもしれないけれど、自分にとっては「当たり前」でした。
いろんな感覚が「当たり前」で、私のなかの当たり前があって、逆に友達にも施設ではない親元で暮らしているという、私とは違う当たり前があって。でもそれぞれ当たり前や環境が違っても、「変わらないもの」もあるはず。もちろん施設ではない生活を羨ましく思ったりもするし、自分にないものが良く見えたりもするけど、「施設で育った」とか「施設で育ってない」とか、そういう見方の「その先」というか、それを超えた関係性を築いていきたいと思った。どういうものかっていうと、あやちゃんとの関係性です。この関係性が、自分の大事にしたいところなんだな、という気づきがありました。
小坂:育った環境は全然違うけれど、結生さんの言葉は私の心にグサグサと刺さってきます。「自分らしく生きる」とか「正解を求める教育でいいのか」とか、「他人の期待に応えなきゃ」「ノーと言えない」「私は悪くなくて誰かのせいにしたい」とか……。「人に頼りたくても頼れない」「誰かに認められたい」なんて言われると、「いや、私もおんなじやけど」って思う。働き方の取材をずっとやってきて、就活生や早期離職の若者、子育てとの両立に悩むお母さんらの話をたくさん聞きましたが、結生さんが抱えているしんどさと共通するものもたくさんありました。結生さんの心のあり方をひもとくと、そこには、多くの人が考えたり悩んだりしていることが詰まっているんですよね。
一見すると「虐待を生き抜いた子」「少年院にいた子」の話に見えるかもしれないけれど、同じ経験をしていない人との間にも、ちゃんと共感がある。結生さんの心を描くことで「私と同じ」を感じてもらえる気がして、一番大事にしたのはやっぱりそこです。人としての感情は結生にも同じようにあって、同じ社会を生きてる人であることを伝えられるはずだという思いがありました。
■たくさんの人にとって「この本が希望になりますように」
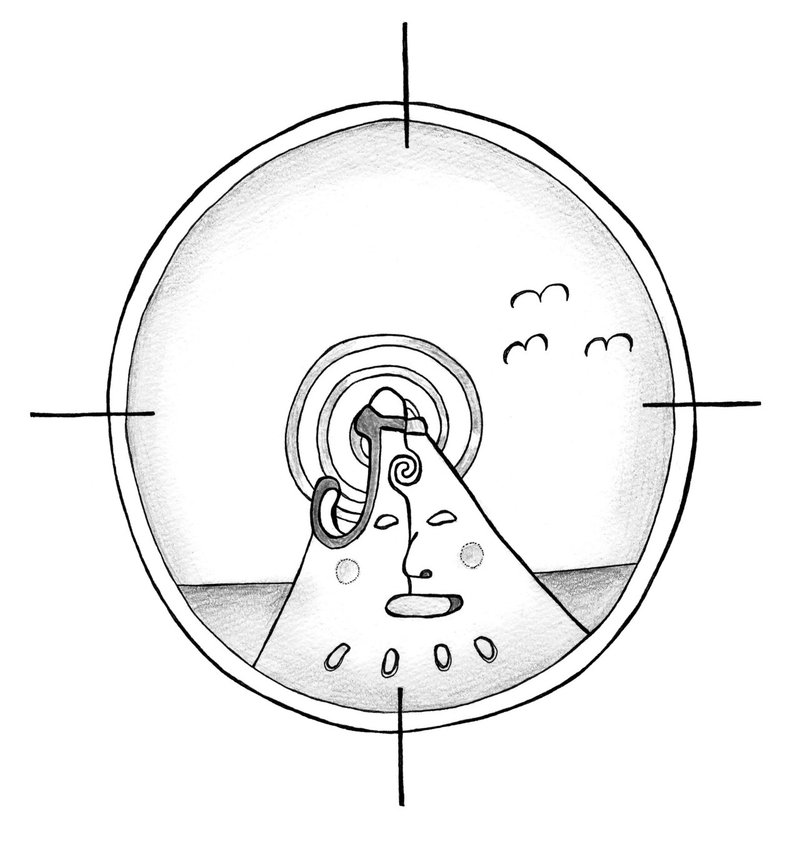
結生:この本を作る上で、変わらない関係性はすごく大事だなって思っていました。あやちゃんとの関係が、この本を作る過程でどう変わったかというと、何があっても変わらなかった。その関係性の大切さに気づけた、っていうこと。あやちゃんともそうやし、この本を読み直して今思うのは、自分にかかわってくれる施設の先生や、支援者の方々も、自分がどんな状況にいてもずっと変わらないでいてくれたということが心の支えになっていた。すごく救われた体験だったな、というのがありますね。
小坂:この本ではところどころに支援者の目線を入れているんですけど、それは、伴走する人の存在が結生さんにとって大きかったと思うからです。でも結生さん本人は、自分にとって大切な存在であることに、その時点では気づいていないこともある。出会いの大切さや、その人が発した言葉の意味を何年もしてから知る。振り返って「そうだったんだ」って気づくことの重要性も、本を作りながら感じました。
結生さんの人生に限らず、誰の人生でもそういう出会いってあると思うんです。10年後、20年後になって、実はあの出会いには意味があったと感じることがあるはず。結生さんがあとがきのところで「一つ一つの出会いに心を閉じないで」って書いた、あの言葉の意味はそこにあるんですよね。「諦めない」っていうのは、「誰かに強くすがる」とかじゃなくて、「この出会いはもしかしたら何かに繋がるかもしれない」って思ってほしいし、目の前の人との出会いを一つ一つ噛みしめて、大事にして生きていってほしいっていうことなのかなと。結生さんのあとがきには、「この本が希望になりますように」っていう一文もあって、この「希望」っていう言葉にも、いろんな思いが込められているんじゃないかな。
結生:お世話になった人で、すでに本を買って読んでくれた人がいて、その人が連絡してくれたんですよ。「この出版に向けての取り組みが、結生ちゃんの振り返りや、よき歩みの整理になればなどと思っていましたが、読み終えた今、何よりも私自身の振り返りや整理や気づきや反省や学びや確認や、希望になっていることに気づきました。結生ちゃんのあとがきにある、この本が希望になった、きっと第一号です」って伝えてきてくれたんです。うれしかった。
小坂:支援者の方からの感想やったんよね。子どもの、とくに傷を抱えた子たちの伴走って、簡単じゃないと思うんですよ。弁護士の安保さんのお話にもあるんですけど、「もう無理」「限界」って感じる瞬間があるかもしれない。でも、そんななかでも「人は変われる」とか「自分の伴走には意味がある」っていうことを信じることができれば、伴走者や支援者としても「諦めない」でいられる。そういう希望を持ってもらえたならうれしいですね。
結生:この本を読む人って、いろんな立場の人がいると思うんですけど、この本の示しているものはシンプルだと思います。あやちゃんとの関係がそうであるように、誰か一人とでもいいから心地いい関係性があるだけで人生って生きやすくなるし、視野が一気に広がるっていうこと。心地いいってどんな関係性かっていうと、「あっち」と「こっち」とか、属性じゃなくて、単純に「好き」っていう気持ちで繋がるみたいなこと。それって、簡単そうだけど、みんな固定概念に縛られている部分が多くて案外難しいんじゃないかな。
本当は、人間みんな弱っちい部分があって、「自分を認めてほしい」っていう気持ちがあって、そういうのって誰にでも、私にだってあるし、読んでくれている人にもあるはずなんですよね。だから、「私と違う世界の人の話だな」って思ってこの本を読み進めていても、途中で、「この気持ちわかるな」って、自分と重ねて共感してもらえる部分があったらいいなと思います。
小坂:結生の生育環境から遠いところにいる人にとっては、読んだ後に「あれ? 違う世界の人だと思ってたけど、実は自分と同じ?」という感覚をもつかもしれません。結生さんの心に触れることで、遠かった世界そのものがぐっと自分に近づく、そんな体験をしてもらえるのではないかなと。私が最初そうだったように、読みながら、いい意味で混乱してもらえる一冊になっている気がします。
結生:本を作ってみて、「違うけど同じ」っていう感覚がすごく大事だなって思いました。私が、「自分を変えることができるんだ」って気づいて希望をもったみたいに、読む人もいろんな悩みがあると思うので、同じように希望をもって読んでもらえたらうれしいです。
結生 (ゆうき)
1996年生まれ。生まれてすぐに実父のDVから乳児院に預けられ、児童養護施設で育つ。一時的に実母と継父と暮らすが虐待を受け再び施設へ。度重なる非行から少年院に入り、出院後は服飾の専門学校に進学。その後、教育系、福祉系NPO勤務などを経て現在はアパレル会社で働く
小坂綾子 (こさか・あやこ)
1974年、京都府生まれ。新聞社勤務を経て、2017年からフリーライターとして活動。教育、文化、社会福祉などをテーマに取材し、新聞や雑誌、ウェブメディアで執筆する
