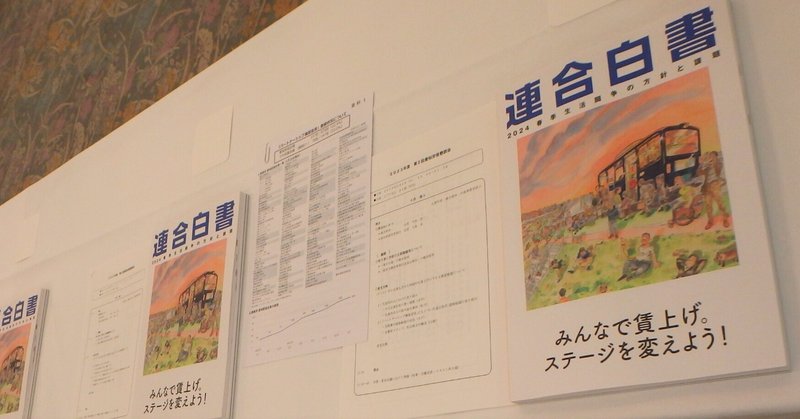
春闘前夜を振り返る~30年前のトヨタ労使の「ウェハース」からサプライチェーンのそれへ
■4か月前の春闘前夜を振り返って
ほぼ春季労使交渉が終わり、大企業を中心に2年続けて大幅な賃上げ回答が出ていました。一方で円安による資材価格や物価高騰も企業財務や消費者の懐に響いています。電力料金の激減緩和阻止の補助もなくなります。本当の物価と賃金の好循環の詩型が見えてくるのは、これからです。以下の記事は2024年2月に書いた春闘前夜の原稿です。
■2024年2月1日の愛知労使懇談会

今年も春季労使交渉、いわゆる春闘の季節になりました。2024年2月1日に愛知県経営者協会と連合愛知による愛知労使懇談会が名古屋市内で開かれ、取材に行きました。1994年にトヨタ春闘の取材を始めてから30年。春闘には関心を持ち続けてきた記者の一人です。 懇談会では、連合愛知の可知洋二会長(電機連合)と愛知県経営者協会の大島卓会長(日本ガイシ会長)から方針が示されました。 可知会長は「昨年は約30年ぶりに高い賃上げ水準となりましたが、残念ながら、実質賃金は低下しており、さらに社会の隅々まで行き届いていない」と課題を提示しました。 経営者協会の大島会長は「労使や個社の努力だけではなかなか難しいこともあることもわかっています。取引や価格転換の問題、サプライチェーン全体でちゃんと整備してほしいと思っております」と方向性を示しました。 記者の取材は冒頭のあいさつまででした。昔から記者がいると本音の議論がしずらいという風土は、今も残っているようです。
■30年前のトヨタ春闘 1994年の名古屋、豊田市で担当したトヨタ自動車の春闘は、いまも思い出します。労使が腹を割って話し合い、決着すればあとくされなく生産に励む。日頃の労使関係が「つかず離れず」という絶妙な関係を保っていることが大切なことでした。それは、記者と労務を担当する役員「労担」にもいえる「つかず離れず」の距離感です。
■100円玉に命を吹き込む交渉 1993年のトヨタ春闘は3月22日未明に決着しました。経営側は電機など他産業の動向をみながら、1万1100円で回答する方針だったようです。ところが、労組側は前年実績を1㌽以上も下回るということで、強く反発して労使の折衝が続けられ、100円上積みした1万1200円で決着しました。この最後の「百円玉」は、組合員の士気を高めるうえで、とても重みのあるものでした。
翌94年春闘は急激な円高のなかで進みました。1月に発表されたトヨタの国内生産は前年比9.4 %減の356万台。初めて3年連続のマイナスとなる中での幕開けでした。時代は日本車の北米輸出攻勢に対して、アメリカが強く反発して、海外生産の動きがまさに加速しようというときです。利益と雇用を
産み出してきた国内生産の「空洞化」が懸念されていたときでした。
■円高不況よりも厳しかった
当時の労務担当の専務は、組合との交渉の前線にいました。いわゆる「労担」でした。その労担は「円高不況後の87年春闘(妥結額8000円)よりも厳しい。今年は賃上げ幅の選択の余地が厳しい」と、記者に相場観を話してくれました。当然、組合幹部にも伝わります。組合委員長は「政府や企業、組合が縮み志向に陥らず、賃上げで景気浮揚に取り組むべきだ」と論陣を張ります。結果は前年妥結額を2000円下回る9000円でした。ただ、上積み額に重みがありました。
■「チャリン、チャリン」
前夜、労担に「チャリンですね」と探りを入れていたのですが、決着の翌朝は「チャリン、チャリン」。つまり200円積み上がっていました。労組が要求していた賃上げ率5%に対して、「3%はない」と厳しく言い放った労担でしたが、3%をわずかに超える、双方痛み分けの決着だったのです。
■労使はお菓子のウエハースのようなもの
3年間お世話になった労担は、1995年5月に59歳で亡くなられました。追悼記事で労担が時に涙を流しながら交渉したことや、交渉哲学ともいえる言葉も書きました。
そのひとつが、「労使はお菓子のウエハースのようなもの。交渉が平行線でも、真ん中にクリームがある。これがなかったら、ギスギスしてポロポロこぼれる」でした。
95年春闘も急激な円高の中で、胃を手術した体にムチ打って労使交渉に臨んでいました。
■時代は適正な価格転嫁が急務
あれから30年。ようやく「おもてなし、サービスは無料ではない」(大島会長)が当たり前の世の中に近づいてきました。
2024年労使懇談会は、例年と異なり、懇談会後に「持続的な賃上げと適正な価格転嫁に向けた愛知会議」がひらかれました。ここから報道陣も会場に再入場して取材ができました。

労使に加えて、愛知県の大村秀章知事、厚生労働省愛知労働局の阿部充局長が新たに参加。最後に最後に「持続的な賃上げと適正な価格転嫁に向けてそれぞれの役割、責務を果たすこと、また課題解決に向けて連携して取り組んでいく」ということを愛知会議として宣言しました。
4者の足並みがそろっていました。個社の労使が内輪で議論して完結する時代ではないのです。「国内の中小企業は国内での経済活動が中心ですが、取引先の輸出型大企業が円安で恩恵を受けていることによるフィードバックがない」(大島会長)など、構造的な課題が山積しています。中小企業が賃上げの原資を得るためにも、サプライチェーン全体で適正な価格について支援していくことも不可欠となっています。
■サプライチェーンでの「ウェハウス」
かつては、労使のギスギスを緩和するウェハウスでしたが、いまはサプライチェーンのなかにこそウェハウスが必要です。先日のトヨタグループ決算のなかでも、取引先の中小企業への適正価格を表明するグループ企業もありました。会社ごとに働きやすさを議論していく一方で、経済界、労働界全体で価格適正化に務める賃上げ風土を作っていけるのか、今春闘のポイントの一つだと考えています。
(2024年2月5日)※20240527追加再掲
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
