
年間ベストアルバム2018を選んだ
前回の記事で年間ベスト映画を選んだことだし、次は音楽。この1年を通して、何度も聴いたアルバムの中から強く印象に残ったアルバム9枚を厳選してみた。
9. V.A「ブラックパンサー ザ・アルバム」
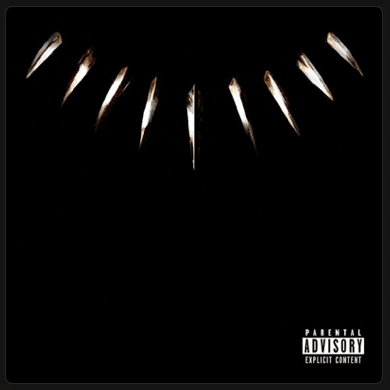
ケンドリック・ラマーもWeekndもSZAも、一介のアーティストの範疇を超えた、カリスマ性に満ち溢れる超人という印象がある。映画「ブラックパンサー」に登場する架空の国、ワカンダで採れた鉱石: ヴィブラニウムが無くとも現代にはそうしたヒーローやスターがいて、コラボレーションでお互いを高め合っている。そんなことを再認識させてくれるコンピだ。
ジェイムス・ブレイクが構築した硬質なビートが心地良く、後半にはケンドリックの怒涛のフローが炸裂する「King's Dead」から、インタールードを経てBPM120台でノせてくる「Redemption」に雪崩れ込む流れは圧巻。
8. Geotic「Traversa」
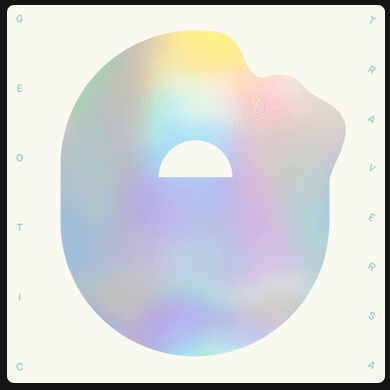
もし、レディオヘッドの「Everything in Its Right Place」や「KID A」のような音色で、強迫観念や緊迫感ではなく、穏やかさや温もりを湛えた4つ打ちの音楽が連綿と続いていくアルバムがあったらめちゃくちゃ聴きたくなる人って結構いるんじゃないだろうか。これはそういう一枚なのかなと思う。
普段聴いている音楽ではアタックの強いビートや低音で音圧疲れしていたのか、このアルバムで鳴っている優しくて軽めの音に浸っていると、毛布にくるまって思考を空っぽにできるような安堵感に包まれる。それが心地よくて、ついつい再生してしまう。
7. ジョン・ホプキンス「シンギュラリティ」

10年前にリリースされて世界的に大ヒットしたコールドプレイのアルバム「VIVA LA VIDA」の冒頭曲、「天然色の人生」の幕開けで鳴っているループはジョン・ホプキンスが提供したものだと最近知った (そのループをジョンが一曲に発展させて2009年に発表した楽曲が「Light Through the Veins」)。ジョン・ホプキンスのアルバムをまともに聴いたのは本作「シンギュラリティ」が初めてだったけど、彼の作った音にはとっくに触れていたことになる。
シンギュラリティ、すなわち特異点がもたらす不連続性に至る過程では (厳密な数学的定義をちゃんと押さえているわけではなくて恐縮なんだけれども)、Δx, Δy, Δz, Δt がいずれもゼロに収束していく中、f(Δx,Δy, Δz, Δt)はゼロにはならずに、確かなエネルギーが観測できる……という現象が起こっているようなイメージがある (だいぶテキトーだ)。そしてこれは、そんなイメージをそのまま音楽化したようなアルバムになっていると思う。各々のトラックがシームレスに繋がっている時間方向の連続性に加えて、楽曲を構成する各パートがレイヤー感の境界を無くしていくように結合している。だからと言って似たムードの似た曲が続くような退屈な時間に陥らせず、壮大なスペクタクルを穏やかな心持ちで眺めているような気分にさせてくれる。
6. ヨルシカ「負け犬にアンコールはいらない」

会社の軽音部で年上の方 (僕が生まれた年に入社された、という感じの年の差がある)とバンドをやることになったのだけど、その年上の先輩が決めた曲目のリストが「プリンセスプリンセスとヨルシカ」というすごい振れ幅のある組み合わせだった。おっどろきー。プリプリは世代なんだろうけど、ヨルシカ!? n-buna時代から聞いてたんですか!? ボカロ好きですか!? とワクワクしていたら「子供が好きだから覚えた」とのこと。今、ギター・ロックっていうとPENGUIN RESEARCHとかが人気なのかなと思っているけどちゃんとヨルシカも若年層に認知されてるじゃん。うれしい。
ひと夏の焦燥と葛藤を描きながら、季節が一巡すればまた夏がやってきてしまうことと、天に昇った魂が輪廻のサイクルを経てふたたび地面に降り立つことを重ね合わせた世界観に、切なくも暖かい気持ちになる。この「輪廻」を作品全体で表現するように、冒頭と末尾にインスト曲を配置してアルバム全体が自然なループになるように構成されている。さらに、そのインスト曲から前作「夏草が邪魔をする」に自然につながるようにも作られており、繰り返しと分岐を表現しようとしているようにも取れる。
(プロデュース・作詞作曲・ギターを務めるn-bunaさんのツイート)
(を、貼っていたが削除された模様。2020/6/28追記。)
「ループもの」の映像作品において作品群がひとつの作品軸に収斂されているように、ヨルシカというプロジェクトもひとつの軸に繋がっていくものになるのかもしれない。
5. ポスト・マローン「beerbongs & bentleys」

真夏のアメリカってこんな感じなのかな、という空気感がなんとなく共有できてしまうマジックが宿っている。前のアルバムよりも音数は抑えて、アルバム全体のトーンを統一させることでモヤモヤした夏独特の雰囲気: 鬱々してるけど しんどくはない絶妙なダウナー感にずっと浸っていられる。ラップというよりもメロディを伴うフロウによって聴き手の心を引き込んでいくスタイルに自然に惚れ込んでいくうちに、いつの間にかXXXTENTACIONらをはじめとするアーティストのアルバムをすんなり聴けるようになっていた。僕にとっての、(2010年代の)ラップ・ミュージックにちゃんとハマるきっかけになってくれた、すごく大きな一枚だと思う。
彼がゴシップ映えする話題性をたくさん振りまく破天荒な人物だということは最近まで知らなかった。あるとき海辺ですごく優しい笑顔をくれたちょっと悪そうな兄ちゃんが、実はだいぶヤバイ奴だった的な暖かみがあって、とってもいい。
4. チャーリー・プース「Voicenotes」
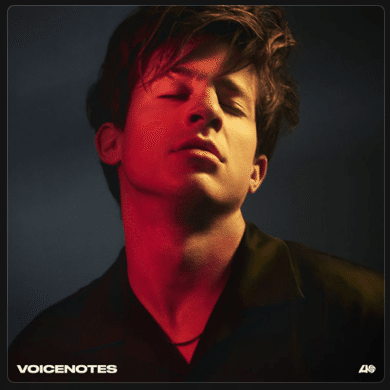
チャーリー・プースは、まだ2枚しかアルバムを出してないのに大阪のエディオンアリーナ (キャパ8000人)・幕張メッセ・東京国際フォーラムホールAというツアーを組んで全公演平日なのに全公演ソールドアウトという大快挙を成し遂げてしまった。えええええええええええ。数字だけ見ればWeekndを超える動員力があると言えてしまうわけであまりの人気ぶりに驚くけど、このアルバムを聴けば、彼が確かな実力とセンスに裏打ちされたアーティストとして納得の売れ方をしているのだと実感できる。
バックストリート・ボーイズをはじめとする「バカ売れしてた洋楽ポップス」を彷彿とさせるメロディ展開とハーモニーを、2010年ならではの軽快なビート・プロダクションに乗せて、抑制された熱量で見事に仕上げている。冒頭曲「The Way I am」で、インパクトのあるギターフレーズを控えめに鳴らしつつループさせてメロウなアコギのカッティングを重ね、歌とキックが同時に入るオープニングでガッツリとハートを掴まれてしまった。
3. D.A.N「Sonatine」
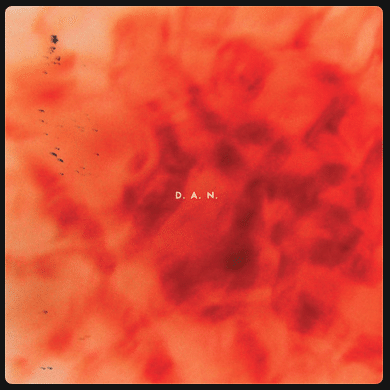
川の流れに乗って揺蕩っているうちに、気がついたら海かと見まごう大河に出ていて、ぼやけた地平線を眺めているうちに自我と世界の境界が曖昧になって融け出していくような、空間的にも感覚的も壮大なスケールを体感させてくれる境地に到達している。
このアルバムを聴きながら街を歩いていると、いつの間か意識がぼーっとしてきて、水底に沈んだ街を鰓呼吸しながら徘徊しているような気分になった。それは100歩譲って暑さのせいもあったのかもしれないが、D.A.Nの楽曲には脳機能の一部をスリープさせるような特殊なヤバみが確実にある。
2. The 1975「A Brief Inquiry into Online Relationships」

現代は私たちを見捨てた。いつだって死にたくなる。
インターネットを通していろんなページにアクセスしたり、多様なアプリを使いこなしたりできても、結局待っているのは自分が1 mmも前に進んでいないような虚無感、孤独感だ。「Love It If We Made it」ではイギリス人の立場で難民問題やトランプ大統領を引き合いに出しているけど、一方日本のリスナーとして日本国内の政治に関するニュースに目を向けようにも、目も当てられない。この国で生きていることが恥ずかしくなることばかりだ。消えてしまいたい。
それでも、最後の曲「I Always Wanna Die (Sometimes)」の “Sometimes” という一語から「死にたいわけじゃないときもある」ことが見出せるように、私たちには絶望する時間だけが与えられたわけじゃない。成し遂げた何かがあるなら、たとえそれがネット上で情報が動いただけの実体の無い成果物だったとしても、それを大事に抱えていくことを希望と呼ぼう。
このアルバムを2018年11月30日未明の配信開始直後に聴きはじめ、歴史的大傑作を解禁直後に浴びて打ち震える体験をTwitterで共有した多くの人たちが、同志がいるという事実だけで僕は胸の奥がなんだか熱くなる。そういう体験を共有できたことだってきっと、ささやかでも確かな希望だ。
混迷の時代にネット上の関係性が生んだ、暖かい光だと信じていたい。
1. 小袋成彬「分離派の夏」

彼の歌声を初めて聴いたのは、80kidzが2016年3月にリリースしたアルバムの収録曲「Doubt」でボーカルとしてフィーチャリングされた時だった。澄んでいるのに確かな存在感がある、独特な良い声だなぁと思った。しかし今思うと、あの曲の煌びやかでアッパーな4つ打ちエレクトロ・サウンドでは彼の歌声の本質的な良さを活かしきれてなかったように感じられる。
アルバム「分離派の夏」については以下の記事で深掘りした。
この記事を書いたときはリズム・符割りのことにフォーカスしていて、彼の歌が持つ日本語の響きの心地よさについて触れられていなかった。「美酒」「親父」「苗場の月明かり」「きっとうんざりするほど近い未来」などなどのフレーズが、毅然とした姿勢と甘美な雰囲気を合わせ持ったアルバム全体の佇まいに見事にマッチして、聴いているうちに小説の世界に入り込んだような気分にさせてくれる。
アルバムの最後からひとつ前の楽曲「門出」で「深い愛の物語には 栞をつけましょう」とあるように、このアルバムは金字塔とか一里塚というよりも栞であって、2018年の日本という今・ここが決して忘れられなくなるように刻みつけてくれているんだと思う。
ちなみに去年選んだのはこんな9枚。
「分離派の夏」についてのコメントで「毅然とした姿勢と甘美な雰囲気を合わせ持ったアルバム」と書いたけど、僕が好きなのは大抵そういうのなんだとなんとなくわかってきた。特定のジャンルじゃないんだよね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
