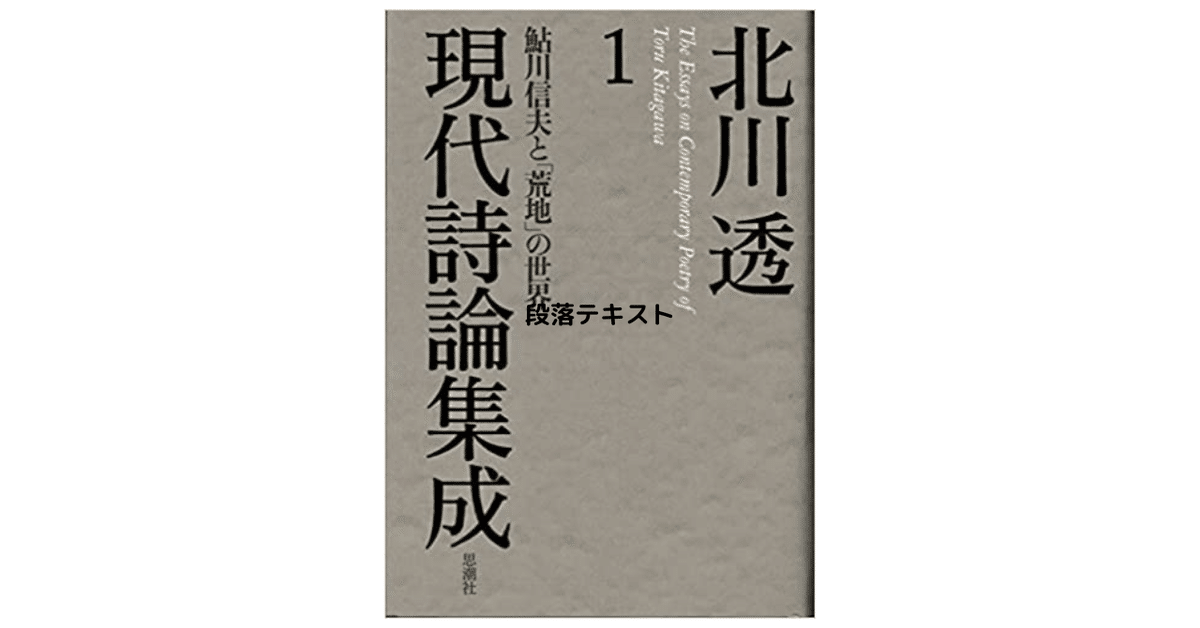
戦後詩(史)の行方(鮎川信夫編)
『北川透 現代詩論集成1 鮎川信夫と「荒地」の世界』
「むしろ、自らの詩の方法や言語感覚と異質な他者の作品ほど、彼は無心にその世界を読み取ろうとする。わからなさを指し示し、それを批判するにしても、わからなさを大事にして、そのまま理解しようとする。……詩を批評する自らの目が、自らの批評言語や概念でがんじがらめに縛られることが何よりも嫌いなのだ。北川透詩論のフェアさがここにある」(佐々木幹郎・月報より)。 「「荒地」周辺をめぐり、ほぼ半世紀にわたって書かれた論の数々。読めば読むほど、引きこまれていく。半世紀。時代も風潮も、変わっていく。著者の論は、その着眼点や論じ方を変化させていく。……詩を書く人、書こうとする人は多い。けれど、他のだれが、詩作品とともにこれだけの詩論を執筆することで同時代の詩とともに歩もうとしただろうか」(蜂飼耳・月報より)。 詩があるがままの姿で批評を孕む――。敗戦後の昏迷から、時代の危機を鋭く表して、同時代の思想と文化を先導した「荒地」の詩人たち。「無名にして共同なる社会」をつくるための「精神の架橋工作」を果敢に実践しつづけた鮎川信夫をはじめ、田村隆一、北村太郎らの詩的言語の画期的意義を論じ、その変容をふまえて未来の再生を予告する。絶えざる現在性の批評として、半世紀にわたって詩論の最も高い稜線を形づくってきた北川透の営為を精選する、待望の集成、刊行開始!
「荒地」の鮎川信夫に興味があって手に取った。詩の批評を読むことがなかったので難儀している。批評というものの独特な言葉使いにも辟易している。吉本隆明に似ている感じがする(というか吉本隆明論も含んでいた)。
鮎川信夫と「荒地」の詩人であり、興味深いのは吉本隆明は「荒地」の人かと思っていたのだがちょっと違うようだった。鮎川信夫が中心となっていた「荒地」は戦時中から「荒地」の理念、それはT.S.エリオットの詩「荒地」からなのだが、ヨーロッパは第一次世界大戦で世界の終末を見ていた。それがモダニズム詩人としてのT.S.エリオットらの出発点であった。
モダニズムが現実社会の荒廃を見て精神世界(古典文学)に希望というか幻想を見出す時に、それはエリートの教条主義的なルネサンス(芸術復興運動)となったと思われる。その反動として出てきたのがプロレタリア文学で、日本のモダニズムに問題も後にプロレタリア文学に吸収されない者が精神性として日本主義的なものを見出していった。
それはそうだろう。現実を否定して精神主義の幻想を現実社会に見いだしていくならば、それは宗教的なさらにたちが悪い一神教的な理念に近づくかもしれない。そうしたモダニズムの批判として鮎川信夫らの「荒地」は始まった。
そして彼らが注目を浴びたのは第二次世界大戦で焼け野原の状態で出発せねばならなかった詩人としての拠り所として戦後詩ということで注目されて行った(廃墟の上に立つ詩人として)。
それは破壊された世界の中にあって、彼らが見出すのは言葉の力(詩的言語)で幻視された世界だった。それは詩の彼岸性(死者たちの世界)というものかもしれない。現実社会の否定性から成り立つのは死の観念として、そこに交わるエロス的なものがあるからだと思われる(バタイユやブランショの思想を感じる)。それは例えば現実の神よりも詩神(ミューズ)であるような喪失した恋人たち(女に限らず男の場合も、戦友という死者を思い浮かべればいいだろう)との永遠と続いていく幻夢の世界なのだ。
「荒地」派の詩人たちが呼び覚ましたのは、そうした故人(戦死者たち)との世界であった。
吉本隆明は戦後詩の問題として戦争責任論が文学世界で問題となったときに、大衆の理論とモダニズム的エリートの理論の対立を見た。それが吉本的マルクス主義的文学観なのか(二分法でアウフヘーベンさせていくという論理哲学)。それを文学という精神性というものを対峙させたのだと思う。そしてそういう精神性が幻想世界だと見抜いていたのだ(『共同幻想論』)
戦争責任論が大衆からの突き上げで行われるときに、そこにファシスト的なスターリン的なものを感じたのだ。そのことは「荒地」に吉本隆明を招くことになったのだが、そのことから「荒地」が内部崩壊して行った。それは個々の詩人たちの戦争責任論という中で、その社会に生きて詩を書いていたことは少なくとも戦争責任というものを逃れられないものがあったのだ。そのことで、例えば仲間の中に戦意高揚詩を書いていたものがいたとか無視できないことになっていく。
そもそも吉本の戦争責任論の目論見は、高村光太郎が当時もっともモダニズム詩人とされたのに戦争翼賛詩を書いたことに言及する。それはモダニズムのエリートの理念(モダニズム)が大衆の欲望に飲まれていく過程であり、それはモダニズムばかりでなくプロレタリアも大衆の欲望に飲まれた結果なのだと、その大衆論が後期の吉本とどう結びつくのかわからないが、それが『ハイイメージ論』として展開していくのだろうと思う。ここでは吉本を扱う場ではないが吉本の論理が「荒地」を内部崩壊させたという北川透の批評なのだと思う。
それぞれの「荒地」派の詩人論は章立てて述べてあるのだが、今回はそこまで読みきれなかった。鮎川信夫の戦後の孤立性は、すでに破壊された世界の中にあって経済発展というアメリカ型の資本主義を受け入れた時点で死者たちの背信行為であり、どんな連帯も受け入れられなかったということなのかもしれない。それは究極の個人主義なのか?吉本の共同体論と相反するものだったのか?
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
