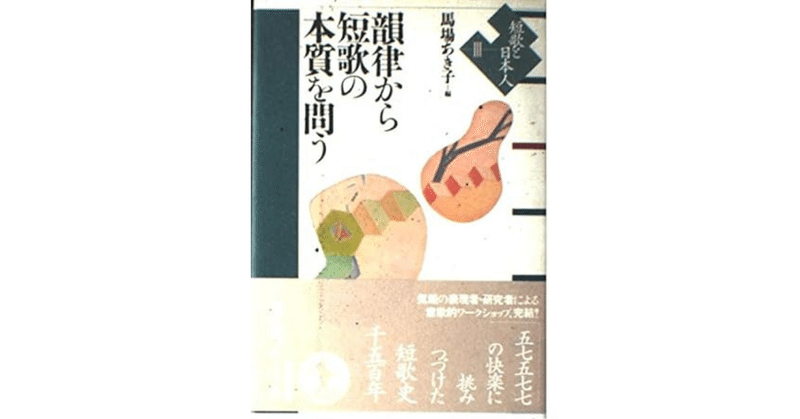
韻律の研究
『短歌と日本人〈3〉韻律から短歌の本質を問う』馬場あき子(編集)
短歌を短歌たらしめているのは韻律なのか.短歌においてきわめて重要とされる韻律を,古代歌謡から現代短歌まで,検証する.
目次
〈批評とエッセイ〉現代短歌の口語律と文語律…岡井隆/韻律から見た俳句と短歌…坪内稔典/歌謡律と短歌律…馬場あき子/定型の魅力…高野公彦/「病雁」の律と「小えび」の律…米川千嘉子/音読される短歌律…水原紫苑/枕詞の復活…加藤治郎(座談会)宝生閑・岡野弘彦・馬場あき子/川本皓嗣・佐佐木幸綱・馬場あき子
口語と出会った短歌律…馬場あき子
「短歌律」は五七五七七の律。今まで文語で書かれていたものを石川啄木がこのままでは短歌は滅亡していくと考えて口語短歌を作り出した。それは厳密な口語短歌ではないのだが、啄木が目指したのはわかりやすい短歌ということで行分け短歌として、短歌律ではない現代的な律を模索したのだ。例えば、
東海の小島の磯の白砂に
われ泣なきぬれて
蟹とたはむる 石川啄木
短歌の律にすると
東海の 小島の磯の 白砂に われ泣きぬれて 蟹とたはむる
啄木の歌は初句切れが多いという。次の歌が初句切れだった。
頬につたふ
なみだのごはず
一握の砂を示し人を忘れず 石川啄木
初句切れは『新・古今集』に多く用いられるのだが、初句切れにすることで、五 七五 七七の形となり、古典的な律の五七調から現代的な律の七五調になるという。そして一番多いのが五七 五 七七の型だという。五七で切るのは二句切れで古くからある古典調が、「短歌」では三句切れが「百人一首」などに見られる方法から全般的に主流となり、軽快な感じを受けるという。初句切れはさらに軽快というわけだった。俳句をやっていると五七五、七七という形になり上句、下句という律になりやすく野暮ったいということだった。最初は初句切れからやってみよう。
初句切れと言っても啄木の場合行分けで切れを入れている場合が多く、上に上げた初句切れも通常では「頬につたふなみだのごはず」と修飾されていくのだった。このように行分けで初句切れにしている句は『一握の砂』では三分の一あるという。それが啄木の短歌律だという。
このような短歌の律の読みを指定した歌人は、釈迢空がいる。短歌の律にこだわった作家は啄木、釈迢空、塚本邦雄と変遷していくのだった。啄木の口語短歌の影響は寺山修司にあるようで、俵万智もその流れのようだ。最近は、文語と口語を混ぜて併用するのが流行りのようである。
韻律から問う(鼎談「韻律から問う」馬場あき子X岡野弘彦〈折口の弟子〉X宝生閑〈能役者〉)
いろはがるたでは関西と関東では音律が違って、関西では「一寸先は、闇」とか「ほとけの顔も、三度」と下の句は短いものが多いという。江戸だと同数律に近いものが多い。「憎まれっ子 世にはばかる」とか「貧乏 暇なし」というような違いがある。
和歌ももともと諺的な言霊と(贈答)歌と二種類あったようで、諺的なものは呪術の言葉として、短い言葉のリズムの積み重ねていくものがあったという。それが長歌の五七調七五調となって最後に七七調と締める歌になってゆく。古代の謡は五七調が多く、岡野弘彦はそういう長歌を作っているが校歌を依頼されるときは現代の人に合わせて七五調にするという。ジャズは七五調とか。五音は刹那い響きが多いとか、最初の呼びかけは五音が多い。初句切れは感情を伝えるので『新古今集』で流行ったという。
聞くやいかにうはの空なる風だにもまつに音する習ありとは 宮内卿
この歌はまだ恋も知らないで二十歳で死んでしまった宮内卿の歌だがこれが『隅田川』で母が死んだ子供の歌となると哀切な感情が出てくる。宮内卿の歌は感情よりも技巧としての歌(フィクション)なのだが、それが人の声(母の声)に乗ると感情が湧き出てくる。歌の調べとはそういうことらしい。短歌は意味が半分で調べが半分だという。短歌の切れはいろいろ研究してみる価値はあるという。俳句だと切れを入れるのも初句か二句切れで、あまり意識してないかも。
「現代短歌の文語律と口語律」岡井隆
短歌の口語律の興隆期は次の四つの時代があった。
明治末から大正初め時代(1900年代と言ってもいい)
大正末から昭和初期(1920-1930年代)
戦後、唱和二十年代(1940年代)
唱和後期から平成・現代まで(1960年代-)
1、2、3の時代の口語律は短歌滅亡論(短歌否定論、〈第二芸術論〉など)のさなかに現れてくる。4、は「前衛短歌」の行き詰まりとリアクションからコピーライティングのような口語短歌が出てきた。ただ分断化があり一方では難解な口語短歌があり、一方でコマーシャルのような短歌があるのだ。
1は「言文一致」運動が言われた頃だが、短歌ではそこまで「言文一致」の歌はなかったという。例えば与謝野晶子の『みだれ髪』も君という言葉を使っているが、それは万葉時代の「君」とほとんど変わらない。
やは肌のあつき血汐にふれも見でさびしからずや道を説く君 与謝野晶子
この時代に口語短歌に意欲的に挑戦したという青山霞村『地塘集』では
できましたか阿方(あなた)の後を継ぐ女皇(めぎみ)神戸の小さいあの王国に 青山霞村『地塘集』
これだけでは意味が通じない。自序にアメリカから帰ってきた幼稚園の女教師へとあり、贈答歌だった。女皇はアイロニーだろうか?
他に独泳歌として季節を詠んだものがあるが、それほど目新しい歌ではないという。
蝶の夢花の夢草も春の夢雲のかたちもまた夢のやう 青山霞村『地塘集』
しかし霞村『地塘集』は半分は今まで通りの文語短歌になっていった。霞村が流行らした口語表現としては「ごとく」を「やうに(な)」という柔らかい表現になっていくぐらいだった
2はプロレタリア短歌の全盛期。
出稼ぎに若い男女がでかけてゆく貧しい村の冬がまた来た 中村孝助
斎藤茂吉『赤光』の場合
数学のつもりになりて考へしに五目ならべに勝ちにけるかも (明治38年)
赤き池にひとりぼつちの真裸のをんな亡者の泣きゐるところ (明治39
年)
文語だか口語だかわかりにくいが「なりて」「考えし」「勝ちにけるかも」が口語的用法だという。この頃はまだ言文一致が確定しない時期であり漱石『坊っちゃん』が出たのが明治39年だという。その歌は連作「地獄極楽図」の一首で初句が6音なのが音数を乱す口語化だという。結語の「ところ」は正岡子規の口語を真似たという。この頃の短歌は近代化を求めてナショナルな作風だという。それが『赤光』の中に復古調の歌が出てくるのだ。
青玉のから松の芽はひさかたの天(あま)にむかひて並びてを萌ゆ (明治39年)
古語の定型に負けて内容は乏しいという。万葉調ということみたいだ。「萬葉調」と「写実」が「アララギ」派の二大テーゼであった。後年、茂吉は「写実」という現代性を獲得していく。まだ復古調が抜け出れない歌は、
かぎろひの夕べにの空に八重なびく朱の旗ぐも遠にいざよふ (明治40
年)
この頃は「万葉調」でありながら会話文の導入という口語化も試みている。
床ねちにぬくまり居れば宿つ女が起きねと云えど起きがてぬかも (明治41
年)
1998年の『短歌』9月号「口語を生かす」という特集から。
屋上にねころんで手をつないでみた無力な二枚の木の葉のように 俵万智
ぼんやりと耐へてゐるんだゆく夏の傘に集まる雨の重さに 山本富士郎
もうゆりの花びんをもとにもどしてるあんな表情をみせたくせに 加藤治郎
朝の陽にまみれてみえなくなりそうなおもあえを足で起こす日曜 穂村弘
おいとまをいただきますと戸をしめて出てゆくやうにゆかぬなり生は 斉藤史
さういふなら君の両掌でみどりごのくれなゐの耳をぎつてごらん 塚本邦雄
米川千嘉子『たましひに着る服なくて』を読む
現代短歌は、和歌の伝統として文語の中に斎藤茂吉のように口語を取り入れるような混合文が多くなっている。
みづあふれ子どもは生まれみづは閉ぢこの子のどこかへかへりたそうで 米川千嘉子
「みづあふれ」は助詞を省略した口語調。米川の短歌は子どもに向かうときは口語調になり、父(亡き父の歌)に捧げられる時は文語表現が多くなる。ただ短歌の律を整えるために文語表現が活用されるのだ。
薄き刃のあたるしづけさ緑陰に入りゆくはパプステマのしづけさ 米川千嘉子
前半は音数律に則って懐古調の表現だが「パプステマ」と外来語が入ることで音数律が乱れて破調になる。
「韻律論」川本皓嗣
なかなか説明するは難しいのだが、日本人のリズムが四拍子というのは一拍に二文字で、五七五七七に当てはめていくと五音の時は3・2で二拍と一文字の休符と見ていく。そして4拍が5回繰り返されていくという。一拍というときは最初文字が強で次が弱とくり返していく。これはあくまでも音韻論で実際には1拍の中に3音のときもある(三連符はブルースになりそうだ)。8ビート(8文字)の四拍子ということだった。その理論は面白い。あくまでも理論ということなので実際の短歌は違うという話。
それを実際に作品に当てはめて見ればわかるかも。
君恋ふと消えこそわたれ山河にうづまく水のみなわならねど 平兼盛
きみ/こふ/と◯/◯◯
きえ/こそ/わた/れ◯
やま/かわ/に◯/◯◯
うづ/まく/みづ/の◯
みな/わな/らね/ど◯
綺麗に音韻が揃っているな。
やは肌のあつき血汐にふれも見でさびしからずや道を説く君 与謝野晶子
やは/はだ/の◯/◯◯
あつ/きち/しお/に◯
ふれ/もみ/て◯/◯◯
さび/しか/らず/や◯
みち/をと/くき/み◯
後半乱れているのか。
さびし/からず/や◯/◯◯
みちを/とく/きみ/〇〇
三連符になってモダンな韻律なのかもしれない。
白川の関屋を月のもる影は 人の心を留むるなりけり 西行
しら/かわ/の◯/◯◯
せき/やを/つき/の◯
もる/かげ/は◯/◯◯
ひと/の◯/こころ/を◯
とど/むる/なり/けり
こんな感じか。
床ねちにぬくまり居れば宿つ女が起きねと云えど起きがてぬかも 斎藤茂吉
とこ/ねち/に◯/◯◯
ぬく/まり/おれ/ば◯
やど/つめ/が◯/◯◯
おき/ねと/いえ/ど◯
おき/がて/ぬ◯/かも
こんな感じか。人によって詠みのリズムは違うかもしれない。
屋上にねころんで手をつないでみた無力な二枚の木の葉のように 俵万智
おく/じょう/に◯/◯◯
ねこ/ろんで/てを/◯◯
つな/いで/みた/◯◯
むりょ/くな/にまい/の◯
この/はの/ように/◯◯
俵万智は難しいな。音韻が現代的なのか?
薄き刃のあたるしづけさ緑陰に入りゆくはパプステマのしづけさ 米川千嘉子
うす./きは/の◯/◯◯
あたる/しづけ/さ◯/◯◯
りょく/いん/に◯/◯◯
いり/ゆく/は◯//◯◯
パプステマ/の◯/しづ/けさ
現代短歌は音韻が掴み難い。
これもまた家族のかたち灰色の下着が二枚並ぶベランダ 小佐野彈
これも/また/◯◯/◯◯
かぞく/の◯/かたち/◯◯
はい/いろ/の◯/◯◯
したぎ/が◯/にまい/◯◯
ならぶ/ベランダ/◯◯/◯◯
三連符主体の読みにしてみた。カタカナはそれで一拍。なんとなく対になっているような気がする。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
