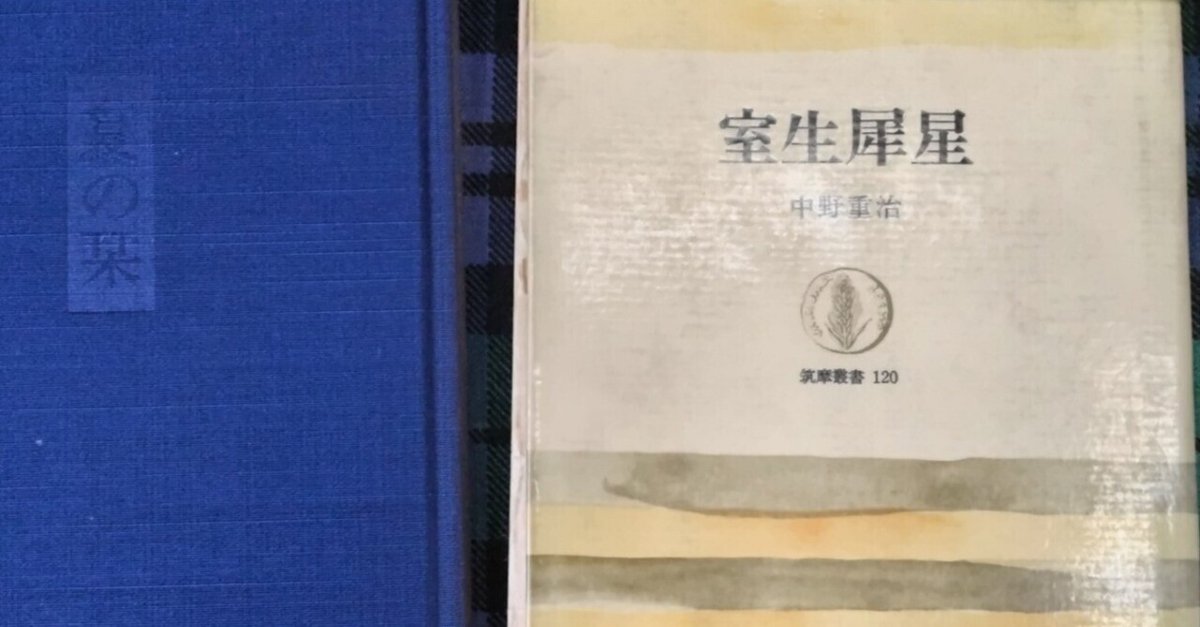
中野重治+佐多稲子+室生犀星(その2)「室生犀星」読後感
中野重治の室生犀星(筑摩叢書、1968年)(明治22(1889)年8月1日金沢生まれ、昭和37(1962)年3月26日肺癌のため虎の門病院で没)を読んだ。アジア人物史の中野の項では評論集とあったが、要は犀星の人と作品について、中野が犀星全集の解説用に書いたものなど17年分を整理したもので、社会を論ずる風というよりは、犀星の魅力を語るもの。自然を愛する心の表現が、徳富蘆花とも違うし、宮沢賢治とも違うが、どこか通じるものがあるようにも思わなくない。中野にとって「驢馬」の会(1926-1928)は、死ぬまで大きな存在で、犀星はそれを育てて、優しく見守ってくれたとの思いが随所に感じられた。これは佐多稲子の中野に対する思いに共通する。
第1編は、それぞれのエッセイに表題はあるが、「人と作品」としてまとめたもの。
金沢の犀川べりの雨宝院の住職の内縁の妻赤井ハツに私生児として育てられ、7歳で住職室井真乗の嗣子室井照道となった。貧しく不遇な境遇からではあるが、新聞記者を経て文壇への道に生きることができた。
「運命とその交錯」の中で語られる大きな出来事は、大正10年(1921)に生まれた長男を一歳そこそこで失ったことがある。大正12年には長女朝子が生まれるが、その5日後が、関東大地震であった。(p.34) 自分に引き写す意味はないが、東日本大震災の翌年に、33歳の長男を失った。
「豊熟と途上の障碍」では、それ以上の打撃として昭和13年(1938)妻とみ子が脳溢血で倒れたことである。折しも戦争の時期で作家として悩ましい時代であった。(p.56) 大きな社会変動と個人的に遭遇する死や病の重なりは、人の一生の中で生き方を変えるというようにどうしてもなってしまうものであろう。自分が75歳まで夫婦ともに健康でおれることはありがたい。
「二つの廃墟から」では、戦後1949年になって、「ぼつぼつ書きはじめた。」とあり、さらに「還暦をむかえて彼はいっそう元気になってくるように見えた。」(p.70)とある。朝子の結婚、芸術院会員など良いことも続き、軽井沢から東京に戻り、筆が進むようになった時代だ。馬込第三小学校の犀星作詞、平井康三郎作曲の校歌もこの時代だ(昭和25年)。
「七十歳」で妻とみ子を見送る。犀星の生母を知る唯一の従兄が仙台で没。義兄の赤井真道も金沢で死去。義母の母親が前田の御殿女医であったことを知る。
「仕事の中での七十三年」では、「こうして、ある静かで平安な老年期がきても不自然でないきわになって、新しく、文学というものに初めてはいって行くような気組みでさらに書きつづけてゆこうとする」(p.86)と書いているのは、自分(中野)の将来への励ましのようにも読めた。
第Ⅱ編は犀星の人となりのエッセイをまとめたもの。その冒頭で、犀星は教師らしくないと言っている。そして「驢馬」の人間は、人間主義的であり、平和主義的、非好戦的であったと。(p.108)「室生犀星は人にたいして親切だった」(p.142)は、まさに中野重治に対してということなのであろう。
第Ⅲ編は、作品が語られる。冒頭で、犀星の文学は「母乳のごときもの」で、ひどい文学が溢れるなかで、母乳に立ち返れと言う。
最初期の詩集を読んだときの感動を述べている。「抒情小曲集」「愛の詩集」「第二愛の詩集」の3編である。朔太郎の「月に吠える」と同時期に発行した「愛の詩集」は自費出版した処女詩集であると犀星自身が書いている。(p.160)義父室生真乗の残した財産の世話になったようだ。そういえば、宮沢賢治場合も、最初の詩集「春と修羅」を自費出版して売れ残ったことを、そして映画の「銀河鉄道の父」の中での父の経済的支援が思い浮かぶ。デビューしたての犀星や朔太郎も含めて、多くの日本の若い感性が生んだ詩人の言葉が、新しい世界を生もうとしていた時代だったということかと想像する。さらに「エレナと曰える少女ネルリのこと」については、聖書のこと、レ・ミゼラブルのこと、ドストエフスキーのことに触れているのが興味深い。(p.163) 馬込第三小学校の犀星作詞の校歌の「幼年の日を送る、・・・師よ導きを、与えてよ」を歌うとき、いつも讃美歌のようであり、体育館が教会になったようなイメージを浮かべるのである。
萩原朔太郎は室生犀星と同時期に活躍しているわけだが、「室生犀星詩集」の編集の中で朔太郎は「自分と室生は水魚の交わりをつくして来た。我々は詩壇に出世を同じくし、生活を共にして来た。明白に言へば、自分と犀星との間には一の避けがたい気質の相違がある。」(p.166)と書いている。中野に言わせると朔太郎は論理的、犀星は非論理的となる。犀星の庭と庭つくりとを愛する心持ちも、たとえば「夏は涼しく秋は枯葉の音のするやう落葉樹を雑えて植える・・」(p.172)と引いていて、自然への感性を強くもっている。
「心のこりの記」は、犀星全集を編むにあたってのさまざまな心残りを記している。三好達治の死、犀星の葬儀での正宗白鳥、佐藤春夫の弔文を載せられなかったと。二人とも犀星の後を追うように亡くなった。引き続き「うろ覚えの記」で、それら弔文が現れる。佐藤の弔辞では、谷崎潤一郎とともに犀星を訪ねたときの思い出が語られ「ドン・キホーテのように闘いつづけた」という表現が現れる。また、経済観念にこだわらない犀星を追想している。大森の家も建物だけで土地は借りたままのものだった。犀星の死後の身の振り方について、姉弟と中野とで意見のちがいが出たという。
あらためて犀星の一生を振り返り、関東地震と長男の死、国民精神総動員の運動の時に妻のたおれたことは、ともに彼に大きな打撃であったと。佐多稲子の中野(77歳で没)への想いも、中野の犀星(73歳で没)への想いも、すでに逝った周りの仲間も偲ばれて、より鮮明に人が浮かんでくる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
