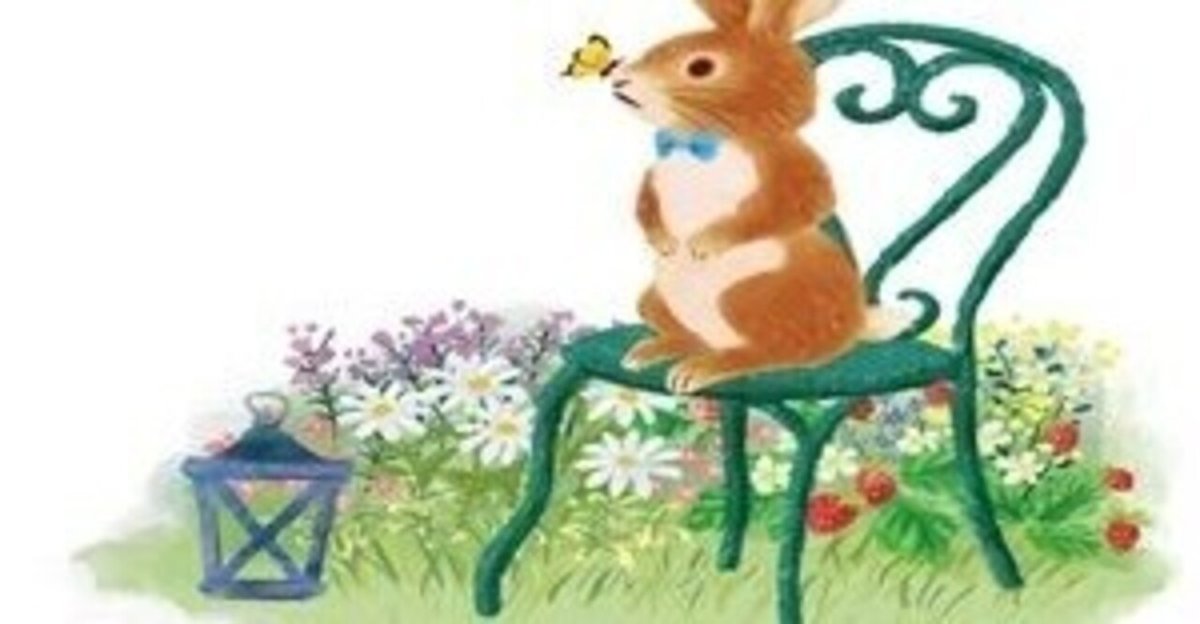
ももこの幼稚園生活 ②
幼稚園の玄関先で泣き、教室で泣いていたももこは、いつの間にか泣かないで「お仕事」に没頭するようになっていた。
モンテッソーリ教育を行う幼稚園では、子どもが自主的に行う事を「おしごと」と呼び、子どもたちのために多くの教具が用意されている。
ももこが3年半の幼稚園生活を通して大好きだったのが、シール貼り。色々な形が描かれた台紙にシールを貼っていくもので、シール数枚で形を作れるものから、複雑な図形をシールで埋めていくものまである。
たかがシール貼りと思うかもしれないが、幼いももこは配色や絵柄を考えながらシールを貼る作業がとても気に入っていた。
園では挨拶を厳しく指導していた。朝や帰りの挨拶はもちろん、園内でお友達の間でも言うべきことはどんな小さな子でも言うように指導された。登園時、玄関でお迎えをしてくださる先生に「おはようございます」とあいさつするのは当たり前。慌てて靴を脱いで挨拶をしない子がいても、「おはようございますでしょう」という言い方は一切せず、先生方は子どもが何を言うべきか気付くまで「おはよう○○ちゃん」と何度も言うのだった。
もう少し年齢が上がると、挨拶をしない子はさすがにいなくなるが、うっかり忘れてしまうと、「ももちゃん、何かいう事はないかな?」と言って先生方は誘導するのだった。
それは、「ありがとう」「ごめんなさい」も同様だった。どちらを言われても、言われた子は「どういたしまして」と返すのが常だった。
そうして、基本の挨拶を日々の幼稚園生活で身に付けるだけでなく、子どもと先生だけで行われる遠足では、年長さんが年少さんと手をつないで道路を歩き、電車に乗り、現地に向かうということも教育として行われていた。
年長さんは白線の外側を歩く、公共の乗り物では騒がない、大きな声で話をしない、他の乗客の邪魔になるような所に立たないなど、幼稚園のころから叩き込まれた。そうした教育が身についているお陰で、ももこが大人になった今でも基本の姿勢は何ら変わることはない。
こう書いて行くと、どんなにお利巧さんな子どもだったのかと思われるかもしれないが、母親である私は葛藤の連続だった。
2歳児から出始める自我を大切にするというのは、理屈では理解していても、日常の生活でももこのやりたい事を優先させることは相当難しかった。
例えば、朝のお着換え。自分でパジャマを脱ぐ、畳む、洋服に着替える。この一連の行動は想像以上に時間がかかる。幼稚園に通い始めの頃は、私が服を着せていたが、「なるべく自分でできることはさせるように」と園からのお達しで、時間の余裕を持たせていたものの、実際はそれ以上に時間がかかり、ももこが着替えるのを待つのすら胃が痛くなる思いで見ていた。
着替えはかぶるものであれば何とかなるが、ももこがボタンのある洋服を選んでしまうと、私の「待つ」覚悟は頂点に達する。まず、ボタン穴にうまくボタンが入らない。そしてボタンを入れる場所が違う。基本的に、その日着る洋服はももこが決めるので、私はお天気を考えてアドバイスするだけ。さっさと着せて幼稚園に連れて行きたいと思っても、ももこは自分でやると言ってきかないので、私は終わるまで待つしかない。
ボタンがかけられるようになるまでの長い時間を待つ。ファスナーの金具を入れられるようになるまで待つ。前の日に道具はリュックに入れてあるので(両手が使えるように幼稚園かばんはリュックという決まり)、食事と着替えだけなのだが、朝から一体何時間待たなければならなかったことか。
仕上げは玄関で靴との格闘。入園したての2歳半の時はスリッポンのようなもので良かったが、年齢が上がるごとにベルクロス、紐靴とレベルも上がって行った。紐が付いたスニーカーを履くとき、ももこは最後の蝶結びにこだわり、自分で綺麗に結べるまで玄関に座り込んだ。「もう行かないと遅れちゃうよ」と私が言っても聞こえないふり。
紐が上手く結べずに玄関で格闘したために遅れました、と幼稚園の玄関で告げると、先生方は決まって遅れた事を咎めもせず、ももこに向かって「上手に結べたね」とほめてくれた。遅刻をしないことが大切なのではなく、遅刻をしてでも最後までやったことを褒める、という感覚を持っていなかった私は、ももこを通して「待つこと」と「認める」ことを学んでいった。
行動が人より遅い、手先は器用な方ではない、自分が気に入ったものだけに執着するももこだけれど、誰一人ももこを否定する先生はいなかったこと、ももこはももこで良いのだと思わせてくれたことが、ももこ自身より私が救われたように思う。
そんなももこの幼稚園生活は、ももこにとって一番楽しい場所であったが、年長さんになると平和でない日も増えてくることになる。
次回に続く
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
