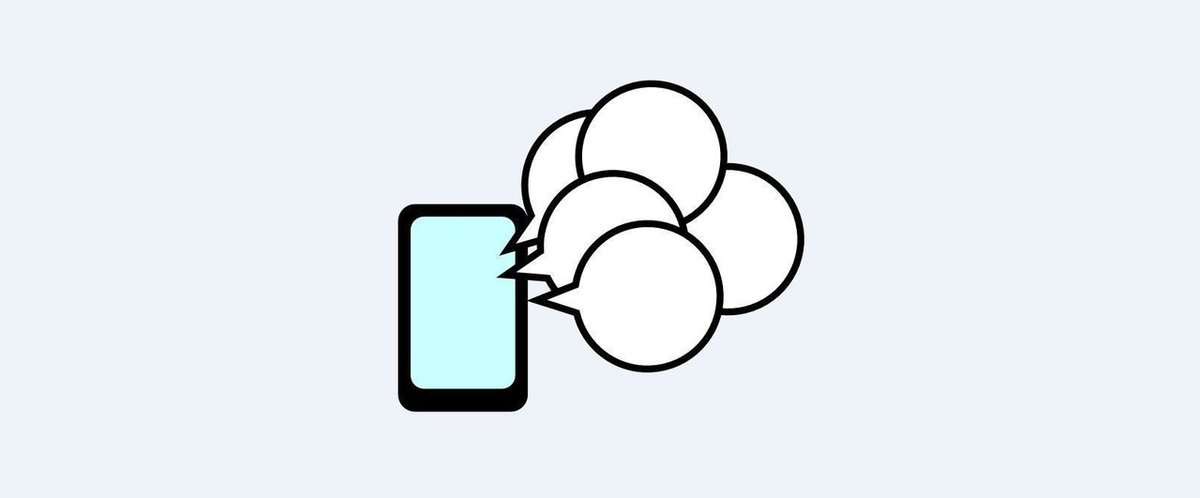
昼のサル,夜のサル
読者諸氏にお尋ねしよう,諸氏は「昼行性」だろうか,「夜行性」だろうか。コンビニエンス・ストアが日常の一部と化し,スマートフォンを通じて昼夜問わずさまざまな娯楽がもたらされている昨今では,夜になるほど目が冴えて活発になるという,「夜行性」とも言うべき人が,いよいよもって増えているようである。とは言っても,我々の社会は朝起きて夜眠ることを前提に成り立っている。一方で,実は我々霊長類の祖先は夜行性であった,というのが研究者の一応の総意である。一応の,というのは,霊長類の祖先が昼行性であったという説も,昼にも夜にも活動していたという説もあるためだ(※1)。
さて,現在生きている霊長類たちに話を移そう。小型で愛らしいロリス(下図)をはじめとする,より「ヒトから遠い」サルたちの多くは夜行性である。

しかし,霊長類の中でもより「ヒトに近い」分類群である「真猿類」に属するもの(中南米にすむマーモセット,サキ,クモザルといった広鼻猿類や,ニホンザルなどのオナガザル上科,チンパンジーなどの類人猿)はほぼすべてが昼行性であり,例外的に,その名も「ヨザル(リンク: 英語版wikipedia)」科のみが夜行性である(※2)。ヨザルというのは南米に住んでいる,広鼻猿類に属する霊長類で,大きな目と非常に長い尾をもっている。
月夜のサルは
「真猿類」たちは進化の過程で夜行性から昼行性になったと考えられているが,ヨザルはその後再び,昼行性から夜行性へと戻ったようだ(※2)。ほかの「真猿類」たちが昼行性であり続けている一方で,ひっそりと夜行性に戻っていった孤高のヨザルは,いったいどんな風に生活しているのだろうか。これは多くの研究者にとって気になる問題だったのだが,何しろかれらは夜に活動しているので,観察が難しく,なかなか研究が進んでいなかった。
そこでアルゼンチンの研究者たちは,このヨザルの行動生態を調べるため,「Actiwatch」という自動計測システムを用い,6-18ヶ月間,野性のヨザル10頭の行動と,その場所の光の量や温度といった環境要素を5分おきに計測した(※3)。その結果,ヨザルの行動は日没ごろに非常に活発化するが,その後徐々に行動量が減り,再び日の出ごろ活発化し,そして日中はほとんど活動しないということが分かった。さらにヨザルは,夜間においては明るいほど行動が活発だった。この実験期間中に3度月食が起きたのだが,月が欠けるに従ってヨザルの行動量が減少し,また月が現れていくに従ってヨザルの行動量が増加していた。
夜行性のサルだから暗ければ暗いほど活発化するのかと思いきや,そう単純ではなく,明るい夜ほどよく動く,というのがなんとも複雑で,面白いではないか。これから,霊長類の昼行性と夜行性の進化のメカニズムが少しずつ分かっていくことを楽しみに待ちたい。
(執筆:James)
文献
(※1)Primate color vision: A comparative perspective, Jacobs, Visual Neuroscience, Volume 25, Issue 5-6, 619-633, 2008
(※2)Diurnality and nocturnality in primates: An analysis from the rod photoreceptor nuclei perspective, Joffe et al., Evolutionary Biology, Volume 41, Issue 1, 1-11, 2014
(※3)Moonstruck primates: Owl monkeys (Aotus) need moonlight for nocturnal activity in their natural environment, Fernández-Duque et al., PLoS One, Volume 5, Issue 9, e12572, 2010
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
