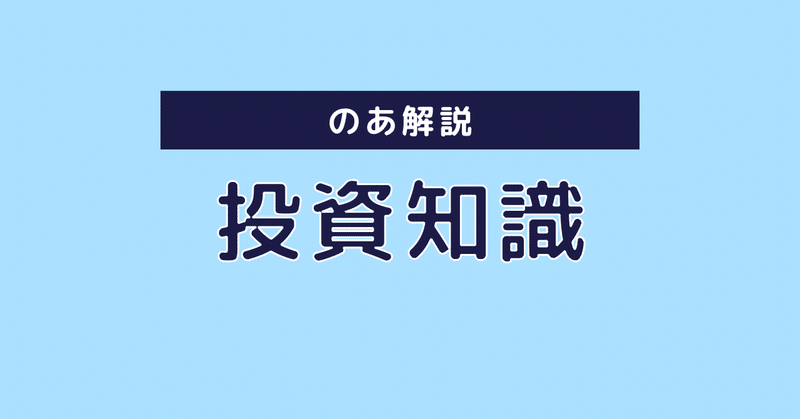
のあの米国株見通し
少し前にこちらの記事に書いた通り、私はアメリカ株よりも日本株、その中でも小型株に注目して投資しています。今回はその理由と根拠(雰囲気)と、私が思い描いている米国株のストーリーを詳しく書きます。
今回の記事は無料で最後まで読めますのでどうぞお楽しみください✨
⭐️今回の結論
私の米国株見通しは全て雰囲気です!先に言っておきますが、雰囲気でございます。
その上で今の米国株見通しは短期的には少し悲観的、中期的には強気、長期的には悲観的です。
短期・中期・長期でどのようなストーリーを考えているかを次のパートで順序立てて説明していきます。
✨短期的には少し悲観的
2024年末〜2025年秋頃まで米国株は調整局面を迎えると考えています。
まず、現在のアメリカ経済を簡単に言うと「インフレを抑えるために利上げをしているけど、なかなかインフレ率が下がらなくて株価が絶好調!」です。
FRB(=アメリカの中央銀行)は物価と賃金がとめどなく上がっていくインフレを沈静化させるために、政策金利を5.25%で据え置いています。これにより人々や企業は借金をしたくなくなって、消費行動が減退し、いずれインフレが落ち着くだろうという算段です。
しかし現在は雇用も消費も下がらず、米国経済は好調です。そのため株式市場も好調なのですが、「資産効果」により消費が下がりません。
資産効果というのは、株価が好調だと投資によってお金が増えた人が多くなって、消費意欲が高まり続けるという現象です。これによってインフレがなかなか収まりません。
しかしインフレが収まるまでFRBは政策金利を引き下げることはしないでしょうから、いずれ企業決算の数字が悪化し始めてくることでしょう。実際、METAや大手メガバンクの決算も2024年度の業績は良いものの、来期の見通しが悪いものばかりです。今朝発表されたスポーツベッティング大手で、水原一平さんで少し話題になったドラフトキングス(DKNG)も来期の売上予想がコンセンサスを下回っていました。
「ギャンブルする人の使うお金が減ってきている」というのは将来の景気見通しが暗いことを意味します。
パッとしない見通しの決算を受けて、株式市場は4月に急落しました。日本企業の決算も海外売上高が多い会社ほど株価が軟調で、逆に内需企業ほど株価が堅調です。
これは世界経済の先行きを悲観的に見ている投資家が多いことを意味しているのでしょう。
けれども、株価が下がれば逆資産効果でインフレは沈静化に向かいます。株価の下落がかえって利下げに向かわせる材料になるのです。
ここからが私が短期的に悲観的な理由ですが、これから株価の下落と共に米国経済が悪化し、次々と悪い決算が出てくる事で段階的に株価が下がっていくような気がするからです。
さらに企業業績の悪化は失業率を増加させ、人々の不満が高まります。「借金が多いのに仕事もない、政府は何やってるんだ!」と今の日本のように現政権への不満が爆発して、「トランプ大統領再選」の機運が高まります。
また2年毎の半導体サイクルのピークをそろそろ迎えます。米国株式のリーダーたるNVIDIAが下落すれば、株式市場全体が下落することになるでしょう。この傾向は今回の記事の後半に書く『ニフティフィフティ相場』に繋がります。
・米国経済の悪化
・トランプ政権再誕によるリスクオン
・半導体サイクルのピーク
これらが重なる2024年末から1年程、下落相場がやってくると思っています。
✨中期的には強気
しかし中期的には私は強気。超強気です。2026年〜2028年にかけて米国株はバブルに突入すると見ています。詳しくはこちらの記事をご覧ください。
簡単にまとめると、アメリカ株には17年サイクルがあって、2011年から2028年の17年は強気トレンドを形成します。
さらに17年サイクルの最後は歴史上必ずバブルが起きていることから、AIバブルの全盛期がやってくるのではないかなって気がするんです。
バブルというのは意外にも長続きするもので、日本のバブルは6年、ITバブルは5年、中国バブルは6年続きました。2023年から始まったAIバブルも2028年まで続いてもおかしくありません。
さらにバブルの前にはリセッション(=景気後退)が起きやすいんです。日本のバブルの前はブラックマンデーが、ITバブルの前はアジア通貨危機が起きています。このような危機が過ぎた後は『強烈な安心感』から買いが殺到してバブルに向かうのではないかと思っています。まるでコロナショックの後の株価暴騰のように。
そして2024年末〜2025年にかけての景気後退で株式市場には〝 ちょうど良い調整 〟がやってくると、いよいよ心配事が無くなったアメリカ株はバブルに突入していくでしょう。
その頃にはAIの実用化も進み、マネタイズに成功する企業が次々と表れ、「AIがマネタイズできなかったのは過去の話!これからは真のAI革命だ!」という言説が強くなり、誰もAIがバブルだと言えない雰囲気になってくると思います。
NVIDIAの時価総額は1000兆円を超えて、Microsoft、META、Googl、Amazonの株価も押し目をつけずに上昇していくでしょう。ビッグテック上位10社だけでS&P500の時価総額の50%を超えてきて、インデックス運用で年間20〜30%のリターンが得られるという「インデックスファンド全盛期」がやってくるのもこの時期だと思います。
日本の小型株に投資している私は肩身の狭い思いをして、Xのフォロワーも減少に転じるでしょう・・・
今でもそうですが、これからますます「日本の小型株はオワコン」と言われ続けると今から覚悟しておきます🥺
✨長期的には悲観的
バブルは弾け、2029年〜2046年頃まで米国株は長期停滞局面が到来。1970〜1983年頃までの『株式の死』が再来すると見ています。
その裏で日本株が大きく上昇し、今まで日の目を浴びなかった小型バリュー株に資金が集まるようになります。
2028年まで、米国株は時価総額加重平均のおかげでインデックスファンドのリターンは過去最高に良くなりますが、バブル崩壊後はその弊害が顕著に現れ、銘柄の入れ替えや株価の復活に時間がかかることで長期停滞局面が訪れると予想します。
詳しくは記事後半の『時価総額加重平均の怖さ』と『ニフティフィフティ相場』をご覧ください♪
⭐️ヘムさんのポスト
私が日本の小型株に投資を始めたきっかけでもある、ヘムさんのポストがとても興味深いです。
「S&P500(米国株)への積み立てが最適解だ‼️」についての深目の考察をしてみました。ヘムはこの考え方に少し不安を感じてしまいます。少しと言いましたが正直に言うと物凄く不安を感じています😨
— ヘム/ 配当&優待&DOE 雪だるま☃️投資 (@pygmy_hem) May 2, 2024
✅S&P500の直近のPERは25.06倍
✅直近のドル円の為替は1US$=155円
です。
それでは考察を始めます。… pic.twitter.com/OpKP1QgFwO
素晴らしいポストなので是非最後まで読んでもらたいですが、ヘムさんのポストを簡単にまとめさせていただきますと・・・
・S&P500のPERは最高値圏
・為替も34年ぶりの円安
・マグニフィセント7の合計時価総額が上場している日本の全企業の1.8倍
・何事も分散が大事
✨のあの意見は?
私もこの意見には賛同しつつも、この歪みはしばらく続くどころか、さらに拡大していくと思っています。
短期的には株価は下落するものの、2028年まではグングン上昇していくと思います。
トランプさんが大統領になったら、「俺はバイデンとは違って優秀なんだよ!」と国民にアピールするために真っ先に経済対策をしていくでしょう。
「俺は窮地に陥ったアメリカ経済を救ったヒーローだ!」と喧伝するはずです🤭
大統領による経済支援もあって、AI関連株のバブルにより、米国株は再び最強伝説が復活すると思います。
だから私は日本の小型株に投資しつつも来年は米国株に全力投資する予定です。
しかし、バブル崩壊と時価総額加重平均の弊害によって『株式の死』が訪れた過去があったことは知っておいた方がいいでしょう。
✨ニフティフィフティ相場
1960年代。アメリカの株式市場は「ニフティ(素敵な)フィフティ(50社)」相場というとても好調な上昇トレンドに沸いていました。
50社という数少ない人気成長株が指数全体を牽引し、PERを無視したバブル相場になっていました。
これは「マグニフィセント7」・「FANG+」・「S&P10」といった呼び名や投資信託が生まれている現在にとても近いです。こういう投資信託が生まれる事自体「一部の銘柄に資金が集まっている」という証拠です。
一部の超大型株が市場を牽引して2023年の相場を作ったこともニフティフィフティ相場と合致しています。
しかし、そんなニフティフィフティ相場はニクソンショックとオイルショックで呆気なく崩壊してしまいます。
ドルと金を交換できるようにしていたため信用が担保され、1ドル=360円という固定相場制ができていましたが、オイルショックによる急激なインフレで通貨価値が下がり、固定相場制を維持できなくなりました。それがニクソンショックです。
急激なインフレと急激な利上げで企業の利益が損なわれ、〝 成長株が成長できない 〟というジレンマに陥ります。
すると、〝 成長する前提で上がっていた株価 〟に疑問符がつきました。
「適正株価は今よりもっともっと下だよね?」
こうしてニフティフィフティ相場は終焉を迎えます。しかし本当の地獄はここからでした。
✨時価総額加重平均の怖さ
時価総額加重平均とは、時価総額が大きい会社の組み入れ比率を増やし、逆に小さい会社の組み入れ比率を下げるという投資信託の運用方針のことです。S&P500やTOPIXなどの有名な指数も時価総額加重平均が用いられています。
この時価総額加重平均のメリットは株式市場の平均値に投資できるという点です。
一方で、一部の時価総額が大きな企業の株価が下落したら指数全体に与える影響が大きいというデメリットもあります。
ニフティフィフティ相場は50社という数少ない人気成長株だけに資金が集まった結果、指数全体に占める割合が大きくなり過ぎました。それにより50社の株価が下落すると指数全体が値下がりしてしまい、銘柄を入れ替える際に大きな損失を出しながら入れ替わっていったために超長期停滞局面、『株式の死』がやってきました。
みなさんのポートフォリオを考えてみてください。一部の主力株が暴落した場合、その銘柄を入れ替えるとポートフォリオの資産全体に「逆複利効果」が働きます。
例えば100万円のポートフォリオを想定します。
A株50万円
B株30万円
C株20万円
合計100万円
ある時、主力のA株に−50%の暴落が起きました。するとポートフォリオはこうなります。
A株25万円
B株30万円
C株20万円
合計75万円
ここからA株をD株に入れ替えます。S&P500などはこのように下がった銘柄は入れ替えて、代わりに将来有望な株が新規採用されるという新陳代謝が行われています。
A株→D株25万円
B株30万円
C株20万円
合計75万円
入れ替えた後、D株が元々A株だった50万円まで回復するのに何%上昇が必要かわかりますか?
+100%です。
A株の下落は50%なのに、D株に求められる上昇は100%です。これでもようやく元の資産額に戻るだけです。
時価総額加重平均はリターンも最大化できる一方で、リスクも最大化していきます。ニフティフィフティの時価総額が大きくなり過ぎた結果、下落したそれらを入れ替えてから元々の株価に戻るまで大変な時間がかかってしまったんです。それが『株式の死』の正体です。
暴落のきっかけはオイルショックとニクソンショックという悲劇でしたが、『株式の死』は起こるべくして起こった運命だと思います。
私は2028年にかけて真の意味でのAIバブルになると予想しています。NVIDIAの時価総額が1000兆円を超えて、メガテック企業の株価が大幅に上昇します。
その恩恵を最大限に受けるのが時価総額加重平均を採用するインデックスファンドです。しかしバブル崩壊後は、失った時価総額を取り戻すために膨大な時間がかかると思います。一部の銘柄に資金が集まって人気化すればするほど、時価総額が大きくなればなるほど、回復するまでに時間がかかってしまいます。
現在、「時価総額加重平均は均等加重平均よりも優秀だ」という言説が強くなっています。Xを見ても均等加重平均ETF(SPYDやFANG+)はバカにされていますし、均等加重平均がデメリットと言われています。実際に過去15年のリターンを見ると均等加重平均よりも時価総額加重平均の方がリターンが良かったので、そう思ってしまうのも無理はありません。
しかしこのような意見が強くなればなるほど、潜在的なリスクは掻き消され、人々は盲目的になり、暴落の後に起こる本当の悲劇を知る機会を失います。
株式の死が訪れた時、投資家は米国株に見切りをつけて損切りし、資金退避先として日本株が選ばれることでしょう。
ここに書いたことは全て私の妄想です。
なんなら今書いてる小説のネタバレも入ってるんですけど😂
これが今の私の米国株見通しです!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
