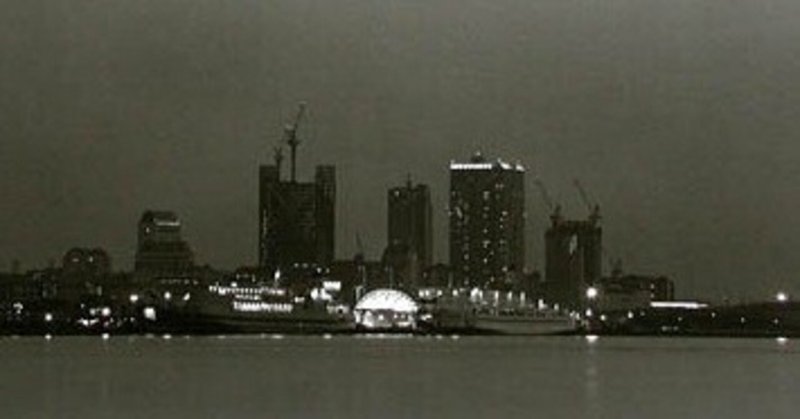
(仮)トレンディ電子文 第28回:Tsudio Studio「My Room」
北に紫色の山々がつらなり、そこから碧い海の方へ一帯にひろがっている斜面にある都市、それはあなたがよく承知の、あなたのお兄様のいらっしゃる神戸市です。そう云えばあなたはいつか汽車で通ったとき、山手の高い所にならんでいる赤やみどりや白の家々を車窓からながめて、まるでおもちゃの街のようだ、といったことがありましたね。それから、あの港から旅行に出かけた折、汽船の甲板から見るその都会の夜景が、全体きらきらとまばたく燈火にイルミネートされて、それがどんなにきれいであったかについても、あなたはかつて語りました。
そう、かつて語ったのだ。Tsudio Studio新譜のリード曲「My Room」のPVは神戸の青空のカットから始まり、当人の一日が何ともコミカルに描かれるのだが、そこに誰かとの対話や雑踏などとの交わりが無いことに自分は先ずいたく感銘を受けたのだった。かつて語った人の不在、がこのPVには(ぬいぐるみとトランプしたりとひじょうに自足しているにも関わらず)確かな感触としてある。あの子やあいつはいったいどこへ消えたのか?それはひょっとしたら過去へ。しかしその種のありきたりな感傷一辺倒へとこのアルバムは連れて行きはしない。むしろ現在への楽観主義が、デスクトップの奥から発光しつつ楽曲のそこかしこに散りばめられている。件のぬいぐるみや「Moo Moo Land」という楽曲など、どうも動物モチーフには殊にそうした楽観が顕れているような気もするのだが、それは例えば喪失=死を知らない生き物としての動物への生成変化志向(?)があるのか。そういえばこのぬいぐるみや「Moo Moo Land」の牛や猫は「元人間」という感じが無くもない。かつて人間だった、それらの無性にタイニィな記憶…
ところで、神戸のことだ。「そこには、わたしたちの思い出がしみついているんです……個人的な、他人には関係のない思い出ですけど、それだってやはり土地の霊には変わりないでしょう」このCDの裏ジャケには「lost City lost paradiso」と印字されている。デビュー盤のタイトルが「Port Island」であったことからもちろん震災を思い起こしもするそのlostには、この土地の記憶や名前、かつてこの土地に生きた人々のことが込められているに違いないのだが、しかしこのアルバムは「場所」という定義づけがどうしても付加してしまうある種の封じ込め(例えば同じ港町である横浜のミュージシャンによくあるレぺゼン感のような、その土地の太鼓判を押された「地場産」的な身振り)を、不思議と免れている。その軽やかな"抜け"の一要素として、ヴェイパーウェイブ以降の「オンラインネイティヴ」と言っていい環境下でTsudio Studio名義でのキャリアがスタートしたという点はもちろんある。あるのだが、しかし何より新型コロナウイルス禍の「デジタルテクノロジーを介した」生活様式にこそ、そうした開かれの契機があったようにも思えるのだ。土地の記憶や日々の営みを媒介とした「新しい生活様式」ハッキング。言い換えると、このアルバムの中で立ち昇る「lost city」感覚は(それをほぼメイン・テーマに据えたと言っていいデビュー作「Port Island」よりも)遥かに「動的」なものとして聴くことができるのだ。「My Room」に招かれたゲスト・ミュージシャン達の、決して「部屋」の世界を強調することのない方向での闊達さもその表れだろうし、彼らが参加したTrip楽曲群は「旅」をテーマに据えた前作「Soda Resort Journey」よりも不思議と飛距離のようなものを実感できる。このアルバムの旅は「自分の記憶の中の砂漠の探訪」といったような、「場所」に縛られることのない(身動きの取れなさを逆手に取った)自由さがある。ヴェイパーウェイヴというオンラインの重層の靄をくぐりぬけて歩みを進めてきたこれまでのキャリアから、それは必然的に導かれるものだったのだのだろう。
そうした稀有な開かれのある「空間」性を形にできたのはしかし固有のトポスである"lost city"、神戸の持つ神通力の賜物ではあるのかもしれない(先の引用、稲垣足穂の大正時代からこの地には「場所」の軛をくぐりぬけていくファンタシウムがあるのだから…)そしてそこに対置する場所となると、やはり東京になるのだろうか。思い出したのが昨年のドラマ「大豆田とわ子と三人の元夫」中のとっておきの"記名地帯"として代々木八幡を執拗に使っていたことで、その画面には「権力装置」として身動きの取れなくなった、特権性に担保を置こうとしつつその実(同じ山手通り沿いの)東中野とさして面貌の変わらない「場所」が、無残に刻み付けられていたのだった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
