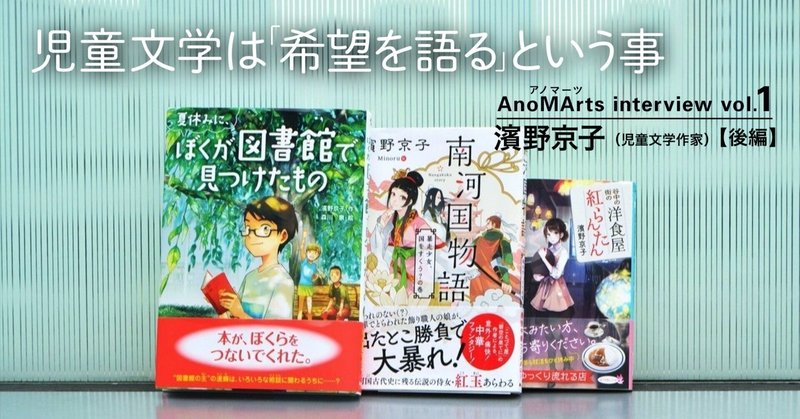
児童文学は「希望を語る」という事|濱野京子(児童文学作家)さん【後編】子どもの本のインタビューvol.1
オチャノマート(OCHANOMART)インタビュー
「子どもの本のインタビュー」vol.1

この度こちらの記事では、子どもの本に関わる様々な方のインタビューを紹介していきたいと思っています。2020年の始まりは、児童文学作家の濱野京子さんの後編です。児童文学を志したきっかけや、影響を受けた本、児童書への向き合い方、子供たちに伝えたい思いなど貴重なお話を聞かせていただきました。
【前編はこちら】
子どもの居場所としての図書館
●それでは『夏休みに、ぼくが図書館で見つけたもの』ですが、こちらは図書館が舞台のお話ですが、濱野さんには図書館の思い出はありますか?
ありますよ。私の子どもの頃には図書館が少なくて、私が育った板橋区には二つしかなかったんです(現在は11館)。たまたま、そのうちの一つが私の小学校の隣にあった。そこは板の間で、なんと靴を脱いで入るんです。漫画雑誌も置いてありました。学校の帰りにしょっちゅう寄って、『小公女』など古典的な世界の名作を読んだ記憶があります。
今回の作品を書くにあたって図書館の役割みたいなことを考えたんですよね。「学校が始まるのが死ぬほどつらい子は、学校を休んで図書館へいらっしゃい」というツイートが話題になったことがあります。それを担当の編集者から教えてもらって。不登校の子どもでも、とりあえず行ったら落ち着くみたいな、居場所としての図書館を考えました。不登校の子どもが保健室登校する話は前からよく聞いてましたが、そういう子どもの居場所って大事ですよね。子ども食堂なども増えてきていますけど。関係性が断ち切れがちな社会になってしまったので、それをつなぐ場所が必要なんですよね。
取材協力させてもらった三芳町の図書館がとても面白いんですよ。本に出てくるアリスクラブはここの活動がモデルです。地域の子ども達の居場所にもなっている感じが伝わってきます。

●今回は、不登校以外にも、シングルファザーだったり、家庭環境が違う子どもたちが登場しましたが、どのようなメッセージがあったのでしょうか?
いろんな立場の子どもが登場するということは意識しています。貧困問題も切実でしょうし、外国ルーツの子どもも物語の中に登場させたい。それをテーマにして大きく取り上げるのではなく、違った家庭環境の子どもがいるのが当たり前、という風に書きたいです。 時代とともに家族像も変わり、何十年も前ですと、お母さん=専業主婦みたいなものが多かった気がしますが、今 は変化しています。むしろ、シングル・マザーや、シングル・ファザーがあたりまえのように登場して、それも一面どうなのかな、という気がします。ただ、多様性は大事です。
●外国のアニメや映画では、主人公がステップファミリーだったり、お父さんとお母さんが違う人種だったりすることが多いですよね。でもそれがテーマではなくて、お話は普通の冒険物語だったり。家族の形の多様性が当たり前に描かれているのがすごいですよね。
ところで、児童書は「絵」がとても大事な要素ですが、イラストレーターの方とは どのように本を作っていくのですか?
絵に関しては編集者さんにだいたいおまかせしています。『夏休みに、ぼくが図書館で見つけたもの』は森川泉さんの絵がすごくいいですよね。とても面白い構図や、全然違うタッチで、登場人物の母親が描いた絵、という設定の油絵風のタッチの絵を描いてくれました。他にも一枚の絵で時間経過を感じさせる絵など、いろんなことにチャレンジしてくれています。
世の中は多様だよって言いたい
●どういうきっかけで小説を書き始めたのでしょうか。
小学校のクラブ活動で文芸部というのがあって、そこで小学校6年生の時に初めてお話しを書いたんです。中学生、高校生の頃もそれなりに書いてはいたんですが。20代、30代はずっと書きたい書きたいと思いながら、仕事などもあり遠ざかってしまい……。40代になって、このまま仕事だけやっていても面白くないと感じ始めたんです。
そんな時、自分の育った小学校のすぐそばに引っ越した事がありました。その時に子どもの頃を思い出したら、物語を書く事も思い出したんです。それからもう一度やってみようかなと思って。だから、私はデビューが遅かったんです。純文学は若い時にデビューする方が多いですけれど、児童文学の場合はある程度歳をとっている方でもデビューされている人もたくさんいます。
とはいっても、初めから児童文学をやろうと思ってたわけではないんです。当時、たまたま思いついたのが10代半ばの子が主人公のお話で、それを児童文学の公募に出したら2次選考くらいまで行きました。児童文学との関わりはそこからですね。知り合いの作家さんでも、小さい頃から童話作家になりたかった、という人もいます けど私の場合は違うんです。ただ、児童文学と関わってよかったのは「希望を語る」という事に親和性があるジャンルだった事ですね。
●読者にオススメの一冊を選ぶとしたらどんな本がありますか?
好きな本は沢山あって、一冊というのは難しいですね。児童文学とは関係ないですが、『自由からの逃走』 (エーリッヒ・フロム/著)は若い時に読んで影響をうけました。『チボー家の人々』(ロジェ・マルタン・デュ・ガール/著)も好きです。また、日本の作家で好きなのは夏目漱石です。同時代の作家では多和田葉子さんがすごく好き。児童文学では、五年の教科書にのっていた『たまむしのずしの物語』が好きでした。子ども向けだけど哲学的だったんですよね。相対的な見方をすることの原点です。
そのほかに子どもの頃好きだったのは『雪の女王』。『アナと雪の女王』の原作ですね。『アナ雪』は見ていませんが、内容は原作とずいぶん違うようですね。女の子が活躍するお話が好きだったんです。小学生の高学年の頃、『ナルニア国物語』が翻訳された少し後で、人気がありました。『ゲド戦記』は大人になってハマりました。他には森達也さんや、社会問題や戦争を取材しているジャーナリストなどのノンフィク ションもよく読みます。
●「子どもの本・九条の会」※1 に入られていますが、どのような思いで入ったのでしょうか?
「子どもの本・九条の会」はその呼びかけ人に、松谷みよこさん、古田足日さんなどそうそうたるメンバーがいらっしゃいました。九条には憲法の象徴的な意味合いがあって、大切な条項ですが、私は9条よりも人権条項と思っています。個人の尊重です(11・12・13条)。基本的人権の尊重が徹底されたら戦争はありえない。「<公共>の福祉」って言葉が、「<公益>及び公の秩序」、という言葉にすり替えられてしまって人権が保証されなくなってしまってはいけないですよね。
●「新しい戦争児童文学委員会」の<文学のピースウォーク>※2 という活動で『すべては平和のために』(新日本出版社)という作品を書かれていますよね。
戦後70年以上たって、戦争は良くないというのをちゃんと伝えていくという意識が弱くなったのでしょうか。戦争はダメっていうのは、私が若い頃はかなり共通の感覚だったと思うんですけど。最近、こんなにも、近隣の国との関係が悪くなっているのは、被害感情だけじゃなくて自分達がひどい事をしてきたという加害の事実に向き合ってこなかったからではないでしょうか。加害に向き合うのはつらいけど、そっちの方が本当はいさぎよいし、勇気がいることだと思うんですけどね。

●作品をとおして、子どもたちに伝えたいことはありますか?
人間は生き直せるってことですかね、いつも頭にあるのは。やり直しができるっていうのは大事ですよね。若い時はこれがダメだったら行き止まりって思いがちですけど、そんな事はない。
大人になる事を恐れるな、ということも言いたいです。大丈夫だよ、なんとかやれるからって。ただ、現在ではこのことを少し言いづらい気もしているんです。これからの時代を考えたらそんなに簡単に、大丈夫だよって言えないという気持ちもあるので。
それでも、人には希望が必要です。遠くの方にぽつんとある明かりのようなイメージで希望を語りたい。遠くて小さいけれどそこを目指して歩いて行ける道しるべというか。薔薇色じゃない。実際、つらいことやキツイことも多いですから。それでも光はある、と。
●若い時や学生時代のほうが、見ている世界も小さいし、学校のスクールカーストや同調圧力に押しつぶされて、息苦しさを感じるかもしれませんね。社会に出たほうが、嫌な事から逃げられるし、世界は広がりますよね。
学生時代をなんとかやり過ごして、大人になればもう少し自分で選べるようになるよとは、伝えたいです。数年我慢して学校行きなさいっていうんじゃなくて、そのうち状況変わるよって。それで終わりじゃないから。世の中は多様だよってことですね。いろんな人がいて、いろんな人生があっていい。多様さを示すのも、子どもの本の役割かなって思うんです。
聞き手・写真/水木志朗

濱野京子
熊本県に生まれ、埼玉県在住。『フュージョン』でJBBY賞、『トーキョー・クロスロード』で坪田譲治文学賞を受賞。主な作品に『この川のむこうに君がいる』(2019年度 青少年読書感想文コンクール課題図書)、『石を抱くエイリアン』『ドリーム・プロジェクト』ほか、「レガッタ! 」シリーズ、「ことづて屋」シリーズなど。
※1 子どもの本・九条の会
子どもの本の関係者が「平和あっての子どもの本」を合言葉に、2008年4月に設立した会です。憲法9条を守り抜く思いを広げ、深める活動を重ね、今年で11年目となります。(2019年「戦争と平和を考える子どもの本展」チラシより引用)
※2 文学のピースウオーク
2003年の秋、日本政府が自衛隊のイラク派遣を決めた直後に、日本児童文学者協会は「新しい戦争児童文学」委員会を発足させました。委員会では、作品の募集や合評会などを重ね、それらは短編アンソロジー<おはなしのピースウォーク>全六巻(2006年〜2008年)として結実しました。その後、「新しい<長編>戦争児童文学」の募集を開始し、やはり合評を重ねこのたび完成したのが長編作品による<文学のピースウォーク>(全六巻)です。(『すべては平和のために』より引用)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
