2005年地学A(固体地球分野)


問1で、(ア)では、オゾン層で遮られる生物に有害なものは紫外線。(イ)で原始大気に大量に含まれていて海水に溶けて海底に固定されたものは二酸化炭素。よって答えは2。
問2で、オゾン層は成層圏では下の方。よって答えは3。ちなみに対流圏は11kmくらいまでで、成層圏はその上。
問3で、オゾン層の破壊が顕著に起きているのは極域。よって1は×。オゾン層破壊の原因は熱帯雨林の減少ではない。2は×。地球上の雪氷面積が減ると太陽放射の反射率が減り温暖化が加速する。3は×。火山灰が大気上空に広がり太陽放射を遮って寒冷化したことがある。4は○。よって答えは4。
雪氷には温暖化の「抑止力」としての役割がある。地球は太陽からの放射エネルギーの約7割を吸収して3割を大気圏外に反射している。つまり、地球の反射率(これをアルベドといいます。)は30%。残りの70%の太陽放射エネルギーは地中および大気や雲に吸収されている。ところで、地球の約7割を占める海の反射率はおおむね10%以下、農地や森林などの陸域の反射率も30%以下。にもかかわらず、地球全体の反射率を30%まで引き上げているのが雪氷や雲の存在。雪氷は状態にもよるが、30%から90%の高い反射率を持っており、地球全体の反射率を高める役割を果たしている。ところが、一旦、温暖化が進み、雪氷域が融解していくと、地球の反射率が低下し、地球表面における太陽放射エネルギーの吸収が増加し、さらに温暖化を加速させることになる。この現象を雪氷アルベドフィードバック(ice albedo feedback)という。こうしたメカニズムがあるからこそ、私たちは地球の雪氷の分布状況の変化を慎重に見守っていく必要がある。(http://www.tric.u-tokai.ac.jp/rsite/r2/kodou/kodou30j.html より)


問1で、大陸棚について。この図では200mより浅い部分が大陸棚になる。(世界の大陸棚の平均値は−130m〜−140mと 報告されているものが多い)よって1は×。大陸斜面は200mから4000mくらいまで続いている。この水平距離がだいたい100㎞くらい。斜面30度は深さ1:水平距離2になるから圧倒的に緩いとわかる。2も×。海底谷の谷壁の深さは等高線間隔が1000mなので20mでは表現されない。よって3も×。深海底に相当するのは、陸から見て海溝の外。よってここは5000mだから、4は○。
問2で、海底谷とは、海底の大陸斜面に存在する渓谷である。海底谷は一般に大陸からの大河川の延長として海底へ連続的に伸び、最大距離数百km深度1kmに及ぶ。よって1は×。2も×。4も×。よって答えは3。
問3で、山のような地形だとわかる。これは海山。答えは1。

https://www1.kaiho.mlit.go.jp/KAIYO/tairiku/20081031_css_conclusion.pdf より

問4で、セメントの材料になるのは石灰岩。よって答えは1。
問5で、石灰岩は生物の殻や骨格が堆積したもの。火山性ではないので2か4を選ぶ。珪藻ではないので4。よって答えは4。
問6で、誤っているもの。御影石は花崗岩。よって1は×。答えは1。



問7で、コランダム、正長石、タルクの硬さを考える。研磨剤なのだからコランダムは硬いはず。タルクはかなり柔らかい。よって答えは3。
問8で、多形は化学組成が同じもの。ダイヤモンドは炭素Cでできているがカオリンの化学組成は Al4Si4O10(OH)8。構造は層状ではない。ダイヤモンドはキンバリー岩に含まれている。高温高圧でできるので、低温高圧の変成帯では見つかっていない。よって答えは3。

ウィキペディアより
問9で、水晶はSiO2。1はコランダム。4もコランダム。3の結晶面角は90度ではない。よって答えは2。光ファイバーの材料は石英ガラスが多い。

https://www.gsj.jp/Muse/hyohon/mineral/m14493.html



問1で、石油鉱床について。日本では秋田から新潟にかけて産出するが、新生代の地層からである。世界の主流は中生代の地層である。石油鉱床には背斜構造が必要。天然ガスは石油が気体になったものではない。石油は生物の遺骸が堆積したもの。よって答えは4。

https://www.eneos.co.jp/binran/part01/chapter01/section02.html
問2で、まず1960年レベルでは、埋蔵量305を1年に8ずつ採掘するとして可採年は38年。同様に1995年レベルでは、埋蔵量1017を1年に23.8ずつ採掘するとして可採年は42年。ゆえに、こうなっているグラフは2。
問3で、間違っているものを選ぶ。(1)は1990年には原子力が10%を占めている。○。(2)は、石油で1970年代に75%でその後50%になるのは○。(3)で天然ガスが増えている。○。(4)で、新エネルギーはまだ少ない。よって×。答えは4。


問4で、鉱床の生成温度。高い順に正マグマ、(ア)、接触交代、(イ)、堆積作用の鉱床(ウ)を選ぶ。まず、設問に出てくるのが、ペグマタイト鉱床、熱水鉱床、残留鉱床の3つ。このうち、堆積鉱床は、マグマ性鉱床ではないものだから、残留鉱床と思う。すると、ウを残留鉱床として、候補は2か5。熱水鉱床は海底に熱水が噴き出すものだから、マグマの冷却過程にあるペグマタイトより低温。ゆえに答えは5を選ぶ。
問5で、正マグマ鉱床は、苦鉄質に富むマグマの結晶分化および固化に伴って生成されたもの。マグマだまり中において結晶分化作用の比較的初期に生成される。この鉱床においては白金族元素のほか、クロム、銅、ニッケル、チタン、バナジウムなどが産出される。よって答えは4。
問6で、接触交代(スカルン)鉱床は、銅,鉛,亜鉛といった有用金属が濃集している。スカルンはマグマが石灰岩に接触し,マグマの成分(ケイ素,鉄,アルミニウムなど)が 石灰岩の成分(カルシウム)と反応してできた,カルシウムやケイ素などを主成分とするスカルン鉱物と呼ばれる各種の鉱物の集合体である。よって答えは3。


問7で(エ)はリモートセンシングという。(オ)は、ランドサットは極軌道にあって地球が自転することにより全地球をカバーできる。(カ)は、気象衛星ひまわりは赤道上の静止軌道にいる。よって答えは3。
「極軌道」とは軌道傾斜角が90度、もしくはこれに近い角度の軌道のことをいう。衛星が軌道を周回しているあいだ、地球が自転するため、北極・南極を含め、数日後には地球全体をカバーすることができまる。そのため、全地球の観測に適しており、多くの地球観測衛星は極軌道、あるいは極軌道に近い軌道に投入されている。一方、気象衛星のひまわりは、地上からつねに静止して見える、「静止軌道」の衛星である。「静止軌道」とは、軌道傾斜角度0度、つまり、赤道上空の高度約36,000kmの円軌道を毎秒約3kmの速度で周回する軌道のこと。衛星の周期は、地球の自転周期と同じ約24時間なので、地上から見るとつねに静止しているように見える。そのため「静止衛星」といわれる。気象衛星や放送衛星など、広く利用されている。(https://www.weblio.jp/content/%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E8%A1%9B%E6%98%9F%E3%81%AE%E4%BB%A3%E8%A1%A8%E7%9A%84%E3%81%AA%E8%BB%8C%E9%81%93)
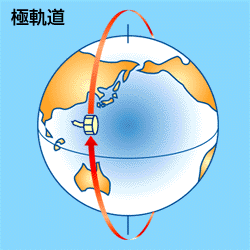

問8で、周期は、低い方が短い。1は×。静止するためには地球の自転と周期を合わせるからいろいろな高さということはない。2は×。観測はいろいろな波長を拾うセンサーを搭載して行う。3は○。画像解像度はセンサーの性能による。https://www.eorc.jaxa.jp/rs_knowledge/mecha_resolution.html などでは数mの解像度の画像が紹介されている。4は×。
地球を 1 周する時間「周期」
人工衛星が地球を 1 周する時間を「周期」という。周期は高度や軌道の形(円・楕円)によって変わる。円軌道の場合、高度が低いほど周期は短く、高くなるほど周期が長くなる。(http://www.yac-j.com/labo/list/pdf/2.Satellite/2-2.pdf より)
問9で、ランドサットの可視画像について。可視画像なので温度は見ない。なんとなく形状から白いものは川。川から海へ水を含んだものが出て行っていると思う。答えは4。

JAXAウェブサイトより:http://www.sapc.jaxa.jp/use/data_view/


問1で、温度が下がって発泡するガスは二酸化炭素。(ぬるくなったサイダーはあまりぷつぷつしないことを考えるとわかる。)よって答えは3。
問2で比較的穏やかにマグマで出てくるのは溶岩流。よって答えは3。
問3で爆発的な噴火をするのは流紋岩質マグマ。これは粘性が大きいため。ゆえに答えは3。

問4で、(b)は南海地震、(c)は自動的に濃尾地震、となり、答えは2。
問5で、誤ったものを選ぶ。1は単性火山のこと。○。2も○。3は、内陸性地震の周期はもっと長いので×。4は○。よって答えは3。

問6で、プレートの境界で起きる地震は震源が浅ければ津波被害をもたらす。よって1は×。建物の倒壊被害は沖積地が多い。2は○。死者数は場合による。3は×。余震も大きな被害が出る。4は×。よって答えは2。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
