2008年地学1(固体地球分野)

問1の答え:3
海底の生成されるところ→海嶺、大陸プレートの下に沈み込むところ→海溝
ホットスポット→プレートより下のマントルに生成源があると推定されるマグマが吹きあがってくる場所若しくはマグマが吹きあがってくるために(海底)火山が生まれる場所のことをいう。代表:ハワイ島、タヒチ島
トランスフォーム断層→プレート境界において生成される横ずれ状の断層のことである。代表:サンアンドレアス断層

問2の答え:2
海溝型地震の原因(http://www.hinet.bosai.go.jp/about_earthquake/part1.html)

プレートが跳ね上がることによって起きる。海溝型巨大地震の発生するメカニズムを模式的に示す。上段では、沈み込む海洋プレートと陸側プレートとがボルトでとめられているように描かれているが、実際には摩擦力によって固着した状態となっている。この状態がどんどん進行して、蓄えられた歪エネルギーがある限界を超えると、摩擦力よりも,元に戻ろうとする反発力が勝って、同図下段のようにボルトを断ち切り、陸側のプレートが跳ね返ることにより、大地震の発生となる。このような跳ね返りは急激に生じるため、その際の強い震動が地表に伝わって被害をもたらすと同時に、断層運動による海底の隆起によって持ち上げられた海水が、津波となって沿岸に押し寄せることになる。

問3の答え:4
深発地震について(http://www.hinet.bosai.go.jp/about_earthquake/part2.html)
深さ100km を越えると普通は温度と圧力が高くなって地震が起きにくくなる。しかし、実際は日本列島のような島孤、またはそれに準ずる構造の地域で深い地震が見られる。その深い地震が起きている面は深発地震面と呼ばれプレートの沈み込み面を表す。これを発見者に因んで和達ーベニオフ(帯)ともいう。

沈み込む海洋性プレートに関連して発生する地震には、境界面で起きる地震のほかにプレート内部で破断を生じるようなタイプの地震がある。沈み込んだプレートはスラブと呼ばれるため、このような地震のことを「スラブ内地震」と言いう。東北地方における震源断面図に見られたような、深発地震の二重面に沿って常時発生している中小の地震は、すべて沈み込むプレートの内部で発生している「スラブ内地震」である。中央海嶺の下は浅い地震。日本海の真下まで太平洋プレートは入り込んでいるので深い地震は起こる。家屋に対して地震の被害を考えると浅い地震の方がエネルギーが減らないので被害は大きい。直下型地震はマグニチュードの割に震度が大きく被害が大きい。

問4の答え:1
試験問題は、深さ17km の地震で震源の真上の地震計という設定。ここから(1)真下から来ている波なのでP波は上下動、S波は水平動になる。(2)まっすぐ上に進む。17km÷5km/秒=3.4 秒、17km÷3km/秒=5.6 秒。到達時間差は5.6-3.4=2.2 秒。この2つから答えは1.
*
地震の記録(http://www.okinawajma.go.jp/ishigaki/school/200301/jisin01.htm)

地震の振動の方向は立体的なので、水平2 成分(南北・東西)と上下の3つの成分の動きに分解して、地震計で記録する。
P波:最初に来る波(Primary-Wave)を略してP 波。進行方向に平行に振動する。速度は岩盤中で5~7km/秒.
S波:次に来る波(Secondary-Wave)を略してS 波。進行方向と直角に振動する。固体を伝わる。 速度は岩盤中で3~4km/秒、P 波に続いて到達
P波の揺れの始まりからS波の揺れの始まりの間の揺れを初期微動といい、S波による大きな揺れを主要動という。初期微動の時間(初期微動継続時間)が長いほど、震源までの距離が遠くなる。
P 波・S 波を「縦波」・「横波」と呼ぶことがあるが、あくまでも進行方向に対しての縦横であり、P 波で家が上下に揺れる、あるいはS 波で家が左右に揺れるとは限らない。
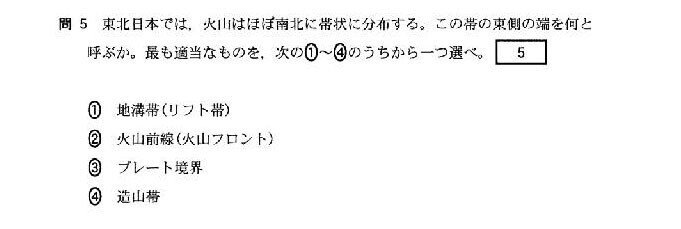
問5の答え:2
火山フロント(http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/whitep/2-4.html)

陸のプレートの下に沈み込んだ海のプレートからの水の働きによって上部マントルの一部が融けて上昇していき、マグマが形成される。このような過程でいったんマグマだまりに蓄えられるなど様々な作用を受けて地表に噴出し、これが海溝沿いの火山となる。したがって、海溝にほぼ平行に火山が分布することとなり、この火山分布の海溝側の境界を画する線を火山フロントという。一般に火山フロント付近に火山が密集している。

答え:3
アセノスフェア(図中5の層)
1は地殻、2はマントル、3aは外核、3bは内核、4はリソスフ
ェア、5はアセノスフェア。
アセノスフェア(asthenosphere)とは、地球のマントルを力学的性
質で分類したうち、リソスフェア(プレート)とメソスフェアの間
の部分。上部マントル中に位置し、深度100km~300km の間にある。
地震波の低速度域であり、物質が部分溶融し、流動性を有している。
低速度域のみがアセノスフェアとされるが、場合によっては下限を660km の面と考える説もある。マントル構成層であり、主要組成はかんらん岩で鉱物相もかんらん石(α 相)である。電気伝導性、電流異方性を示す。
モホロビチッチ不連続面は地殻とマントルの境界
海洋プレートの厚さは約100km



答え:4
ケイ酸塩鉱物:ケイ酸塩鉱物だけで、地殻中の鉱物の90%近くを占める。教科書の鉱物では長石(斜長石、カリ長石)、石英、輝石、角閃石など、である。違うのは方解石。組成は炭酸カルシウム(CaCO3)。(こういうとき違うやつを覚えた方が早い)


答え:2
SiO4 というのだから、基本セットはSiが1つ、Oが4つ。2個セットの時はOの2個がダブり。よってSiが2個、Oが6個。


答え:3
表1 を見ると、SiO2 が60.18%とある。下の図によれば、この値は中性岩ということになる。
だからこの中では安山岩。



答え:2
おおまかにSiO2 が60%、Al2O3 が16%、とする。
Si が28、O2 が16*2=32 であることより、60%を28:32 で分ける。
Si は全体の0.6*7/15=0.28、O は0.6*8/15=0.32
Al が27*2=54、O3 が16*3=48 であることより、16%を54:48 で分ける。
Al は全体の0.16*9/17=0.08、O は0.16*8/17=0.075
この段階で、Al(0.08)<Si(0.28)<O(0.32+0.075=0.395)
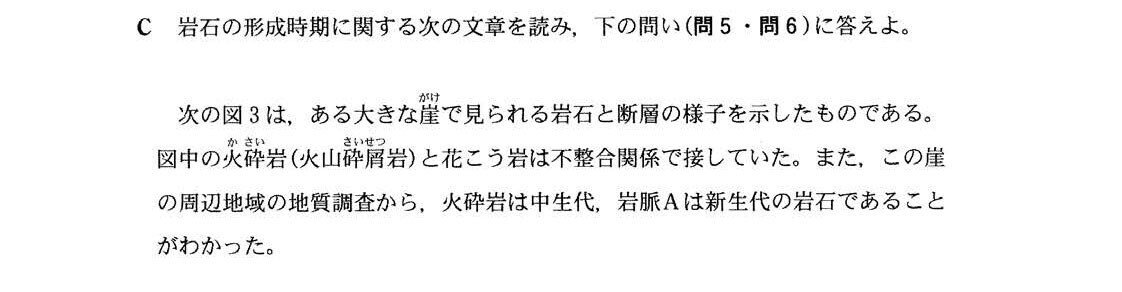

答え:2
1. 何からも切られていないのが一番新しい→岩脈A(新生代)
2. 断層は岩脈A以外すべてを切っている→2 番目に新しい
3. 岩脈Bは火砕岩(中生代)を切っている→岩脈Bが新しい。
4. 火砕岩は不整合で花崗岩の上。花崗岩が古い。
5. よって、以上から、花崗岩→火砕岩→岩脈B→断層→岩脈A


答え:3
年代測定:14C は土壌か石灰岩等に使う。よって残りは3.
代表的な半減期14C:5730 年
Rb→Sr:4.75×10^10 年
40K→40Ar:12.5×10^8 年


答え:3
地質図の地質境界を表す線が曲がっている→一定の傾斜角を持って平行に重なっているが地形に起伏があるとこうなる。
地質図の地質境界を表す線が等高線と平行→水平に地層が重なっている。

答え:2
斜交層理(斜交葉理、クロスラミナ、cross-bedding)←河床の砂岩層だからこれが答え
水流や風の速さ、向きが変化する環境で堆積が起こったときにできる、層理面と斜交した細かな縞模様である。当時の水流などの方向が推定できる。
漣痕(砂紋、リップルマーク、ripple mark):水底に波が形成した模様が残ったものである。堆積した当時の上方に尖った形で残るため、上下判定に役立つ。
片理 :高い圧力で変成した結晶片岩にみられる構造で、雲母、緑泥岩、滑石のような鱗片状鉱物、角閃石、陽起石のような長柱状鉱物が平行に発達することにより、一方向にはがれやすくなっている。
へき開は鉱物にみられ、片理は結晶片岩という変成岩にみられるもの。
モレーン:モレーン(moraine、堆石)とは、氷河が谷を削りながら時間をかけて流れる時、削り取られた岩石・岩屑や土砂などが土手のように堆積した地形。
級化成層(級化層理、級化構造、graded bedding):構成粒子が、下部が粗粒で、上部に向かうにつれて連続的に細粒へと変化している単層のことである。時間とともに粒子を運搬する水流が弱まった場合や、乱泥流によって運ばれた粒子が堆積した場合に生じる。粗粒のほうが堆積した時点での下部だと分かるため、もともとの地層の上下方向を決めるのに役立つ。
スランプ構造(スランピング、slumping structure):海底などに堆積した堆積物が、固化していないうちに海底などの斜面を滑り落ち、不規則に乱堆積してできたものをいう。
底痕(ソールマーク、sole mark):堆積粒子や水流そのものにより堆積物表面につけられた溝が、その上に堆積した砂礫によって充填されたもの。特にタービダイトのように泥層上に砂礫が堆積する際に形成されたものは、露頭では差別侵食のために観察しやすく、古流向を知る手がかりとして役立つ。
化石層(fossil bed):水流などにより、化石が掃き寄せられて密集したものをいう。貝殻はよく化石層を形成している。
砂管(サンドパイプ、sand pipe):海底の砂の中に生息していた動物が作った巣穴の跡である。巣穴の最上部は当時の海底で、巣が掘られている方向が当時の下だと推定できる。


答え:2
火山灰の粒を実体顕微鏡で見るのにすりつぶしてはいけない。


答え:2
柱状節理(ちゅうじょうせつり、columnar joint)は岩体が柱状になった節理。六角柱状のものが多いが、五角柱状や四角柱状のものもある。玄武岩質の岩石によく見られ、マグマの冷却面と垂直に発達する。
玄武岩→斑状組織、黒っぽいから輝石、かんらん石。(第2問 問3 の解答を参照)

答え:1
Aでフズリナ→石灰岩は古生代(石炭紀~ペルム紀)
Bでビカリヤ→砂岩は第三紀中新世
Eでカヘイ石(ヌンムリテス)→未区分:第三紀漸新世
Fは黒い火成岩がコンターと平行→水平に堆積
古い順ではA、B、E
地質断面を考える。
・まず調査済みのX'側から。石灰岩、火成岩、砂岩はある一定の傾斜を持って平行に重なっている。→問1参照 。ここで候補は1か4.
・Dと東側の火山灰層が同一だとすれば、石灰岩、礫岩、砂岩、火山灰、砂岩という、地層の繰り返しも同じと考えて、1.

答え:4
等高線から西側は、川より山地なので下流の礫はとりあえずおいておく。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
