
STUDY:シティポップとは何だったのか?第1回
インド渡航を明日に控えた人のnoteではないのは分かっている。
インドに行って何かを喪失しそうな、もう以前の自分に帰れないような気がしてならなかったので、以前の自分がずっと考えてきたテーマを完結させてやろうじゃないかと、この一週間ひたすら机に向かって書き上げた文章。シティポップー。その言葉にとらわれてきた半年間、これを書くことで、自分の中のブームを終結させようとしていた、が…より悪化してしまったのは言うまでもない。ということで、この一週間の短期研究の成果をここに提示したいと思います。
シティ・ポップ (City pop) は、日本のポピュラー音楽のジャンルのひとつ。 正式な音楽用語ではないが、主に1970年代後半から1980年代に流行した、都会的なイメージを前面に出したポップスを指す。ーwikipedia
シティポップとは何だったのか?
―イメージが作り出した虚構の都市のサウンド―
シティポップ―。音楽好きのあなたには分かるだろうか。そして、その言葉を聞いて何を想像するか。きらびやかな摩天楼、夜のハイウェイ、白いタキシードにワイングラス、真っ赤な車にマーティーニ、それかもしくは、ヤシの木とビーチにサンセット?これらのイメージとは裏腹に、シティポップの曲を思い浮かべるのは難しい。聞いてみて、「ああこれはシティポップだね」と頷くことが多い。さて、一体シティポップとは何だったのだろうか。
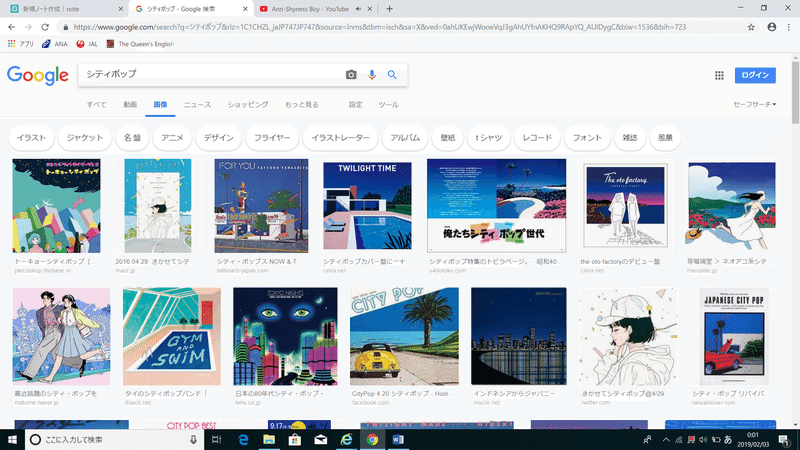
その言葉がリバイバルしてから少し経つ。昨年のsuchmosの紅白歌合戦出場は記憶に新しい。シティポップの現代的解釈をしたバンドがメインストリームで受け入れられる現象こそ、まさに80年代のシティポップのにおいがするのだ。リバイバルブームも成熟しただろう。そして日本国内にとどまらず、いや、日本以上に海外では空前絶後のシティポップ大ブームなのだ。テレビ東京の「Youは何しに日本へ?」では大貫妙子や山下達郎のレコードを買い求める訪日観光客が取り上げられ話題になった。そのブームのきっかけとなった曲こそ、竹内まりやの「プラスチック・ラブ」なのである。Youtubeにあがったこの曲は莫大な再生回数を誇り、コメント欄はほぼ英語という現象を引き起こしたが、なんと昨年末に削除されてしまった。しかし新しくあげなおされた動画の再生回数はすでに130万。投稿しなおされてまだ一か月である。
今回、私はシティポップについて触れつつも、近年大爆発中のシティポップリバイバルの謎も解明していきたいと思う。しかし研究時間が絶望的に足りないため、これはただのレポートに過ぎない。いつか近いうちにデータを踏まえて書けたらと思う。
1シティポップ、二つの定義
私よりも音楽に詳しいお偉い方々は、どのように定義をしているのだろうか。
今回は「レコードコレクターズ」が2018年3月に出版した「シティ・ポップ 1973-1979」とスージー鈴木の「1984年の歌謡曲」を参考に考えてみる。
前者では「自分たちが暮らす都市を描く音楽として捉えなおされるシティ・ポップ」と表現され、「都市と周辺という本来ひかれていた領域が、徐々に距離を詰め、重なり合い、独特のテンションを保ちながらポップミュージックとしての着地を目指した」そうだ。つまり、大まかにいうと都市と自分たちとの関係性を描くようなジャンルで、音楽性に対しては言及されていないのである。
一方でスージー鈴木は音楽性に対して言及している。彼は前者と同じように「東京人による、東京を舞台にした、東京人のための音楽」と表現しているが、音楽性に関しては「歌謡曲とニューミュージックの融合した先にある音楽」と表している。(ニューミュージック:70年代後半に生まれた、洋楽志向の強い自作自演の音楽)そして「キャッチコピー的な歌詞と複雑なアレンジコードを駆使」した音楽ジャンルであると定義している。具体例を挙げるならば安全地帯の「ワインレッドの心」。ニューミュージック出身の玉置浩二が歌謡曲よりのメロディをうたい上げたこの曲は、スージー鈴木に言わせると「ニューミュージックか、歌謡曲かという二元論が不毛に感じてしまうようなふところの深い楽曲」だそうだ。
ここで今一度私の中の「シティポップ」定義を提案したい。本レポートは過去だけではなく現在進行中のシティポップブームやFuture Funkについても考察する予定である。そこで考えなければいけないのは、竹内まりやの「プラスチック・ラブ」だ。この曲が収録されているアルバム「VARIETY」(84)は2年間の活動休止後に発表された、作詞作曲 竹内まりや・プロデュース 山下達郎の名盤である。なんとスージー鈴木の指摘した転換期の時代である84年に発表された曲ではないか。
そして歌謡曲を歌うアイドルだった竹内が自作自演するという現象は、安全地帯のそれと真逆であるが、「融合」という点では同じだろう。この「VARIETY」はスージー鈴木の指摘にピタッと当てはまる。そして中でも「プラスチック・ラブ」は、タイトルからみても「プラスチック」(=消費主義的)。この曲は多くのユーザーの中で「シティポップの代表作」として扱われる。投稿されているCity Pop MIXなどを聴いてみると必ずと言ってもいいほど入ってくる一曲だ。これらからスージー鈴木の指摘「歌謡曲とニューミュージックの融合した先にある音楽」をシティポップの定義としたい。それ以前に、今のリバイバルブームの受け手である人々は歌詞の意味を理解しようとしていない。サウンドメインに考えるのが正しいだろう。
ちなみに今でこそ「シティポップ」と称される曲の作り手たちは、当時からその自覚があったわけではないようだ。レコードコレクターズの「シティ・ポップ 1973-1979」で真っ先に取り上げられたのが南佳孝の「摩天楼のヒロイン」(73)
松本隆がプロデュースしたこの名盤は、ヨーロッパでもニューヨークでも東京でもない、どこか架空の幻想都市を表現したコンセプトアルバムだ。聴いてみると、「プラスチック・ラブ」とは大違い。どちらかというとジャズ色の強いメロディに詩的な歌詞。「キャッチコピー的な歌詞と複雑なアレンジコードを駆使」とは正反対な楽曲なのだ。聞き手が違えば概念が違う。 当の本人、南佳孝はネット記事のインタビューでこんな風に答えていた。「時代の気分として、東京生まれ、東京育ちである『オイラの音楽』を確立したい。洗練されたかっちょいい音楽をね」。『洗練されたかっちょいい音楽』-。確かに南佳孝をシティポップにくくるよりも、『洗練されたかっちょいい音楽』と表すほうがピンとくる。70年代中盤から後半にかけて、このような『洗練されたかっちょいい音楽』(それは決してロックにあふれたニューミュージックとは違う。どのジャンルからも離れた、まさに「幻想」のような実体のない曲たち)が少なかれ存在していた。ほかに挙げるとしたら、吉田美奈子の「冬の扉」(73)か、ティン・パン・アレーの「キャラメルママ」(75)だろうか。
第二回予告:虚構のジャケットー角松敏生から考える
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
