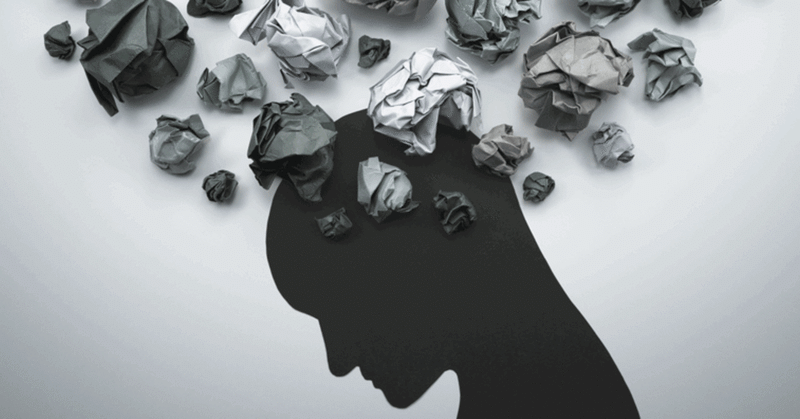
「哲学する」において最も重要なこと
「哲学する」において(前回の記事でも述べたが「哲学を勉強する」「哲学を研究する」ものとは違うことに留意)一番重要なことは何かと問われれば、私は哲学作品を読んだり、外国語を勉強したり、それどころか哲学に関する論文を書いたりするわけではないと考えている。では「哲学する」において何が一番重要なのかといえば、
「疑うこと」
だと思っている。
世の中には「当たり前」となっていることが無数にある。だがその「当たり前」に改めて目を向けて、それを徹底的に吟味すること、それが哲学である。
分かりやすい例を一つあげよう。
今君の目の前に茶色い机があるとする。その机を君はいつものようにみている。そこで映って来る光景は極めて当たり前の光景と言えるだろう。だがここで顕微鏡を準備してみるといい。顕微鏡を使ってその机の一部分を覗き込んで見るといい。するとそれまでとは違ったものが目に見えてくる。
日常的に「当たり前」のようにみている机も、とても細かくみると違った様相を呈する。そうなると普段その人が日常的にみている机は「当たり前」のものではなくなる。
あるいは色についても同じことが言えるだろう。その人間にとってその机は茶色に映っている。だがそれは「その人にとって」にしか過ぎないのかもしれない。これはカントの論だが、見る人や動物、生き物によれば茶色に見えなかったりする。もしかすると緑に見えるかもしれない。その茶色という色合いもまた「当たり前」ではないことに気づく。
これは物質的な面での「疑う」だが、疑う対象は物質だけに限らない。例えば法律や言語、道徳と言った日常生活に当然の如く取り込まれているものもそうである。だが当たり前のようにあるそれらも、詳しく吟味していけば特別な意義、思わぬ成立過程や効用があったりするものである。そしてそれらは正しいのか、間違っているのか、そもそも正しいことなんてあるのかといった疑問点を連想させて考察していくことが哲学なのだと思っている。
哲学史上、一番最初の哲学はタレスによって「万物の祖は水である」と主張されたこととされている。実際に「万物の祖は水である」かはともかくとして、これは世界の成立・構成について目を向けたものである。それまでは当たり前のようにあった世界に対して「疑い」の目を向けたのだ。生計を立てたり娯楽に耽ったりと主観的に過ごしていたそれまでの思考様式から抜け出て、「疑い」によって客観へと向けられたのである。
このように「疑う」というのは人間を人間たらしめる究極的なもの・根源的なものと言えるかもしれない。というのも「疑う」というのは能動的なものであり、それは主体的になされなければならないものである。動物は基本疑うことを知らず、また人間においても別に「疑う」ことはせずとも生きていける。というより「疑う」ことをしない方が楽ですらあるように思われる。それでもなお「疑う」というのは世界へと精神的に己を投げかけるものであり、そこから何かしら自分を確立していく営みなのかもしれない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
