漢字の由来って結構おもしろいよ、ってゆー話。
最近(でもないけど)、漢字の由来や成り立ちについて色々と調べるのにはまってたり・・・・。
昔から算数や英語などは苦手だったけど、国語だけは何故か点数良くてパソコンやネットが無かった時代は、暇なときに家にある国語辞典を開いて「へー、神社にいる鹿って”しんろく”って読むんだ-」とか絵もちょこっと書いてるから「かささぎってこうゆう鳥なんだ-」とか行き当たりばったりな、どーでもいい事を色々とみるのが好きな時期があったんですが(めっっちゃくちゃ暇な時ね)、その延長線上なのかどうなのかはわからないけれど、漢字の成り立ちを調べるのも中々面白かったりする・・・・。
ネットでそれなりに有名な、由来を知ると実は怖い漢字でいえば、
「民」っていう文字。
由来を知るまでは「人間皆平等だよ」「協力して生きていかなきゃね!」みたいなホンワカした意味合いだと思ってたんだけど、ところがどっこい、
実はコレ、左目を錐状のもので突き刺している状態を表していて、
昔の中国で戦いで負けた他民族を奴隷にする際に、奴隷だと見分けがつくように左目を潰して片方の目の自由を奪っていたという所から来た漢字らしい。。(ひどい・・・)

なので昔は、奴隷のことを「民」と呼んでそれ以外の人間を「人」と呼んでたのだって。
・・・・・・・・なにソレ・・・(-_-;)
かなり穏やかじゃないゾ。日本の「民主主義」なんてのも、この由来だけを聞くと「民」のとこだけちょっと変えた方がいいんじゃないかと思えてしまう・・・。
あと個人的に感動したのが「星」っていう文字。。
星という漢字は略字で今の漢字になったのだけど、昔は上に”日”が3個ついてた。

この漢字ってよくよく考えると、とても不思議な気持ちになる。
だって「星」は夜に見えるもののはずなのに、
なんで”太陽”を表す”日”という漢字が上に3つもついてるんだろう?
そもそも夜は太陽は見えない。
太陽が見えるならそれは”昼”で、夜に太陽が見えないのは当たり前。
ーーーーーひょっとしたらこの漢字を作った人は、
誰に教わると言うこともなく夜に浮かぶあの点々と光る丸い粒も「恒星」であると、なんとなくわかってたんじゃなかろうか・・・。
現代の人達だったら夜空に浮かぶ星のほとんどは、太陽と同じ「恒星」であると知ってるけれど(月とか金星とか地球に近いモノは除くヨ)、ガリレオが今までずっと信じられてた地動説を覆す発見をする何百年も以前に、そんなことを考える人間がいたらと思うと、なんとなく感動してしまう。(本当にそんなことを考えて漢字を作ったのかは不明だけど)
日本では「夜」というものは、誰かが上から大きな黒い布で覆い、その布には小さな穴が開いていて、その穴から光が漏れ出して「星」というものが出来る。と言われてたらしい。
そんな中、
「あの小さな光の粒は全部太陽だよ。太陽は1つだけじゃ無く、夜になるとたくさん太陽が出るんだよ」と誰かに言われたら、昔の人達は一体どっちを信じるんだろう??
本当にその時代にあれが「恒星」だと思ったのかはわからないけれど、
ずっと前にテレビで、どこかの地主かなんかの家の蔵の中を色々と物色して大分大昔の物や道具なんかを発掘する番組があったのだけど、その中で江戸時代に作られた唐傘が出てきて、なんとその唐傘、折り畳み傘みたいに半分になってて、いざ使うときに柄の部分をまっすぐに立て普通の唐傘と同じように使えるというシロモノが出てきたのだが、折り畳み傘という発明が成される大分前から、誰かが折り畳み傘を作りそれを使用していた時代があったのだと思うと、
あながち、夜の満天の星空を眺めてそんな事を考える人もいたっておかしくはないんじゃないかなあ・・・と、
思わなくもない。_(._.)_
次に「なるほど~~」と、感心したのが
「暇」ってゆう漢字。
「ああ~~暇だなあ」なんて聞くと自堕落であるとか、他にやることないの?とか人生サボってる?なんて思いがちだけど、
実はこの漢字、何気に真理に近い由来を持ってた。
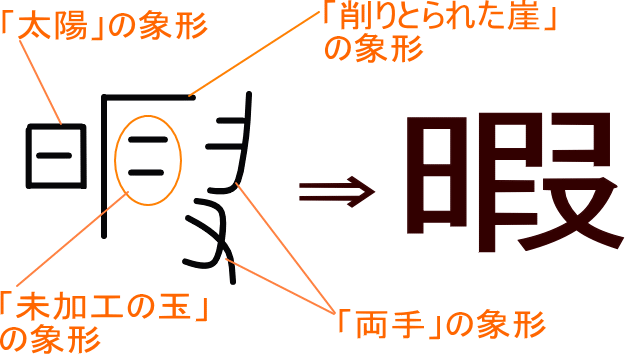
一番左側の文字は「太陽」を表し、何も磨いても加工もしていない原石を、
岩の中から両手で削り取ろうとしている所から来てるらしい。(ホントかどうかはわかんないけど・・・)
そんな解釈でこの漢字を見ると「暇」な時間も、色々と考えられて、その中でアイディアとか発想とかが生まれるので、実は全然無駄な時間じゃなくて意外と人間には必要な時間だったりするの・・・・カモ。。
そんな感じで漢字の成り立ちや由来を調べると結構知らなかった事がわかったりするし、何より友達とかに披露すると思いきり「どやあっ」ってドヤれるので、
中々どうして漢字って、
案外知ると面白いよ。。ってゆー話。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
