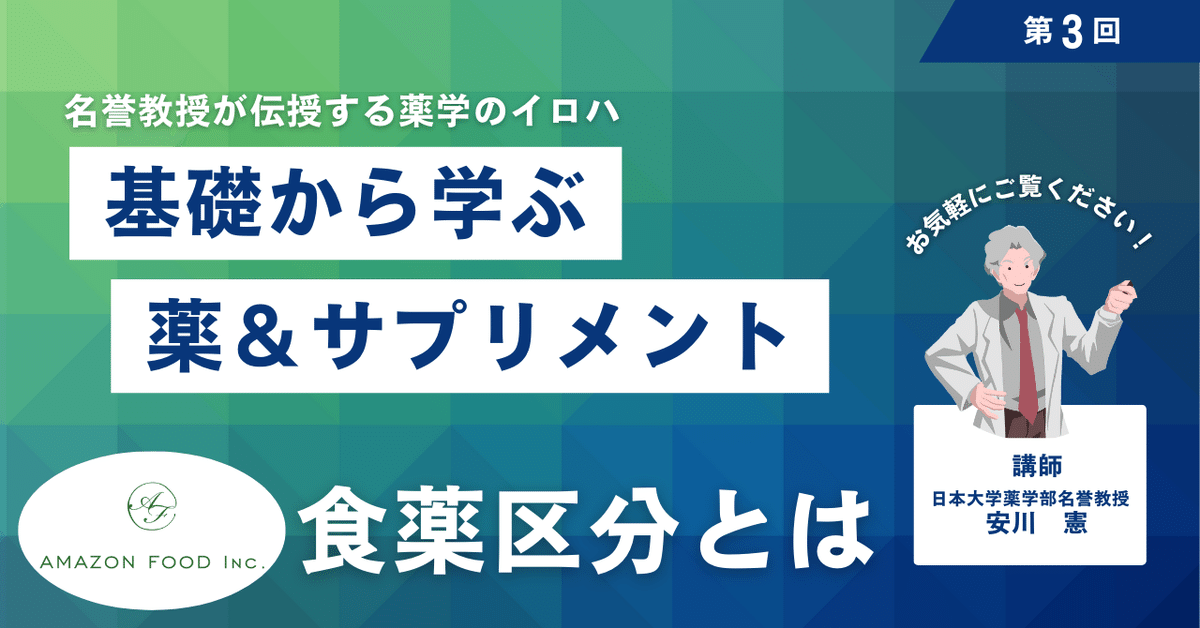
食薬区分
食薬区分とは
食品と医薬品を法的に区分するための基準です。これは、消費者の安全を守るため、また食品や医薬品の正しい使用を促進するために重要な役割を果たしています。
昭和46年に厚生省から無承認無許可医薬品の指導取締りについてとして、食薬区分が通達されました。
食薬区分の実例
食品:日常的な食事(米、野菜、肉、魚)、飲料(ジュース、コーヒー、ミネラルウォーター)、お菓子、調味料(塩、醤油、酢)など。
医薬品:処方薬(抗生物質、降圧剤、抗うつ薬)、市販薬(風邪薬、胃腸薬、鎮痛剤)、サプリメント(ビタミン剤、ミネラル剤)など。
ただし食品とされるリストには、危険と思われるものも見られます。
一例をご紹介します。
茜色素(セイヨウアカネ)
セイヨウアカネの色素成分は、食品の着色料にもちいられています。
しかし妊婦の服用で流産、動物実験では、腎臓・肝臓などに発癌性を示すことが判明しました。

コンフリー(ヒレハリソウ)
ヒトの肝静脈閉塞性疾患などの健康被害例が海外で多数報告されています。米国では、業者の自主回収を勧告、カナダでは許可ないものは販売禁止。

ギリシャやローマ時代には、骨折や傷の治療に用いられていたとされています。
β-カロチン
中国で癌予防に効果があると言われていましたが、欧州の介入試験では、肺癌などの発生率が増加したため、試験が中止されました。栄養状態が良い地域では、過剰摂取は逆にリスクが増加したと考えられます。

人参、かぼちゃ、マンゴー、サツマイモなどに多く含まれています。
セントジョーンズワート
医療的利用は、古代ギリシアまでさかのぼって記録されています。うつ病や不安障害の一般的な処置として用いられています。セントジョーンズワートの抽出エキスは、薬物代謝酵素を誘導し、服用中の医薬品の効果が減退することがあるので注意が必要です。

イチョウ葉
EUにおいてアルツハイマー病や認知症に用いられているイチョウ葉製剤。有効成分は、フラボノイド類、テルペノイド類とされていて、その含有量が規定されています。イチョウ葉には、銀杏で被れる成分「ギンコール酸」が含まれ、製剤中では5ppm以下と規定されているが、健康食品にはその規定がないため、注意する必要があります。

特に記憶力や認知機能の向上、血液循環の改善に効果があるとされています。
サイシン
植物の地上部には、腎毒性を有する「アリストロキア酸」が含まれているため、薬局方では、純度試験で地上部の混入を規制している。

特に風邪や頭痛、咳などの治療に用いられることで知られています。
