
くるりの『ハローグッバイ』の歌詞世界を素人が解体するノート
くるりファンなら皆知っているし皆大好きな『ハローグッバイ』。
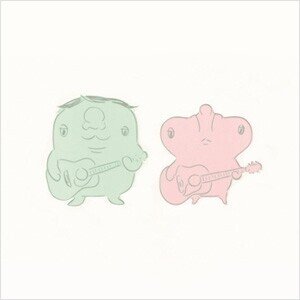
2002年5月のシングル『男の子と女の子』のカップリング曲として発表され、のちにシングル表題曲を集めたベスト盤アルバム『ベスト・オブ・くるり/TOWER OF MUSIC LOVER』にリマスター版が収録、さらに破格のカップリング集となる『僕の住んでいた街』にも収録されている名曲。端から端まで網羅している熟練ファンでなくても、「とりあえずくるりをザッと履修してみよう」というライトなリスナーでも触れる機会があるnotシングル曲の一つではないだろうか。
私はこの曲が本当に大好きで、何年経っても聴くたびに涙が出てしまう、なんてエピソードを言おうものならどれだけのくるりファンが「私もだが?」と手を上げるだろう。「ハローグッバイで泣く」なんていうのは「東京のイントロだけで胸がいっぱいになって苦しくなる」とか「ワンダーフォーゲルで飛び跳ねたくなる」とか「ばらの花を聴くとジンジャーエールが飲みたくなる」とか「琥珀色の街、上海蟹の朝を聴くと自然と体が揺れる」とか「宿はなしを聴くと梅小路公園の景色が見える」とかそういうレベルのくるりファンあるあるだろう。
だが、『ハローグッバイ』にはかなり即効性の催涙作用があるのが特徴的だと思っている。所謂「スルメ曲」などとよく言われるくるりの楽曲だが、『ハローグッバイ』についてはまるで上質な映画のクライマックスのみを凝縮させて観たかのような万感を呼び起こす力があり、なおかつその腕力が凄まじいのだ。
このことについて、サウンドやメロディについては「コード進行…とは…?」レベルのクソボロの素人なので語ることは出来ないが、「言葉」についてならギリ出来るかもしれない! 小説とかも、ちょっとなら読んでいる!! ということで、素人が『ハローグッバイ』の歌詞世界の解体を試みるというノートです!
一応言っておきますが、解釈という名の二次創作みたいなものですので、きっとあなたと、皆さんと、同じ解釈なわけがありません。読みながら「ちげえわ~~~」と思うことだってきっとあるはず。それを踏まえた上で読んで頂けると幸いです。要は「いちリスナーの妄言だから殴らないで!」という予防線です!!!!!!!!
くるり『ハローグッバイ』の歌詞世界を順番に解体する
さっそくやっていく。どんどんやっていく。
始発電車とその次を なんとなく乗り過ごしてみた
まずこの歌詞の入り。最強である。
物語の主人公が「始発電車を待っていた」のがまず分かる一文だが、これでリスナーは一気に明け方の世界に引き込まれる。匂いや、気温や、まだ薄暗くぼんやりした建物の輪郭が浮かんでくる。
加えて始発とその次の電車を乗り過ごしているところが素晴らしい。ここで想像するだに、主人公は「昨晩、あるいは始発を待つ前の出来事や時間」に何か未練を感じているのではないだろうか。
始発電車に乗ってしまえば「今日」が始まってしまう、「昨晩」あるいは「未明」にあった「なにか」の余韻が消えてしまうことを無意識に拒み、駅のホームに留まってしまっている主人公の姿が浮かぶ。
退屈のなか気付かず 目に埃が入ったのか涙が出た
自分で始発電車とその次を見逃しておいて、言うに事欠いて「退屈」などという主人公。気付かずこぼれた涙さえ、埃のせいにしてしまう。
このしらばっくれ感はまるで主人公が何かを「大したことではない」かのように取り繕っているようだ。
恐らく主人公は「始発電車に乗ることが出来ない」自分の感情を、「大したことではない」かのように扱うことしかできず、すっとぼけている。思えば人は悲しみや痛みがまだ生傷であるときほど「大したことない」かのように振る舞ってしまいがちではないだろうか。
この次はいつだろう 間に合えば何処へ飛んでいくの
「この次」とは「どの次」のことだろう。恐らく始発電車を待つ前には存在していた「何か」だと思う。そして「次はいつか」と思い耽る「何か」というのは「出来事」や「人」というよりも「機会(チャンス)」などがしっくり来る気がする。その「折(おり)」が「次」にいつ来るかも分からない。約束も予定もない、この寄る辺なさ。
「間に合えば」とは何のことだろう。前述の「機会」を生かすなら、「いつ来るかは分からないが、次の機会は間に合うだろうか」というところだろうか。少なくとも今の主人公の心情としては「何か」に「間に合わなかった」か、「間に合いそうにない」「間に合うと思えない」状況なのだと思う。そして間に合ってしまったら、「何処へ飛んでいくの」と案じるのは恐らく「心」や「想い」の行き先だ。「もし間に合ったら、どんな気持ちになるのだろう」と夢想しているように思えるが、ほんのちょっぴり虚しく、諦めを含んだニュアンスもある。
(ハロー&グッバイ ハロー&グッバイ ハロー&グッバイ)
くるりの楽曲はとにかく「出会いと別れ」を繰り返す。歌唱では「&」が省略されているが、この部分はまさにその最たるものだ。
全体的にこの楽曲は「別れ」の匂いが濃く、主人公もまさに「別れ」を終えたところだと読み取れるが、「ハローグッバイ」とリフレインされることで想起するのは、「別れ」ではなく「出会い」の瞬間を何度も反芻させているような、豊かで丸みを帯びた情景だ。
この気持ち説明できる言葉も覚えた
「気持ちを言葉で説明できる」というのは知性によるところが大きく、特に子供から大人へと精神が成熟・成長していく過程で学んでいくことが多い分野だと思う。「別れ」をきっかけに主人公が成熟したのかもしれないし、「せっかく言葉を得て大人になったのに」別れが来てしまったのかもしれない。
注目したいのは最後の「覚えた」の部分だ。説明できる言葉が「分かった」でも、説明できる言葉を「見つけた」でもなく、主人公はこの言葉を「覚えた」と表現している。「覚えた」ということは、この言葉を「忘れずに使い続ける」と決心しているようにも思える。
やるせなくて今日も夜が明けるのを待っている 待っている
「やるせなくて」というのは前述の「覚えた言葉」を受けてだろうか。
そして始発電車に乗る踏ん切りさえつかないのに、夜が明けるのを(2度繰り返すほどに)切実に待っている主人公は矛盾しているとも言える。でも「夜が明けて欲しいけど、始発にはまだ乗りたくない」なんていう一見矛盾した感傷は、始発電車を待った経験(や、それに近い経験)がある人なら結構共感できるものではないだろうか。
主人公が夜明けを待っているのが「今日”も”」なのも着目しておきたい。ようやく言葉にできた気持ちに対する「やるせなさ」は主人公が昨日今日で感じたことではないようだ。少なくとも決して短くはない間、主人公は夜明けが待ち遠しいようである。そういう見方をすれば「夜明け」は単純に「太陽が昇る」のを待っているのではなく、別の何かの比喩である可能性も出てくる。
話は逸れるが前述の「矛盾」について念のため言っておくと、この楽曲に限らずくるりの歌詞は矛盾していることが結構ある。それはくるりファンなら皆さん思うところであろうが、そこの所謂「外し感」がくるりの”味”の一つだろう。
それも、『ハイウェイ』のような「僕が旅に出る理由はだいたい百個くらいあって」→「僕には旅に出る理由なんて何ひとつない」に代表される、構成上のよくある対比のレトリックだけでなく、本当に細かい部分に小さな矛盾が、よくよく歌詞を読むと潜んでいたりするのが面白い。これは行動や時間経過でいくらでも移ろいでしまう人の心や思考の軌跡にとてもよく似ているし、くるりにはそんな人間の情緒の倒錯性を温かな目で見つめる知性と器の大きさがあるのだ。
なので「矛盾している」なんていうのは大した問題ではない。でもそれほどにこの物語の主人公は感情のおさまりどころを探しているのかもしれない。
最後のお願い窓開けて 遠い昔のこと悲しくもない
ここの歌詞もまた少し不思議な印象を受ける。思うにこの歌詞には「二つの時間軸」が同時に存在しているように聴こえるからではないだろうか。
「最後のお願い 窓開けて」は現在形の言葉、つまり今まさに主人公が願っている言葉のように思える。未来形、あるいは過去形で「最後のお願い」をするのは不自然だからだ。
しかし続く歌詞では「遠い昔のこと悲しくもない」と過去の話をしている。
「今」の主人公が「遠い昔」に向かって語りかけているとも取れる。
そして誰に向けた「最後のお願い」なのかは分からないが、その願いが「窓開けて」という些細な頼みであるのも気になる。窓がある場所に自分もいるならば自分で開けてもいいはずだが、主人公としては開けて欲しい。これには以下の読み取りが出来ると思う。
①「あなたに」窓を開けて欲しい
②「自分以外の誰かに」窓を開けて欲しい
③自分には窓を開けることが叶わないので、開けて欲しい
私のイメージでは③。「”今”の自分には”遠い昔”のあの窓を開けることが出来ないから、開けて欲しい」というニュアンスだ。「遠い昔」の窓が主人公の頭の中(あるいは心の中)にはあって、その窓を開けたいのに届かない。今の自分からは開けることが叶わない。ここの歌詞から感じるのは、「二つの時間軸」と、それによるどうしようもない「不可逆性」だ。でもそれも主人公は「悲しくもない」と言っている。果たして、こぼれた涙を埃のせいにするような主人公のこの言葉は本心だろうか。
僕のロッカー 君のロッカー 斜め向かいだった
気のせいさ
来ました、ロッカーです。
絶妙に核心の周縁をなぞるような、遠回しな言葉運びをしてきた『ハローグッバイ』の、クライマックス直前に突如現れた「ロッカー」。
しかもロッカーが「斜め向かい」というのはかなり印象的な位置関係だ。「隣」でも「上下」でも「向かい」でもなく、「斜め向かい」なのがポイントである。
ロッカーが直接的な意味なのか、「僕と君の何か」の比喩なのかは分からない。しかし「斜め向かい」という言葉には「すれ違ってはいたけれど、決して遠くはなかった」という印象を受ける。そして主人公にとっては「斜め向かいだった」ということはきっと特別なことだったに違いないのだが、それすらも「気のせいさ」と打ち消してしまう。
どこか人と人の繋がりというものの「脆さ」「儚さ」という側面が垣間見えるようである。
いつからか
あなたのこと忘れてしまいそう
まるで何かが爆発したかのようにかき鳴らされるサウンドと共に放たれるこの歌詞が、本楽曲の最高涙腺突破点ではないだろうか。(私はそうです)
「忘れてしまいそう」で分かるのは、主人公が「あなた」ともう二度と会えないことを覚悟、あるいは予見していることだ。このまま会えなければ、いつかは忘れてしまうのではないかと危惧している。
そしてリスナーがこの歌詞に感情を揺さぶられているときに浮かぶのは「忘れたくない人」や「忘れたくないもの」ではないだろうか。
この歌詞と力強いサウンドの奥底には、反語として「忘れたくない」という小さな祈りが潜んでいるように思える。
この次はいつだろう
歩きたいのに雨が降っている
雨が降っている
「この次はいつだろう」がまたここでも登場する。
そして「次=未来」のことを思いながらも、雨を言い訳に歩き出すことが出来ない主人公。「いつか忘れてしまいそう」であることに抵抗しているのだろうか。「歩きたいのに」という言い回しも、どこか心もとなく感じてしまう。「雨」というは、心の憂いのことだろうか、それとも涙のことだろうか。
いずれにしてもこの歌詞のバックで繰り返される「ハロー&グッバイ」と、情感たっぷりのサウンドは豊かな雨のように降り注ぎ、この物語に最上級のカタルシスをもたらしてくれる。
しかしそこに不思議と湿っぽさはなく、雨と雨の間にはキラキラとしたささやかな光が見えてくるようでもある。きっと主人公も、いつかは歩き出すのだろう。「埃が入った」などとすっとぼけたり、「覚えた」言葉をたまに使ってみたり、「悲しくもない」などと強がったり、「気のせいさ」と打ち消してちょっと笑ったり、「忘れてしまいそう」と思って胸がキュッとなりながら、歩いていくのだと思う。
まとめ
20年来ほどのゆるゆるくるりファンではあるが、楽曲まるまる一本の歌詞世界の解体を試みるのが今回初めてで、すごく楽しかった。
くるり、というか岸田さんの生み出す歌詞世界は「言いきらな型」というか、全体像のごく一部のかけらを散りばめているような言葉たちなので、聴き手はどこまでも想像を膨らませることが出来る。その点ではいくらでも語れてしまうのだろうし、また語る人によって受け取るものも多種多様になるのだろう。
そして「出会いと別れ」はくるりが様々な楽曲で取り上げ続けているテーマだが、一貫して別れさえも寂しさとともに肯定的に捉えている手つきが本当に好きだし、今回改めて『ハローグッバイ』は完成度の高い素晴らしい楽曲だと噛み締めるように思った。
おわりです。
ありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
