第2回 有賀恒夫さん(中編)
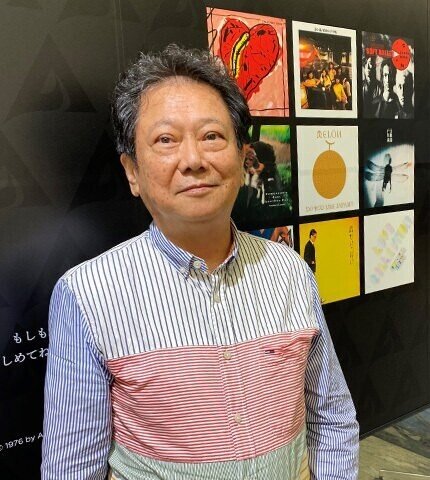
アルファミュージックの創設者・村井邦彦の片腕として、数多くの名曲・名盤のディレクションを手がけた有賀恒夫へのインタビュー、中編となる今回は、『COBALT HOUR』や大ヒット作「あの日にかえりたい」など、みごとブレイクを果たした荒井由実の後期作品について、ユーミン作品での豪華なコーラス陣にまつわるエピソード、そしてユーミンとともに70年代中期のアルファを支えた山本潤子、山本俊彦、大川茂のトリオによるコーラス・グループのハイ・ファイ・セットとの仕事について伺った。
![]()
ーーーーー荒井由実さんは75年4月に「ルージュの伝言」を発売しますが、この曲はそれまでの2枚のアルバムとはだいぶ趣を異にしているように思います。
「たしかに『ルージュの伝言』で、彼女の世界が大きく変わりました。それまでの彼女の音楽は、自分のインサイドで作っていた。だけど、この曲が収録されているアルバム『COBALT HOUR』を作った段階で、もっと大きなアーティストになったんです。インサイドを抜け出して、外界にまで手を伸ばしていったんですね」
ーーーーー「ルージュの伝言」は循環コードで作られたオールディーズ風のナンバーですし、アルバムもアメリカン・ポップスの匂いがありますね。
「そうですね、そこではっきりとそれまでとは作風が異なってきました。このアルバムの中では、タイトル曲の『COBALT HOUR』がコード的にも凄い楽曲だと思います」
ーーーーーこの曲や、前作『MISSLIM』の「生まれた街で」などもそうですが、キャラメル・ママ~ティン・パン・アレーの演奏も間奏で凄いプレイを披露しています。
「いやあ、もう最高ですよ。すごくいいです」
ーーーーーこのアルバムの中で、先行シングルで出た「ルージュの伝言/何もきかないで」の2曲だけが、ティン・パン・アレーではなくダディー・オー!の演奏になっています。
「これは、おそらくユーミンが言い張ったんだと思う。当時はずっとツアーをやっていて、バックは必ずダディー・オー!のメンバーでしたから」
ーーーーーそして、前作『MISSLIM』から吉田美奈子さんに加え、シュガーベイブの山下達郎さん、大貫妙子さんといったメンバーがコーラスに参加しています。特に『COBALT HOUR』以降はコーラスを重視するようになっていきますね。
「これはマンタ(松任谷正隆)が、達郎に頼んだんじゃないかな。コーラスに関しては達郎が全部仕切って決めていました。レコーディングの時に、コーラスは1本のマイクで録音するんです。そこで3人並んだら、美奈子の声が一番大きいわけです。だから『美奈子、下がって、下がって』と言っているうちに、どんどん後ろに行ってしまう(笑)。達郎も声が大きいからその真ん中にいて、ター坊(大貫)が一番手前で、遥か遠くに美奈子が立っている。でも、そうしないと上手く3人の声がブレンドしないんですよ(笑)。でも、達郎のコーラスに関してのサジェスチョンは、僕もとてもいいと思った。あまり注文を出した覚えがないです」
ーーーーーそして、75年10月5日にリリースされたシングル「あの日にかえりたい」でユーミンはチャートの1位を獲得し、大ブレイクします。この「あの日にかえりたい」ですが、元は別の詞が乗っていたそうですが。
「そうです。最初は『スカイレストラン』というタイトルで、まったく違う詞でした。歌い出しが♪町灯り~、となっていたんです。一度その歌詞でレコーディングして、ミックスまで終えていたんですが、この曲はTBSのドラマ『家庭の秘密』の主題歌になることが決まっていて。番組のプロデューサーからドラマと詞の内容が合わないので、歌詞を書き直してくれないかと注文が入り、そのことをユーミンに話したら『いいわよ』とすぐに直してくれて、今ある『あの日にかえりたい』の詞が完成したんです。もうミックスも終わっているので僕はあまり気が進まなかったけど、まあしょうがないですね」
ーーーーーその使われなかった歌詞に村井邦彦さんが新たな曲をつけて「スカイレストラン」として、ハイ・ファイ・セットのシングルになったと。
「まったくその通りです。でも『スカイレストラン』の歌詞は非常によくできていると思いました。サビの部分で『出がけには髪を洗った』というフレーズがありますが、ハイ・ファイ・セットのレコーディングの際に、主人公の女性はどうして髪を洗ったんだろう? という話になったんです。その時、僕は調整室にいたんですが、僕を含めハイ・ファイ・セットの男性2人(山本俊彦、大川茂)、エンジニア、アシスタントも全員男性で、唯一女性が潤ちゃん(山本潤子)だけだった。男たちはみんな「元彼に合うので、綺麗にしていきたかったんだろう」という意見だったのですが、潤ちゃんだけ意見が違ったんです。どう思うの? と聞いたところ、しぶしぶ言い出したのが『元彼と会ったら、その後ベッド・インするかもしれないから、髪を洗ったんじゃない?』と言うんです。男たちは、そんなことはないだろう、と言ってたんですが、潤ちゃんも譲らない。それで、仕方がないのでユーミンに電話して聞いてみたら『潤ちゃんが正しい』と(笑)」
ーーーーーそれは、深いところまで歌詞の意味について意見を戦わせるんですね。
「それで、レコーディングを続けたんだけど、今度は潤ちゃんのヴォーカルが問題になった。彼女は堂々と歌うタイプの人で、赤い鳥時代の『竹田の子守唄』などもそうでしょう? そこは村井さんが気に入っているテイストなんです。だけど、『スカイレストラン』をその感じで歌うと、面白くないんですよ。だから僕は、もっと小声でナイーヴに歌って欲しいと言って、鼻歌みたいに歌ってもらってOKになった。聴いている人が詞の奥行きというか、この女性の内面を感じられるように聴こえないとダメだったんですね。歌い方を変えたら俄然良くなって、今の形になったんです」
ーーーーーいっぽう「あの日にかえりたい」では冒頭で山本潤子さんが印象的なスキャットを披露されています。
「あれもマンタの采配です。メロディーも歌い方もいいし、結果として凄く印象に残りましたね」
ーーーーーその後に出た「翳りゆく部屋」は、もともと作家デビュー当時に書いた「マホガニーの部屋」という曲が原曲で、やはり「ひこうき雲」や、加橋かつみさんに書いた作家デビュー作「愛は突然に」と同じく、プロコル・ハルムや教会音楽の影響を感じさせるスケールの大きい作品でした。
「教会で、パイプオルガンを使ってやった曲ですね。僕はそんなに前に書いた歌だと知らなくて、その時にできた曲だと思っていた」
ーーーーー「翳りゆく部屋」は、バックがティン・パン・アレーではないそうで、ギターは大村憲司さんだそうですが、演奏メンバーは覚えていますか?
「あの曲はドラムがちょっと大仰だよね? 林立夫のタッチではない。たしか村上ポンタが叩いたんだと思いますよ。何かの都合でティン・パン・アレーのスケジュールが合わなかったんじゃなかったかな? アレンジはもちろんマンタだから、彼がメンバーを決めたはずです」
ーーーーーその後、ユーミンは76年末の『14番目の月』を最後に、アルファを離れますが、有賀さんはその後もユーミン作品のコンピレーションやカヴァー集などを製作されています。
「コンピレーションはいろいろやりました。でも、僕がアルファでやっていた時は『ひこうき雲』だけは入れなかったんです。これはユーミンの友人のことを歌った、ある意味プライベートな曲でもあったから、彼女も『この曲だけは(コンピに)入れないでね』と言っていました。僕はその約束を守って、僕がアルファに在籍中は『ひこうき雲』だけはコンピに収録しませんでした。その後、僕は東芝で、小野リサが紹介してくれたタチアナというブラジル人女性シンガーで、ユーミンのボサノヴァ・カヴァーを4枚、40曲作りました。ニューヨークに住んでいた僕は、ブラジルへ行って、40曲キー合わせをして、当時17歳の彼女とお父さんをニューヨークに呼んで、SOHOの増尾好秋のスタジオで、録音しました。アレンジャーは、Gil Goldstein、ボサノバ・ギターはスタジオで超売れっ子、ホメロ・ルバンボ。楽しかった。
その中にも、『ひこうき雲』だけは入れませんでした。彼女との約束を守るという気持ちからです。『私のカヴァーはいろいろあるけれど、有賀さんがやった『タチアナ』が一番好きよ。』とユーミン本人が言ってくれました。」
ーーーーーユーミンの作品のベースの1つにはラテン音楽やボサノヴァがあるので、凄くしっくりきますね。
「しかも、ポルトガル語で歌っているんだけど、彼女のメロディーに言葉が乗るんです。しかも全部ボサノヴァなので、歌い方が半拍食い気味になるんです。それが面白い。」
ーーーーーアルファの時代、ユーミンはハイ・ファイ・セットにかなりの数の楽曲提供をしており、一緒にコンサート・ツアーも回っていました。ああいった楽曲はハイ・ファイ・セットに歌わせる前提で依頼していたんですか?
「僕がユーミンに依頼しています。『卒業写真』などはハイ・ファイ・セットのほうが先に出ていますよね? そういう曲は彼女がハイ・ファイ・セットのために書いて、それをセルフ・カヴァーした、ということです。人に書くと世界が広がるんですよ。自分の中の世界だけでなく、他人が歌うことをイメージして書くわけだから。どちらのバージョンもいいですよね」
ーーーーーユーミン作品を歌うハイ・ファイ・セットは、やはり山本潤子さんのヴォーカルの魅力に依るところが大きいように思います。
「そうですね。ユーミン作品のなかでも『朝陽の中で微笑んで』という曲は、潤ちゃんならではの世界観を持っていて、他の人ではあそこまでの世界は生まれないと思う。ユーミン自身のセルフ・カヴァーは別としても、潤ちゃんでなければ歌えない曲ですよ。彼女は声が高いでしょう? だからああいったスケールの大きな曲で、ハイトーンで歌うと素晴らしくなる。『海を見ていた午後』はカヴァーということになるのかな? あれもいいですよねえ。潤ちゃんに歌わせたいと思って入れたんです」
ーーーーーハイ・ファイ・セットの世界観は、あの当時かなり洗練された都会的なポップスという印象がありました。ああいう形の音楽を作り出したのは、最初は村井さんのアイディアでしょうか。
「というより、赤い鳥でやっていた時の村井さんの作品、『翼をください』とか『忘れていた朝』など、洋楽寄りの発想から村井さんを通して出てきたような曲、潤ちゃんたちはそれが好きだったんだと思います。それに、あの頃四畳半フォークが全盛時代だったので、洋楽系のポップスは目新しかったわけです。僕らは四畳半フォークの経験はないし、洋楽的なポップスから出発しているわけだから、おしゃれにしようとしたわけではなく、これが普通だったんです」
ーーーーーモーリス・アルバートのカヴァー「フィーリング」は彼らの代表作になりましたが、あの曲はどうしてカヴァーすることになったんでしょうか。
「あれは、川添象郎さんが村井さんに持ち込んだ話かもしれない。元の曲がいいし、田辺信一さんのアレンジがしっとりとしていいですよね。実は、その前に三保敬太郎さんに頼んでアレンジしてもらい、レコーディングまでしたんです。ところが、ちょっとポップになり過ぎてしまって、もっとしっとりいきたい、という話になって、慶應のライトミュージックソサエティの先輩である田辺さんにお願いしたんです」
ーーーーー田辺さんは映画音楽などで素晴らしいアレンジをされる方ですから、エレガントな仕上がりになっていましたね。また、「メモランダム」という曲では、滝沢洋一さんを起用していますが。
「滝沢くんはどこで知り合ったのかは忘れたけれど、僕のところへデモテープを持ってやってきて、それが良かったのでハイ・ファイ・セットとサーカスで起用して、その後もずっと付き合いがありました。アルファで1枚アルバムを出しているけれど(『レオニズの彼方に』)、あれは僕のディレクションではないです。惜しくも、もう亡くなられてしまいましたが」
ーーーーーそのアルバムは、今やシティ・ポップの名盤の1つに数えられています。ところで、ハイ・ファイ・セットは女性1人に男性2人という組み合わせですが、ヴォーカルのバランスやハーモニーなどは有賀さんが決められていたのでしょうか。
「コーラスって、本当は4声じゃなきゃいけないんです。ハイ・ファイ・セットは3人だから1人足りないんですよ。レコーディングでは、潤ちゃんにセカンドを録音してもらって、4声でやったりもしています。『ファッショナブル・ラヴァ―』に入っている「フェアウェル・パーティー」などは4声ですね」
ーーーーーそれは山本潤子さんが2パートを録音しているということですか。
「そうです。基本は何でも4声でやるので、彼らの曲をステージで聴くと、ハーモニー的には歯抜けになってしまう。それは嫌だな…とずっと思っていた。その点、サーカスは女性2人、男声2人の4声だから、スタジオでレコーディングしたものをそのままステージでも再現できる。そこは良かったですね」
ーーーーーハイ・ファイ・セットはどの作品まで担当されていたんですか。
「最後はたしか『THE DIARY』というアルバムでした。オールディーズの「恋の日記」のカヴァーがリード・トラックでシングルにもなりましたが、ジャズっぽいアレンジにしています。アレンジャーは、Fifth Dimensionのヴォーカル・アレンジャー『Bob Alcivar』レコーディングは、LAのA&Mスタジオ、エンジニアはCarpentersの録音担当でした。コーラスのミックス法とかアドバイスくれました。」
ーーーーー彼らはその後、和製マンハッタン・トランスファー的な、4ビートジャズに傾倒していきますが、もともとジャズ・ヴォーカル的な方向に興味があったんでしょうか。
「興味は凄くあったみたいです。アルファで僕がやっていた頃は、そこまでジャズ的な作りは意識していなかったけど、僕が離れ、アルファからも離れていったとき、楽曲をジャズアレンジにしていましたね。でも、全部4ビートにして、ジャズのノリでやって面白ければいいんだけど、そうとも限らないじゃない?」
ーーーーーやはりポップスのフィールドでこそ輝くグループだったのかもしれませんね。ところで、先ほどお話に出たサーカスも、やはり有賀さんがご担当でした。ある時期はハイ・ファイ・セットと両方のコーラス・グループのディレクションをされていたことになりますが、この2グループの違いはどこにあるとお考えでしょうか。
「ハイ・ファイ・セットの良さというのは、結局のところ潤ちゃんの魅力に集約されるんです。サーカスの場合はメインが女性2人で、男性2人もサポートとしては申し分ない。その違いでしょうね」
![]()
荒井由実がそれまでの内省的な作風から一転して、ジャパニーズ・ポップスの外海へ旅立って行った記念すべき1作『COBALT HOUR』もまた、現在ではシティ・ポップの文脈で高い評価を得ている名盤である。そして、ユーミン作品を中心に、洋楽的でハイセンスなポップスを立て続けに放ったハイ・ファイ・セットもまた、時代に大きく先行した、洗練度の高いグループであった。ハイ・ファイ・セットのアルファ時代の楽曲は、村井邦彦やユーミン、松任谷正隆をはじめ。頭抜けたポップ・センスをもつ作家陣によって築かれたが、これもまた有賀の洗練を見抜く感度の高さがあってこそ、成立した世界だということがお分かりいただけたと思う。70年代中期のアルファのカラーはこの2人(組)に集約されると言っても過言ではないだろう。ロング・インタビューの最後となる次回は、70年代後期の有賀ワークスの、もうひとつの代表的なコーラス・グループであるサーカス。そして79年にアルファに移籍してきた兄弟デュオ、ブレッド&バターの仕事について、貴重なエピソードを開陳していただく予定である。
Text:馬飼野元宏
