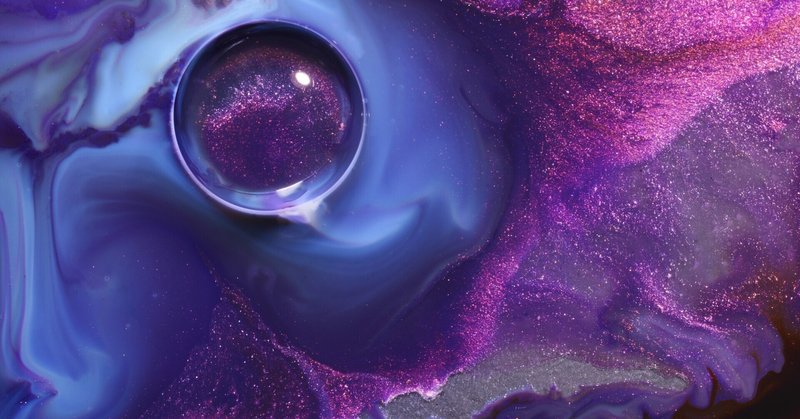
一輪の花を手向け
なんていい曲なんだろう。
ジョバンニがある夜無くしたチケットが、瞬間自分の手のひらに現れたようであった。銀河鉄道に生きながら同乗できる機会などそうそうない。それにこんな月夜である。ヘッドホンから流れる仮音源に、あらためて絵を描こうという覚悟を決め、いつか図書館で読んだ詩集をもう一度買い直して持ち歩く。文庫本はいいな。黄身を帯びた白の直方体を指でずらせば、くっと意識を引っ張られて、眼は紙の白とインクの黒を認識しているはずだけど、紙を離れた文字列は網膜を伝ってあたまのなかに色彩を広げてゆく。
よく思い出す色彩体験がある。応挙の水墨の『龍門鯉魚図』描かれていないはずの虹色に出会ったこと。応挙が滝そのものを描かずして描き切った力量ゆえか、墨の五彩の解釈か、塗られていない色彩のありかを、画学生のころは絵画のほうに問い続けていた。時が経つにつれ、人間(自分)の眼によるものなのではないか?と、問いの矢印がぐるりと反転し真っ直ぐに自分の方向を差したのは、自分の作品が人目に触れる機会が増えた状況も関係があるだろうか。問いの矢印が混乱したコンパスのようにクルクルと画と自分の間で廻るなか、原美術館ARC「觀海庵」で同じく応挙の『淀川両岸図巻』を観た。
ショーウィンドーを覗き込む形で鑑賞する絵巻だが、作者の視点は両岸に挟まれた河の真ん中に浮かぶ位置にあり、あちら側から見ても、こちら側から見ても、どちらか一方の山並みは必ず反転しているアジの開きのような画である。色彩の生まれるところが自分の眼と画面の作用による、どちらでもない浮いた場所に定められたように、『淀川両岸図巻』でも応挙は鑑賞者の持つ矢印をぐるぐると回転させる。絵巻の中では景色と共に重力がドーナツ状に存在していて、穴の位置にある画中の船に乗り込んで周囲を見渡さない限り、まっすぐ立つことができないだろう。そして恐ろしいことに目の居心地が良いであろうドーナツの穴の部分には、舟が一艘も描かれていない。落ち着くべき座標が与えられずに、また目と認知がかき混ぜられる。作者の目だけがそこに浮かんでいる。あちら側とこちら側に挟まれた河の真ん中で・・・

考え事を閉じて手の中の詩集に意識を戻す。病を患いながら遺した物語の数々、原稿上を走る万年筆の太字をなぞって読んでいたらきっともっと作家自身の情報を拾えてしまえるだろう。私はこうして活字に整頓された賢治の文が好きだ。
かねてより銀河鉄道のようなものに乗りたいと思っていた。それは次の状態への変身途中か、橋掛か、どこかへゆくためのホームのようなものが設けられていて、束の間旅人と話せる場所。今日はとりあえず空港と博物館が溶け合ったような大きな駅舎を想像して、スッと集中して入ったならばあの人やあの人に一言話しかけられるような気がする。心の痛みは実際の肉体に痛みを感じさせるように、美しさも依り代を多くの場合必要とする。今日は汽車の形を手がかりにしながら、支持体が想像できたならば、あとは描きはじめるのみ。無形のメディウムを想像することは私にとって祈りの手立てだ。

ポール・ヴェルレーヌ『月の光』に漂う憂いときらめきや、宮沢賢治『補遺詩篇』のなかでの画家を感動させた緑がそのまま同じ色彩のままに厳しい飢えを予感させる象徴であること、どうにもできない物事や社会情勢と直面しながら、詩や曲は美しさのための器となってみずみずしく輝いている。詩の降りるところのヴェルレーヌと本人の私生活はずいぶん印象が違うことを思うと、作者の外側に肉を得た美しさというのは、なんて不思議な存在だろう。エッセンシャルオイルのような、砂金のような、オパールのような、、
この1年『月の光』と『星巡りの歌』の中で遊泳した。
キャンバスの上の泡沫を眺めながら、輪と和と円と球と呼びかけ方を変えながら、聖火の納まるところにどんな一言を添えられるのか。いまだ河をどちらにも渡りきることなく浮かんでいると、あらゆる矢印が自分の周りをぐるぐると飛んで、反転した向こうの山並みに飛んでゆくのが見える。ここにもドーナツ状の秩序があるようだ。向こう岸に反転した人はいないのだろうか。報道番組の逆走車、その人だけは正しく逆さまに空を走り抜けている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
